以前から読もう読もうと思っていて、なかなか手が出なかった山田風太郎著『魔界転生』です。
『ぼくらが惚れた時代小説』で縄田一男さんが2位に推されていた作品です。
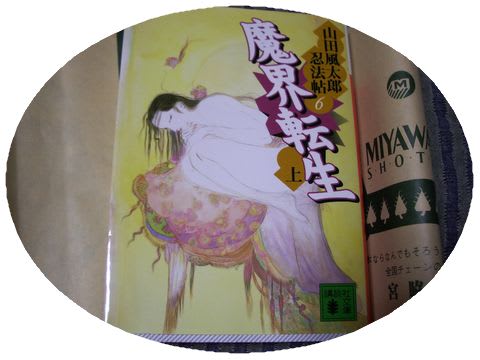
山田風太郎って小さい頃から知ってたような気がするけど、忍者物でちょっとエッチな話を書く人と思っていました。
先日NHKの番組でこの人の特集をやってて、たまたま観たのですが、先の戦争に強く反対されてた方みたいで、急に興味が湧いたのでした。
でも表紙からして、なまめかしい。
ところがどっこい、この小説メッチャ面白い。架空の話だけに何でも書けるというわけです。
物語は寛永15年(1638年)島原の乱が収まった原城を取り囲む陣に、由比正雪が宮本武蔵を訪ねるところから始まります。将軍は三代・家光の頃です。
原城からこっそり逃げ出す森宗意軒一行を目で追う武蔵、その目の前で宗意軒に切られた女から、なんと荒木又右衛門が出てきたのでした。
話は長くなるので控えますが、このように魔界から転生した剣豪は、居合い切りの田宮坊太郎、槍術の宝蔵院胤舜、鍵屋の辻の荒木又右衛門、島原の乱の首魁・天草四郎時貞、将軍家剣術指南役・柳生但馬守宗矩、柳生家宗流を標榜する柳生兵庫こと柳生如雲斎、そして二刀流・宮本武蔵の7人であります。
そして宗意軒は紀伊の大納言・徳川頼宣を将軍にする企てから、かの大納言を魔界転生させようと企み、その目的のためにもう一人魔界転生させる男として柳生十兵衛を選び、最後己の指10本目と引き換えに魔界転生させるのは宗意軒本人です。
そう宗意軒は忍術『魔界転生』で、自分の掌の指1本の犠牲につき一人を甦らせることが出来るのです。

紀伊の殿様・頼宣が危ないので紀州・徳川家を助けてくれと家臣から託された十兵衛、この事から転生衆7人の標的となり、次々と対決していくのですが・・・
十兵衛以下柳生衆は一旦那智の青願渡寺で集まりそこから和歌山城を目指すことに、柳生衆は奈良の山側から降りて行き、十兵衛は大辺路を南下・・・ここで十兵衛は古座川の橋を渡る件<くだり>があるのです。
私はびっくりしたものです。
司馬遼太郎が古座に来て感嘆して家まで作った、ここにきて山田風太郎が己が作品で古座川を紹介している、現代作家は少なくとも数人は古座の地を訪れていたのです。
ところで、江戸時代の初期に古座川に橋が架かっていたのかという疑問がムクムクと首をもたげてきたのでした。
古座川は江戸時代以前は重畳山の登り口にあたる神野川辺りまで河口があったとか、そうなると河口としてはとてつもなく広い河口になってしまいます。
ただ江戸時代には現在と同じような地形だったそうで、どのようにして、どれくらいの年月を費やしてそうなったのかは定かではありませんが、河口だけがやたらと広かったのかも知れません。
古座川河口には戦前大きな中洲があり、軽業師などの興行があって屋台が並び賑やかだったとか、だから西向側から古座側まで現在のように橋が架かっているのではなく、西向から中洲、中洲から古座へと一旦途切れていたのですね。

鉄橋の付け根から見た古座川の中洲ですが、昔はもっと大きかったといいます。
河口には昔から渡しがあり、戦後大きな橋が架けられても、町民は渡しに乗っていたと言われています。
そういう今判ってる話から想像すると、十兵衛の時代には橋は無かったのではないかと思ってしまうのです。
ただ紀州藩は大辺路の整備を急ぎました。おそらく田辺で中辺路への道と別れてからすさみを通り(42号線とは違う旧の道も随分通っていたと思うのですが)串本まで来た時、現在の串本の街を通らずに袋辺りから橋杭の方へ山道を選んだと思うのです。何故ならここに大辺路の立て札があるからです。
そして姫駅前のある旧道を通り、伊串を抜けてJRに沿う道を歩き、神野川まで来ると成就寺に向かう道を通り、岩淵まで来たなら目と鼻の先に現在のJRの鉄橋があるのです。
もし十兵衛の時代に橋があったとすれば、そのJRの鉄橋の辺りではなかったかと想像してしまいます。
しかし昔から林業が盛んであった古座川上流から、伐採された木材が流れてくるのですから、雨が続いて大水が出るような川では、作った橋もすぐに流されてしまうので、渡し舟が有効だったと思うのです。
司馬遼太郎は『街道をゆく』シリーズで古座街道を取り上げ、七川ダムの下の真砂から川を下っていますが、江戸時代に橋が架かっていたのかどうかという詮議はしていません。
まぁ、どちらにせよ現実離れしたストーリーです、古座川にかかる橋の上で十兵衛が紀州藩の侍数人とすれ違ったとする筋書きの方が大事で、時代考証はたいして必要ないのかもしれません。
『ぼくらが惚れた時代小説』で縄田一男さんが2位に推されていた作品です。
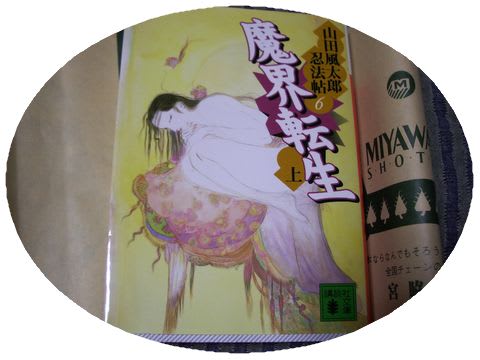
山田風太郎って小さい頃から知ってたような気がするけど、忍者物でちょっとエッチな話を書く人と思っていました。
先日NHKの番組でこの人の特集をやってて、たまたま観たのですが、先の戦争に強く反対されてた方みたいで、急に興味が湧いたのでした。
でも表紙からして、なまめかしい。
ところがどっこい、この小説メッチャ面白い。架空の話だけに何でも書けるというわけです。
物語は寛永15年(1638年)島原の乱が収まった原城を取り囲む陣に、由比正雪が宮本武蔵を訪ねるところから始まります。将軍は三代・家光の頃です。
原城からこっそり逃げ出す森宗意軒一行を目で追う武蔵、その目の前で宗意軒に切られた女から、なんと荒木又右衛門が出てきたのでした。
話は長くなるので控えますが、このように魔界から転生した剣豪は、居合い切りの田宮坊太郎、槍術の宝蔵院胤舜、鍵屋の辻の荒木又右衛門、島原の乱の首魁・天草四郎時貞、将軍家剣術指南役・柳生但馬守宗矩、柳生家宗流を標榜する柳生兵庫こと柳生如雲斎、そして二刀流・宮本武蔵の7人であります。
そして宗意軒は紀伊の大納言・徳川頼宣を将軍にする企てから、かの大納言を魔界転生させようと企み、その目的のためにもう一人魔界転生させる男として柳生十兵衛を選び、最後己の指10本目と引き換えに魔界転生させるのは宗意軒本人です。
そう宗意軒は忍術『魔界転生』で、自分の掌の指1本の犠牲につき一人を甦らせることが出来るのです。

紀伊の殿様・頼宣が危ないので紀州・徳川家を助けてくれと家臣から託された十兵衛、この事から転生衆7人の標的となり、次々と対決していくのですが・・・
十兵衛以下柳生衆は一旦那智の青願渡寺で集まりそこから和歌山城を目指すことに、柳生衆は奈良の山側から降りて行き、十兵衛は大辺路を南下・・・ここで十兵衛は古座川の橋を渡る件<くだり>があるのです。
私はびっくりしたものです。
司馬遼太郎が古座に来て感嘆して家まで作った、ここにきて山田風太郎が己が作品で古座川を紹介している、現代作家は少なくとも数人は古座の地を訪れていたのです。
ところで、江戸時代の初期に古座川に橋が架かっていたのかという疑問がムクムクと首をもたげてきたのでした。
古座川は江戸時代以前は重畳山の登り口にあたる神野川辺りまで河口があったとか、そうなると河口としてはとてつもなく広い河口になってしまいます。
ただ江戸時代には現在と同じような地形だったそうで、どのようにして、どれくらいの年月を費やしてそうなったのかは定かではありませんが、河口だけがやたらと広かったのかも知れません。
古座川河口には戦前大きな中洲があり、軽業師などの興行があって屋台が並び賑やかだったとか、だから西向側から古座側まで現在のように橋が架かっているのではなく、西向から中洲、中洲から古座へと一旦途切れていたのですね。

鉄橋の付け根から見た古座川の中洲ですが、昔はもっと大きかったといいます。
河口には昔から渡しがあり、戦後大きな橋が架けられても、町民は渡しに乗っていたと言われています。
そういう今判ってる話から想像すると、十兵衛の時代には橋は無かったのではないかと思ってしまうのです。
ただ紀州藩は大辺路の整備を急ぎました。おそらく田辺で中辺路への道と別れてからすさみを通り(42号線とは違う旧の道も随分通っていたと思うのですが)串本まで来た時、現在の串本の街を通らずに袋辺りから橋杭の方へ山道を選んだと思うのです。何故ならここに大辺路の立て札があるからです。
そして姫駅前のある旧道を通り、伊串を抜けてJRに沿う道を歩き、神野川まで来ると成就寺に向かう道を通り、岩淵まで来たなら目と鼻の先に現在のJRの鉄橋があるのです。
もし十兵衛の時代に橋があったとすれば、そのJRの鉄橋の辺りではなかったかと想像してしまいます。
しかし昔から林業が盛んであった古座川上流から、伐採された木材が流れてくるのですから、雨が続いて大水が出るような川では、作った橋もすぐに流されてしまうので、渡し舟が有効だったと思うのです。
司馬遼太郎は『街道をゆく』シリーズで古座街道を取り上げ、七川ダムの下の真砂から川を下っていますが、江戸時代に橋が架かっていたのかどうかという詮議はしていません。
まぁ、どちらにせよ現実離れしたストーリーです、古座川にかかる橋の上で十兵衛が紀州藩の侍数人とすれ違ったとする筋書きの方が大事で、時代考証はたいして必要ないのかもしれません。










