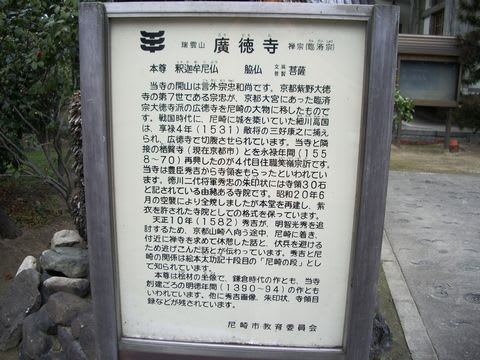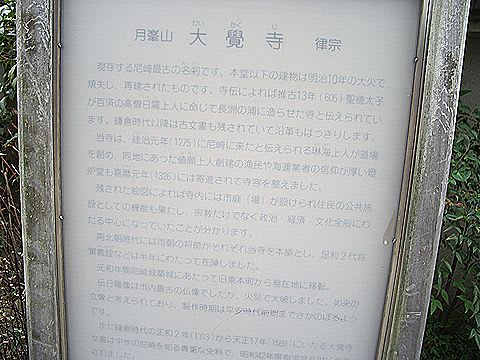台風のお話・・・尼崎市役所の一部です。
何を撮りたかったのかと言うと、中央やや右寄りに木の中からニョッキリと突き出た標識です。
見難いのですが、上が昭和9年室戸台風、下が昭和25年ジェーン台風の最高水位を示しています。
私の目線は室戸台風とジェーン台風のほぼ中間にあります。

同じものが阪神尼崎駅前にもありました。
ところが、とてつもなく高い所を示しています。
阪神の尼崎駅から市役所まで南北の距離で1Kmぐらいでしょうか。
その間に1~1,5mぐらい土地が高くなっていることになります。
なだらかな、坂とは感じることもない坂が続いているのでしょう。
平均満潮位 OP+2.10m
室戸台風が OP+5.10m
ジェーン台風 OP+4.30m

平均満潮位より室戸台風の最高潮位は3mも高かった、ジェーン台風は2.2m高かったという計算上のものしか解りません。
示されている高さまで水が浸かったのか・・・それは違うと思うのですが、もう少し丁寧な説明が必要なように感じます。
OP自体、何を示しているか解りません。辞書を調べてもそれらしき答えは見つかりません。

再び市役所にある標識、根元がツツジの草に隠れて見えていません。
市側が市民にどれだけ理解を求めているのか・・・疑問に感じます。

阪神尼崎の標識の下方にあるものですが、全てを比べてみて何を現しているか、理解に苦しみませんか・・・?
何を撮りたかったのかと言うと、中央やや右寄りに木の中からニョッキリと突き出た標識です。
見難いのですが、上が昭和9年室戸台風、下が昭和25年ジェーン台風の最高水位を示しています。
私の目線は室戸台風とジェーン台風のほぼ中間にあります。

同じものが阪神尼崎駅前にもありました。
ところが、とてつもなく高い所を示しています。
阪神の尼崎駅から市役所まで南北の距離で1Kmぐらいでしょうか。
その間に1~1,5mぐらい土地が高くなっていることになります。
なだらかな、坂とは感じることもない坂が続いているのでしょう。
平均満潮位 OP+2.10m
室戸台風が OP+5.10m
ジェーン台風 OP+4.30m

平均満潮位より室戸台風の最高潮位は3mも高かった、ジェーン台風は2.2m高かったという計算上のものしか解りません。
示されている高さまで水が浸かったのか・・・それは違うと思うのですが、もう少し丁寧な説明が必要なように感じます。
OP自体、何を示しているか解りません。辞書を調べてもそれらしき答えは見つかりません。

再び市役所にある標識、根元がツツジの草に隠れて見えていません。
市側が市民にどれだけ理解を求めているのか・・・疑問に感じます。

阪神尼崎の標識の下方にあるものですが、全てを比べてみて何を現しているか、理解に苦しみませんか・・・?