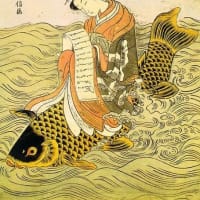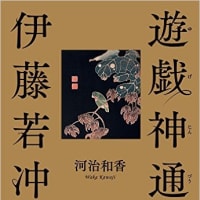洛西の地に住んで、もう20年を過ぎました。引っ越してきた当初、近所のユニークな地名にまず感心してしまいました。たとえば乙訓・大枝・神足・鶏冠井・羽束師・向日などなど。読みは文尾につけておきます。
なかでも読めなく不思議に思ったのが、物集女(もずめ)です。物を集める女とは何か? この地名の解明が、京に来て最初の課題でした。
長岡京市に、勝龍寺城という城が再興されています。小さいけれどもなかなか可愛い、味のある城です。わたしは播州の姫路城を見慣れ育ったために、ほかの城をみるとつい、おらが城と見比べてしまう。不用意な表現になることを、少年のころから反省しているのだが…。
三浦綾子著『細川ガラシャ夫人』の文章にもある。「勝竜寺城は、坂本城とは比較にならぬ小さな城であった。城というより、大きな寺といったほうがいい。それでも周囲にめぐらした濠が一応城としての体裁を見せていた」
近江の坂本城は明智光秀の居城である。光秀の娘の玉、のちのガラシャ夫人が勝龍寺城の細川忠興(ただおき)に嫁いだ。忠興の父の藤孝は、したたかな文武のひととして知られる細川幽斎である。
織田信長が軍を率いて上洛したのは1568年だが、このとき藤孝は乙訓あたりの支配を、信長に認められた。玉が父光秀の親友である藤孝の嫡男、忠興の妻として勝龍寺城に入ったのは、信長上洛の10年後である。
藤孝がこの地、桂川右岸を治めるにあたって、最大の障害となったのが、地侍との関係である。戦国時代、土地土地には土豪が力を得ていた。桂川西岸には、桂・川島あたりの有力な国人である革嶋(かわしま)氏、つい数年前までJR線の駅名だった神足氏、城の西にいまも地名のある友岡氏や、対岸八幡の志水氏などは、新領主である細川藤孝に従い、与力になった。ところが、現在の向日市の物集女忠重は、細川氏に抵抗する。しかし多勢に無勢。物集女氏はこのときに滅亡する。
新しく配下に入った地侍たちはその後、細川家の国替に伴って丹後から九州、肥後熊本藩へと移る。ただ革嶋氏だけは細川氏との良好な関係を保ちながらも、川島村に大庄屋として留まる。革嶋一族の末裔は、いまも京都に健在である。
なお細川幽斎を初代とする細川家の18代当主、細川護煕氏は元総理大臣。彼の先祖によって、この地の豪族であった物集女氏は滅ぼされたのである。
いまの京都市西京区や向日市、そして長岡京市などにあたる古代の乙訓郡をみると、物集女あたりの地名は「物集」郷、「もず」と記されている。この近辺には、土師(はじ)氏が住んでいた。彼らは機内各地に居住し、古墳の造営や喪葬儀礼に携わり土師器で知られる土器や、埴輪の製作にかかわった氏族である。古墳建設という土木工事でたくさんの人夫を管理することから、軍事にも関与した。また外交分野でも活躍している。
平城の都を長岡京から平安京に遷したのは桓武天皇であるが、桓武の母は高野新笠(たかののにいがさ)という。墓は大枝の沓掛(くつかけ)にある大枝稜である。彼女の父は和乙継(わ・やまとのおとつぐ)、母は土師真妹(はじのまいも)。真妹は名の通り土師氏の出身であり、母と娘は大枝あたりの生まれではないかともいわれている。
八世紀末の記録によると、土師氏には四氏族があった。いまの奈良市内の菅原町と秋篠(あきしの)町あたりに居住した二氏族。ほかに大阪府堺市百舌鳥(もず)と、南河内の古市あたりを本拠とした2グループである。
彼らは相次いで改姓願いを提出し、新しく三氏が誕生する。菅原氏、秋篠氏、そして大枝氏である。菅原氏からは後に学問の神様と称される菅原道真が生まれ、新笠の流れの大枝氏は大江氏に再改姓し、儒家として栄える。
真妹の生家は毛受(もず)腹といわれる一族であるが、和泉の百舌鳥(もず)の一派であろう。かつて最大の古墳、伝仁徳天皇陵などを造成したと思われる彼らの仲間が、現在の物集女町あたりにも移住したのである。
京都盆地において、いちばん早くに前方後円墳がいくつも造られたのは、乙訓地域であった。太秦(うずまさ)に秦(はた)氏が渡来し、活躍するかなり以前から、桂川右岸は山代(やましろ)国における経済や文化の最進地域であった。ちなみに山代はその後、山背そして山城へと表記がかわる。
この地、いまの物集女は当初「もず」と呼ばれたであろうが、その後の読みには毛都米や毛豆女が当てられ、「もずめ」「もづめ」に変化し、「ず」と「づ」は混乱している。そして中世には物集女村と呼ばれる。物集「もず」に女「め」が付くのは不思議だが、桓武天皇の生母である新笠や、外祖母の土師真妹という、ふたりの女人の影響を思ったりもする。
ところで余談だが、大枝の地は本来「おおい」と呼ばれていたという。その名残りが老ノ坂の「おい」であり、大枝や酒呑童子の大江山などの「おおえ」に変化している。
さて、この文は十数年前に書いたものです。今回は横着なリライト版です。実は先日、糸井通浩先生にお会いし、物集女のことが話題になりました。先生は元龍谷大学、いまは京都光華女子大教授。京都地名研究会の主宰者のおひとりでもあります。このときの話題がきっかけで、再録することにしました。
来週、糸井先生から物集女関係の資料コピーをいただく予定です。「もずめ」「もづめ」、「ず」と「づ」の混乱についての論文も、近々発表されるとのこと。また物集女の「女」について、古代の遊部、そして葬儀の泣き女・泣女・哭女との関連という示唆もいただきました。資料を頂戴するのが楽しみです。
※ 乙訓おとくに・大枝おおえ・神足こうたり・鶏冠井かいで・羽束師はずかし・向日むこう
<2010年1月16日 南浦邦仁> [206]