貞観津波は、平成東日本大震災によく似ているようです。青森、岩手および宮城県北部の三陸沿岸部は度々、大津波の被害にあっています。数十年に一度来襲すると言っても、過言ではありません。
ところが宮城県南部、男鹿半島の西部から仙台平野そして南に続く福島県浜通りにかけては、「大津波が来襲することはない」とふつう言われ続けてきた。だが貞観津波の記録『日本三代実録』や各地の伝承は、この常識に反するものであった。
そこではじまったのが、1990年からの発掘トレンチ調査である。まず開始したのが東北大学だが、箕浦幸治氏(東北大学大学院理学研究科教授)は「調査の結果、仙台平野が貞観津波に襲われたことは実証された」と2001年、実に10年前につぎのように記しておられる。
「仙台平野の海岸部で、最大9mに達する到達波が7~8分間隔で、繰り返し来襲したと推定された。福島県相馬市の海岸にはさらに、規模の大きな津波が来襲した」
災害制御研究センターの今村文彦氏らとの共同研究の地中分析による、客観的自然科学的な研究成果である。箕浦先生が成果を一般向けに発表したのは2001年、すなわち10年も前に、すでに指摘されていたのです。仙台平野のみならず、福島県浜通り沿岸部も、貞観大津波によって壊滅的な打撃を受けていたのです。
そして土中のトレンチ調査から、過去3千年間に3度、今回の津波が4千年間で4度目ですが、ほぼ千年に一度、巨大津波が宮城や福島などを襲っていたことが、証明されました。
箕浦先生は10年前、つぎのように記しておられます。
伝承や文献記録の内容がすべて真実であるとは限りません。しかしながら、1100年余の時を経て語り継がれた仙台平野での津波災害の発生には、幸運にも、津波の科学的研究を通して、文献と伝承の正当性が実証されました。こうした破壊的な災害には数世代を経ても、あるいは遭遇しないかもしれません。しかし、海岸域の開発が急速に進みつつある現在、津波災害への憂いを常に自覚しなくてはなりません。歴史上の事件と同様、津波の災害も繰り返すのです。
そして「貞観津波の襲来からすでに1100年余の時が経ており、周期性を考慮するならば、仙台湾沖で巨大な津波が発生することが懸念されます」
残念ながら、この警鐘は聴き届けられなかった。多くの人々にも、東京電力にも。あまりにも無念である。
次回「貞観津波 後編」は、産業技術総合研究所(産総研)の岡村行信氏が、2009年に経済産業省での委員会で述べられた津波の警告を紹介します。
ずいぶん長いワーキンググループ名ですが「総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員会 地震・構造設計小委員会 地震・津波、地質・地盤 合同WG第32回」。議事録を検証する予定です。
○参考書 箕浦幸治「津波災害は繰り返す」 東北大学発行「まなびの杜」第16号 2001年
なお、全文がネット上に公開されています。
<2011年5月15日>
※日本経済新聞5月28日。東北大学の研究チームは、貞観津波で内陸部に運ばれた砂や貝などの分布状況から、仙台平野での浸水域を分析し、海岸線から約 3.5キロまでと算出した。今回の浸水域は最大で 5キロ。当時の海岸線の確定はむずかしいとは思いますが。貞観地震の大きさは M 8.35と推定。仙台平野海岸部の津波高は、約 7mと算出した。<5月29日追記>
※産業技術総合研究所は、5月22日から開催された日本地球惑星科学連合大会で、貞観津波についての調査結果を報告した。産総研は3カ所での土壌から、津波が運んだ堆積物分布を調べた。仙台市若林区・宮城県山元町・南相馬市。堆積物内植物成分の放射性炭素からの年代測定から、4度の津波襲来を確認した。まず紀元前 390年ころ、西暦430年ころ、869年の貞観地震津波、1500年ころの津波。周期は 450年から 800年になる。<6月11日追記 南浦邦仁>










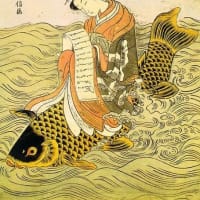



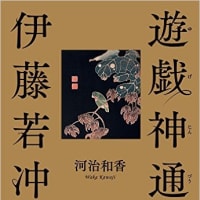





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます