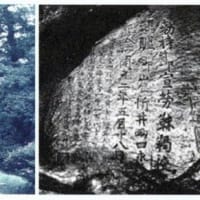間時代に成長の記
田 中 光 春
わたしの「戦後五十年の体験記」はへしまげられた人間成長の体験談である。
(一)
小学校二年(一九三六年)のとき、「修身」の授業でテストがあった。問題は五題ほどであつた。わたしは五間とも問題はやさしく全部正しく答えたと思いこんでいた。ところが先生から試験用紙をかえきれてみると一問だけペケ印がついていたぞれをそてわたしは「アレッ?」とおどろいた。ペケ印のついた問題は「さむいときあたたかくするにはどうしますか?」という設問であった。
わたしはすぐとなりの席の子の答えをみせてもらったぞこには「そとに出て体操をします」と書いてあった。わたしが書いた答えは「家のなかで、ふとんをしいてねます」。これで暖かになる。これがペケであった。
このペケにわたしは納得がゆかなかった。「体操する」も暖かくなるが、今日のような暖房のない当時としてはふとんをしいてねれば暖かくなるこれは確実であり、間違いないのになぜペケ印なのか?と思った。
このことからわたしは良い成績をとるには、正しいこと、本当のことを書いてもダメなのだ、先生が求めている答えを書かないとダメなのだと実感した。良い成績をとったり、人からほめられたりするには先生や上に立つエライヒトの言うことに合わせて物を言ったり、考えたりしないとダメなのだとさとった。
わたしは一九二九年 (昭和四年)に生まれた。わたしが二才のとき、わが「大日本帝国」は中国・東北の柳条湖で侵略戦争をはしめた。太平洋戦争の開始である。わたしが尋常小学校に入学した翌々年(一九三七年)に中国・華北の廬溝橋で戦争をおこし、侵略戦争は中国全域へ拡大する。そしてわたしが県立中学校に入学した年(一九四一年)に「大日本帝国」は米・英・佛・蘭に「宣戦布告」をし、ハワイ・真珠湾を爆撃して戦争を太平洋全域に拡大した。
わたしが生まれ育ったのは愛知県の太平洋に面した片田舎である。気候温暖なねむったような街である。ここで一九二九年から十六才までをすごした。いまも手もとにある小学校入学の記念写真をみると、三月生まれのわたしは口をポカンと開け無邪気な顔をして写っている。それが「小国民」、「軍国少年」に育ち上がってゆく。わたしが少しでも人間らしく育ちはしめるのは「大日本帝国」が戦争にやぷれた一九四六年からである。
わたしは小学校に入るまで文字を知らなかった。小学校一年に入学してはしめて文字を覚えることになる。文字を覚えるためにつかわれた教科書は「小学国語読本・巻一」尋常科用・文部省)である。この本の初めの方に出ている文章は「ススメ ススメ ヘイタイ ススメ」である。「ヒノマルノハタ バンザイ バンザイ」もある。それには色刷りの絵がでている。「サイタ サイタ サクラ ガ サイタ」もある。これらの文章でわたしははしめて文字を覚えた。文字だけでなく当然ながら、文字と一緒にこの文章から物事についての考え方や意識を身につけていった。今日の小学校一年の「国語読本」ではどんな文章が使われているのであろうか?
「尋常小学校修身書・巻二」(児童用・文部省)もあった.。最初に見開き二頁で東京・千代田の皇居二重橋からの天皇の行列の絵が色刷りで出ている。数頁後には東京・代々木の練兵場で白馬にまたがった昭和天皇の絵が出てくる。この絵には高い松の木が後方に一本立っている。これらには文章はついていない。
一年生担任の先生はどんな説明を子供達に行ったのであろうか?わたしなどがいまも忘れない「キクチコヘイ ハ テキ ノ タマニアタリマシタ ガ シンデモ ラッパ ヲ クチカラ ハナシマセン デシタ」もこの教科書に絵入りで出ている。この題目は「チュウギ」となっている。
(二)
わたしが小学校のとき(一九三五~四二年)は毎年、「四大節の儀式」があった。当日は学校の授業は休みであった。各家庭に「日の丸」の国旗を立ててから学校にくるように言われた。一月一日・四方拝、二月十一日・紀元節、四月二九日・天長節、十一月三日・明治節である。紀元節は神話の建国記念日であり、天長節は当時の天皇の誕生日、明治節は明治天皇の誕生日である(大正天皇はなぜか記念日がなかった)。
当日は学校の講堂に全児童が並んだ。白手袋に身をただした校長先生が天皇の「御眞影」(写真)を伏し拝み「教育勅語」をろうろうと読みあげた。「一旦緩急アレハ義勇公二奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ・・・」(教育勅語の中心的な一節)「皇運」とは天皇家の幸運のことである。わたしたち幼い子どもは一知半解で頭を下げて聞くのみであった。眼にみえるものは講堂の床と自分の足であり退屈なものであった。なにより鼻水がたれてきて因った鼻水をすすりあげる音があちこちでした。教員たちは「静かに、静かに」という眼つきで緊張していた。
そしてこの四大節の儀式では紺色の袴に白足袋をはいたおんな先生がピアノをひき、みんなで「君が代」を合唱した。「君が代は 千代に 八千代に さざれ石の いわおとなりて 苔のむすまで」この歌の趣旨は「天皇の御代(みよ) がいつまでも、つづくように」ということであり、この歌は当時も今も、また世界的にみても、国内的にみても天皇家のわがまま勝手の歌である。
この儀式を年四回、小学校の六年間に二十四回体験したことになる。
小学校の「唱歌」の授業では良いうたもあったがひどい歌があった。「君が代」もその一つであるが「海ゆかば」というのがあった。「海ゆかば みづく屍(かばね) 山ゆかば くさむす屍 大君(おおきみ)の へにこそ死なめ かえりみはせじ」。おおきみ、つまり天皇のために戦争で海・山のどこへ出かけて死んでも本望ですという歌である。小学生がこれに哀調をおびたメロデーをつけてうたった。天皇のために死ぬことを賛美する歌を堂々と、ことあるごとに繰り返してうたった。
(三)
小学校三年生の春(一九三八年)「図画」の授業で校外写生があった。みんなで校外に出てそれぞれに写生をするのはたのしい。たんばや森のむこうに山がみえていた。クレヨンをつかって写生した。
描きおえてあそんでいるとおとこ先生から「タナカ!」とよばれた。先生はわたしの描いた画面をさして「この画をよくみろ」と言った。画面には山なみの一番高いところに「日の丸」の旗が書かれたいた。『タナカ!あの山のどこにこんな「日の丸」の旗がたっているか?在りもしないものを書くナ。もっと真面目に書け』 とおこられた。
先生のいうとおり山に旗などたっていない。わたしが勝手に画面につくったのである。わたしは先生に云われてシユンとなりうなだれてしまった。校外写生の楽しさもあり、わたしは気持ちが高揚したまま、当時の「行け、行け進軍ラッパ」で「日の丸」の旗を山のうえに立ててしまったのである。わたしは、画は対象の在るがままに写し描くべきで、在りもしない余計なものを描くべきでないと痛感した。
後年、わたしは美術館で東山魁夷画伯の「白馬のいる風景」をみた。その端正な静謐にひきつけられた。それとともにわたしはその画面の森のなかに描かれている白い馬に執着した。実際には白馬がこんな池のはとりの森のなかにいるとは思えません。これは東山画伯の想いがつくった白馬であり、これが画面に緊張感を生んでいると思った。
自分の想いを対象と画材に託して描きだす画かきはわたしのなかで成長しませんでした。わたしの画かきは在るがままの対象を光と影、色と構図でつくる写真のような画かきとなった。自分の考えや想いを大切にし、仲間と論を交わしてそれを発展きせるなどということとは無縁な、上から言われることに当てはめて考える、そのことに集中努力する人間に成長した。その具体的な中味は「軍国少年」であった。
(四)
太平洋戦争が終わって二年ほど経過した一九四七年、わたしは十八才の労働者となっていた。職場の先輩から話かけられた。「田中君は、戦争中、学徒動員ではどこの工場で働いていたの?」、「小野田セメントですヨ」わたしは答えた。「ところで田中君、君はそこで給料をもらったの?」という質問である。わたしはこの問いに一瞬こたえられなかったごの質問はそれまでのわたしの常識をこえた質問であった。わたしは中学四年生(一九四四年)から授業は中止して毎日工場労働をした。(「一九四三年、学徒戦時動員体制確立要綱、一九四四年三月、決戦非常措置要綱二基ク学徒動員実施要綱」)。
わたしは一日も早くセメントをサイパン島などに送って戦争に勝つのだと思い、毎日、石灰岩を積んだトロッコを押して働いた。「給料をもらう」などということは全く頭になかった。わたしは先輩に答えた「給料をもらった記憶はありませんヨ」(その後の調査でも給料をもらったと答えた同級生はいない。他の工場ではもらったという人もいた)。先輩はきらに質問をしてきた。「それでは小野田セメントはそのセメントを国に寄付していたのかネ?売っていたのかネ?」この質問もわたしの常識をこえていた。そもそも勤労動員が売るだの買うだの商取引だという意識は全くなかった。先輩は「売っていたんだよナ田中君」と指摘した。いわれてみればその通りだとわたしは初めて気づいた。
後年しらべてみると小野田セメントもその傘下にあった三井合名会社や三菱合資会社などの財閥(持株会社)は太平洋戦争の末期まで大きな利益をあげつづけている。例えば三菱商事は一九四一年から一九四五年三月まで毎期十一%の株式配当を維持している(一九八六年、三菱商事社史)。
わたしは一つの物事に自分の考え以外のほかのいろいろな考え方があることを知り自分の無知に驚いた。事実に即して自分の頭で考え、自分の考えをもたないと又だまされると思った。わたしは教条主義の思考と皇国史観にこり固まっていたのだ。
今日でもわたしは頭では唯物弁証法の考え方が正しいと理解しているが実際にやることは教条主義的で、またなにごとにつけすぐ秩序立てることが好きで困っている。