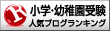開智特有の授業=「パーソナル」
昨日の校長の話にも出てきましたが、「個」に焦点をあてる開智の方針に沿った授業です。
開智のHPには、こう書いてあります。
パーソナルの授業は、こどもたちが学習したいこと、学習しなければならないことを自分で考え、自分で学習する時間です。
この授業でこどもたちは学習習慣を身に付け、自分の教科学習の弱点を補い、得意な分野をさらに伸ばす学習をします。
最終的には自分の学力をしっかり捉え、長期的な展望に立った学習計画をたてられるようになります。
このようにパーソナルの授業で「主体的に学ぶ」「学び方を学習する」ことによって、受身でない、主体性のあるリーダーが育つのです。
現在、1年生で週4コマの「パーソナル」の時間があります。
「生活」でも2コマなので、4コマと言えば、けっこうな時間を費やします。
先日の保護者会では、何をしたいのか子どもとよく話して欲しい、という説明がありました。
でも、子ども自身も、イマイチ、何をしていいのかイメージがわかないのでした。
1年生はまだほとんど授業が進んでいない。
一体何を勉強させればいいの
…というのがママたちの本音。
しょうがないので、うちは、入学準備でやっていた算数と漢字のプリントをまたやろうか、ということになり、とりあえずコピーして先週持たせたのです。
…でも、なんか違う気がしたんですよねー
そこで、本屋さんに行って「何かないかなー」とぷらぷら探していたら…
ありました
良いものを見つけました
 「辞書引き学習」ってヤツです。
「辞書引き学習」ってヤツです。
立命館小学校の深谷圭助現校長が考案されたもので、好きな言葉を辞書で調べて意味を書いたり、辞書からいろんな言葉を集めたりして意味を調べたりするものです。
…で、それだけ聞くと、「えーっ、めんどくさー」ということになってしまうのですが…そうならないよう、子どもが楽しめるような工夫がされています。
それは、「付箋(ふせん)」
あの、メモや伝言を書いてペタッとはるもの。
調べた言葉には番号を付けて、調べたという印に付箋をはりまくるのです。
辞書は見る見る付箋だらけになってさらにぶ厚くなるのですが、これが子どもの達成感になるのですね
子どもは自ら調べたいものを考え、見つけ、調べます。
たとえば、今日は「赤いもの」を辞書で引いてみようと決め、まず自分の思いつくだけの「赤いもの」を集め、辞書で調べ、ノートに書きます。
小学生の場合は「小学国語辞典」みたいな、ルビのふってあるヤツがいいでしょうね。
イチゴ、りんご、トマト、ポスト、血、カーネーション…etc
その調べた言葉は付箋に書いて、辞書のそのページにはるのです。
他にも、その言葉を使って文を作ってみたり、いろいろな勉強法が考えられますね。
うちの娘。
以前、百金で色とりどりの付箋をおねだり…
理由を聞いてみると、私が仕事でよく付箋を使うものだから、それを見ていて自分もやってみたくなったそう。
「折り紙辞典」で挑戦して折れたもののページに付箋を貼ることを自分で思いついたらしいのです。
折り紙の折り方って、難しいものになると大人でも説明見てもイマイチよくわからなーい、ですよね
だから、できたらおもいっきりほめまくります
すると、娘は大喜びで、できたページに付箋をペタペタ…
で、そのカラフルな「ぴろぴろ」を見て悦に入る
これだ
私が進学塾に勤めていた10年間。
その間、小学生や中学生の子どもたちの国語力は、階段状にみるみる落ちていきました
子どもたちは、毎年、毎年、作文が書けなくなっていったのです。
だから、受験に対応できる国語の読解力や記述力をつけさせるのは、並大抵のことではありませんでした。
その進学塾は当時、東京の「男子御三家」まで引率して受験させていたので、御三家対策とかもやっていました。
武蔵の国語なんてハンパじゃないですよ。
答えは全て記述式ですから…
あれに対応できるだけの記述力を、たかが小学高学年の数年間で身につけさせるのは至難の業でした
そんな若かりし時もあったなぁー…
なつかしいなぁー…
もう20年くらい前の話ですぅー
あのときの6年生は、今は、もう2児のパパくらいになっているんでしょうねぇ
もし、娘が「辞書引き学習」を続けることができたら、すごい語彙力が身につくと思います。
語彙力だけでなく、正確な知識が身につくし、世の中のこともだんだんわかってくることでしょう。
それが文章を書く力にもつながっていくはず。
昨日の校長の話にも出てきましたが、「個」に焦点をあてる開智の方針に沿った授業です。
開智のHPには、こう書いてあります。
パーソナルの授業は、こどもたちが学習したいこと、学習しなければならないことを自分で考え、自分で学習する時間です。
この授業でこどもたちは学習習慣を身に付け、自分の教科学習の弱点を補い、得意な分野をさらに伸ばす学習をします。
最終的には自分の学力をしっかり捉え、長期的な展望に立った学習計画をたてられるようになります。
このようにパーソナルの授業で「主体的に学ぶ」「学び方を学習する」ことによって、受身でない、主体性のあるリーダーが育つのです。
現在、1年生で週4コマの「パーソナル」の時間があります。
「生活」でも2コマなので、4コマと言えば、けっこうな時間を費やします。
先日の保護者会では、何をしたいのか子どもとよく話して欲しい、という説明がありました。
でも、子ども自身も、イマイチ、何をしていいのかイメージがわかないのでした。
1年生はまだほとんど授業が進んでいない。
一体何を勉強させればいいの

…というのがママたちの本音。
しょうがないので、うちは、入学準備でやっていた算数と漢字のプリントをまたやろうか、ということになり、とりあえずコピーして先週持たせたのです。
…でも、なんか違う気がしたんですよねー

そこで、本屋さんに行って「何かないかなー」とぷらぷら探していたら…
ありました

良いものを見つけました

 「辞書引き学習」ってヤツです。
「辞書引き学習」ってヤツです。立命館小学校の深谷圭助現校長が考案されたもので、好きな言葉を辞書で調べて意味を書いたり、辞書からいろんな言葉を集めたりして意味を調べたりするものです。
…で、それだけ聞くと、「えーっ、めんどくさー」ということになってしまうのですが…そうならないよう、子どもが楽しめるような工夫がされています。
それは、「付箋(ふせん)」
あの、メモや伝言を書いてペタッとはるもの。
調べた言葉には番号を付けて、調べたという印に付箋をはりまくるのです。
辞書は見る見る付箋だらけになってさらにぶ厚くなるのですが、これが子どもの達成感になるのですね

子どもは自ら調べたいものを考え、見つけ、調べます。
たとえば、今日は「赤いもの」を辞書で引いてみようと決め、まず自分の思いつくだけの「赤いもの」を集め、辞書で調べ、ノートに書きます。
小学生の場合は「小学国語辞典」みたいな、ルビのふってあるヤツがいいでしょうね。
イチゴ、りんご、トマト、ポスト、血、カーネーション…etc
その調べた言葉は付箋に書いて、辞書のそのページにはるのです。
他にも、その言葉を使って文を作ってみたり、いろいろな勉強法が考えられますね。
うちの娘。
以前、百金で色とりどりの付箋をおねだり…
理由を聞いてみると、私が仕事でよく付箋を使うものだから、それを見ていて自分もやってみたくなったそう。
「折り紙辞典」で挑戦して折れたもののページに付箋を貼ることを自分で思いついたらしいのです。
折り紙の折り方って、難しいものになると大人でも説明見てもイマイチよくわからなーい、ですよね

だから、できたらおもいっきりほめまくります

すると、娘は大喜びで、できたページに付箋をペタペタ…
で、そのカラフルな「ぴろぴろ」を見て悦に入る

これだ

私が進学塾に勤めていた10年間。
その間、小学生や中学生の子どもたちの国語力は、階段状にみるみる落ちていきました

子どもたちは、毎年、毎年、作文が書けなくなっていったのです。
だから、受験に対応できる国語の読解力や記述力をつけさせるのは、並大抵のことではありませんでした。
その進学塾は当時、東京の「男子御三家」まで引率して受験させていたので、御三家対策とかもやっていました。
武蔵の国語なんてハンパじゃないですよ。
答えは全て記述式ですから…
あれに対応できるだけの記述力を、たかが小学高学年の数年間で身につけさせるのは至難の業でした

そんな若かりし時もあったなぁー…
なつかしいなぁー…
もう20年くらい前の話ですぅー

あのときの6年生は、今は、もう2児のパパくらいになっているんでしょうねぇ

もし、娘が「辞書引き学習」を続けることができたら、すごい語彙力が身につくと思います。
語彙力だけでなく、正確な知識が身につくし、世の中のこともだんだんわかってくることでしょう。
それが文章を書く力にもつながっていくはず。