
申京淑がこの5月に刊行した小説「どこかで私をよぶ電話が鳴って(어디선가 나를 찾는 전화벨이 울리고)」は、期待を裏切りませんでした。
あまりネタバレにならないよう心しつつ紹介します。
大学の教室の外から集会の音声が聞こえてくる。授業の終わり際、窓の外を見つめていたユン教授はふり向いて学生たちに問う。「君たち、クリストフという人物の話を聞いたことがあるか?」。
女子学生チョン・ユンは「ジャン・クリストフ」は読んだことがあったが、教授の語ったクリストフは、キリスト教伝説中のクリストフだった。
カナーン出身の大男クリストフは、真に仕えたいと思う人物に巡り合えぬまま、川べりに家を建て、旅人を無償で向こう岸に背負って渡すことを始めた。ある夜、一人の子どもの頼みで、その子を背負って川に足を踏み入れる。ところが、軽いはずの子どもがだんだん重みを増し、ついには異様な重さとなってクリストフは川に流されて死ぬかも知れないとまで思う。
やっとの思いで対岸にたどり着くと子どもは消え、眼前にイエスが現れ、そして言う。 「クリストフ、おまえが今背負ったのは子どもではなく私、キリストだ。おまえが川を渡った時背負っていたのはこの世のすべてだったのだ」。
語り終えてしばし沈黙した後、ユン教授はふたたび口を開く。
「では、ここでひとつ質問をする今ここにいる君たちはクリストフなのか? 背に負われた子どもなのか?」
ユン教授の原稿のタイピングを志願したチョン・ユンは、教授の研究室で男子学生イ・ミョンソと、その女友だちユン・ミルを知る。あとでわかるのだが、2人は幼なじみで、少し前までミルの姉も含め3人で同居していた・・・。
チョン・ユンにもタニという名の気心の知れた幼なじみの男友だちがいる。
・・・・この4人が主な登場人物です。
地方出身のチョン・ユンは自分の住むトンスン洞のオクタプパン(屋塔房)を起点に、ソウルの街ここかしこを日々歩いて廻る。しかしある日、集会・デモの鎮圧に巻き込まれ、鞄も靴もなくして途方に暮れていると、思いもかけず「チョン・ユン!」と呼ぶ声が・・・。
この偶然を契機に、主人公たちのコミュニケーションが深まってゆき、また彼らの過去も徐々に明らかになっていきます。
小説はチョン・ユンの視点から描かれていて、その中にミョンソの手記が挟まれているという体裁で、政治的・社会的背景は詳しく書き込まれてはいませんが、申京淑自身が学生だった当時、すなわち80年代の民主化闘争の時代状況が色濃く感じられます。
その中で、青春期真っ只中の男性2人女性2人。当然恋愛の要素もありますが、それがメインというわけではありません。ある書評には「青春小説であり、成長小説であり、恋愛小説である・・・」とありました。
物語は、彼らの大学時代だけでなく、その何年も後まで描かれているという重層的な構えになっています。
この本の帯に記されている文芸評論家シン・ヒョンチョルの評を引用します。
「自身の生を、同僚の死を、さらには共同体の運命を背負わなければならなかった一時代の<クリストフ>たちがここにいる。4人の青春が、ガラス瓶に入れて流された手紙が今の青年たちの心に無事に届くように。彼らのつらい時間に戻るのではなく、そのつらさを忘れることなく、ついにはつらさのない時間の方へ歩んでゆくために。」
申京淑はこの本のあとがきでも、また「東亜日報」のインタビュー記事でも、90年代以降の韓国の若者が主に日本の小説を読んで成長してきたという現実を口惜しく思って、「青春の感受性を代弁する、品格ある韓国小説を作るため文章もできる限り韓国語の美しさを生かして、正確に書こうと念を入れた」と述べています。
少し前、このブログで「韓国は日本の24年遅れ」という俗説(?)を開陳したところ、さる方から「韓国人の友人たち(30代)が育ってきた環境、傾向がどうも私の両親の世代(今の50代)と似ている」とのコメントをいただきました。
たしかに、この小説を日本の全共闘世代が読むと遠い40年前のもろもろを、さまざまな感情を伴いつつ思い起こすのではないでしょうか? ただ、韓国の386世代と比べると学生時代ははるか昔だからかなり風化しているかもしれませんが・・・。
さて、申京淑が若い世代に投じたこの小説、反響はどうでしょうか? ヌルボの感想は、なんともまあ、重い直球で勝負したなあ、ということ。日本の作家が読まれているのは、その軽さとエンタテインメント性ゆえ。それを知りつつ、20数年前の感性を霧消させることなく、その後の省察を加えてよく作品化したものです。したがって、「重い」です。先に掲げたクリストフの物語のように、当時の青年たちは時代の重さを背負わざるを得なかった、あるいは自ら背負おうとしたわけですから・・・。
実際、YES24等のサイトで読者の感想を見ると、高評価が多い中で、「重い」の一語で★3つという評価もありました。
ただ、決して思弁的で難解な作品ではありません。この人たちの関係はこれからどう展開するのだろう、というドラマ的興味も喚起されたり、また「えっ、そういうことだったの!?」というオドロキも何ヵ所かあって、全然退屈することなく読み通せました。
あの闘争の時代に、たとえば命を落とした青年、あるいは当時の若かった自分自身の心情が込められた、まさに「ガラス瓶に入れて流された手紙」のような小説です。
この小説のタイトルにある、「どこかで私をよぶ電話・・・」も、そんな過去からの声なのかもしれません。
※ユン教授の語るクリストフについては、ウィキペディアの<クリストフォロス>の項目参照。
※この小説には、主人公たちが住んでいたり、歩いたりするソウルの地名がいろいろ出てきます。3月17日の記事で紹介したDAUMの中のロードビュー(←韓国版ナンチャッテStreetView)で町のようす等を見ることができますが、20年以上前と今とではかなり変わっているはず。
※主な登場人物(?)の中にネコのエミリー・ディキンソンも入るかもしれません。<ターキッシュアンゴラ>というこの猫は左右の目の色が違うことが多く、また「青い目のある側の耳は聞こえない(右目が青ければ、右耳が聞こえない)」とか。エミリー・ディキンスンは全然聞こえない。
※申京淑の他のいくつかの作品同様、「もしあの時自分が○○していれば××だったのに・・・」という悔恨、そして深い雪の場面は、この小説にもみられます。












![韓国内の映画の興行成績 [8月11日(金)~8月13日(日)] ►「コンクリートユートピア」は期待してよさそう! ►日韓の港町のヤクザ文化(?)と「野獣の血」等のこと](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6a/11/92d870b3e7abfcf50b59506f39b0cba6.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月28日(金)~7月30日(日)] ►「密輸」に続いて「ザ・ムーン」が公式公開前に10位にランクイン ►<サメのかぞく体操>って知ってますか?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/c5/5e7496d2812629ef25604c3e9779b3f4.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月21日(金)~7月23日(日)] ►期待できそう! リュ・スンワン監督の新作「密輸」 ►最近観たドキュメンタリー「世界のはしっこ、ちいさな教室」は良かった!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/a0/12b1fedcdd7d44e3b5ae4cdde7c52ed4.jpg)
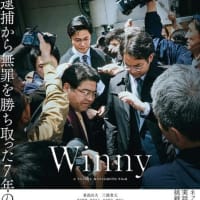
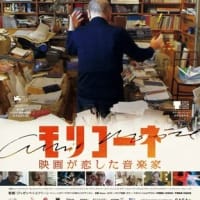
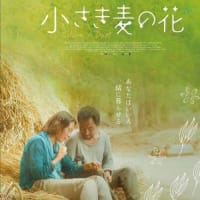
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/97/23df6cbf19458fe4f08e5af9d4969562.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/58/a7/37839be4ca432b6c9dabb103a6fa31b6.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/71/b9/cb7ffe184f0640f4c629be5ba1de9724.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [6月30日(金)~7月2日(日)] ►韓国映画「君の結婚式」の中国版リメイク、韓国で上映! ►ウェス・アンダーソン監督の新作「アステロイド・シティ」、期待していいかな?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/00/81/b0850e17282a4b2ef3dd13867cfce7de.jpg)






はじめまして。。日本の386世代、京城蒼月倶楽部の管理人のtorakoと申します~
昨日、ふとした検索でこちらにお邪魔して、翌日の仕事に差し支えるほど?過去記事を順番に熟読させていただきました。
すると光栄なことに、我が徒然のつぶやきをご紹介いただいている記事を発見!
さまざま、かつミーハーな動機ながら、隣国の文学や歴史文化に心惹かれている日常を過ごしてはおりますが、残念ながら、ご紹介いただいた本を自由に読みこなす語学力はありません。でも、記事を拝見して、次に韓国に行った時はぜひ入手し、少しずつでも読み進めたいと思いました。
そして我が国と彼の国の同じ世代が背負っているものの「共通性」と「違い」について、自分に置き換えて考えてみることができたら…などと思っています。また、お邪魔させてくださいね~
これからもよろしく・・・。