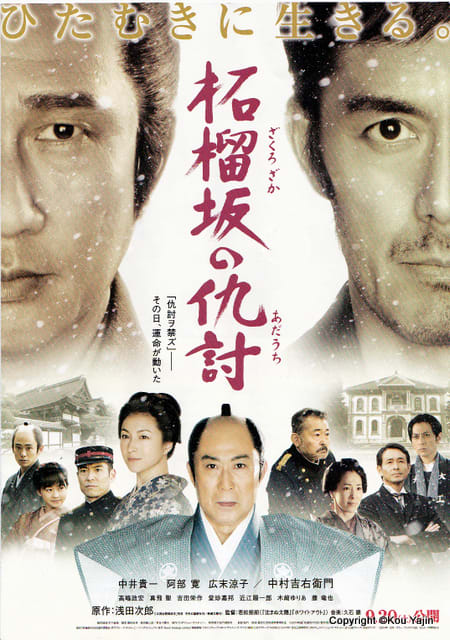秋・・・。
雲の峰が湧きたち、夜に入ってから雷の後に驟雨があった。

ここ二日間、比較的過ごしやすい湿度だ。
肌合いはサラッとしている。
朝寝の快適な事・・・。
昼寝の健やかな事・・・。
午後寝の不謹慎なほど爽やかな事・・・。
要するに、24時間過ごし易いのである。

「秋の雲猛々しくも地から湧く」

雲の峰である。
重厚で、侵し難い領域が広がっているのだ。
秋・・・雲の峰の見頃である。
秋・・・誰でもが詩人になれる季節。
秋・・・時間は静かに移行していく。
秋・・・風が生まれる時が見えるのだ。

夕方、光芒が空を覆った。
ダ・ヴィンチが筆の先を刺したようである。
荒 野人
雲の峰が湧きたち、夜に入ってから雷の後に驟雨があった。

ここ二日間、比較的過ごしやすい湿度だ。
肌合いはサラッとしている。
朝寝の快適な事・・・。
昼寝の健やかな事・・・。
午後寝の不謹慎なほど爽やかな事・・・。
要するに、24時間過ごし易いのである。

「秋の雲猛々しくも地から湧く」

雲の峰である。
重厚で、侵し難い領域が広がっているのだ。
秋・・・雲の峰の見頃である。
秋・・・誰でもが詩人になれる季節。
秋・・・時間は静かに移行していく。
秋・・・風が生まれる時が見えるのだ。

夕方、光芒が空を覆った。
ダ・ヴィンチが筆の先を刺したようである。
荒 野人