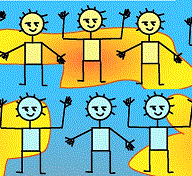「自閉スペクトラム症」についての非常に不毛な論争が長らくあった。例えばスティーブ・シルバーマンが『自閉症の世界 多様性に満ちた内面の真実』(ブルーバックス)にそれを描いている。病因が遺伝なのか環境なのかの論争である。環境派は、さらに、母親が冷たいからか、それとも甘やかしたからかに分かれる。
なお、シルバーマンの本の原題は、”NeuroTribes: The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity” だから、シルバーマンは私と同じく「自閉スペクトラム症」は病気でないとの立場であろう。
シルバーマンの本を読めば、すぐ、わかるのだが、親がお金持ちであれば、その子が社会と関係を持たず、一人で好きな研究をやっていても、幸せに一生を送ることができる。シルバーマンは、万有引力定数をはじめて測定し、地球の質量を決めたヘンリー・キャヴェンディッシュを例としてあげている。
「自閉スペクトラム症」の問題は、金持ちでない親からみれば、「身勝手で自己中」ばかりの社会をこの子は生きていけるかの悩みである。身勝手で自己中なのは、子どもでなく、社会の大人たちなのだ。
シルバーマンの本によれば、そのような親の気持ちを手玉にとって、自閉症を治せると子どもを預かり、かえって子どもを廃人にする療育センターが米国にあったという。そうでなくとも、母親が悪いとなじるだけの精神分析医やセラピストが多いともシルバーマンが本で書いている。
最近読んだ『分子脳科学: 分子から脳機能と心に迫る』(DOJIN BIOSCIENCE、化学同人)の18章で、内匠透は、「自閉スペクトラム症」は間違いなく遺伝が病因で、薬で治せるはずだが、複数の遺伝子が複雑に絡んだ発現過程であるらしく、いまだに特定できていないと書いている。これって、遺伝であるかどうか、いまだにわかっていない、と言っていると同じではないか。
一方、遺伝子が同じでも、ばらつきが生じることがクローン技術の実験からわかってきた。有性生殖と異なり、クローン技術で、まったく同じ遺伝子の子どもを作れるのである。
2001年になって猫のクローンが作成されるようになったが、驚いたことに、遺伝子が同一なのに、成長したクローン猫たちの体毛の模様は異なることがわかった。さらに、クローン猫たちの性格もそれぞれ異なっていた。
したがって、遺伝子を特定するより、子どもを薬で治そうと思うよりも、まず、多様性を認め、長所を伸ばし、親や他の隣人と共存していけば良いのだ。これが、シルバーマンの言う「ニュロー諸族」の未来のあるべき姿だと思う。
ところが、先ほどの内匠透は、勝手に「患者本人だけでなく、その家族やさらには社会の負う経済的、心理的マイナスは莫大なものになる」と言い切り、「自閉スペクトラム症」治療薬の開発にのめり込んでいる。大きなお世話だ。
NPOでの私の担当する子に、学校からみんなでディズニーランドに行くより、学校で勉強しているほうが好きだという子どもがいる。薬を開発し、みんなとディズニーランドに行きたいと言わせることが、そんなに素晴らしいとは私には思えない。