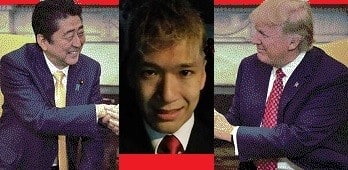2018年6月12日に朝日新聞がドイツの哲学者マルクス・ガブリエルを招いて、民主主義の危機についてのシンポジウムを行った。そのとき、彼のおこなった基調講演『危機に瀕する民主主義』で、次のような一節があった。
《古代ギリシャの民主主義がなぜ失敗したのかについて話しましょう。簡単に言えば、その民主主義が「みんなのための」民主主義ではなかったからです。当時は奴隷がいました。奴隷は、民主主義の基本的な理念と矛盾しています。奴隷は奴隷所有者のために働くことを義務付けられており、自分のしたいことを行うことができません。こうしたエリート主義的なシステムでは民主主義は実現しませんでした。》
じつは、「古代ギリシャの民主主義が失敗したか」は自明ではない。M. I. フィンリーは『民主主義 古代と現代』(講談社学術文庫)で、ギリシャの民主主義が200年安定して続いたという。この民主主義を実践した民衆(デーモス)は、教育を受けた上層階級のひとびとは少数で、多くは、市民であった農民、小売商、職人たちであった。アテナイの民主政治は直接民主制であり、民会とは、何千もしくは何万の18歳以上の市民からなる野外集会であったという。
だからこそ、プラトンが靴職人や船大工が国政に参加すべきでないと『国家』(岩波文庫)でいうのだ。プラトンは、教育を受けたエリートが統治すべきと考える立場であった。
民主主義かエリート主義かは、昔からある争いである。「民主主義」という考え方に根本的な欠陥あるというより、自分が優秀だから他の人たちを支配できるというエリート主義者と、人が人を支配することを拒否する民衆(デーモス)が争っており、民主主義の危機はエリート主義者によって引き起こされる。
バートランド・ラッセルは、古代ギリシャの民主制は、王制派との血みどろの戦いによって、ようやく実現されたものである、と『西洋哲学史』(みすず書房)に書く。古代アテネがスパルタに負けたことで、アテネの民主主義が崩れ、プラトンのようなエリート一族がスパルタの後押しでアテネの政治舞台に躍り出たのである。民主制が古代ギリシアで始まったときは、奴隷にたよった社会ではなかった。
プラトンは口の立つものが民主制から独裁制に導くと『国家』で言っているが、注意深く読むと、民主制のもとで「自由」のため貧富の差が拡大して争いが生じ、私兵を集めるようになり、口の立つものが私兵の力で、民主制を覆すと書いている。
プラトンの言い分では、人のもつ強欲が民主制を覆すと言っているだけで、自分の立場を正当化するために人の強欲性を肯定している。抑圧される立場からすれば、こういう言い分は、たまったものではない。
戦後、日本で、敗戦で「棚ぼた」のように得られた民主主義が後退したのは、第1に労働運動の弱体化、第2にいわゆる「東西冷戦終結」による国際バランス崩壊に起因する。
労働運動の弱体化は、石炭から石油への転換を名目に、国策として全国の炭鉱を閉鎖し、もっとも強力だった炭鉱労働組合を解散させ、ついで、国有鉄道の民営化を強行し、国鉄労働組合を抜けることを条件として、JRへの再採用を行った。また、公立学校の職員に階級制を導入し、教職員組合の弱体化を図った。日本は、エリート主義者が政権を握りしめ、計画的に民主主義の基盤を崩してきたのである。
北海道大教授の吉田徹が、「東西冷戦終結」を民主主義の勝利のように語るが、ソビエト連邦の崩壊は、エリツィンとプーチンの独裁政権をロシアに生みだし、世界中の金持ちは金持ちにとって都合のよい政治を露骨に押すようになった。これが、トランプやブルームバーグが政治の舞台に出てくる背景である。
民主主義はそのために戦うものがいなくなれば、崩壊するのはあたりまえで、民主主義はそれを求めるものの努力によって維持されるのである。