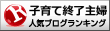先日の、ドビュッシーの前奏曲集第一巻「帆」に続いて、
前奏曲集第一巻⑧「亜麻色の髪の乙女」のお話をします。
(島谷ひとみさんの大ヒット曲ではありません。)
亜麻色の髪をした乙女のかぐわしい香りが匂い立つような美しい旋律でできています。
すがすがしい感じで、親しみやすい曲です。
この曲は変ト長調で作られていますが、親しみやすく感じる秘密は
7つから5つに音の数を減らしているからなのです。
①ソ♭ ②ラ♭ ③シ♭ ④ド♭ ⑤レ♭ ⑥ミ♭ ⑦ファ の7つの音から、
④ド♭ ⑦ ファの2つの音を減らして作られているのです。
5音音階を利用してつくられているこの曲は、冒頭から5音音階で始まっています。
19小節からも5音音階になっています。
ドビュッシーは、この曲をスコットランド民謡の「スコットランドの歌」という詩から着想を得て
取り入れて作ったそうです。
日本の演歌や民謡なども5音音階なので、日本人にも耳障りがよく、なじみ深く
親しみやすいのだそうです。
ドビュッシーは作曲家として無名だった頃、
パリ万博(1889年)で東洋の音楽に初めて触れ感動したそうです。
ジャワのガムランの単純な音の構成の中に
豊かな響きを生み出す、この異国の音楽に不思議な感動を覚えました。
彼は、
「ジャワの音楽には、あらゆるニュアンスが含まれている。
そこでは西洋音楽の規律など子供のお遊びのように思える。」
と語っています。
ドビュッシーは、そんな東洋音楽との出会いがあって、
今までの西洋音楽にはないあらたな響きの世界つくりだしていくことになるのですね。
ドビュッシー「亜麻色の髪の乙女」MIDOはこちらです。懐かしいような響きの曲です。
夏の明るい陽をあびて
ひばりとともに愛をうたう
桜桃の実のくちびるをした美少女
(ルコント・ド・リール「スコットランドの歌」『古代詩集』)
ドビュッシーは、この曲を、ルコント・ド・リールの詩のなかの少女(亜麻色の髪の乙女)に捧げたそうです。
“普段、私達が耳にする音楽の大半は、ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シの7音を基本とする7音階です。
それが、5つの音しか持たないのが5音音階。
その5つとは、ド・レ・ミ・ソ・ラです。
この独特の音階によって、素朴さ、懐かしさが生まれてくるわけです。
実は、世界の民族音楽のほとんどがこの5音音階。
つまり、人類の音楽の原型が5音音階なのだといえますね。
だから、この音階だと、独特の素朴さ、懐かしさを感じることにつながるのでしょう。
実際、日本の演歌、民謡もそうですし、童謡と呼ばれるものの大半も5音なんですね。
例えば、童謡の「夕焼け小焼け」、「めだかの学校」などです。
音階の力って不思議ですね
また、いくら5音音階だから、と理論的なことをいっても、
良い曲というのは、感覚的に心に残ります。良いと感じられますよね。 ”
ー以上、いろいろな文献を元に書かせていただきました。
にほんブログ村に参加しています。
宜しければワンクリックお願いします。
↓ ↓