宍粟50名山ファンクラブ登山会へ参加し、△高峰へ登りました。
草木坂登山口
初めからの急登をやり過ごし、ふと振り返ると集落がもう下に見えました。
明瞭な道標
急登を経て尾根を詰めました。
朝陽の登山道は新緑で爽やか


△高峰845m 登頂。
(中)御形神社の社有地一反歩を示す石柱がひっそりとありました。
△三等三角点
点名:高峰
標高:844.66m
周囲:山頂
頂上から林道までは緩やかな自然林の下りでした。

△四等三角点
点名:受信塔
標高:613.53m
周囲:小さなピーク
保護石:5個
方角:南
埋標:昭和48年9月15日
☆NHKアンテナ塔から尾根沿いの小さなピークに、埋標されていた四等三角点です。
点の記には「保護石4つ」とありましたが、実際は5個。守られて幸せそうな標石でした。
林道を歩きながらも、GCの方々が樹木や植物についてお話をして下さいます。
斜面に鹿の骨もありました。「角(つの)の一つの枝分れが一歳、ということです、これは三つの枝分かれだから三歳かな。」
「藤など、蔓(つる)の巻き方はたいがいが右上がりに巻いていきます、野田藤は・・・」
単独行では得られない知識がいただけて、今回も充実の山行でした。
2015.4.29(水)*みどりの日* △高峰(宍粟50名山) 845m
△高峰(宍粟50名山) 845m
行程往路 家=神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=R29=県道6号線=JAサンパティオ集合=(マイクロバス)=百千満家=草木登山口―△高峰―NHK電波塔―林道―JAサンパティオ
復路 往路に同じ
地図:宍粟50名山ルートマップ [34] 高峰
1/25,000地形図:
☆久しぶりに大人数のパーティで歩く山行に参加しました。
口下手な私ですが、少しづつ色々な方とお話をするうちに気持ちが打ち解けて
時にはこういう山登りも良いなあ・・・と思いました。
登山歴の長い方々や、50名山は2巡目、3巡目、という方もおられて、
若輩者の私は感心しきりでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
二年前の4月28日(みどりの日)は、同登山会の「杉山・笠杉山」登山がありました。
当日、集合場所に車を停車してまもなく、携帯電話へ夫から連絡が入り、父の訃報を知らされました。
近くで待機しておられたGCの方に急な欠席の旨を伝え、Uターン。
登山口から林道を経て29号線、IC、高速・・・動転しながらも帰路を急ぎました。
あの日も新緑の山々が目に痛いほど眩しかったなぁ・・・
山を歩きながら、穏やかな気持でこの二年の経過を思いました。
帰路の道すがら、「新戸倉スキー場」の入り口に気付き、
少し寄りました。
いつの間にか閉鎖していた様です。
廃校とか、廃坑とか、廃スキー場とか、役目が終った施設になぜか惹かれます。


建物はいつか朽ち、滑降斜面は年数をかけて少しずつ自然(山)に
戻っていく・・・
雪深い波賀地区はヤマザクラが盛りで、静かにゲレンデを見守っていました。
宍粟50山の△藤無山から△銅山を縦走、往復しました。
県道48号から県道251号へ入り、林道を登山口Pまで
上がりました。
△藤無山 沼谷登山口の標柱
ここに車をP
尾根に乗ると、道標がしっかりとあり、安心。

△藤無山 1139.2m 登頂
△二等三角点
点名:三本杉
保護石:無し
方角:南
周囲:頂上
☆眺望の良い広々としたピークですっかりくつろぎ過ぎ、慌てて銅山へ向かいました。
写真の枯れ草の斜面を急降下し、尾根伝いに銅山を目指しました。
尾根に点々と埋まる境界杭が道案内

△銅山 954m 登頂
△三等三角点
点名:筏
保護石:無し
周囲:頂上
方角;南
☆木々の間から西側の眺望がわずかに得られました。
寸暇の休憩を取り、すぐに引き返しました。
☆ △銅山から△藤無山への登り返しが急登で、ちょっと気合いが要りましたが、
無事に往復できたので満足!

☆公文川のせせらぎは冷たくて美味しい水でした。
2015.4.26(日)
 △藤無山(沼谷登山口ルート)-△銅山 縦走・往復
△藤無山(沼谷登山口ルート)-△銅山 縦走・往復
行程:往路 神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=R29=県道48=県道521=沼谷登山口標柱P
―藤無山 谷コース―△藤無山―△銅山―△藤無山―(谷コース)―登山口P
復路:往路に同じ
出発 10:50~下山16:00 (休憩:1h)
今日の歩数:28,500歩(家ー登山―家)
参考地図:宍粟50名山 ルートマップ
1/25,000 地形図:
☆二山を繋いで縦走出来て充実した山行でした。
尾根伝いのルートは終始明るく、大展望のトレイルでした。
つきましては、宍粟50山GCのたく さん、メ~さんの山行記録から
参考にさせていただき、とても助かりました。
晴れ渡る青空の下、まだ残雪の氷ノ山や宍粟の名峰が
眺望出来ました。
ブナ林に新緑が繁る頃、また一段と美しい景色に変わることでしょう。
新緑に誘われて市民の森を歩いてみました。


父がよく幼い長男を連れて来た公園です。
遊具で遊ぶ長男を、少し離れた所から父がスケッチしていたっけ。
そんなことが懐かしく思い起こされました。
二十年前と変わらない風景ですが、もうあの頃は二度と来ないんだなぁ・・・
と、あらためて思いました。
父の三回忌で帰省しました。
実家で目覚める朝はいつものコースで散歩をします。
こちらも畑は夏の準備。
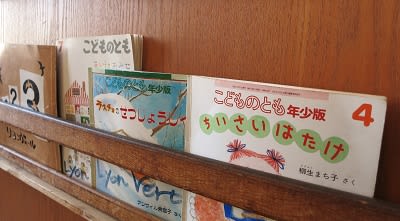
リヨンベールさん(ベーカリー)でお昼のパンを買います。
カフェスペースのラックには「こどものとも」(絵本)
最後の目的地はもちろんこの公園。
すっかり桜も新緑
今日は娘が通う幼稚園の入園式です。
念願叶い、この春から娘は幼稚園の先生になりました。
おこがましくも年少組の担任を受け持つことになり、
ここ1ヵ月は準備に追われる日々だった様です。
今日、娘が初めて対面する26人の可愛い園児さん達は
どんなお子さん達でしょう・・・
どうか、誠意を持って子ども達に接し、保護者の方々を
安心させられる様な先生になれるよう、日々頑張って
欲しいと願います。
年少 ばら組 の新米先生へ
ピアノと一緒に陰ながらエールを贈りたいと思います。
(今日は親バカな内容で、失礼いたしました。)


登山口へ向かう途中、水田の真ん中にある、『お玉の清水』へ立ち寄りました。
美味しい水を汲んでいこうと思いましたが、いくら井戸を漕いでも一滴も出てこなくて残念でした。
汲む為の名水、という施設ではなかったみたいです。
こごみと(食べられない)シダの区別が判りません。
近々、詳しい人に教えてもらおうと思います。

下山した所が「龍野城公園」
とても美しい場所でした。右の写真は本丸御殿(再建)

お城のお庭と思いきや、中学校跡地、龍野女学校跡地、の碑がありました。
すっかり公園に造り直され、学校だった面影は無かったので意外でした。
龍野は、薄口醤油と播州そうめんが有名です。
薄口醤油記念館を見学しました。
黒塀の古い町並みや、レトロな建物が残っていて良い雰囲気でした。
揖保川は、源流が宍粟市の藤無山(ふじなしやま)から流れる河川です。
好きな川です。




畦を狸が飛び回っていました。 のら猫の様に悠然としていたので、狸の居る風景はあたりまえの日常なのでしょう。
狸って、身体がモコモコしていますね。

山中の水溜りにざわざわと気配がしたので覗いてみると、たくさんのオタマジャクシ。ひじきみたいな小ささでした。



竜野の古い町並みの一角に、猫ちゃんのサンルーム?がありました。
日当たりの良いこの場所は、きっと彼の一等席に違いありません。後ろの猫模様のカーテンから出たり入ったりしていました。
たつの市の新龍アルプスを縦走しました。
(播磨新宮「新」から龍野「龍」を繋ぐ連山をこう呼ぶようです。)

姫路から初めて乗った「姫新線」(姫路~新見)は、新しくきれいな車輌でした。
播磨新宮までしか乗りませんでしたが、風景がとても良かったので、いつかもっと長い距離を乗りたいです。
水布谷口登山口から登りました。
今の時季、どこの山もヤマツツジが盛りです。


△祇園嶽340m登頂
△三等三角点
店名:祇園山
方角:南
周囲:祇園嶽のピーク
☆眼下にのどかな田園が望める展望地でした。

△亀山(城山)(きのやま)458m登頂
△四等三角点
点名:亀山
方角:南
周囲:山頂
☆亀山と書いて「きのやま」と読むそうです。

△四等三角点
点名:佐野
標高:382.0m
周囲:登山道
☆比較的、新しい標石でした。頻繁に三角点に出会える、嬉しいトレイルです。

△的場山登頂。
△三等三角点
点名:竜野
標高:394m
周囲:山頂


☆広い面積のピークからは、竜野の町、播磨灘、揖保川が広々と見渡せる好展望地でした。
写真の箱には、登山ノートが入っていました。毎日この山に登る方々がおられる様です。
私も登頂を記録しました。

△鶏籠山(けいろうざん)218m登頂。
☆戦国時代、赤松氏の古城があったそうです。
下山。 2015.4.8(水)
2015.4.8(水)

△新龍アルプス縦走
行程:JR新三田7:14発=(福知山線)=JR尼崎=(神戸線)=JR姫路=(姫新線)=JR播磨新宮9:39着
―水布弥口登山口―△祇園嶽―△城山(亀山)―382,0m地点―△的場山―△鶏籠山―龍野城
―龍野の城下町―JR本竜野=(姫新線)=JR姫路=(神戸線)=JR尼崎=(福知山線)=JR新三田
☆18切符使い切り計画として、駅to駅で登れる山、を
探していたところ、「関西ハイキング2015」(山と渓谷社)に紹介されていた
『新龍アルプス縦走』がまさに適ルートと思い、行ってみました。
低いながら終始展望が良く、気持ちの良いトレイルでした。
登山時間は約4時間、1日の歩数、28.500歩
以前から気になっていた場所は、小学校の跡地であったと知り、訪ねてみました。



古の入学式の日も、この坂道を子供が上がったのでしょうか。
もう校舎はとうに無くなり、今、公民館として使われている建物は、
元は体育館だったと聞きましたが・・・
石の校門は残ったままでした。



敷地をぐるっと囲む桜の木。花びらがずっと舞っていました。
校舎に対して校庭はこの位置だったのかな・・・なんて想像をめぐらしました。
















