久しぶりに、『The MALT’S』(右の茶色缶)を買ったので、
三種、飲み比べをしてみました。
やっぱり・・茶色缶のモルツが好みでした。
ただ、TheMALT’Sは大型店や酒屋さんにしか置いてなくて、
ちょっと残念です。
10月の森林塾(5回目)を受講しました。
*10月21日(木)
於:有馬富士公園
主催:キッピーフレンズ
☆今回は、「万葉植物をたずねる」というテーマで
公園内を観察をしながらお話を聴きました。
(※こちらの写真は万葉とは関係無い被写体ですが・・)
カシワ(ブナ科)の実を見ると、マカダミアナッツチョコを
連想します。

コブシ(モクレン科)の袋果からはじけた実。
一粒を引っ張ってみると、つつーっと糸で結ばれていました。
ぶらんとぶら下がることで鳥に運ばせる効果があるとのこと!
アカメガシワ(トウダイグサ科)の葉裏にびっしりと小さな毛虫が付いていました。
ドクガの幼虫とのことです。
☆今回の講師は、いつものIさんに加え、何とブイブイの森クラブの
先輩でもあるMさんでした!
今日は万葉集に登場する植物に絡めて植物・樹木をご案内いただきました。
古典の視点を持って、自然を観察することは初めてでしたが、
意外に楽しく、良い勉強になりました。
神姫観光氷ノ山ツアーに同行し、氷ノ山に登りました。
GPS軌跡(2回クリックで二段階拡大されます。)
2021.10.17(日)

行程:宍粟市役所駐車場(集合地)=R29=氷ノ山坂ノ谷登山口ー三ノ丸ー△氷ノ山ー大段ヶ平(おおだんがなる)=(横行林道)=宍粟市役所駐車場
1/25000地形図:『戸倉峠』『氷ノ山』
メンバー:氷ノ山ツアーにご参加の方々15名・宍粟50名山ガイドクラブ
氷ノ山 坂ノ谷登山口
名所、熊の大杉にてYガイドのお話に耳を傾ける参加者
三ノ丸の休憩舎にてお昼休憩
△氷ノ山三ノ丸 1464m 到着

△氷ノ山 1509.8m 登頂。
△一等三角点
標高:1509.77m
点名:「氷ノ山」(ひょうのやま)
☆雨天の頂上には我々のパーティ以外、誰も居らず。
小屋に駆け込み、風雨を凌いでひと休みしました。
冷たい雨に打たれながらの下山、皆さんは逞しくも元気で賑やかな
進軍でした。
☆終日、あいにくの天候でしたが、足並み揃った元気な参加者の方々の
お陰で、雨もまた楽し・・の登山になりました。
皆さん、風邪など引かれなかったでしょうか・・・
解散後、私は山崎の伊沢の里(温泉)へ。
ゆっくりとお湯に浸かり、今日一日を想い返しました。
イタヤカエデ
ウリハダカエデ
ブナ
コミネカエデ
コハウチワカエデ
ウワミズザクラ
マンサク
ツタウルシ
オガラバナ
(『紅葉ハンドブック』で判別・・・)
朝の散歩で写した植物です。(十月中旬)
ミゾソバ(タデ科)
☆川の近くに毎秋群生しており、薄いピンク色のつぼみが可愛く、つい毎秋撮っています。

イシミカワ(タデ科)
☆例の和名の由来図鑑によると、イシミカワの名の由来は諸説ある様です。
「薬草としての本種は石見川村(現、河内長野市)のものが良質だったから・・」の説
「石の様な実と皮だから・・・」の説 他。
アサガオ(ヒルガオ科)
☆ぽつんと一輪、爽やか水色でした。
タチバナモドキ(バラ科)の実
☆毎春、真っ白い花をたくさん付けているタチバナモドキ、
秋は真っ赤な実をたくさん実らせています。
コスモス(キク科)
☆種が飛んできたのか一輪だけ。以前は小群生がありましたが、淘汰されたのか・・
やはりセイタカアワダチソウには勝てない様です。
ジュズダマ(イネ科)
和名の由来辞典によると、「壺型の実を包む、硬い苞葉(ほうよう)を糸で
繋ぎ、数珠(じゅず)にした」とありました。
昔は食料として食べていた、とも。
マルバルコウ(ヒルガオ科)
毎秋、方々で群生しています。畑で群生すると害草扱いの
様ですが、マメアサガオ同様、花自体は可愛いと思います。
手持ちの野草図鑑、数冊にはいずれも掲載が無く、
「雑草図鑑」に載っていました。
ヤマメ茶屋から坂ノ谷登山口経由で氷ノ山へ登りました。
GPS軌跡(2度クリックでワイドに拡大されます。)
2021.10.9(土)
 △氷ノ山
△氷ノ山
行程:(往復)神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=R29=氷ノ山登山口/ヤマメ茶屋=駐車地ー(坂ノ谷林道)ー坂ノ谷登山口ー△氷ノ山三ノ丸ー△氷ノ山山頂
1/25000地形図:『戸倉峠』『氷ノ山』
宍粟50名山ルートマップ:『1氷ノ山三ノ丸』
メンバー:夫・自分
先月はEバイクで登った道ですが、久しぶりに歩いてみると
忘れかけていた発見が色々とありました。
朝日差す早朝の林道
今日はお天気が良さそうです。
坂ノ谷登山口へと殿下登山口への分岐
坂ノ谷登山口
昨年、伐採作業が行われて作業道が付けられた部分は
土が固められ、登山道の誘導ロープもありました。

地面に・・チャワンタケのなかまでしょうか。
緩やかな登山道は息切れの心配も無く、おしゃべりも弾みます。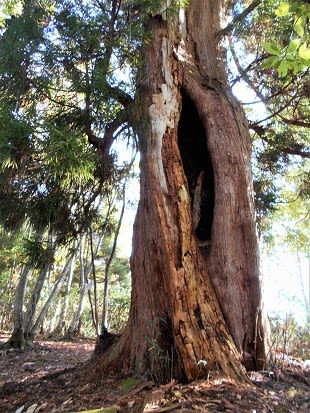
熊の大杉
観音大カツラ

大きな枝を伸ばすブナに、雪原の季節を思い出しました。
殿下登山道への分岐
氷ノ山若狭スキー場への分岐
ネマガリザサが海原の様です。この風景もあと数か月で雪原へ
変わると思うと、季節の変化に驚きます。
三ノ丸避難小屋
氷ノ山三ノ丸(宍粟50名山最高峰) 1464m 到着
今日は晴天で、山頂までくっきり眺められました。
展望櫓からは鳥取の海岸線も見えました。
山頂を目指します。
氷ノ山山頂のトイレ付休憩舎
ソーラー発電設置の為、作業用足場が組まれていました。
△氷ノ山 山頂避難小屋
☆小屋にて休憩。
△氷ノ山 1509.8m 登頂。
△一等三角点
標高:1509.77m
点名:「氷ノ山」(ひょうのやま)
☆7月以来の山頂でした。
下山は往路を戻ります。
ツタウルシの葉が真っ赤に紅葉していました。
小さなキノコも
今日は我が5班の方々とすれ違う予定でした。
どこかで会えると解っていても、姿が見えたら嬉しいものです。
脳みそみたいなキノコ
顔みたいな模様の甲虫(こうちゅう)カミキリムシの仲間でしょうか。
名前を調べ中。
無事、坂ノ谷登山口へ下山し、再び林道をヤマメ茶屋へ歩きます。
檜皮葺を剥いだ跡でしょうか、『檜皮葺』について初めて知ったのも、この場所でした。
車や自転車で通るのもいいですが、歩くと見える風景もありますね・・
足元の幼虫や
林道途中、羊ヶ滝入口横の橋げたには「昭和三十七年十一月架」と
刻まれていました。
橋の名前はひらがなで「そのはし」
更に下の方に架かる橋は「砥潟橋」と刻まれ、
「昭和三十六年十二月架」と。約60年の歴史ある橋だと解りました。
駐車地も近く、今日の登山が終わります。
☆来週に控えた氷ノ山ツアーへの下見を担当班で行う日でしたが、
夕刻早めに帰宅する都合があり、今日は別行動をさせていただきました。
△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳ー△山王山(三田市)を周回縦走しました。
GPS軌跡(クリックで拡大されます。)
2021.10.6(水)

 △峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳ー△山王山
△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳ー△山王山
行程:自宅=R176=駐車地ー大根谷林道ー作業道入口ー△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳ー△山王山ー作業道ー県道ー駐車地=自宅
1/25000地形図:『篠山』
メンバー:山友達4名+自分
☆一昨日と同じ行程を経て、峰ヶ畑まで登って来ました。
まずは今日の唯一三角点で。
△三等三角点
点名:峰ヶ畑
標高:659.72m
もちろん、オレンジ色の櫓へも。
足元には終わりかけのオミナエシ(スイカズラ科)
ウバメガシや灌木など、低い木々の自然林を辿ります。
次のピーク、△扶養ヶ岳へ到着。
ここでお昼休憩。
眺望の無い地味な頂上も、賑やか仲間と一緒なら、素敵な場所に思えます。
今日は皆の若い頃の話で盛り上がりました。
△山王山(さんのうざん)登頂。(石碑裏側)
お昼を食べた後は、アップダウンを経て△山王山(さんのうざん)へ。
ピークには石碑が建っています。
(石碑表側)
図根三角点も埋まっていました。
往路を戻る予定でしたが、ショートカットを思い付き、作業道を下りました。
☆地元の山仲間と母子(もうし)の山々を渡り歩きました。
峰ヶ畑以西の二座は地味なルートになりますが、
気の置けないメンバーと歩く道のりは終始笑いが絶えず、
今日も楽しい山行でした。
△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳(三田市)に登りました。
GPS軌跡(クリックで拡大されます。)
2021.10.4(月)
 △峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳
△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳
行程:自宅=R176=駐車地ー大根谷林道ー作業道入口ー△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳ー作業道ー作業道入口ー大根谷林道ー駐車地=自宅
1/25000地形図:『篠山』
メンバー:単独
ここの近くに車を停めて、大根谷林道(花とみのりの道)を南下して歩き出します。
△三等三角点
点名:峰ヶ畑
標高:659.72m
☆まずは三角点へ。
そして峰ヶ畑のランドマーク、オレンジの櫓へ。2020年元旦以来です。
(初日の出登山に数回来たことがある場所です。)
何と!この鉄塔の巡視に来られ方々が居られました。
この山で人に会うのは初めてで、びっくりでした。
対して先方は「どこから来たのですか!」と驚かれていました。
めったにない逢瀬、鉄塔についてお聞きしたいことはたくさんありましたが、
帰宅時間に制限があり、残念ながら挨拶を述べ、先を急ぎました。
扶養ヶ岳へ向かう途中、展望地からは近くの大野山(おおやさん:猪名川)や、
深山(みやま)、
そして大船山や宝塚の山々などが眺望出来ました。
とても大きなヌタ場
そして△扶養ヶ岳 660m 到着。
数年前以来の登頂です。
少し休憩して往路を戻ります。
復路は作業道を選んでショートカット。
簡易舗装や・・
砂利道もあったり。
アサギマダラも飛んでいたり・・・
沢の近くにはアケボノソウ(リンドウ科)が盛り。
立派なスラブ状の岩もあったり・・初めて歩いた作業道では発見が楽しかったです。
送電線鉄塔は青空をバックに素敵な感じでした。
☆久しぶりに峰ヶ畑~扶養ヶ岳を歩きました。
宍粟50名山ふれあい登山会に参加し、
△笠杉山に登りました。
GPS軌跡(クリックで拡大されます。)
2021.10.3(日・登山の日)
 △笠杉山
△笠杉山
行程:自宅=神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=宍粟市役所P=R29=上千町駐車地ーやけのごやーおおたわー△笠杉山ーやけのごやー駐車地=市役所P=山崎IC=(中国自動車道)=神戸三田IC=自宅
1/25000地形図:『神子畑』
宍粟50名山ルートマップ:『23笠杉山』
メンバー:参加者55名・宍粟50名山ガイドクラブ
上千町終点より林道を歩き、やけの小屋登山口から山道へ入山します。
笠杉山登山口
車道を横断し、横断された尾根の取付きより再び山道へ。
下方に基幹道を眺めながら
△笠杉山 1032m登頂!
ひとつの雲も無く、素晴らしい快晴!
△三等三角点
点名:藤尾峠
標高:1032.11m
笠杉山ヌシの居られる岩山
今日は大勢の人で賑やかなせいか、ヌシは顔を出しませんでした。
氷ノ山はばっちり眺望出来ました。
頂上周辺に多く植わっているコハクサンボク(エゴノキ科)
眺望を楽しみながらゆっくりお昼休憩を取り、尾根ルートで
やけの小屋を目指して下山。
おおたわ北登山口まで下りたところ。
基幹道を横断し、谷ルート登山道へ。
センブリ(リンドウ科)
アケボノソウ(リンドウ科)
☆約2年ぶりにふれあい登山会が開催されました。
多くの方々が集まり、懐かしい方々との再会も出来ました。
秋晴れの下、和気あいあいの楽しい登山会でした。

ブイブイの森にて除草作業中、笹の茎に「何これ?」
という生き物?を見つけました。
聞くと、毛虫に寄生した蜂の繭(まゆ)とのこと。
繭がお米粒にも見えます。思わず、「おべんと付けてどこ行くの♪」と
言いたくなりますが・・
帰宅して調べるに、笹や竹を食べる『タテカレハ蛾』の幼虫に
寄生した『コマユバチ』の繭(まゆ)と解りました。
生きた幼虫から養分を得ながら、寄生している様です。
後に、繭から成虫となった蜂が出てしまうと、
衰弱した幼虫はやがて死ぬそうです。
これはヨモギの虫こぶで、『ヨモギツボタマバエ』
という寄生バエの虫えいと解りました。


















