メタエンジニアの眼シリーズ(102)TITLE: 「ダ・ヴィンチの右脳と左脳を科学する」
書籍名;「ダ・ヴィンチの右脳と左脳を科学する」 [2016]
著者;レナード・シュレイン 発行所;ブックマン社
発行日;2016.4.11
初回作成日;H31.1.16 最終改定日;H31.1
引用先;文化の文明化のプロセス Converging
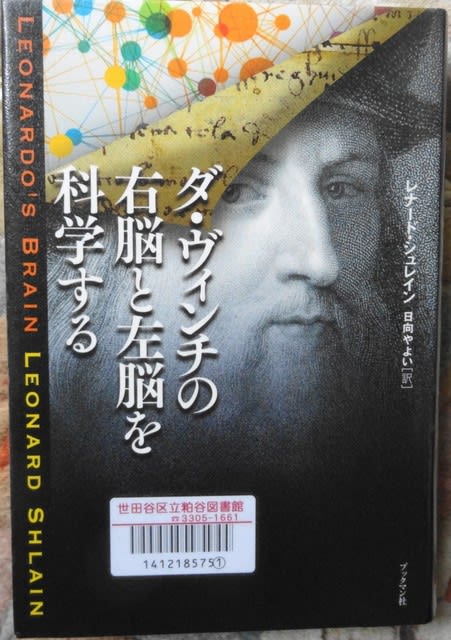
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
表紙の後に、17枚のカラーの図が並んでいる。「モナリザ」からはじまり、「アルノ川に副水路を設けるための運河計画図」で終わっている。
第1章は「芸術/科学」で始まる。「芸術と科学の流れは、時代とともに遠ざかり、・・・。」なのだが、レオナルドによって、完全にひとつの流れになった。この流れが、人類の将来でどうなってゆくのだろうか、それを「科学する」のであろう。
『レオナルドの特異な書法は、彼の脳の二つの半球が桁外れに緊密に結びついていたことを強く示唆する。片方の半球がもう片方に君臨するという従来の優位パターンは、レオナルドの脳には当てはまらないようだ。レオナルドと同じく鏡文字が書ける人々の脳を調べてわかったことから推定すると、それぞれの半球が他方のやっていることを十分に知っているようにしておく、太い脳梁が存 在したことは明らかだ。』(pp.24)で、始まっている。
さらに続けて、『レオナルドの脳梁が、半球同士を結びつける過剰なニューロンでかなり膨れ上がっていたことを示す証拠がもうーつある。彼が芸術と科学に焼きを入れ、切れ目なく繋ぎ合わせたことだ。 おびただしい数の神経科学の研究によって、主に芸術、音楽、イメージ、暗験、感情、調和、美、それに比率に対する審美眼に関係するユニットが、右利きの人では一般に右半球にあるとされている。 右利きの人の左半球にあるのが、論理的かつ線型に順序よく分析するのに必要なスキルで、文法や構文、推理、数学などに欠かせない。』(pp.24)
この現象は、「並外れて頑丈な脳梁を持っている」としている。
レオナルドの幼少期からの様子と、当時のルネッサンスを概説した後で、第9章は「創造性」について記している。そこまでは、レオナルドの成長を示す歴史だ。レオナルドは、史上最も想像力の豊かな人間に成長した。
『レオナルドが史上最も創造力豊かな人物であることは、疑う余地がない。 ところで「創造カがある」とはどういう意味だろうか。それはどこで生まれるのだろうか。どのようにして発揮されるのだろうか。
ギリシャ神話では、アポロは太陽神であり、光と理性と論理の輝かしい代表者だった。彼は知的な探求の神の具現だった。彼の神殿の入り口は、「汝自身を知れ」とか「中庸を知れ」といった簡潔な格言が掲げられていた。しかし彼はまた、ユーモアを解さず慢でもあった。』(pp.150)
ここから、「ヒト」と他の動物との違いの説明が始まる。
『あらゆる脊椎動物には脳がある。しかし、たったーつの種だけが、ほかの全脊椎動物とは大幅に異なるレベルの創造力を持つようになった。人間の脳が異なる機能を持つ二つの半球に分割されたことは、決定的に重要な意味を持つ適応だった。そのせいで人間は、自然界の他のすべての生き物から遠ざかる方向へ自らを押しやることになったのだ。二十世紀社会学の始祖の一人であるエミール・デュルケームは、頭蓋の両側からそれぞれ異なる二つの性質が生まれることを事実として認め、 人間を「ホモ・デュプレックス」と呼んだ。』(pp.150)
左脳と右脳の話が続く。
『左半球の最も高度な機能、すなわち批判的思考の核となっているのは論理を支える三段論法的公式化である。正しい答えにたどりつくには規則に従わなければならず、逸脱は許されない。それほどまでに規則に依存しているため、初期の分離脳患者の多くを手術した神経外科医のジョセフ・ボーゲンは左脳を「命題脳」と呼んでいる。情報を一連の基本命題に従って処理するのだ。これに対して、右脳は全く逆のことをするため、彼は右脳を「同格脳」と呼んだ。情報を非線形かつ規則に基つかないやり方で処理し、互いに異なる収束する決定因子を、首尾一貫した思考に組み込む。』(pp.152)
具体的な「創造」の始まりについては、このように記している。
『創造的なプロセスの最初の段階では、何らかの出来事、正体不明の物体、いつもと違うパターン、奇妙な取り合わせなどが右脳の注意を喚起する。すると、実態のまだよくわからない謎めいたプロセスで、右脳が左脳をつついて質間を発する。正しい質問をすることが、創造力の核心に達する鍵となる。質間こそが、ホモ・サピエンスの強みだ。』(pp.153)
この「左脳へ質問」というプロセスの発想は面白い。日本人は、西欧人よりも多くのことを左脳で認識してしまう。ということは、「左脳へ質問」というプロセスが働かないことになってしまう。これは、困ったことだ。日本人が、世界的な変化に鈍感なのは、このためではないだろうか。
そして、レオナルドの多くの業績を説明した後で、最後の第19章は「進化/絶滅」となっている。つまり、「ヒト」は、進化に向かっているのか、絶滅に向かっていくのかである。そこには、「芸術と科学」の関係が係わっている。
『アルベルト・アインシュタインが次のような見解を述べている
この「宇宙に対する信仰心のような」感情を、全くそれを持たない人に説明するのはきわめて 難しい…
あらゆる時代の敬虚な天才は、教義を持たない種類の信仰心によって、それと認められる…わたしの考えでは、この感情を目覚めさせ、それを受け入れる力のある人のなかに生かし続けることが、芸術と科学の最も大事な役割である。』(pp.315)
「進化/絶滅」には、いずれにせよ「変化」がある。
『高等な種が絶滅、または新しい種への移行を経験する前に過ごす生存期間は百万年から百二十万年である。 ホモ・サピエンスは十五万歳で、種としての寿命からすれば、わたしたちはおよそ十二歳から十五歳に当たる。これはほぼ正しい。わたしたちはより強くなりつつあり、より致命的なやり方で互いに傷つけ合うことが可能になっている。 それでも、自らの強さと、それを抑えたいという願望にもっとよく気づくようになっている。これはまた思春期が始まる年齢でもあり、わたしたちには生理機能の急速な変化が起こる。』(pp.316)というわけである。
そして、21世紀の現代はこのような状態にある。
『地球の混雑ぶりは、脳の左側に宿る自我と超自我の不安を掻き立てている。右半球に対する左半球の優位は、サバイバリストモードの持続を確実にする。
人口過剰にこの二つの特質、すなわち武力に訴えたがる傾向と自然破壊が加わると、思ったより早く人類の絶滅が起こりかねない。わたしたちが変わらない限り、そうなってしまうだろう。では、 変化はどこから来るのだろう? レオナルドが遺伝子プールに現れたことが、希望を与えてくれる。 彼は戦争が是認されていた時代に生きた。それでも晩年には戦争を認めず、真実と美の追求に集中した。自分は自然の一部であると信じ、自然を支配するのではなく、理解し、描くことを望んだ。』(pp.318)
さらに続けて、
『いま、二一世紀前半に入ったわたしたちは、テクノロジーと生命体の改良に没頭している。次に何が来るか、誰に予測できるだろうか? 歴史上や先史時代の驚くべき発展を予測できなったように、この先何がわたしたちを待っているか、わたしたちにはわからない。ひょっとすると、権カにそれほど関心を持たず、心の問題にもっと関心を持つ人が増えるにつれ、ホモ・サピエンスの改良版に進化するのかもしれない。』(pp.318)
つまり、「ヒト」の身体と脳は、確実に変化の時を迎えているというわけである。
『体内で炭素の量に対してケイ素の量が増え、人間がいわゆる「サイボーグ」(sybernetics十Organic) になるにつれ、ダーウィンの自然選択説は再び見直しを迫られる可能性がある。
一部は無生物、―部は生物となった人類は、すでに全く新しい生命体となり始めているのだ。
コンピュータの性能が向上し 、どこにでも見られるようになったのも、二酸化ケイ素のおかげである。新たな進歩が起こるスピードには目を見張るものがある。携帯電話やコンピュータ、インターネットのおかげで、人類はますます生産的な人生を送れるようになっている。』(pp.320)
最期は、「最後の晩餐」で次のように終えている。
『レオナルドの「最後の晩餐」において、遠近法の始点はイエスの額の中心にあるのではないか。そう思うかもしれないが、違う。レオナルドはイエスの右脳の上にある一点に遠近法の中心を置くことを選んだ。彼はわたしたちに何かを告げようとしていたのだろうか。それともただの偶然だろうか。しかし、この絵には「偶然」などーつも含まれていない。この非凡な天才、この並外れたホモ・サピエンスは、一体何をわたしたちに告げようとしていたのだろう。 書かれた言葉より、右脳によって処理されるイメージ・ゲシュタルトのほうが優れていることを、 レオナルドは直観的に悟っていた。「君の舌は麻庫するだろう……画家が一瞬で示すものを言葉で表現する前に」と彼は書いている。ほかの多くの事柄同様に、この発言についても、彼は先見の明があった。この新しい時代では画像が優位を占める。多くの言葉を費やしても描写できないことを、 画像は一瞬で、はっきり示すことができる。』(pp.323)
この書のテーマは、「右脳と左脳を科学する」であって、その好例としてダ・ヴィンチを想定した。ダ・ヴィンチの業績が科学と言っているわけではない。ダ・ヴィンチの業績は芸術と技術(この場合は工学ではなく具体的なエンジニアリング)と思う。著書のあちこちで、ここは「芸術と技術」とするべきと思った箇所がある。人類を戦争に導いたり、自然破壊をするのは、科学ではなく技術なのだから。
私はメタエンジニアリングは、通常のエンジニアリング、すなわち技術的な活動の後で、その成否を問うために「右脳と左脳の合体」によって行う行為と考えている。右脳と左脳を同時に働かせることを身に着けること。だから、ダ・ヴィンチは最高のメタエンジニアなのだ。彼の生き方をこのように科学されると、人類の将来のためには、「芸術 ⇒技術 ⇒芸術」というプロセスが必要に思えてくる。
私は、日本人の脳に関する角田理論を信じる。モネやルノワールが興奮したジャポニズム絵画は、平安時代の蒔絵や障壁画にもあった日本固有の絵画形式で、すでに多くのエンジニアリング的なセンスが盛り込まれている。ヨーロッパ絵画は、人物も風景もいかに現実と一致させるか、現実以上に美しく見せるかに拘っているように思う。一方で、近代以前の日本の絵画は影を書かないなど、現実にはこだわっていない。それでも、おかしいと思わないのは、技術が大きくかかわっている。
日本では、はるか昔から「工芸」という分野があり、高く評価されていた。そこも、西洋との違いだ。だから、本書の内容は受け入れやすいし、むしろ自然で当たり前なことに受け取ることができる。著者が、角田理論に通じていれば、更に展開された議論になっていたと思う。
すべての創造的なタスクに係る人は、真の芸術の理解からスタートしなければならない時代が来るのかもしれない。
書籍名;「ダ・ヴィンチの右脳と左脳を科学する」 [2016]
著者;レナード・シュレイン 発行所;ブックマン社
発行日;2016.4.11
初回作成日;H31.1.16 最終改定日;H31.1
引用先;文化の文明化のプロセス Converging
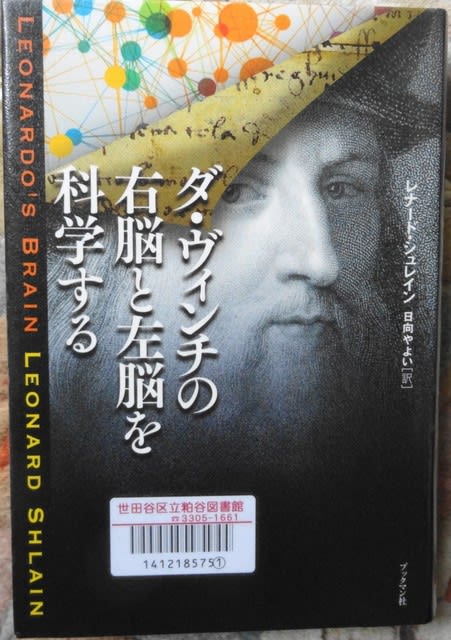
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
表紙の後に、17枚のカラーの図が並んでいる。「モナリザ」からはじまり、「アルノ川に副水路を設けるための運河計画図」で終わっている。
第1章は「芸術/科学」で始まる。「芸術と科学の流れは、時代とともに遠ざかり、・・・。」なのだが、レオナルドによって、完全にひとつの流れになった。この流れが、人類の将来でどうなってゆくのだろうか、それを「科学する」のであろう。
『レオナルドの特異な書法は、彼の脳の二つの半球が桁外れに緊密に結びついていたことを強く示唆する。片方の半球がもう片方に君臨するという従来の優位パターンは、レオナルドの脳には当てはまらないようだ。レオナルドと同じく鏡文字が書ける人々の脳を調べてわかったことから推定すると、それぞれの半球が他方のやっていることを十分に知っているようにしておく、太い脳梁が存 在したことは明らかだ。』(pp.24)で、始まっている。
さらに続けて、『レオナルドの脳梁が、半球同士を結びつける過剰なニューロンでかなり膨れ上がっていたことを示す証拠がもうーつある。彼が芸術と科学に焼きを入れ、切れ目なく繋ぎ合わせたことだ。 おびただしい数の神経科学の研究によって、主に芸術、音楽、イメージ、暗験、感情、調和、美、それに比率に対する審美眼に関係するユニットが、右利きの人では一般に右半球にあるとされている。 右利きの人の左半球にあるのが、論理的かつ線型に順序よく分析するのに必要なスキルで、文法や構文、推理、数学などに欠かせない。』(pp.24)
この現象は、「並外れて頑丈な脳梁を持っている」としている。
レオナルドの幼少期からの様子と、当時のルネッサンスを概説した後で、第9章は「創造性」について記している。そこまでは、レオナルドの成長を示す歴史だ。レオナルドは、史上最も想像力の豊かな人間に成長した。
『レオナルドが史上最も創造力豊かな人物であることは、疑う余地がない。 ところで「創造カがある」とはどういう意味だろうか。それはどこで生まれるのだろうか。どのようにして発揮されるのだろうか。
ギリシャ神話では、アポロは太陽神であり、光と理性と論理の輝かしい代表者だった。彼は知的な探求の神の具現だった。彼の神殿の入り口は、「汝自身を知れ」とか「中庸を知れ」といった簡潔な格言が掲げられていた。しかし彼はまた、ユーモアを解さず慢でもあった。』(pp.150)
ここから、「ヒト」と他の動物との違いの説明が始まる。
『あらゆる脊椎動物には脳がある。しかし、たったーつの種だけが、ほかの全脊椎動物とは大幅に異なるレベルの創造力を持つようになった。人間の脳が異なる機能を持つ二つの半球に分割されたことは、決定的に重要な意味を持つ適応だった。そのせいで人間は、自然界の他のすべての生き物から遠ざかる方向へ自らを押しやることになったのだ。二十世紀社会学の始祖の一人であるエミール・デュルケームは、頭蓋の両側からそれぞれ異なる二つの性質が生まれることを事実として認め、 人間を「ホモ・デュプレックス」と呼んだ。』(pp.150)
左脳と右脳の話が続く。
『左半球の最も高度な機能、すなわち批判的思考の核となっているのは論理を支える三段論法的公式化である。正しい答えにたどりつくには規則に従わなければならず、逸脱は許されない。それほどまでに規則に依存しているため、初期の分離脳患者の多くを手術した神経外科医のジョセフ・ボーゲンは左脳を「命題脳」と呼んでいる。情報を一連の基本命題に従って処理するのだ。これに対して、右脳は全く逆のことをするため、彼は右脳を「同格脳」と呼んだ。情報を非線形かつ規則に基つかないやり方で処理し、互いに異なる収束する決定因子を、首尾一貫した思考に組み込む。』(pp.152)
具体的な「創造」の始まりについては、このように記している。
『創造的なプロセスの最初の段階では、何らかの出来事、正体不明の物体、いつもと違うパターン、奇妙な取り合わせなどが右脳の注意を喚起する。すると、実態のまだよくわからない謎めいたプロセスで、右脳が左脳をつついて質間を発する。正しい質問をすることが、創造力の核心に達する鍵となる。質間こそが、ホモ・サピエンスの強みだ。』(pp.153)
この「左脳へ質問」というプロセスの発想は面白い。日本人は、西欧人よりも多くのことを左脳で認識してしまう。ということは、「左脳へ質問」というプロセスが働かないことになってしまう。これは、困ったことだ。日本人が、世界的な変化に鈍感なのは、このためではないだろうか。
そして、レオナルドの多くの業績を説明した後で、最後の第19章は「進化/絶滅」となっている。つまり、「ヒト」は、進化に向かっているのか、絶滅に向かっていくのかである。そこには、「芸術と科学」の関係が係わっている。
『アルベルト・アインシュタインが次のような見解を述べている
この「宇宙に対する信仰心のような」感情を、全くそれを持たない人に説明するのはきわめて 難しい…
あらゆる時代の敬虚な天才は、教義を持たない種類の信仰心によって、それと認められる…わたしの考えでは、この感情を目覚めさせ、それを受け入れる力のある人のなかに生かし続けることが、芸術と科学の最も大事な役割である。』(pp.315)
「進化/絶滅」には、いずれにせよ「変化」がある。
『高等な種が絶滅、または新しい種への移行を経験する前に過ごす生存期間は百万年から百二十万年である。 ホモ・サピエンスは十五万歳で、種としての寿命からすれば、わたしたちはおよそ十二歳から十五歳に当たる。これはほぼ正しい。わたしたちはより強くなりつつあり、より致命的なやり方で互いに傷つけ合うことが可能になっている。 それでも、自らの強さと、それを抑えたいという願望にもっとよく気づくようになっている。これはまた思春期が始まる年齢でもあり、わたしたちには生理機能の急速な変化が起こる。』(pp.316)というわけである。
そして、21世紀の現代はこのような状態にある。
『地球の混雑ぶりは、脳の左側に宿る自我と超自我の不安を掻き立てている。右半球に対する左半球の優位は、サバイバリストモードの持続を確実にする。
人口過剰にこの二つの特質、すなわち武力に訴えたがる傾向と自然破壊が加わると、思ったより早く人類の絶滅が起こりかねない。わたしたちが変わらない限り、そうなってしまうだろう。では、 変化はどこから来るのだろう? レオナルドが遺伝子プールに現れたことが、希望を与えてくれる。 彼は戦争が是認されていた時代に生きた。それでも晩年には戦争を認めず、真実と美の追求に集中した。自分は自然の一部であると信じ、自然を支配するのではなく、理解し、描くことを望んだ。』(pp.318)
さらに続けて、
『いま、二一世紀前半に入ったわたしたちは、テクノロジーと生命体の改良に没頭している。次に何が来るか、誰に予測できるだろうか? 歴史上や先史時代の驚くべき発展を予測できなったように、この先何がわたしたちを待っているか、わたしたちにはわからない。ひょっとすると、権カにそれほど関心を持たず、心の問題にもっと関心を持つ人が増えるにつれ、ホモ・サピエンスの改良版に進化するのかもしれない。』(pp.318)
つまり、「ヒト」の身体と脳は、確実に変化の時を迎えているというわけである。
『体内で炭素の量に対してケイ素の量が増え、人間がいわゆる「サイボーグ」(sybernetics十Organic) になるにつれ、ダーウィンの自然選択説は再び見直しを迫られる可能性がある。
一部は無生物、―部は生物となった人類は、すでに全く新しい生命体となり始めているのだ。
コンピュータの性能が向上し 、どこにでも見られるようになったのも、二酸化ケイ素のおかげである。新たな進歩が起こるスピードには目を見張るものがある。携帯電話やコンピュータ、インターネットのおかげで、人類はますます生産的な人生を送れるようになっている。』(pp.320)
最期は、「最後の晩餐」で次のように終えている。
『レオナルドの「最後の晩餐」において、遠近法の始点はイエスの額の中心にあるのではないか。そう思うかもしれないが、違う。レオナルドはイエスの右脳の上にある一点に遠近法の中心を置くことを選んだ。彼はわたしたちに何かを告げようとしていたのだろうか。それともただの偶然だろうか。しかし、この絵には「偶然」などーつも含まれていない。この非凡な天才、この並外れたホモ・サピエンスは、一体何をわたしたちに告げようとしていたのだろう。 書かれた言葉より、右脳によって処理されるイメージ・ゲシュタルトのほうが優れていることを、 レオナルドは直観的に悟っていた。「君の舌は麻庫するだろう……画家が一瞬で示すものを言葉で表現する前に」と彼は書いている。ほかの多くの事柄同様に、この発言についても、彼は先見の明があった。この新しい時代では画像が優位を占める。多くの言葉を費やしても描写できないことを、 画像は一瞬で、はっきり示すことができる。』(pp.323)
この書のテーマは、「右脳と左脳を科学する」であって、その好例としてダ・ヴィンチを想定した。ダ・ヴィンチの業績が科学と言っているわけではない。ダ・ヴィンチの業績は芸術と技術(この場合は工学ではなく具体的なエンジニアリング)と思う。著書のあちこちで、ここは「芸術と技術」とするべきと思った箇所がある。人類を戦争に導いたり、自然破壊をするのは、科学ではなく技術なのだから。
私はメタエンジニアリングは、通常のエンジニアリング、すなわち技術的な活動の後で、その成否を問うために「右脳と左脳の合体」によって行う行為と考えている。右脳と左脳を同時に働かせることを身に着けること。だから、ダ・ヴィンチは最高のメタエンジニアなのだ。彼の生き方をこのように科学されると、人類の将来のためには、「芸術 ⇒技術 ⇒芸術」というプロセスが必要に思えてくる。
私は、日本人の脳に関する角田理論を信じる。モネやルノワールが興奮したジャポニズム絵画は、平安時代の蒔絵や障壁画にもあった日本固有の絵画形式で、すでに多くのエンジニアリング的なセンスが盛り込まれている。ヨーロッパ絵画は、人物も風景もいかに現実と一致させるか、現実以上に美しく見せるかに拘っているように思う。一方で、近代以前の日本の絵画は影を書かないなど、現実にはこだわっていない。それでも、おかしいと思わないのは、技術が大きくかかわっている。
日本では、はるか昔から「工芸」という分野があり、高く評価されていた。そこも、西洋との違いだ。だから、本書の内容は受け入れやすいし、むしろ自然で当たり前なことに受け取ることができる。著者が、角田理論に通じていれば、更に展開された議論になっていたと思う。
すべての創造的なタスクに係る人は、真の芸術の理解からスタートしなければならない時代が来るのかもしれない。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます