◆一般者
長谷川先生解説の城郭ビイスタ
論動画は希代の学説として動画
視聴者と幾何学論投稿に着目す
る有識層文化人多いと聞きます。
聞き及びます所と日本国の城、
のみに限定適応される理論枠
を飛び越え中国東洋史的範疇
で語られ賞賛される理論と聞
いていて大論説と聞いてます。
◆質問者
中国の北京には何回都城が
建設されたのでしょうか?

◆長谷川
契丹を基とする
遼国の都「南京」
女真を基とする
金国の都市「中都」
モンゴルを基とする
元国の「大都」後に
明清の「北京」とし
て隆盛した都市です。
◆質問者
元の大都にはビイスタ工法
「見栄え理論」が存在する
のでしょうか?
◆長谷川
各門への放射状パース見放ち腺
を読み取る事が出来ます。正面
は三門形式、北は二門形式にし
各門へと放射配置したビイスタ
様式「扇型縄張」と思われます。

◆長谷川
勿論この様な測量術は日本の中原
の覇者織田信長の安土城の縄張に
も応用されています。安土城の瓦
は唐人一観を招聘して焼成させた
事は文献『信長公記』詳しいです。
また織田信長は明国の永楽帝への
憧憬もあり永楽通宝を旗印に使っ
ています。永楽帝の居城、こそが
明の時代の北京城である事は誰も
が知っている周知の事実です。
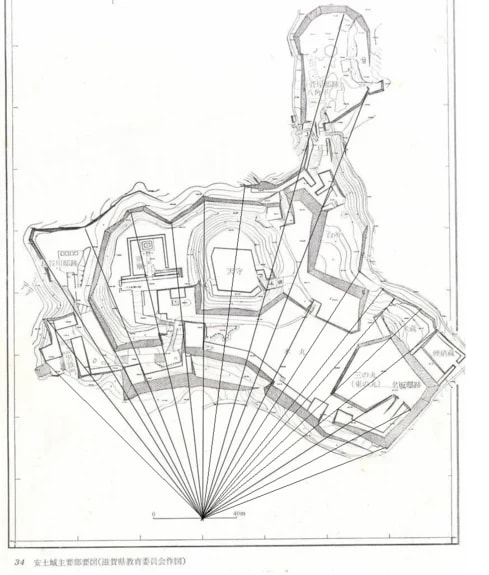
◆長谷川
大明国制覇を目指して日本の
九州の肥前名護屋に太閤秀吉
が本陣を構えた肥前名護屋城
も同じくこの扇型ビイスタ論

◆一般者
長谷川先生の城郭ビイスタ論や
幾何学理論は前代未聞東洋史学
の大論と言う事に気づきました。
◆質問者
この様な測量術や伝統は中国
に古代から存在したのですか?


◆長谷川
ギリシャのピタゴラスの三平方
の定理より中国の『算術』の方
がより古く古代より存在した事
を認識して東洋や中国や日本の
城の測量文化を考察して下さい。
◆質問者
元の大都の城壁の中心とは?
幾何学的に考察出来ますか?

◆長谷川
対角線で形成された中央ビイスタ
の中心点が「中心の閣」に相当。

◆ウイッキペデイアより大都を引用
て現在の北京の地に造営した都市で、元朝の
冬の都(冬営地)である。現在の中華人民
市街に匹敵するほどの規模を持つ、壮大な
都市だった。
◆質問者
元の大都の街区を考察
して下さい。▼大都図

◆長谷川
先ず日本の国の城と比較研究
して城内通路に①の筋交い道
②にも二か所の筋交い道あり
④と⑤には横矢の設計も存在
致します人類の街路設計思想
を研究する上に比較研究論は
重要です物事の系譜やルーツ
を考察する際には最重要項目

◆質問者
元の大都には緑色の腺が
視認できますがこの意味
は何でしょうか?
◆長谷川
難しい問題で一口で言えませ
んが都城の宮殿や巨大な池も
放射状に人口作庭した作庭術
ビイスタ工法でありましよう。

◆質問者
明の永楽帝の居城 北京順天府城
にビイスタ工法が存在しましたか?
※永楽帝=1402年~1424年在位
※生没=1360年~1424年

◆長谷川
明の永楽帝の居城 北京順天府城
にもビイスタ工法は読み取れます。
▼南からのビイスタ工法 近距離

▼南からのビイスタ 遠距離

▼北よりのビイスタ

◆北よりのビイスタ
◆質問者
明の北京城には正方形や湾曲
した塁腺が認められますが?

◆長谷川
それはビイスタ工法が潜在して
いると私は考察しております。

◆長谷川
明代よりはるか古代三千年以上
前の河南省鄭州商城にも塁腺の
同種屈曲が認められ研究の余地
があろうと思われます。四角形
の都城が営まれていない場合に
はビイスタ工法で解釈される都
城もあろうと私は考察してます。
▼鄭州商城のビイスタ工法
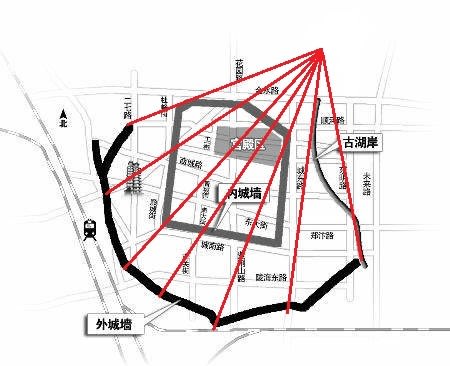
◆質問者
外城の湾曲の理由も更に解説
を加えて下さい。

◆長谷川
都城の東西からビイスタ工法
を用いて測量築城しているか
と言えます。ビイスタ理論は
普遍性と広範性双方兼ね備え
た測量方法に基づく築城工学
と言えると考察しています。

◆一般様
私は安土城にも紫禁城に行きま
したこんな事ならば長谷川先生
に解説を受けてから現地見学を
するべきだったと思いますのよ。
◆対談者
私長谷川先生と越前一乗城見学
した経験や安土城見学した経験
があります。やはり私個人には
バッチリの現地解説で価値あり
ました。何しろ城の見学の基本
を本当の意味で知っる先生です。



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます