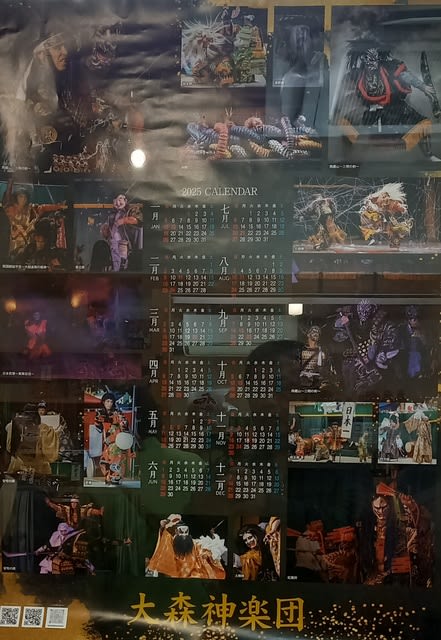
2/13(木) 1℃ 曇り☁️→晴れ⛅ 新雪0センチ
おはようございます。
昨日の雨が降ってくれたお陰で3分の2位まで積雪が減り、嬉しい反面、まだまだ残っている残雪にはガッカリ😖⤵️。車が汚れるので雨が好きではありませんが、今は早く融雪して欲しいので湯来のこの雪が溶けるまで毎日でも降って欲しい心境です。
🎵雪ぐ溶けて 川になって流れて行きます 土筆の・・・🎵
春の訪れが待ち遠しいです。
そんなこんな今時、湯来交流体験センターではこの時期恒例のテントサウナ⛺がされてました。外国人のご家族がBBQをされていたのでサウナされるのかなぁーって見てたら、今回の予約者は日本人の若い男性グループ。誰にも迷惑がかかる環境ではないので、テントの中でも外でもワイワイガヤガヤされてました。
雪が降っているので少ないかなぁ~って思ていたらけっこうな人が来ていてビックリ😨、かまくらを作ったり雪合戦されてたり、足湯に入られていたり、もちろんBBQされていたり、調理実習室でサックス🎷の練習されてたり、各々が自分の時間を楽しまれてました。
若い、青春、私の青春時代にはこんな施設は無かったからなー😅、羨ましい😄。



今日は「苗字布告記念日」だそうです。
明治8年(1875年)の今日、明治政府の「平民苗字必称義務令」という太政官布告により国民はすべて姓を名乗ることが義務づけられことに起因しています。
私の回りでは少ないんですが、佐藤さんや鈴木さんがどこにもある苗字らしいですね。
苗字と身分には、次のような関係があるとあるサイトに書いてありました。
氏(うじ)は一族を、姓(せい)は身分や地位を表すとのことで、
1,姓は、天皇家が分家した一族に与えたもので、
臣下であることを示す称号
2.姓(せい)は原則として変更できず、昔は変更するには
天皇の許可が必要だったと言うことでした
平安時代には、源氏・平氏・藤原氏・橘氏の4つの氏族が朝廷の役職を占め、武士たちは、自分の支配する地域の地名を「名字」として名乗ったそうです。
室町時代には農民階層にも「名字」が広がっていき、自分のルーツを探るには、戸籍の収集やお寺の過去帳の閲覧、先祖累代の墓碑の調査などの方法があるみたいですが、我が家のルーツを探してみようと戸籍をを取り寄せたら手数料が1万円でお釣りがくる位かかりビックリ😵、しかも戸籍という制度が出来てからの証明なので1800年代までしか戸籍では分かりませんでした。
名字や家紋を調べることのできるサイトとして、リクスタの「名字由来net」がありまが、このサイトでは、名字の歴史や由来、人数分布などのデジタルデータを調べることができる程度、遡ってのルーツ探し、どこまでやるか、やれるかが調べる気持ちの際限かな?。
昨今、戸籍上の苗字記載で夫婦別姓とかの議論がされてますが、トラブル回避前提の議論を期待したいものです。
何もする事がなければお金はかかりますがルーツ探ししてみませんか?。
あれ?あの人、親戚だったんだ、何て事も有るかも😅。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます