「私たちは怪物を作った: トランプは『アプレンティス』のために作られたテレビファンタジーだった」
トランプ前大統領のイメージは実は作られたもの?リアリティー番組の元担当者が語る真実とは
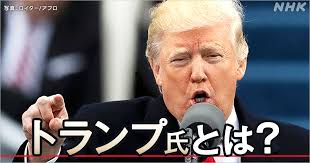
来月5日に行われる米大統領選挙で再選を目指すドナルド・トランプ前大統領が、以前出演していたテレビリアリティショー『アプレンティス』の元広報担当者が公開反省文を作成し話題になっている。
「トランプはテレビショーのためのファンタジーだった」という寄稿文
米NBC放送で『アプレンティス』のプロモーションを指揮していたジョン・ミラー元マーケティング担当ディレクターは17日(現地時間)に、U.S.ニュースに「私たちは怪物を作った: トランプは『アプレンティス』のために作られたテレビファンタジーだった」という記事を寄稿した。
ミラー氏はこの文章でリアリティショーで示されたトランプ前大統領のイメージについて「控えめに言ってもかなりの誇張であり、最悪の場合、それは実際よりも成功して見せる誤った物語だった」とし、誇張があったと述べた。
彼は「成功したほとんどのCEOはリアリティショーに出演するにはあまりにも忙しく、ショーで勝利した誰かを雇いたがらなかった」とし、反対に「トランプは撮影できる時間が多く、注目を浴びることが好きだったので、そのような心配はなかった」とキャスティングの理由を明かした。
また、トランプ前大統領が放送前に、4回も破産宣言をしたことに言及し「私たちが宣伝したトランプのイメージは非常に誇張されたものであり、フェイクニュースだった。我々はマーケティングには成功したが、トランプが成功した指導者であるという誤ったイメージを作り出し、取り返しのつかない害を与えたことを後悔している」との意向を伝えた。
『アプレンティス』ショーのプロモーションするために、トランプが成功したビジネスマンという「フェイクニュース」を作り広め、結果的にトランプ前大統領が政治的巨人になるのに加担してしまったという。実際にトランプ前大統領は2004年から『アプレンティス』に出演し、全国的な認知度を高め、この時に得た認知度と実業家のイメージが、2016年の大統領選勝利の足掛かりとなった。
「お世辞を言うと言いなりになる…プーチン・金正恩も気づいている」
一方、ミラー氏はトランプ前大統領について「彼は巧妙だが、驚くほど操りやすい人間だ」とし、「彼は称賛に関しては埋まらない穴があるので、どれだけしても十分ではない。彼はお世辞を言うといいなりになる」と述べ、ロシアのストロングマン・ウラジーミル・プーチンや北朝鮮の独裁者・金正恩(キム・ジョンウン)もこれに気づいていると語った。
また、トランプ前大統領が『アプレンティス』で黒人と白人の対決を進めることを提案したことも挙げ、広告主たちが人種間の対決を嫌がるだろうという趣旨で遠回しに反対したと伝え、「彼はそれがなぜそんなに悪いアイデアなのか理解できなかった」とし、「彼は疑わしい判断力を持っていた」と批判した。
読まれています
「トランプはテレビショーのためのファンタジーだった」という寄稿文
米NBC放送で『アプレンティス』のプロモーションを指揮していたジョン・ミラー元マーケティング担当ディレクターは17日(現地時間)に、U.S.ニュースに「私たちは怪物を作った: トランプは『アプレンティス』のために作られたテレビファンタジーだった」という記事を寄稿した。
ミラー氏はこの文章でリアリティショーで示されたトランプ前大統領のイメージについて「控えめに言ってもかなりの誇張であり、最悪の場合、それは実際よりも成功して見せる誤った物語だった」とし、誇張があったと述べた。
彼は「成功したほとんどのCEOはリアリティショーに出演するにはあまりにも忙しく、ショーで勝利した誰かを雇いたがらなかった」とし、反対に「トランプは撮影できる時間が多く、注目を浴びることが好きだったので、そのような心配はなかった」とキャスティングの理由を明かした。
また、トランプ前大統領が放送前に、4回も破産宣言をしたことに言及し「私たちが宣伝したトランプのイメージは非常に誇張されたものであり、フェイクニュースだった。我々はマーケティングには成功したが、トランプが成功した指導者であるという誤ったイメージを作り出し、取り返しのつかない害を与えたことを後悔している」との意向を伝えた。
『アプレンティス』ショーのプロモーションするために、トランプが成功したビジネスマンという「フェイクニュース」を作り広め、結果的にトランプ前大統領が政治的巨人になるのに加担してしまったという。実際にトランプ前大統領は2004年から『アプレンティス』に出演し、全国的な認知度を高め、この時に得た認知度と実業家のイメージが、2016年の大統領選勝利の足掛かりとなった。
「お世辞を言うと言いなりになる…プーチン・金正恩も気づいている」
一方、ミラー氏はトランプ前大統領について「彼は巧妙だが、驚くほど操りやすい人間だ」とし、「彼は称賛に関しては埋まらない穴があるので、どれだけしても十分ではない。彼はお世辞を言うといいなりになる」と述べ、ロシアのストロングマン・ウラジーミル・プーチンや北朝鮮の独裁者・金正恩(キム・ジョンウン)もこれに気づいていると語った。
また、トランプ前大統領が『アプレンティス』で黒人と白人の対決を進めることを提案したことも挙げ、広告主たちが人種間の対決を嫌がるだろうという趣旨で遠回しに反対したと伝え、「彼はそれがなぜそんなに悪いアイデアなのか理解できなかった」とし、「彼は疑わしい判断力を持っていた」と批判した。
読まれています




























