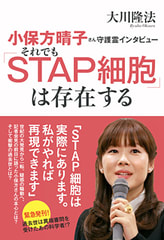宗教的本質を尊重した皇室の拡充を
2014.05.28
http://hrp-newsfile.jp/2014/1480/
文/徳島県本部副代表 小松由佳
◆女性宮家の議論が再燃する可能性
27日、高円宮典子さまのご婚約内定という慶事がありました。現在、安倍政権では、憲法改正に向けた準備が進んでおり、国防面の議論が急がれていますが、天皇や皇室のあり方についても、議論を深めていく必要があります。
現在の皇室は、天皇陛下をはじめ22人で、うち未婚の女性皇族が、典子さまを含め8人です。皇室典範により、女性皇族が皇族以外の男子と結婚した場合は皇族ではなくなるため、典子さまも皇族を離れることになります。
皇族減少への危惧から、「女性皇族は結婚後も皇室に残るべき」という、女性宮家の創設を唱える議論が再燃する可能性もあります。
しかし、天皇の本質は、天照大神の男系男子の子孫として3000年続く皇統を守りつつ、日本神道の最高神官としての役割を果たしてきたことにあります。そのため、やはり女性宮家の創設ではなく、男系を守りつつ皇室を拡充していくことが望ましいと言えます。
◆祭祀者としての皇室の弱体化
そもそも、戦後、皇室の弱体化が問題となってきたのは、政教分離規定の下、宗教者・祭祀者としての天皇の役割を、公の場から排除し、制限しようとしてきたことが原因です。
戦前は、皇室の親戚筋が華族として天皇の周りを固め、中でも歴代天皇の男系子孫が当主である宮家、つまり皇族が多く存在し、天皇家に男子が誕生しなかった場合、天皇を出して皇位継承の伝統を支えることのできる重要な存在として、天皇を支えていました。
皇室予算についても、国家予算の一定額が皇室に奉納され、使い道は皇室の自由とされ、株式投資や土地所有など皇室独自の経済活動も行われ、その収入も莫大でした。
しかし、現行憲法により、490家の華族が爵位と財産上の特権を失い、皇室資産は全て国有となり、皇室独自の経済活動は禁じられました。皇室は従来の経済規模を維持できなくなり、3宮家以外の11宮家51名が皇籍を離脱し、そのいくつかは既に断絶しています。
また、天皇の側近であった内大臣府は解体され、宮内省は宮内府へと格下げされ、行政の管理下に置かれ、規模も縮小しました。
その後、宮内府は宮内庁となりましたが、その長官はじめ幹部は、旧内務省系官庁や外務省からの出向者に占められ、必ずしも皇室の事情や伝統に精通し、皇室を支えようとの意識を持つ人々が選ばれているわけではありません。
このため、宮内庁は、皇室を守る組織ではなく、あくまで皇室を管理・監督する組織となっており、近年、宮内庁関係者が職務上知り得た秘密を漏らす、天皇家に対するマスコミの名誉棄損になるような批判にも何ら反論しない、などの弊害も起きています。
さらに、本来、皇室への公費支援をするのであれば、天皇の本質的な役割である祭祀にこそなされるべきですが、政教分離の下、政府見解では、宮中祭祀をはじめとする宗教的行為は、公費支出の対象である「国事行為」や「公的行為」には含まれず、私的行為である「その他行為」とされています。
昭和後期には、祭祀の簡略化や廃止を目指す動きも出始め、昭和天皇の大喪の礼の際に鳥居が途中で撤去されたり、毎朝の御代拝の侍従衆の服装が束帯姿から洋装に変更されたり、祭祀を手伝う内掌典の任期制が導入されたりするなど、祭祀の伝統が歪められました。
こうした動きに対し、今上天皇(きんじょうてんのう)は、簡略化された四方拝を元に戻すなど、熱心に努力されてきたといいます。
◆皇室の伝統を正しく守るために
よって、天皇の宗教者としての本質を尊重しつつ、皇室を拡充するには、まず、憲法の政教分離規定を削除する必要があります。これにより、表立っては行えなかった皇室への公費支援も可能となるので、祭祀の充実が図られます。
そして、天皇の地位については、多くの保守団体の主張や、自民党の憲法試案では、元首とすることが提言されていますが、歴史上、天皇が実質的な政治権力を握っていなかった時期も長く、天皇元首制が必ずしも伝統に適っているとは言えません。
また、天皇が元首となれば、対外的にも戦争責任などを問われることとなり、地位や生命も危険に晒されます。天皇は、国民から広く選ばれ交代が可能な首相や大統領とは違い、皇位継承者の数も限られているため、天皇制の存続自体が危うくなりかねません。
また、世襲制である天皇を元首とすることは、本来、国民主権や民主主義には合致しません。
さらに、天皇元首制は、日本神道を国教とすることに等しいですが、神道における教義や普遍性の不足は否めず、歴史的にも多くの天皇が仏教に帰依するなど、より普遍的な世界宗教である仏教に依拠してきた面が強いため、神道のみにそれだけの高い地位を与えることには、一定の疑問が付されるでしょう。
今後も、皇室への公費支出を含めた支援を行うこと自体は望ましく、日本神道を一種の公的宗教として扱うこととなりますが、それほど強い政治的権限を与えるのでなければ、伝統に適う範囲内だと言えます。
よって、天皇についての現行憲法上の曖昧な規定は削除し、皇室典範に「天皇の権能と内容」といった項目を新たに加え、主な権能を「日本神道の最高神官としての祭祀」などとし、政治的権力は行使しないことを定める、といった措置が望ましいと考えます。
また、皇室の自由な経済活動を可能とし、独自の資産運用や国民からの寄附によって収入を拡充することが望ましいと言えます。
これにより、皇室が独自に職員を雇用するなど、行政から一定の独立を保ちつつ、皇室を守る組織を創ることも可能になります。宮内庁についても、皇室の事情に精通している人物を幹部に選ぶなどの改革を行うべきです。
さらに、男系男子の皇統を維持するには、皇族・旧皇族とその子孫から養子をとることを認めると共に、旧11宮家を皇族復帰させることが有効だと考えます。
このように、宗教的本質を正しく理解した上で、皇室を守り発展させていくことは、日本の伝統を守り、国家としての誇りを取り戻すことにも繋がるでしょう。
参考文献:
竹田恒泰・八木秀次『皇統保守』PHP研究所
渡部昇一・中川八洋『皇室消滅』ビジネス社