八 「生の哲学」の日本的結実歴史について(1939年)
想起歴史観 時間も歴史も人間の「思い」が作る
EX)死んだ子供に対する母親の愛
基本要素として、日常を生きている私たち自身の中から必然的に発生していく感情、思いで、希望、幸いを
求める知恵、生きる悲しみというものであって、これらが、理知、合理、脳髄、実証という西洋由来の概念に
はっきり対置されている。
ベルグソンの影響(時間論・記憶論)
各人は自分の精神の中に「純粋持続」と呼ばれる、決して空間に転移されない時間性をはらませており、
それこそが私たち一人一人の生の実質を作る。
大森荘蔵 「過去は「制作」されたものであることによって、知覚に取り巻かれた現在とは本質的にその様
相を異にする。
「制作」されたものとしての過去をもっぱら言語命題に基づく「過去形の経験」であることによって
「像」としての過去の現前を排除しようとしていた。
小林のように「思い出」による現前化、事実化として過去をとらえれば、「知覚対言語」という乾いた
二項対立論理による不備は取り除かれ、新しく、過去や歴史という概念が、私たち一人一人の生にとって
親しいものとして総合化される。
九 敗北の必然性を予感戦争と平和(1942年)というエッセイ
戦争を、天災と同じように、「宿命」とか「運命」でとらえてしまう。
この時点で、この民族国家の敗北の必然性をすでに予感、していたのではないか。
(一般的にネガティブと捉えられる)宿命論は敗北主義という逃避行動への傾斜とは異なる。それは手が付けら
れないほど強大な第二の自然と化した人間社会に対する、一つの文学的、生活的な覚悟、なのだ。
「黙って事変に処する」といった言い回しが、一見、運命に甘んじること、怒りを忘れてただあきらめること
のように見えたとしても、そこには、限りある世にある自らの「分」を心の底からわきまえた者たちにとっての、
今日、明日を生き抜く豁然(かつぜん)たる構えが表されている。
十 戦局急を告げる中で中世古典への傾倒
当時の古典論、当麻、無常という事、平家物語、徒前草、西行、実朝
無常という事 死んだ人間こそが、動じない美しい実在感を持って私たちに迫ってくる、生きている人間
は人間になりつつある動物であるという思想
大森哲学でいえば、「知覚」に対する「想起」の優位を説いている。死者への「思い」は生者の努力で
よみがえるのであり、「無常」ということは、生者が死や死者に対してとる基本の構えとなる。(戦争に
よる死者の「予感された死」ともとらえられる。)
平家物語 哀調は叙事詩としての恐るべき純粋さにより由来する。
「鎌倉の文化も風俗も手玉に取られ、人々はそのころの風俗のままに諸元素の様な変わらぬ強いあるもの
に還元され、自然のうちに織り込まれ、僕らを差し招く」と批評される。
小林の「死への構え」が徹底され、同時代の日本人の来たるべき運命に対する凛とした覚悟が説かれて
いる。
西行
「彼は、歌の世界に、人間孤独の観念を、新たに導きいれ、これを縦横に歌い切った人である」 に対す
る疑義(近代人の苦悩を投影しているだけでは?)
北村透谷→藤村→独歩→芥川→太宰 その他多くの私小説作家に通ずる「内面の苦悩」「孤独地獄の煩悶」、
小林にも通底する、自意識や孤独のテーマへ安易な結びつき
実朝
小林・・・実朝の境遇に対する深い哀しみの共感、「側近」として寄り添うような
(私見:太宰治の「右大臣実朝」は側近によって、貴種「実朝」の鎌倉武士団の権力闘争の中での厳し
い境遇と、歌人として貴種としてのその英邁さと孤独、運命に抗する気高さが語られていきます。
同じく戦争期に書かれています。)
吉本・・・実朝の名歌の生まれる所以を、現実の歴史と、万葉以来の歌の歴史という二つの側面からとら
え、文学と社会との両方を重ね合わすように論じる。
事実を事実どおりに歌うほかないところまで追いつめられた実朝の心の特異な様相を鮮やかにあぶり
だしている
〈人々のしゃぶり尽くした「かなし」も「あわれ」も、作者の若々しさの中で蘇生する。(中略)青年にさえ
なりたがらぬような、完全に自足した純潔な少年の心を僕は思うのである。(中略)
才能は玩弄(がんろう)(もてあそぶ)することもできるが、どんな意識家も天稟には引き摺られていく
だけだ。平凡な処世にも適さぬ様な、持って生まれた無垢な心が、物心ともに紛糾を極めた乱世の間に、実
朝を引き摺って行く様を僕は思い描く。彼には、凡そ武装というものがない。歴史の混濁した陰気な風が、
はだけた儘の彼の胸を吹き抜ける。これに対し彼は何の術策も空想せず、どのような思想も案出しなかった。
(中略)彼の歌は、彼の天稟の解放に他ならず、言葉は、殆ど後からそれに追い縋るように見える。
その叫びは悲しいが、訴えるのでもなく求めるのでもない。感傷もなく、邪念も交えず透きとおっている。〉
(小林の「実朝」を媒介に)「死の予感」が、同時代の若き日本兵と七百年前の一人の「少年歌人」を
期せずして結びつけ不思議なハーモニーを奏でているように感じられる。
「彼には、凡そ武装というものがない。」
十一 大文字の「歴史」への「抵抗者」
「思想と文体とは切り離すことはできない。」(私の人生観)
「彼は、美しいものごとや感動的なものごと(ミューズやエロス)を味わおうとする人間の欲求が、私たち一人
ひとりの現実的な生活にとってどういう価値を締めているかを考え抜いたのだ。そしてそのことを通じて、近代
の客観主義的な意識や言語の様式が、個別的・主体的な生の意味を見逃してしまう事態に徹底的に抗ったのだ。」
小林は保守思想家でもなければ芸術派なのでもない。彼は、「社会」とか「政治」とか大文字の「歴史」を中心
と考える時代の支配的なイデオロギーに対し、身近な実存の意味を固守しようとした正真正銘の「抵抗者」なのだ。
小林秀雄の思想的抵抗は、世界についてのどのような客観的見取り図も与えなかったし、また社会の進歩について
のどのような指針も与えはしなかった。しかし、彼の傑出した抗いの姿勢はいわば一つの「勇気」の型というべきも
のを示した。それは、いかなる社会状況や時代状況の中にあっても、動揺せずに守るべき人間的領域があるという事
を今も私たちに告知し続けて止まないのである。
(この箇所は、先にお配りした、瀬尾育生(吉本隆明の言葉と「のぞみなきときの私たち」)の小林秀雄の評価
(P44)と符合します。)
〈人間は、他人とともに生きねばならず、生きるとは他人を信頼することだ。そういう知恵には、社会教育による後
天的なものと考えるには、より根本的なものがある。自然は肉体に健康を授けたように、精神にそういう知恵を授け
た様だ。常識という不思議な言葉を考えていると、私たちに、目や耳がある様に、一種の社会的感覚をつかさどる器
官を、私たちはどこかに持って生まれていると考えざるを得ない。〉
私見:小林秀雄の言説は今読めば、当たり前すぎてつまらない、と思うこともありますが、それは時代的な制約で
あり(当然、制約を超え未だあまりあるということもありますが)、当時(戦前、戦中を含め)(吉本たち戦中
派などの思い入れなどを含め)、「教祖」小林秀雄が在るという存在自体が、希望の星であったことは考慮すべ
きであると思います。
先の吉本隆明の小林秀雄に関する部分を再掲します
(参考)
六 源実朝の悲劇性の鮮やかな分析
吉本は情況に極めて敏感な思想家であり、場合によって抑制の利かない場合がある。
(私見:これは極めて大事な資質であって、敗戦後、吉本は、危機的な状況(敗戦後の絶望的な時期)で、先人の言葉
を渇望した、という体験で、激動期に小林秀雄は答えてくれなかった、との苦い思い出があり、以来必ず、若者の問い
には真摯に答える、という思想的態度をとっています。したがって、二流の(?)の大学の学園祭にでも信頼に足る主
催者に呼ばれれば、必ず出席しており、個人的に、尊い態度とあったと思っています。また、3.11後に、私は、このよ
うな大変な時期に、吉本は何を言うのか、ということに深く興味を持っていましたが、このたび、おまけで添付しま
す。3.11後、この未曾有の時期に、自分自身の思想の営為を通じて、きちんと答えた人は稀であり、改めて、思想者と
して何が「誠実な」態度なのか考えさせられたところです。)
1970年代以降
高く評価できる仕事
「源実朝」(1971年)、「論註と喩」(1978年)の中の「喩としてのマルコ伝」
評価できない仕事
「心的現象論序説」(1971年)、「最後の親鸞」(1971年)、「論註と喩」(1978年)の中の「親鸞論註」
「源実朝」(1971年)について、
吉本隆明は、文学の芸術的価値のみを論じる評論家のみならず、政治や社会や人間の生き方などにかかる浩瀚な視野
をもった、一種の全人格的知力の持ち主であり、実朝の歌は並み居る古典詩人の中でその生きた過酷な時代背景による
運命的なありかたと切っても切れない関係にある。吉本思想のモチーフには、国家権力による無残な死者たちと生き残
った自分や他者たちとの関係をどのようにとらえたらよいのかという戦中派特有の執拗な問いかけがある。適材適所と
はこのことをいう。
(私見:芸術的評価については割愛しますが、
太宰治が「右大臣実朝」の中で(吉本も言及していますが)
「明ルサトハ滅ビノ姿デアロウカ、
人モ家モ暗イ内ハ、マダ滅ビヌ。
平家ハ明ルイ。」
と、実朝が平家物語の弾き語りを聴いた感興を語ったくだりがあり、その造形した実朝の深い独白は大変感
動的です。)
(文芸評論家などの枠を超えた、全人格的知力の持ち主吉本隆明に対する、いわゆるオマージュといっていい
のではないでしょうか。)
想起歴史観 時間も歴史も人間の「思い」が作る
EX)死んだ子供に対する母親の愛
基本要素として、日常を生きている私たち自身の中から必然的に発生していく感情、思いで、希望、幸いを
求める知恵、生きる悲しみというものであって、これらが、理知、合理、脳髄、実証という西洋由来の概念に
はっきり対置されている。
ベルグソンの影響(時間論・記憶論)
各人は自分の精神の中に「純粋持続」と呼ばれる、決して空間に転移されない時間性をはらませており、
それこそが私たち一人一人の生の実質を作る。
大森荘蔵 「過去は「制作」されたものであることによって、知覚に取り巻かれた現在とは本質的にその様
相を異にする。
「制作」されたものとしての過去をもっぱら言語命題に基づく「過去形の経験」であることによって
「像」としての過去の現前を排除しようとしていた。
小林のように「思い出」による現前化、事実化として過去をとらえれば、「知覚対言語」という乾いた
二項対立論理による不備は取り除かれ、新しく、過去や歴史という概念が、私たち一人一人の生にとって
親しいものとして総合化される。
九 敗北の必然性を予感戦争と平和(1942年)というエッセイ
戦争を、天災と同じように、「宿命」とか「運命」でとらえてしまう。
この時点で、この民族国家の敗北の必然性をすでに予感、していたのではないか。
(一般的にネガティブと捉えられる)宿命論は敗北主義という逃避行動への傾斜とは異なる。それは手が付けら
れないほど強大な第二の自然と化した人間社会に対する、一つの文学的、生活的な覚悟、なのだ。
「黙って事変に処する」といった言い回しが、一見、運命に甘んじること、怒りを忘れてただあきらめること
のように見えたとしても、そこには、限りある世にある自らの「分」を心の底からわきまえた者たちにとっての、
今日、明日を生き抜く豁然(かつぜん)たる構えが表されている。
十 戦局急を告げる中で中世古典への傾倒
当時の古典論、当麻、無常という事、平家物語、徒前草、西行、実朝
無常という事 死んだ人間こそが、動じない美しい実在感を持って私たちに迫ってくる、生きている人間
は人間になりつつある動物であるという思想
大森哲学でいえば、「知覚」に対する「想起」の優位を説いている。死者への「思い」は生者の努力で
よみがえるのであり、「無常」ということは、生者が死や死者に対してとる基本の構えとなる。(戦争に
よる死者の「予感された死」ともとらえられる。)
平家物語 哀調は叙事詩としての恐るべき純粋さにより由来する。
「鎌倉の文化も風俗も手玉に取られ、人々はそのころの風俗のままに諸元素の様な変わらぬ強いあるもの
に還元され、自然のうちに織り込まれ、僕らを差し招く」と批評される。
小林の「死への構え」が徹底され、同時代の日本人の来たるべき運命に対する凛とした覚悟が説かれて
いる。
西行
「彼は、歌の世界に、人間孤独の観念を、新たに導きいれ、これを縦横に歌い切った人である」 に対す
る疑義(近代人の苦悩を投影しているだけでは?)
北村透谷→藤村→独歩→芥川→太宰 その他多くの私小説作家に通ずる「内面の苦悩」「孤独地獄の煩悶」、
小林にも通底する、自意識や孤独のテーマへ安易な結びつき
実朝
小林・・・実朝の境遇に対する深い哀しみの共感、「側近」として寄り添うような
(私見:太宰治の「右大臣実朝」は側近によって、貴種「実朝」の鎌倉武士団の権力闘争の中での厳し
い境遇と、歌人として貴種としてのその英邁さと孤独、運命に抗する気高さが語られていきます。
同じく戦争期に書かれています。)
吉本・・・実朝の名歌の生まれる所以を、現実の歴史と、万葉以来の歌の歴史という二つの側面からとら
え、文学と社会との両方を重ね合わすように論じる。
事実を事実どおりに歌うほかないところまで追いつめられた実朝の心の特異な様相を鮮やかにあぶり
だしている
〈人々のしゃぶり尽くした「かなし」も「あわれ」も、作者の若々しさの中で蘇生する。(中略)青年にさえ
なりたがらぬような、完全に自足した純潔な少年の心を僕は思うのである。(中略)
才能は玩弄(がんろう)(もてあそぶ)することもできるが、どんな意識家も天稟には引き摺られていく
だけだ。平凡な処世にも適さぬ様な、持って生まれた無垢な心が、物心ともに紛糾を極めた乱世の間に、実
朝を引き摺って行く様を僕は思い描く。彼には、凡そ武装というものがない。歴史の混濁した陰気な風が、
はだけた儘の彼の胸を吹き抜ける。これに対し彼は何の術策も空想せず、どのような思想も案出しなかった。
(中略)彼の歌は、彼の天稟の解放に他ならず、言葉は、殆ど後からそれに追い縋るように見える。
その叫びは悲しいが、訴えるのでもなく求めるのでもない。感傷もなく、邪念も交えず透きとおっている。〉
(小林の「実朝」を媒介に)「死の予感」が、同時代の若き日本兵と七百年前の一人の「少年歌人」を
期せずして結びつけ不思議なハーモニーを奏でているように感じられる。
「彼には、凡そ武装というものがない。」
十一 大文字の「歴史」への「抵抗者」
「思想と文体とは切り離すことはできない。」(私の人生観)
「彼は、美しいものごとや感動的なものごと(ミューズやエロス)を味わおうとする人間の欲求が、私たち一人
ひとりの現実的な生活にとってどういう価値を締めているかを考え抜いたのだ。そしてそのことを通じて、近代
の客観主義的な意識や言語の様式が、個別的・主体的な生の意味を見逃してしまう事態に徹底的に抗ったのだ。」
小林は保守思想家でもなければ芸術派なのでもない。彼は、「社会」とか「政治」とか大文字の「歴史」を中心
と考える時代の支配的なイデオロギーに対し、身近な実存の意味を固守しようとした正真正銘の「抵抗者」なのだ。
小林秀雄の思想的抵抗は、世界についてのどのような客観的見取り図も与えなかったし、また社会の進歩について
のどのような指針も与えはしなかった。しかし、彼の傑出した抗いの姿勢はいわば一つの「勇気」の型というべきも
のを示した。それは、いかなる社会状況や時代状況の中にあっても、動揺せずに守るべき人間的領域があるという事
を今も私たちに告知し続けて止まないのである。
(この箇所は、先にお配りした、瀬尾育生(吉本隆明の言葉と「のぞみなきときの私たち」)の小林秀雄の評価
(P44)と符合します。)
〈人間は、他人とともに生きねばならず、生きるとは他人を信頼することだ。そういう知恵には、社会教育による後
天的なものと考えるには、より根本的なものがある。自然は肉体に健康を授けたように、精神にそういう知恵を授け
た様だ。常識という不思議な言葉を考えていると、私たちに、目や耳がある様に、一種の社会的感覚をつかさどる器
官を、私たちはどこかに持って生まれていると考えざるを得ない。〉
私見:小林秀雄の言説は今読めば、当たり前すぎてつまらない、と思うこともありますが、それは時代的な制約で
あり(当然、制約を超え未だあまりあるということもありますが)、当時(戦前、戦中を含め)(吉本たち戦中
派などの思い入れなどを含め)、「教祖」小林秀雄が在るという存在自体が、希望の星であったことは考慮すべ
きであると思います。
先の吉本隆明の小林秀雄に関する部分を再掲します
(参考)
六 源実朝の悲劇性の鮮やかな分析
吉本は情況に極めて敏感な思想家であり、場合によって抑制の利かない場合がある。
(私見:これは極めて大事な資質であって、敗戦後、吉本は、危機的な状況(敗戦後の絶望的な時期)で、先人の言葉
を渇望した、という体験で、激動期に小林秀雄は答えてくれなかった、との苦い思い出があり、以来必ず、若者の問い
には真摯に答える、という思想的態度をとっています。したがって、二流の(?)の大学の学園祭にでも信頼に足る主
催者に呼ばれれば、必ず出席しており、個人的に、尊い態度とあったと思っています。また、3.11後に、私は、このよ
うな大変な時期に、吉本は何を言うのか、ということに深く興味を持っていましたが、このたび、おまけで添付しま
す。3.11後、この未曾有の時期に、自分自身の思想の営為を通じて、きちんと答えた人は稀であり、改めて、思想者と
して何が「誠実な」態度なのか考えさせられたところです。)
1970年代以降
高く評価できる仕事
「源実朝」(1971年)、「論註と喩」(1978年)の中の「喩としてのマルコ伝」
評価できない仕事
「心的現象論序説」(1971年)、「最後の親鸞」(1971年)、「論註と喩」(1978年)の中の「親鸞論註」
「源実朝」(1971年)について、
吉本隆明は、文学の芸術的価値のみを論じる評論家のみならず、政治や社会や人間の生き方などにかかる浩瀚な視野
をもった、一種の全人格的知力の持ち主であり、実朝の歌は並み居る古典詩人の中でその生きた過酷な時代背景による
運命的なありかたと切っても切れない関係にある。吉本思想のモチーフには、国家権力による無残な死者たちと生き残
った自分や他者たちとの関係をどのようにとらえたらよいのかという戦中派特有の執拗な問いかけがある。適材適所と
はこのことをいう。
(私見:芸術的評価については割愛しますが、
太宰治が「右大臣実朝」の中で(吉本も言及していますが)
「明ルサトハ滅ビノ姿デアロウカ、
人モ家モ暗イ内ハ、マダ滅ビヌ。
平家ハ明ルイ。」
と、実朝が平家物語の弾き語りを聴いた感興を語ったくだりがあり、その造形した実朝の深い独白は大変感
動的です。)
(文芸評論家などの枠を超えた、全人格的知力の持ち主吉本隆明に対する、いわゆるオマージュといっていい
のではないでしょうか。)














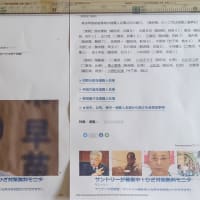





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます