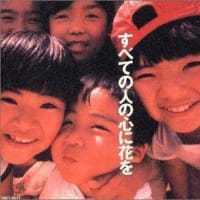この世には「流れ」というものがあります。
体を動かす時にも肉体に先行する流れがありますし、思いや感情、心にも流れがあります。
人それぞれの毎日にも流れはありますし、人生にも流れがあります。
政治や経済、国にも流れというものがありますし、そうしたものが世界の流れとなり、人類の流れとなります。
それらの流れを無視して我を張ってしまうと、天地のエネルギーに自らフタすることになります。
宇宙の流れに対して自分一人で異なる流れを作ろうとするのは、チャレンジなどではなく単なる我執にしかなりません。
それは小さなゴムボートの上、大海の潮目を無視して一人必死に漕ぐようなものです。
といって、私たちは大河の流れに身をまかせるしかないということではありません。
そのまま諦めて流されればいいということでは決してない。
ここで言いたかったのは、大きな流れでも小さな流れでも、真っ向勝負ではどうにもならないということです。
過去に革新的な流れを作りだした人たちにしてもも、潮目を無視していきなり我利我利やったわけではありませんでした。
このことは物事をシンプルに考えればすぐに分かります。
たとえば、ある川の流れを横向きに変えたいとしましょう。
もしそこで真正面に土手を作って、その流れを横に曲げようとしても元より無茶な話だとすぐに分かるはずです。
では土手を決壊させることなく、横向きに流れを変えるにはどうすればいいでしょうか。
ごく当たり前に考えれば、川の流れに逆らわず距離と時間をかけて、緩やかなカーブを描くのではないでしょうか。
要するにそういうことなわけです。

このように、現実の川の流れを変えようとする時には自然に思い浮かぶことなのに、なぜか身のまわりの流れになると私たちは見当違いのことを
やってしまいます。
川の流れをよく見て、バシャバシャと波立てることなく慎重にジックリと事を運ぶ。
川の流れが変わり出した時にはその変化をいち早くキャッチして先んじてカーブを作る。分水路を作る。
それが本筋となり本流となり、彼らは歴史の寵児となります。
しかし、潮目も変わらないのにいきなり分水路を作ろうとしたり、急カーブを作ろうとしては、単なる奇人変人にしかなりません。
日々の生活の中においても、様々なトラブルやハプニングが起きたり、突如思いもよらない展開が始まったりします。
そうした流れに対して私たちは、あわてて何とかしようとバシャバシャやってしまいます。
くじけまいぞと真正面から抵抗して、それこそがガッツや努力なんだと信じたりします。
しかしそもそも本当にそれがガッツや根性、努力と言えるのか、そこを考える必要があります。
その言葉を免罪符にして、味噌クソ一緒に正当化してはいないかということです。
怒りや悲しみのままにゴリゴリ正面突破しようとする。
それは本当に根性、努力なのか。
それよりも、沸々と湧き上がる怒りや苦しみ、恐れといった衝動に飲み込まれることなくその思いを丸ごと受け入れることの方が何倍も大変な
ことです。
そのような感情から離れて、その流れに「ただ心を向ける」。
襲いかかる濁流から目を背けず、そこへ心を向ける。
感情や衝動に流されずにスッと己を保つ。
そこに囚われずに淡々と受け入れる。
それこそが本当の努力であり、根性です。
私たちは困難に直面すると打ちひしがれそうになります。
すると「それではいけない。気持ちを折らず打破しなくては」と、正面からぶち当たろうとします。
しかし「くじける」の反対語というのは「立ち向かう」ではありません。
確かにそれも反対語の一つではありますが、それは一面でしかなく全てを網羅するものではありません。
「くじける」に対する、本当の意味での反対語は「受け入れる」となります。
「頑張る」という表現は、それそのものが前向きでポジティブなイメージとなってますが、だからこそ注意が必要です。
それに寄りかかって我を張りすぎてしまうと、辿り着く先は正反対のものになってしまいます。
「自分は」と「自分が」ではその中身が大きく違ってきます。
受け入れているか、拒絶しているか。
ただ在る状態にあるか、否か。
その差は天地の違いとなります。
天地の流れに対して、自分の流れをぶつける。
無自覚のまま、自分の流れに飲み込まれてしまう。
それは決してガッツや根性、努力などではないわけです。
頑張り時にこそ、感情にまかせず冷静になる必要があるということです。
私たちは何かあると、反射的に、正反対の方向に反応します。
皮膚や体の反応もそうですし、頭に浮かべる発想にしてもそうです。
外部から刺激が加わると無条件に逆の方向に向かう。そうやって全体のバランスを保とうとします。
私たちは、もともと防御本能として、外因的な変化に対して反発するように出来ているわけです。
ですから、この「外因的な変化」というのが大きなヒントになります。
それは内因的な変化ならば反発しないということを意味します。
外的な変化、たとえば生活環境や人間関係の変化、仕事や生活、日々の展開や流れが激変した時、本能的にそれを止めようとして反発心が
芽生えますが、そこでひとまず嘘でもいいからそれを受け入れてしまうと、その変化は私たち自身と同化し、内的な変化となり、反発心は消えて
いくことになるわけです。
「受け入れる」というのは、必ずしも納得したり称賛したりウェルカムの心を前提とするものではありません。
まっいっか、仕方ない、しゃーない、考えてもどうにもならない、否応もなし、是非に及ばず。
嘘でもいいから受け入れる、というのはそういう意味です。
それは大災害など理不尽でどうしようもない場面に直面した時、私たち日本人がこれまで幾度もやってきたことでもあります。
仕方ないと諦める。引きずらない。
すなわち、受け入れる。
それが不得意な国では、現実を受け入れられず泣きわめき、当たり散らし、大地を呪ったり、他の誰かを弾劾追及したりします。
でも悲劇の中に埋没しきったままでいるかぎり、その苦しみはいつまでも消えることなく増大し続けるだけです。
大きな流れが襲ってきた時、それはもうどうしようもないとして諦める。
ただ、諦めるといっても為すがままになるわけではない。
起きた事象に対してガタガタ言うのをやめるだけで、その現実の中で何が出来るのか、そこは最後まで諦めない。
諦めるポイントが違うということです。

大きな流れそのものは拒絶しない。諦める。
その時点でそれは私たちの内なる流れとなります。
そうしたのちに、根気強くカーブを描いていく。そこは諦めない。
間に合う、間に合わないという問題ではない。
それが本当のガッツであり努力であり、根性であるわけです。
この天地には、温かく優しくやわらかく充満しているものがあります。
目に見える世界では、物質と物質の間に断絶があり、「空間」が沢山あるように見えます。
しかし極小の素粒子の世界になると、それはただ、粒子の濃いところと薄いところがあるにすぎません。
さらに微細な世界になると、全てを包み込むような柔らかな流れがあるだけとなります。
喩えるならそれは、母なる羊水のようなものと言えます。
天地宇宙は、あらゆる隅々までこの優しい温もりに満ち満ちています。
そしてそこに「向き」が加わると「流れ」が生まれます。
流れというのは、流そうとして生じるものではありません。
そこに向きがあることで現れるものです。
高い低いという高低差によって下向きの「方向」が生じて、川の流れが現れます。
気圧の高低差によって「向き」が生じることで、風の流れが現れます。
物理現象にしても、目に見えない事象にしても、この「流れ」の理屈は同じです。
受け入れるだとか、流れだとか、言葉だけではなかなか腑に落ちるものではありませんが、理屈を知ればストンと落ちるものです。
たとえば武道において人を投げるというのは、目に見える物理法則と、目に見えない天地の流れの両方にまたがるものと言えます。
私たちが体を動かす時というのは、まず目に見えない何かが先に動いて、それに釣られるようにして肉体が動いています。
これはほとんど同時に起きているため、私たちはいきなり肉体が動いているように感じて、それが当たり前だと信じています。
しかしこうした原理を、何とは無しに感じている場面が、普段の生活の中でも数多くあります。
暖かい床暖房やコタツで横になっている時。
あるいは湯加減の丁度よい温泉に浸かってリラックスしきってる時。
さらには、朝起きて布団でボーッとしている時。
そこで何となく腰を上げようとしても、なかなか起き上がれないことがあります。
そうなった時は、さぁ起きるぞ、と気持ちを固めないと動くことはできません。
体調を崩して寝込んでいる時など尚更です。
まるで自分の体が自分のものではないように重くなったりします。
これはまさしく、肉体の動きに先行するものが動かない状態にあることを示しています。
満員電車で会社に向かう時は体は重く感じますが、旅行や遊びに向かう時は体は軽く感じます。
街中で恋人や友人に会った時には足取り軽ろやかにスーッと近づいていくのに、苦手な人に会った時は足取りも重くなります。
もちろんそれらは心の違いによるものですが、別に心が肉体の動きを止めたり早めたりしているわけではありません。
肉体に先行する何かが、パーッと解放されているか萎縮しているか、その違いがあるということです。
そして、実際に武道で人を投げる時には、この原理が応用されています。
単に物理的なテコの原理だけで投げているわけではありません。
もしも肉体に先行する何かが逆向きに向かっている状態にあるならば、同じ体格同士の人間が筋力やテコの原理だけで相手を投げることは出来ません。
もちろんそのような状態にあってもその逆向き方向ならば倒せますし、相手のバランスを崩せば投げることも出来ます。
でもここで言っているのはそういうことではなくて、「こちらが投げたい方向に投げることができるかどうか」ということです。
いま武道の話をしているのは、この「自分が行きたい方向に行かせるにはどうするか」が、人生万般にあてはまることだからです。

さて、それでは相手を投げるにはどうすれば良いのかですが、それは以下の通りです。
■相手と一つになって、流れに乗る。
もしこれが、自分「が」投げるという心にあると、それは相手の心を無視した状態となり、相手と分離した状態になります。
また、相手「を」投げるという心にある時も同じです。
そのような時、相手は本能的に反対方向に踏ん張ってしまいます。防御本能として誰もが自然にそうなります。
しかし、相手の心と一つになれば、互いの断絶がなくなります。
そこに向きを加えれば、流れが生じて自然に投げられるようになるというわけです。
そしてここが全ての肝になるところですが「相手の心と一つになるにはどうすれば良いか」、それが最も重要かつ最もややこしいことだと言えます。
これさえ出来れば、あとの向きだとか流れだとかいうのはオマケみたいなものと言ってもいいくらいです。
実は「相手と一つになろう」と思ってしまうと、相手と一つになることはできません。
なぜならば「相手」「自分」と考える時点ですでに分離が前提となっているからです。
相手と一つになろうと思った瞬間に、分離してしまうわけです。
これは非常に多くのことを示唆しています。
この理屈でいけば、どれほど正しいこと素晴らしいことであったとしても、そこへ「相手を導こう」と思った時点で、本質的に、分離と反発が
生じてしまうことが明らかだと言えます。
もちろん相手が最初からこちらの話に興味を持っている場合は、相手もこちらの流れに乗ろうとしていますのでそこに分離は生じません。
問題は、意見や考えが対峙している相手の場合です。
相手はすでに相手の流れの上に居ます。
こちらの言ってることが正しいのだからといってその真正面から、自分「が」相手を導こうとしても到底叶いません。
もちろん相手が謙虚な人であれば、自分自身の流れに縛られていませんので、こちらの流れに乗ってくれる可能性はあります。
しかし、相手が自身の流れにしがみついている時はもう絶望的です。
だからといって、こちらから相手と一つになろうと歩み寄っても、これがまた上手くはいかない。
てはどうするのか。
分離することなしに相手と一つになるにはどうすればいいのか。
天地宇宙には優しく柔らかい心が満ち満ちています。
その心と一つになるわけです。
すると、その天地の温もりに包まれているあらゆる存在と、結果として一つになっているという状態が現れます。
天地宇宙に満ち満ちているこの感覚に溶け込んでいけば、そのまま私たちは天地宇宙そのものとなります。
そうなればあとは向きを与えるだけです。
しかしそこで少しでも自我を起こすと、たちまち私たちは天地から分離してしまいます。
こうしてやろう、導こう、投げよう、と思った瞬間、それまでの感覚はシャボン玉のようにスッとはじけてなくなり、個としての自分が現れます。
ですから、ひとたびその感覚になれたならば、あとはその優しい温もりに自分を任せきるのが良いということです。
そうしてその状態を変えずに「向き」を与えると「流れ」が生じる。
相手はまるで波にでも乗せられたかのように勝手に肉体が動いていくことになります。
そしてここでも「流そう」としてはいけない。
「流そう」という思いは自我そのものであり、つまり相手との分離そのものとなります。
余計なことはせず、ただ向きを与えれば、結果として勝手に流れていきます。
私たち自身、体を動かす時には、先行する何かが真っ先に流れて、それに肉体が乗っかって、結果として体が動いています。
相手を投げる時にも、その原理と同じことが起きているわけです。
さてここで言いたかったことは、自分ではない誰かを導く仕組みについてでした。
それは天地の法則ですから、対象は人間に限らず、日々の出来事や事象にもあてはまります。
相手が襲ってきた時、攻撃してきた時、そこには大きな流れが起きています。
その流れに対して正面から当たってしまうと単なる我慢くらべにしかならず、下手したら怪我を負ってしまいます。
大きな流れが来た時には、それを駆逐しようとせず、またそれを止めようともせず、その流れに自分も合流させるのが初めの一歩となります。
自分という流れを起こすのではなく、こちらに吹き抜けてくる流れを受け入れる。
それが「一つになる」ということです。
何とかしてやろう。嫌だ。頭にくる。怖い。悲しい。
そうしたことに心を奪われない。
大災害に見舞われた時のご先祖様たちのように、怒りや悲しみに飲み込まれることなく、仕方ないと諦め、否応もなしと受け入れる。
災難に逢う時節には 災難に逢うがよく候
死ぬ時節には 死ぬがよく候
是はこれ災難をのがるるための妙法にて候
良寛さんが言われたことは、まさにそういうことなのでした。
大きな流れにあがらうと、もっと大きな怪我をしてしまう。
まずはそれを受け入れて一つになることが妙法というわけです。
そうして同化したのち、静心なく向きを変える。
向きを変えるというのは、そちらへ行かせようとするのではなく、文字通り本当に、ただそっちを向くだけのことです。
リラックスして心が通い合った状態で、相手が「あっ」と何かに目を向けますと、こちらも何の気なしにそちらに目を向けてしまいます。
それは単に、相手に吊られて見たという表現をされますが、しかし現実のプロセスとしては、こちらの心がその「あっ」の対象に向いてのち、
視線がそちらに向くことになっています。
つまり相手に主導されたようできても、実は間違いなく自分の中での内発的な衝動が先に起きているわけです。
相手に吊られたようであっても、その時の私は自分の内的変化に導かれてそちらを見た。
何が言いたいかというと、相手に「見て見て」と言われてから見たのと違い、自分の内的な流れに従って見ているのいうのは、受け身では無く、
能動的に自分から見たものに他ならないということです。
このようにして、自分から見た景色というのはストレートにそのままズドンと心に入ってきます。
それは景色に限らず、言葉や会話にしても同じことが言えます。
自らが主体になるのではなく、どこまでいっても相手が主体であり続ける。
それによって、相手は受動的になるか能動的になるか真逆の結果となります。
それが「導く」ということです。
一つになったまま、ただ向きを変える。
一つになったあと、そちらに向かせようとする。
そのにはこのような大きな違いがあるわけです。
それによって相手がそっちを向くかどうかを期待した瞬間、全ては灰塵に帰す。
「馬を水辺に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない」
とは全くもって真理そのものであって、本人が飲む飲まないというところは何とすることもできない。
むしろ無理に飲ませようとするほどに、馬は抵抗します。
向くかどうかなど初めから期待しない。
いや、そもそも、向いた先が本当の正解かどうかなんて誰にも分からないのだから、それを良いの悪いのという比較判断は最初から捨てる。
そのようにして、私心なくフラットなままに、ただ自分がそちらを向くだけでいいわけです。

流れというものは、そこに向きがあることで生じます。
そして向きというのは、そこに高低差があることで生じます。
つまりはこういうことになります。
心が落ち着き切っているならば、そこに相手との高低差が現れます。
するとその向きに沿って流れが生じます。
激流が押し寄せても、その流れを変えようとするのではなく、ただ落ち着き切っていればよい。
その時、私たちは天地宇宙そのものとなって、緩やかに導いていくことができるということです。
技にしてもそう、人間関係もそう、国同士でもそう、日々の出来事にしてもそう。
家庭も仕事も生活も人生も、みんなそう。
天地と一つになって、落ち着いて過ごしていれば、恐れるものなど何も無いのです。
体を動かす時にも肉体に先行する流れがありますし、思いや感情、心にも流れがあります。
人それぞれの毎日にも流れはありますし、人生にも流れがあります。
政治や経済、国にも流れというものがありますし、そうしたものが世界の流れとなり、人類の流れとなります。
それらの流れを無視して我を張ってしまうと、天地のエネルギーに自らフタすることになります。
宇宙の流れに対して自分一人で異なる流れを作ろうとするのは、チャレンジなどではなく単なる我執にしかなりません。
それは小さなゴムボートの上、大海の潮目を無視して一人必死に漕ぐようなものです。
といって、私たちは大河の流れに身をまかせるしかないということではありません。
そのまま諦めて流されればいいということでは決してない。
ここで言いたかったのは、大きな流れでも小さな流れでも、真っ向勝負ではどうにもならないということです。
過去に革新的な流れを作りだした人たちにしてもも、潮目を無視していきなり我利我利やったわけではありませんでした。
このことは物事をシンプルに考えればすぐに分かります。
たとえば、ある川の流れを横向きに変えたいとしましょう。
もしそこで真正面に土手を作って、その流れを横に曲げようとしても元より無茶な話だとすぐに分かるはずです。
では土手を決壊させることなく、横向きに流れを変えるにはどうすればいいでしょうか。
ごく当たり前に考えれば、川の流れに逆らわず距離と時間をかけて、緩やかなカーブを描くのではないでしょうか。
要するにそういうことなわけです。

このように、現実の川の流れを変えようとする時には自然に思い浮かぶことなのに、なぜか身のまわりの流れになると私たちは見当違いのことを
やってしまいます。
川の流れをよく見て、バシャバシャと波立てることなく慎重にジックリと事を運ぶ。
川の流れが変わり出した時にはその変化をいち早くキャッチして先んじてカーブを作る。分水路を作る。
それが本筋となり本流となり、彼らは歴史の寵児となります。
しかし、潮目も変わらないのにいきなり分水路を作ろうとしたり、急カーブを作ろうとしては、単なる奇人変人にしかなりません。
日々の生活の中においても、様々なトラブルやハプニングが起きたり、突如思いもよらない展開が始まったりします。
そうした流れに対して私たちは、あわてて何とかしようとバシャバシャやってしまいます。
くじけまいぞと真正面から抵抗して、それこそがガッツや努力なんだと信じたりします。
しかしそもそも本当にそれがガッツや根性、努力と言えるのか、そこを考える必要があります。
その言葉を免罪符にして、味噌クソ一緒に正当化してはいないかということです。
怒りや悲しみのままにゴリゴリ正面突破しようとする。
それは本当に根性、努力なのか。
それよりも、沸々と湧き上がる怒りや苦しみ、恐れといった衝動に飲み込まれることなくその思いを丸ごと受け入れることの方が何倍も大変な
ことです。
そのような感情から離れて、その流れに「ただ心を向ける」。
襲いかかる濁流から目を背けず、そこへ心を向ける。
感情や衝動に流されずにスッと己を保つ。
そこに囚われずに淡々と受け入れる。
それこそが本当の努力であり、根性です。
私たちは困難に直面すると打ちひしがれそうになります。
すると「それではいけない。気持ちを折らず打破しなくては」と、正面からぶち当たろうとします。
しかし「くじける」の反対語というのは「立ち向かう」ではありません。
確かにそれも反対語の一つではありますが、それは一面でしかなく全てを網羅するものではありません。
「くじける」に対する、本当の意味での反対語は「受け入れる」となります。
「頑張る」という表現は、それそのものが前向きでポジティブなイメージとなってますが、だからこそ注意が必要です。
それに寄りかかって我を張りすぎてしまうと、辿り着く先は正反対のものになってしまいます。
「自分は」と「自分が」ではその中身が大きく違ってきます。
受け入れているか、拒絶しているか。
ただ在る状態にあるか、否か。
その差は天地の違いとなります。
天地の流れに対して、自分の流れをぶつける。
無自覚のまま、自分の流れに飲み込まれてしまう。
それは決してガッツや根性、努力などではないわけです。
頑張り時にこそ、感情にまかせず冷静になる必要があるということです。
私たちは何かあると、反射的に、正反対の方向に反応します。
皮膚や体の反応もそうですし、頭に浮かべる発想にしてもそうです。
外部から刺激が加わると無条件に逆の方向に向かう。そうやって全体のバランスを保とうとします。
私たちは、もともと防御本能として、外因的な変化に対して反発するように出来ているわけです。
ですから、この「外因的な変化」というのが大きなヒントになります。
それは内因的な変化ならば反発しないということを意味します。
外的な変化、たとえば生活環境や人間関係の変化、仕事や生活、日々の展開や流れが激変した時、本能的にそれを止めようとして反発心が
芽生えますが、そこでひとまず嘘でもいいからそれを受け入れてしまうと、その変化は私たち自身と同化し、内的な変化となり、反発心は消えて
いくことになるわけです。
「受け入れる」というのは、必ずしも納得したり称賛したりウェルカムの心を前提とするものではありません。
まっいっか、仕方ない、しゃーない、考えてもどうにもならない、否応もなし、是非に及ばず。
嘘でもいいから受け入れる、というのはそういう意味です。
それは大災害など理不尽でどうしようもない場面に直面した時、私たち日本人がこれまで幾度もやってきたことでもあります。
仕方ないと諦める。引きずらない。
すなわち、受け入れる。
それが不得意な国では、現実を受け入れられず泣きわめき、当たり散らし、大地を呪ったり、他の誰かを弾劾追及したりします。
でも悲劇の中に埋没しきったままでいるかぎり、その苦しみはいつまでも消えることなく増大し続けるだけです。
大きな流れが襲ってきた時、それはもうどうしようもないとして諦める。
ただ、諦めるといっても為すがままになるわけではない。
起きた事象に対してガタガタ言うのをやめるだけで、その現実の中で何が出来るのか、そこは最後まで諦めない。
諦めるポイントが違うということです。

大きな流れそのものは拒絶しない。諦める。
その時点でそれは私たちの内なる流れとなります。
そうしたのちに、根気強くカーブを描いていく。そこは諦めない。
間に合う、間に合わないという問題ではない。
それが本当のガッツであり努力であり、根性であるわけです。
この天地には、温かく優しくやわらかく充満しているものがあります。
目に見える世界では、物質と物質の間に断絶があり、「空間」が沢山あるように見えます。
しかし極小の素粒子の世界になると、それはただ、粒子の濃いところと薄いところがあるにすぎません。
さらに微細な世界になると、全てを包み込むような柔らかな流れがあるだけとなります。
喩えるならそれは、母なる羊水のようなものと言えます。
天地宇宙は、あらゆる隅々までこの優しい温もりに満ち満ちています。
そしてそこに「向き」が加わると「流れ」が生まれます。
流れというのは、流そうとして生じるものではありません。
そこに向きがあることで現れるものです。
高い低いという高低差によって下向きの「方向」が生じて、川の流れが現れます。
気圧の高低差によって「向き」が生じることで、風の流れが現れます。
物理現象にしても、目に見えない事象にしても、この「流れ」の理屈は同じです。
受け入れるだとか、流れだとか、言葉だけではなかなか腑に落ちるものではありませんが、理屈を知ればストンと落ちるものです。
たとえば武道において人を投げるというのは、目に見える物理法則と、目に見えない天地の流れの両方にまたがるものと言えます。
私たちが体を動かす時というのは、まず目に見えない何かが先に動いて、それに釣られるようにして肉体が動いています。
これはほとんど同時に起きているため、私たちはいきなり肉体が動いているように感じて、それが当たり前だと信じています。
しかしこうした原理を、何とは無しに感じている場面が、普段の生活の中でも数多くあります。
暖かい床暖房やコタツで横になっている時。
あるいは湯加減の丁度よい温泉に浸かってリラックスしきってる時。
さらには、朝起きて布団でボーッとしている時。
そこで何となく腰を上げようとしても、なかなか起き上がれないことがあります。
そうなった時は、さぁ起きるぞ、と気持ちを固めないと動くことはできません。
体調を崩して寝込んでいる時など尚更です。
まるで自分の体が自分のものではないように重くなったりします。
これはまさしく、肉体の動きに先行するものが動かない状態にあることを示しています。
満員電車で会社に向かう時は体は重く感じますが、旅行や遊びに向かう時は体は軽く感じます。
街中で恋人や友人に会った時には足取り軽ろやかにスーッと近づいていくのに、苦手な人に会った時は足取りも重くなります。
もちろんそれらは心の違いによるものですが、別に心が肉体の動きを止めたり早めたりしているわけではありません。
肉体に先行する何かが、パーッと解放されているか萎縮しているか、その違いがあるということです。
そして、実際に武道で人を投げる時には、この原理が応用されています。
単に物理的なテコの原理だけで投げているわけではありません。
もしも肉体に先行する何かが逆向きに向かっている状態にあるならば、同じ体格同士の人間が筋力やテコの原理だけで相手を投げることは出来ません。
もちろんそのような状態にあってもその逆向き方向ならば倒せますし、相手のバランスを崩せば投げることも出来ます。
でもここで言っているのはそういうことではなくて、「こちらが投げたい方向に投げることができるかどうか」ということです。
いま武道の話をしているのは、この「自分が行きたい方向に行かせるにはどうするか」が、人生万般にあてはまることだからです。

さて、それでは相手を投げるにはどうすれば良いのかですが、それは以下の通りです。
■相手と一つになって、流れに乗る。
もしこれが、自分「が」投げるという心にあると、それは相手の心を無視した状態となり、相手と分離した状態になります。
また、相手「を」投げるという心にある時も同じです。
そのような時、相手は本能的に反対方向に踏ん張ってしまいます。防御本能として誰もが自然にそうなります。
しかし、相手の心と一つになれば、互いの断絶がなくなります。
そこに向きを加えれば、流れが生じて自然に投げられるようになるというわけです。
そしてここが全ての肝になるところですが「相手の心と一つになるにはどうすれば良いか」、それが最も重要かつ最もややこしいことだと言えます。
これさえ出来れば、あとの向きだとか流れだとかいうのはオマケみたいなものと言ってもいいくらいです。
実は「相手と一つになろう」と思ってしまうと、相手と一つになることはできません。
なぜならば「相手」「自分」と考える時点ですでに分離が前提となっているからです。
相手と一つになろうと思った瞬間に、分離してしまうわけです。
これは非常に多くのことを示唆しています。
この理屈でいけば、どれほど正しいこと素晴らしいことであったとしても、そこへ「相手を導こう」と思った時点で、本質的に、分離と反発が
生じてしまうことが明らかだと言えます。
もちろん相手が最初からこちらの話に興味を持っている場合は、相手もこちらの流れに乗ろうとしていますのでそこに分離は生じません。
問題は、意見や考えが対峙している相手の場合です。
相手はすでに相手の流れの上に居ます。
こちらの言ってることが正しいのだからといってその真正面から、自分「が」相手を導こうとしても到底叶いません。
もちろん相手が謙虚な人であれば、自分自身の流れに縛られていませんので、こちらの流れに乗ってくれる可能性はあります。
しかし、相手が自身の流れにしがみついている時はもう絶望的です。
だからといって、こちらから相手と一つになろうと歩み寄っても、これがまた上手くはいかない。
てはどうするのか。
分離することなしに相手と一つになるにはどうすればいいのか。
天地宇宙には優しく柔らかい心が満ち満ちています。
その心と一つになるわけです。
すると、その天地の温もりに包まれているあらゆる存在と、結果として一つになっているという状態が現れます。
天地宇宙に満ち満ちているこの感覚に溶け込んでいけば、そのまま私たちは天地宇宙そのものとなります。
そうなればあとは向きを与えるだけです。
しかしそこで少しでも自我を起こすと、たちまち私たちは天地から分離してしまいます。
こうしてやろう、導こう、投げよう、と思った瞬間、それまでの感覚はシャボン玉のようにスッとはじけてなくなり、個としての自分が現れます。
ですから、ひとたびその感覚になれたならば、あとはその優しい温もりに自分を任せきるのが良いということです。
そうしてその状態を変えずに「向き」を与えると「流れ」が生じる。
相手はまるで波にでも乗せられたかのように勝手に肉体が動いていくことになります。
そしてここでも「流そう」としてはいけない。
「流そう」という思いは自我そのものであり、つまり相手との分離そのものとなります。
余計なことはせず、ただ向きを与えれば、結果として勝手に流れていきます。
私たち自身、体を動かす時には、先行する何かが真っ先に流れて、それに肉体が乗っかって、結果として体が動いています。
相手を投げる時にも、その原理と同じことが起きているわけです。
さてここで言いたかったことは、自分ではない誰かを導く仕組みについてでした。
それは天地の法則ですから、対象は人間に限らず、日々の出来事や事象にもあてはまります。
相手が襲ってきた時、攻撃してきた時、そこには大きな流れが起きています。
その流れに対して正面から当たってしまうと単なる我慢くらべにしかならず、下手したら怪我を負ってしまいます。
大きな流れが来た時には、それを駆逐しようとせず、またそれを止めようともせず、その流れに自分も合流させるのが初めの一歩となります。
自分という流れを起こすのではなく、こちらに吹き抜けてくる流れを受け入れる。
それが「一つになる」ということです。
何とかしてやろう。嫌だ。頭にくる。怖い。悲しい。
そうしたことに心を奪われない。
大災害に見舞われた時のご先祖様たちのように、怒りや悲しみに飲み込まれることなく、仕方ないと諦め、否応もなしと受け入れる。
災難に逢う時節には 災難に逢うがよく候
死ぬ時節には 死ぬがよく候
是はこれ災難をのがるるための妙法にて候
良寛さんが言われたことは、まさにそういうことなのでした。
大きな流れにあがらうと、もっと大きな怪我をしてしまう。
まずはそれを受け入れて一つになることが妙法というわけです。
そうして同化したのち、静心なく向きを変える。
向きを変えるというのは、そちらへ行かせようとするのではなく、文字通り本当に、ただそっちを向くだけのことです。
リラックスして心が通い合った状態で、相手が「あっ」と何かに目を向けますと、こちらも何の気なしにそちらに目を向けてしまいます。
それは単に、相手に吊られて見たという表現をされますが、しかし現実のプロセスとしては、こちらの心がその「あっ」の対象に向いてのち、
視線がそちらに向くことになっています。
つまり相手に主導されたようできても、実は間違いなく自分の中での内発的な衝動が先に起きているわけです。
相手に吊られたようであっても、その時の私は自分の内的変化に導かれてそちらを見た。
何が言いたいかというと、相手に「見て見て」と言われてから見たのと違い、自分の内的な流れに従って見ているのいうのは、受け身では無く、
能動的に自分から見たものに他ならないということです。
このようにして、自分から見た景色というのはストレートにそのままズドンと心に入ってきます。
それは景色に限らず、言葉や会話にしても同じことが言えます。
自らが主体になるのではなく、どこまでいっても相手が主体であり続ける。
それによって、相手は受動的になるか能動的になるか真逆の結果となります。
それが「導く」ということです。
一つになったまま、ただ向きを変える。
一つになったあと、そちらに向かせようとする。
そのにはこのような大きな違いがあるわけです。
それによって相手がそっちを向くかどうかを期待した瞬間、全ては灰塵に帰す。
「馬を水辺に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない」
とは全くもって真理そのものであって、本人が飲む飲まないというところは何とすることもできない。
むしろ無理に飲ませようとするほどに、馬は抵抗します。
向くかどうかなど初めから期待しない。
いや、そもそも、向いた先が本当の正解かどうかなんて誰にも分からないのだから、それを良いの悪いのという比較判断は最初から捨てる。
そのようにして、私心なくフラットなままに、ただ自分がそちらを向くだけでいいわけです。

流れというものは、そこに向きがあることで生じます。
そして向きというのは、そこに高低差があることで生じます。
つまりはこういうことになります。
心が落ち着き切っているならば、そこに相手との高低差が現れます。
するとその向きに沿って流れが生じます。
激流が押し寄せても、その流れを変えようとするのではなく、ただ落ち着き切っていればよい。
その時、私たちは天地宇宙そのものとなって、緩やかに導いていくことができるということです。
技にしてもそう、人間関係もそう、国同士でもそう、日々の出来事にしてもそう。
家庭も仕事も生活も人生も、みんなそう。
天地と一つになって、落ち着いて過ごしていれば、恐れるものなど何も無いのです。