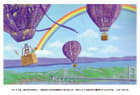1年近く前に、プリンターが壊れてしまいました。
1年近く前に、プリンターが壊れてしまいました。
青色が、上下二段に分かれてしまうのです。
上半分が濃くて、下半分が薄いので、青い部分はみんな縞になってしまいます。
業者に聞くと、昨年の9月で、部品が無くなるので、新しい物を買った方がいいと言われました。
墓は何ともないし、普段は白黒なので、そのまま使っていましたが、いやしに集いのポスターはカラーなので、縞模様がはいっていました。
ところが、先週その青が普通に戻っていたのです。
資料を印刷した時、あれ?と思いましたが、小さな文字では良く分かりませんでした。
ところが、6月のいやしの集いのポスターを作っていたら、全く縞ができずにきれいに出来上がったのです。
何度も、手を置いて祈りましたが、祈りが聞かれたのですね。本当に感謝です。


 徳冨蘆花の奥さんの愛子さんの伝記を読みました。
徳冨蘆花の奥さんの愛子さんの伝記を読みました。
蘆花は異常なまでのやきもち焼きで、奥さんが男性と話をするのを許しませんでした。
そのため、歯医者にも行かせてもらえないし、婦人病になっても病院に行くのも許しませんでした。
女性の産婦人科の医師を探しているうちに、大出血して入院することになったのです。
そんな状態だったので、クリスチャンで洗礼を受けていても、教会にも行かせてもらえませんでした。
蘆花は、異常な性格だったけれど、奥さんがいることでぎりぎりのところで守られていました。
蘆花は、一時信仰から離れますが、冨士登山中、人事不覚の後目が覚めた時、神の啓示を受け、再び信仰を取り戻しました。
二人は毎日聖書を読み、祈っていました。
蘆花が、亡くなった後、愛子は生きる気力を失くします。
死を望みますが、イザヤ54章から「子を産まない不妊の女よ。喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ。喜びの声をあげて叫べ。」「恐れるな。あなたは恥を見ない。恥じるな。あなたは恥ずかしめを受けないから。」「わたしはほんのしばらくの間、あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持って、あなたを集める。」の、御言葉によって支えられました。
この時、愛子は54歳で、子供を産んだことがありませんでした。
愛子は住んでいた屋敷と土地の約3800坪を東京に寄付し、蘆花の作品の著作権もすべて寄付しました。
それが、世田谷にある蘆花公園です。
すべての木や花は、蘆花が植えさせたものでした。
蘆花の住んでいた家が記念館になっているので、一度行って見たいと思っています。
かつて勝家の貸家に住んでいた蘆花は、家を作る時、勝海舟の家に似せて長い廊下で繋げていました。
勝家の門
愛子は、72歳で亡くなる時、友人と賛美歌を歌い終わって、静かに天に召されたのです。
壮絶な夫婦でした。
 明治時代の女性の髪型の写真をいろいろ探しています。
明治時代の女性の髪型の写真をいろいろ探しています。
意外に、初期の頃は、多くの方が三つ編みにして上にあげていたという記録があります。
その後にまた、日本髪に変わったそうです。
どの時代でも流行があり、明治の中頃は、かんざしなどを落ちそうに挿すのが粋だと言われていました。
宣教師のフルベッキは、日記の中で、女性徒の人数分のかんざしが見えると書いています。
坂東玉三郎の映画「外科室」では、衣装に凝っているので、当時の華族の着物の着方を見ることができます。
ところで、玉三郎さんは、現代の若い女性が着ている派手な着物に対してあまり好きではないとどこかで書いていました。
同じ形でも、着物の柄や色や着方の流行は時代を表していて面白いです。












 今日は、ブラジルチームが帰ってきました。
今日は、ブラジルチームが帰ってきました。