天の一角に青く澄んだ湖がある。そこに満々とたたえられているのは清らかで人の渇きを癒す水なのだが、望んでも決して手には入らない。
手に入れた途端に水は干上がった潟の塩からい水のように変質してしまう。もはやその水は人の渇きを癒さない。
大海原に漂流し渇えた人間が海水を飲み、ますます喉が渇いてしまうように、飲んでも飲んでも渇きは増していく。
渇く渇く渇く
あなたはあなたを飲み
私は私を飲み
なお癒えぬ渇き耐えがたく
渇く渇く今
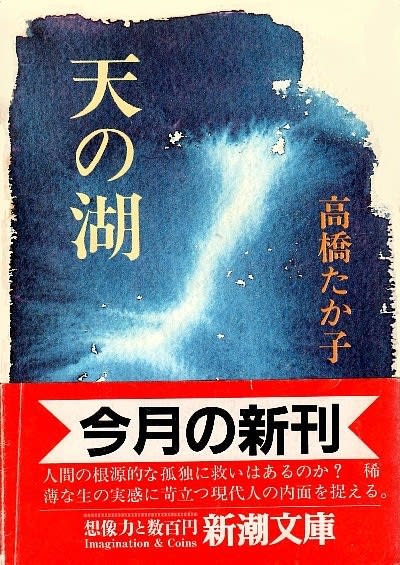
※高橋たか子『天の湖』新潮文庫 / 昭和59年6月25日発行
カバーの解説はこのようになっている。『人間の根源的な孤独に救いはあるのか?両親に疎まれ、愛に渇き、熱病のような不安を胸に生の意味を求めて焦る兄。天稟に恵まれながら、すべてに無感動、自分の居場所がないと感じている美青年の弟。その弟を不毛の愛で包み込む中年の女流画家。それぞれに孤独な三人の内面を鮮烈なイメージで描き、希薄にしか生を実感することができず苛立っている現代人の渇きを捉えた長編。』と。
三者三様の孤独な魂が邂逅して、物語は決定的な破局へとなだれ込む。
ストーリーを明かすと興ざめになってしまうので、ここでは作中に描写される『天の湖』のイメージを引用してご紹介に代えます。
パリから帰る飛行機の窓から、唯子は不思議なものを見たのであった。モスクワを発って二、三時間した頃だろうか、だんだん昼間の日射しではない光が空全体に充ちわたるようになり、夕方に近づいたらしかった。とはいっても、飛行機の飛んでいる上空は地上のように昏れてはいかない。光の度合いの奇妙な変化で、いま地上では夕方と呼ばれる時刻なのだと知られる。ロシアの大平原が果てしなく続いているのが先刻まで見えていたが、雲とはいえない擦ガラスのような気流がそれをもうみえなくしてしまっていた。いわゆる雲など何処にもなくて、黄昏らしい黄ばんだような薔薇色のような光が空いっぱいに溜っているのであった。空を飛んでいるのに、まだ上に空があるのは妙だなあと思いながら、唯子は小さな窓から、その時の空の色合いをじっと見つめていた。いつまで見ていても倦きない、色彩の奇跡と思えた。と、ずっと遠く、飛行機の飛んでいる高さと水平の位置に、湖が見えてきた。雲など何処にもなくて光だけがあるという、その時の具合からして、それは不可解な現象だった。光だけで湖を宙空につくっているとしか考えられない。透きとおる青井水がたたえられていた。これまで見たこともない水である。あれを飲むことができないものだろうか。そう思わずにはいられない色合いである。飛行機の進行とともに、或いは時刻の進行とともに、湖はいよいよはっきりと形をとってきた。岸辺は或るところは黄ばんでいて或るところは薔薇色をしている。岸辺がぐるりと湖をかこんでいるのではない。湖の向うは果てしない水の色が空へと継続しているらしかった。空は茫々とオレンジ色である。
幻ではない。あそこに湖がある。その水をこそ、と唯子が凝視していると、湖を形づくっている色合いが刻々に変化していくのに気がついた。偏在している何色かの色のなかに唐突に血のような色が出現して、それが刻々と広さを増していく。湖の片隅で発声したその赤い色はみるみる湖の青さを犯していく。
ああ。
と、唯子は声をたてた。
暫くすると湖は到底飲めそうもない赤錆の色になってしまった。
作中には、手を伸ばしても決して届かないものが次々と現れる。
するとその人はこんなふうなことを言った。ひどく饒舌になったり訥々としてしまったりする話し方だった。パリにきてもう二十年ほどパイプ・オルガンを弾いてきました。私の弾くのはほとんどバッハです。小学生の頃にバッハに出会い、それからずっとバッハを弾いてきました。最初はピアノでしたが、ほんとうにパイプ・オルガンに取り組んだのはパリにきてからです。バッハは何度弾いても何度弾いても、弾くたびに私にはあたらしい。弾くたびに違うのです。一つの曲がそうなのです。一つの曲を一生弾き続けても、同じものを弾いているのではありません。それは解釈の違いとかいったものではなく、その曲と私とのかかわりが毎回違うのです。私自身が毎回同じ人間ではありませんからね。たとえば私はこの楽譜を見ます。(そう言って、その人は脇に抱えていた古びた楽譜のページをひらいた。何百回何千回とひらかれたのであろう楽譜は綴じ目がぐさぐさになったいる。コラールと書かれていた。コラールだったのか、と唯子は独語した)。弾くたびにこの楽譜は私の指から違った音色を生むのです。私は、だから、この楽譜そのものに決して到達できないという、畏怖のようなものを覚えます。きっと楽譜そのものに到達するために、私は何度も何度も試みているのだと思いますよ。でも楽譜は常に私の向こうにあります。(ああそれは絶対者のようなものと言っていいのですか、と唯子は口をはさんだが、その人はそれを無視して言い続けた)。私はコラールが好きです。同じ曲を繰返し繰返し弾きます。それはいま言ったようなわけです。一つの曲を一生弾き続けているうちに、その曲が生育してきます。その曲は私を写す鏡のようなものです。しかしその曲それ自体を私は一度も弾いたことがありません。そこには到達できない・・・・・・。
望むものが決して手に入らないと知ったとき、人はどうなるか?・・・ときどき読み返したい小説のひとつです。
おまけ:作中に登場するリターン・トゥ・フォーエヴァー(「奇妙に透明な曲でね」と紹介されます)
※Return to Forever ( Chick Corea)
手に入れた途端に水は干上がった潟の塩からい水のように変質してしまう。もはやその水は人の渇きを癒さない。
大海原に漂流し渇えた人間が海水を飲み、ますます喉が渇いてしまうように、飲んでも飲んでも渇きは増していく。
渇く渇く渇く
あなたはあなたを飲み
私は私を飲み
なお癒えぬ渇き耐えがたく
渇く渇く今
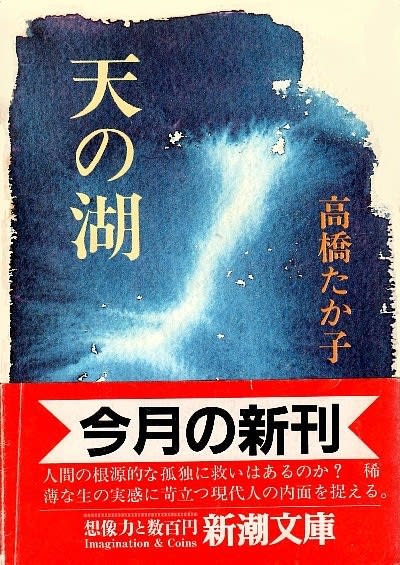
※高橋たか子『天の湖』新潮文庫 / 昭和59年6月25日発行
カバーの解説はこのようになっている。『人間の根源的な孤独に救いはあるのか?両親に疎まれ、愛に渇き、熱病のような不安を胸に生の意味を求めて焦る兄。天稟に恵まれながら、すべてに無感動、自分の居場所がないと感じている美青年の弟。その弟を不毛の愛で包み込む中年の女流画家。それぞれに孤独な三人の内面を鮮烈なイメージで描き、希薄にしか生を実感することができず苛立っている現代人の渇きを捉えた長編。』と。
三者三様の孤独な魂が邂逅して、物語は決定的な破局へとなだれ込む。
ストーリーを明かすと興ざめになってしまうので、ここでは作中に描写される『天の湖』のイメージを引用してご紹介に代えます。
パリから帰る飛行機の窓から、唯子は不思議なものを見たのであった。モスクワを発って二、三時間した頃だろうか、だんだん昼間の日射しではない光が空全体に充ちわたるようになり、夕方に近づいたらしかった。とはいっても、飛行機の飛んでいる上空は地上のように昏れてはいかない。光の度合いの奇妙な変化で、いま地上では夕方と呼ばれる時刻なのだと知られる。ロシアの大平原が果てしなく続いているのが先刻まで見えていたが、雲とはいえない擦ガラスのような気流がそれをもうみえなくしてしまっていた。いわゆる雲など何処にもなくて、黄昏らしい黄ばんだような薔薇色のような光が空いっぱいに溜っているのであった。空を飛んでいるのに、まだ上に空があるのは妙だなあと思いながら、唯子は小さな窓から、その時の空の色合いをじっと見つめていた。いつまで見ていても倦きない、色彩の奇跡と思えた。と、ずっと遠く、飛行機の飛んでいる高さと水平の位置に、湖が見えてきた。雲など何処にもなくて光だけがあるという、その時の具合からして、それは不可解な現象だった。光だけで湖を宙空につくっているとしか考えられない。透きとおる青井水がたたえられていた。これまで見たこともない水である。あれを飲むことができないものだろうか。そう思わずにはいられない色合いである。飛行機の進行とともに、或いは時刻の進行とともに、湖はいよいよはっきりと形をとってきた。岸辺は或るところは黄ばんでいて或るところは薔薇色をしている。岸辺がぐるりと湖をかこんでいるのではない。湖の向うは果てしない水の色が空へと継続しているらしかった。空は茫々とオレンジ色である。
幻ではない。あそこに湖がある。その水をこそ、と唯子が凝視していると、湖を形づくっている色合いが刻々に変化していくのに気がついた。偏在している何色かの色のなかに唐突に血のような色が出現して、それが刻々と広さを増していく。湖の片隅で発声したその赤い色はみるみる湖の青さを犯していく。
ああ。
と、唯子は声をたてた。
暫くすると湖は到底飲めそうもない赤錆の色になってしまった。
作中には、手を伸ばしても決して届かないものが次々と現れる。
するとその人はこんなふうなことを言った。ひどく饒舌になったり訥々としてしまったりする話し方だった。パリにきてもう二十年ほどパイプ・オルガンを弾いてきました。私の弾くのはほとんどバッハです。小学生の頃にバッハに出会い、それからずっとバッハを弾いてきました。最初はピアノでしたが、ほんとうにパイプ・オルガンに取り組んだのはパリにきてからです。バッハは何度弾いても何度弾いても、弾くたびに私にはあたらしい。弾くたびに違うのです。一つの曲がそうなのです。一つの曲を一生弾き続けても、同じものを弾いているのではありません。それは解釈の違いとかいったものではなく、その曲と私とのかかわりが毎回違うのです。私自身が毎回同じ人間ではありませんからね。たとえば私はこの楽譜を見ます。(そう言って、その人は脇に抱えていた古びた楽譜のページをひらいた。何百回何千回とひらかれたのであろう楽譜は綴じ目がぐさぐさになったいる。コラールと書かれていた。コラールだったのか、と唯子は独語した)。弾くたびにこの楽譜は私の指から違った音色を生むのです。私は、だから、この楽譜そのものに決して到達できないという、畏怖のようなものを覚えます。きっと楽譜そのものに到達するために、私は何度も何度も試みているのだと思いますよ。でも楽譜は常に私の向こうにあります。(ああそれは絶対者のようなものと言っていいのですか、と唯子は口をはさんだが、その人はそれを無視して言い続けた)。私はコラールが好きです。同じ曲を繰返し繰返し弾きます。それはいま言ったようなわけです。一つの曲を一生弾き続けているうちに、その曲が生育してきます。その曲は私を写す鏡のようなものです。しかしその曲それ自体を私は一度も弾いたことがありません。そこには到達できない・・・・・・。
望むものが決して手に入らないと知ったとき、人はどうなるか?・・・ときどき読み返したい小説のひとつです。
おまけ:作中に登場するリターン・トゥ・フォーエヴァー(「奇妙に透明な曲でね」と紹介されます)
※Return to Forever ( Chick Corea)




















バッハの代表的コーラルの一つなどを。
https://www.youtube.com/watch?v=gi0DYKGCS1k
私が記事にあげたように、
音符をスラーで三つにまとめらているのは、
キリストの三位一体論を表現しているからなのです。
https://www.youtube.com/watch?v=6df0bUZeL4s
私は、ほかの数曲もですが、キリスト教でもないのに、
この曲を特に極めたくて、音楽を再開したようなものです。
チックコリア、ジャズ!
管理人様らしいですね!
小説は読んでいないのですが、レビューなどからして、
家族の中、自分だけ疎外感を感じている兄と、出来が良く画家の愛人である弟、その画家の三様の閉塞感及び、魂の飢えを書いているような???
このような魂の飢えはそう簡単に、埋まらないものだと思う。
ただ、希薄な方もおり、私はそちら側になりたかった。
人生で手に入らないものは多い、
永遠の憧れとして単に終わるのか、
追いかける、少しでも近づきたくて、もがき続けるのか、
(欲しいものや、憧れに出会っただけでも十分幸せなのだと思うのですが…
それは知らなかった方が幸せだったと思えるほど、
非常に難関な種類のものもあります。)
追いかけることは、
砂漠の中の蜃気楼の偽のオアシスを求めて、到着しては絶望し、
再び、渇きをいやすのに、前に進んでいるようなものです。
片思いを原動力に、前に進める力にする、
少なくとも、私にとっての楽器演奏、音楽の解釈とはそういうものです。
失礼しました。
先入観で、この手がお好きだと。
コメント欄が2日前からgooブログは、
自動的に、gooIDのみ許可になっている方が多く、
訂正がすぐにできませんでしたm(_ _"m)
-------☆☆☆-------
疎外感を感じている兄は生命を奪った経験(相手は鼠なのですが)に、生の充実を感じ、弟を猟銃で撃ってしまいます。物語はそこで終わっていますが、私は『野鳥用の散弾なんかで撃たれた日にゃー痛いだけでなかなか死ねないゾ、きっと』と余計な心配をしてしまいました。
-------☆☆☆-------
ああ、私は疾走感のある音楽でハイトーン・ヴォイスのものが好きなのです。ジャズはほとんど聴きません、はい。