
特集の冒頭、編集部のリードとして「概論的、学術的なサポーター論ではなく」とあるが、それならばなぜ今回の特集は「20年」などという「学術的」な括りなのか。「ではな」いのならばそもそも「サッカー批評」でやる必要があるのかとすら思う。
やはりサッカー批評はロゴの軟化と同時に中途半端に柔らかくなってしまったのか。
ということで「サポーターの実像」とやらを掲げてはいるのだが、いまいち食い足りない感がしないでもない。実像の描き方、取り上げ方ならいくらでもあると思うが、確か白夜書房だったと思うが、かつて2002年のW杯便乗本ブームの最中、代表の話題と共に、Jクラブを2ちゃんノリのゴシップ視点とサポーターの噂話レベル(だけ)で構成した物凄いムックがリリースされたのだが、実は「概論的、学術的ではないサポーターの実態」というのならば、アレを徹底的に参考にすべきだったと思うのだが(今回本の山を探してみたのだが見つからなかった…ので、見つかったら改めて)。
構成は朝日氏が全面に出ているということで東京、柏色が強く、この手の特集では定番のはずの浦和色は薄く、その他大勢というラインナップ。それでいて「概論的、学術的なサポーター論ではなく」では食い足りなくても当たり前である。
サポーター論というならば、それはまず愛の肯定でなければならない。そこから出発することでしか「サポーターは敵か味方か?」などという大仰なタイトルは活きてこない。
座談会の中でサポーターの問題点として木崎伸也氏は、意味をわかって言っているのかわからないが、さらっと「サブカル化」という言葉を使っている。確かに状況として対プロ野球を出発点に、ネット上でコア層が育っていった「サポーター」と言われる人たちは、その意味では実に純粋なサブカルチャー、新しいカルチャーとコミュニティを形成して、その中で生きている。
しかし、そこで問題点をその「愛の重さ=サブカルチャー」にあると言い切ってしまうのは乱暴過ぎないか(恐らく彼はサポーターの「蛸壺化」を批判したいんだと思うが)。そもそも「サブ」って何だ?
そしてサポーターは敵か味方か?――「木崎伸也(に代表されるサッカーマスコミ)にとってサポーターは敵か味方か?」と問われれば、それは「敵」と答えるしかないだろう(彼が中途半端に口を挟んできたオカの移籍騒動の一件しかり)。
それならばサポーター論の次はマスコミ論であるはずだ。「Jリーグ20周年のサッカーマスコミ論」こそ、次にサッカー批評が取り上げるべきテーマなのではないかと思う。
マスコミ論こそ、実はサポーターを映す鏡になると思うのだが。
オレは清水を「死水」と打ち込んだスポニチを忘れない。
<高度成長時代段階の日本に、まだ「会社が嫌い」の変わり者人間が行くべき場所はなかった。しかし、会社員であることを志向しない「フリーター」というものが登場する。事態は一部で、「野球よりサッカー」になる。しかも、その社会状況を成り立たせる“一部”は、商品の売れ行きを大きく左右する若年層である。日本経済は根本で停滞していて、“売れる商品”はかなり限定したところにしか存在しないという状況が来ていた。Jリーグというサッカーは、かくして投資の対象となる。高度成長が行くところまで行った段階で、「辞めます」を平気で口にする奇っ怪な若い社員が増え、「フリーター」という言葉が公然と罷り通る。その段階で、Jリーグの設立はほぼ可能になっていた。Jリーグ誕生の年が「バブルがはじけた」と言われる年の翌年だというのは、だからとても重要なのである。
「日本のサッカー=Jリーグとはなにか?」――この答えは、「将来を期待されることなく勝手に育ってしまった管理社会の余剰部分」ということにしかならない。「Jリーグがプロ野球に取って代わる」ということは、「プロ野球からJリーグへと、スポーツの世代交替が起こる」ということで、それはすなわち、「日本の男達の間に世代交替が起こる」ということでもあった。しかし、“余剰部分”を生み出すような日本社会を作る男達の中に、「世代交替」という発想はない。だから、「今の子供はもう野球をやらないんだそうだ」の一言に、多くの男達は戦慄を感じなかった。サッカーで育った男達の中にも、「戦慄を感じさせよう」などという発想はなかった。それで、“余剰”から生まれたものは“新しい芽”にはならずに、新手の根無し草になる。終わることにピンとこない日本では、終わったものは終わらず、後から始まった新しいものの方が、先に息切れして倒れてしまうのである。一種の寓話のようなものが日本社会の現実だから、それでもしかしたら、日本人はまともに現実を問題にしないのかもしれない。>
(橋本治『天使のウインク』中央公論新社2000/「サッカー社会と野球社会」より)

















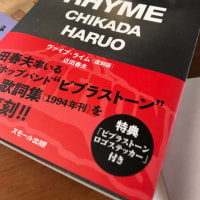


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます