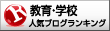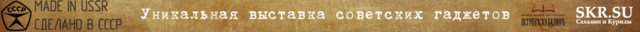梯久美子が語る「私がノンフィクションを書く理由」
Books 文化 2019.03.05
幸脇 啓子 【Profile】
“亡くなっていても、知り合える”と感じるほどの丹念な取材と精緻な文章で、数多くの賞を受賞したノンフィクション作家の梯久美子さん。戦争と昭和を題材にした作品が多い彼女に、平成の終幕を目前に話を聞いた。
梯 久美子 KAKEHASHI Kumiko
ノンフィクション作家。1961(昭和36)年熊本県生まれ。北海道大学文学部卒業後、編集者を経てフリーの文筆家に。2006年に『散るぞ悲しき ―硫黄島総指揮官・栗林忠道―』で、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。同書は、世界8カ国で翻訳出版されている。2017年には『狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ』で講談社ノンフィクション賞、読売文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞を受ける。その他の著書に『昭和二十年夏、僕は兵士だった』『昭和の遺書──55人の魂の記録』など多数。最新作は『原民喜―死と愛と孤独の肖像』。
TwitterFacebook56印刷お気に入りもっと見る39
他の言語で読む
第2次世界大戦で、日米の兵士が文字通り死闘を繰り広げた硫黄島。そこで2万人の兵を率いて日本軍の指揮を執った栗林忠道中将を、デビュー作『散るぞ悲しき』で描き、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞したノンフィクション作家の梯久美子さん。栗林中将の生きざまは、クリント・イーストウッド監督の映画『硫黄島からの手紙』では俳優・渡辺謙さんが演じ、話題となった。その後の著書『狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ』では数々の賞に輝き、近著では原爆作家と呼ばれた原民喜の人生を追っている。日本を代表するノンフィクション作家、梯さんに尋ねる「ノンフィクションを書く」ということとは。そして平成が終わろうとする今、遠くへ去りゆく昭和は、彼女の目にどう見えているのだろうか。
亡くなっていても、知り合える
——梯さんが、ノンフィクションを書くモチベーションはなんでしょうか。
理解したい、という欲望でしょうか。知りたいことを深く知るための手段が、私にとってのノンフィクションを書くということ。私が書いているのは評伝というジャンルなので、書く対象は「ひと」。だからまずはシンプルに「好き」という気持ちから出発します。へえ、というエピソードがあったり、手紙や日記などのプライベートな文章に胸を打たれたり。あと、外見に惹かれるということもあります。島尾ミホさんの場合は、老境に入ってからの写真を見て、異様な美しさを感じたのがきっかけでした。もしかしたら恋愛と似ているかもしれませんね。好きになる相手が必ずしも人間としていい人とは限らないのも恋愛と同じです(笑)。
器用ではないし、頭もよくないので、自分の手で書いてみないと、その人のことが分からないんですね。取材にも執筆にも時間がかかって、特に執筆は、3行書いて5行消す、というようなペースで書いているので、遅々として進みませんが、そうやって苦しみながら文章にすることで、ようやく、その人のことが見えてくる。なぜその人のことを好きになり、書く必要があったのかも、少しずつですが、分かってきます。そうすると、相手がすでに亡くなっている人であっても、徐々に知り合っていく感じがある。この人とは知り合いになったな、と感じられたのは、栗林忠道と島尾ミホ、そして原民喜。いずれも、書くのに難渋した人です。
この人のことをもっと知りたいとスイッチが入るのは、それまでのイメージと異なる一面にぶつかった時ですね。栗林中将は、2万人の兵士を率いて戦史に残る闘いをした硫黄島の指揮官ですが、戦地から東京の家族に宛てた手紙では「お勝手の床板の隙間は塞(ふさ)げただろうか?」と心配し、対処法を言葉で指示するだけでなく、絵まで描いて伝えています。そういう所帯じみたところが意外でした。島尾ミホは、夫の島尾敏雄が書いた『死の棘』の影響もあり、狂うほど夫を愛した聖女というイメージを持たれていました。でも、生前にご本人とお話しした際に、「それって本当?」と思ったんです。女優さんのような、ちょっと芝居がかった感じの方なんですね。
左から『散るぞ悲しき ―硫黄島総指揮官・栗林忠道―』、『狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ』(共に新潮社刊)、『原民喜 死と愛と孤独の肖像』(岩波書店)
——最新作の『原民喜』は、どこでスイッチが入ったのですか。
故郷の広島で被爆し、その経験を「夏の花」で書いた原民喜のこれまでのイメージは、「教科書に載っている原爆作家」。でもいろいろ調べてみると、いいところのお坊ちゃんで、旧制中学校時代の5年間、クラスメートが一人も彼の声をきいたことがなかったという極度の人見知りで、かつ引きこもり。生涯で得た友人は同人誌の仲間だけという、今でいう“コミュ障”です。そして、俳号を「杞憂」としたほど怖がりだった。それなのに、轢死という恐ろしい方法で自殺を遂げる。「なぜ?」という疑問からスタートしました。
ただ、構成には悩みました。生まれてから死ぬまでを時系列で追う方法もありましたが、散々悩んだ末、私が一番こだわっているこの「なぜ?」を読者と共有しようと決め、冒頭に自殺する場面を持ってきました。最期を描いた序章だけで、1カ月以上かかっています。
どの本もそうですが、書き出す前にいかに綿密に取材し構想を練っていても、文章にして初めて気が付くことが必ず出てきます。たぶん、その気付きがなければ、私にとって書く意味はないと思うんです。結論を決めてそこに向かって書いていくのではなく、今書いている一行が次の一行を連れてくることを信じて書いています。
次ページ: 被害者を描くだけが、戦争ではない。
梯久美子が語る「私がノンフィクションを書く理由」
Books 文化 2019.03.05
幸脇 啓子 【Profile】
“亡くなっていても、知り合える”と感じるほどの丹念な取材と精緻な文章で、数多くの賞を受賞したノンフィクション作家の梯久美子さん。戦争と昭和を題材にした作品が多い彼女に、平成の終幕を目前に話を聞いた。
梯 久美子 KAKEHASHI Kumiko
ノンフィクション作家。1961(昭和36)年熊本県生まれ。北海道大学文学部卒業後、編集者を経てフリーの文筆家に。2006年に『散るぞ悲しき ―硫黄島総指揮官・栗林忠道―』で、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。同書は、世界8カ国で翻訳出版されている。2017年には『狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ』で講談社ノンフィクション賞、読売文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞を受ける。その他の著書に『昭和二十年夏、僕は兵士だった』『昭和の遺書──55人の魂の記録』など多数。最新作は『原民喜―死と愛と孤独の肖像』。
TwitterFacebook56印刷お気に入りもっと見る39
他の言語で読む
第2次世界大戦で、日米の兵士が文字通り死闘を繰り広げた硫黄島。そこで2万人の兵を率いて日本軍の指揮を執った栗林忠道中将を、デビュー作『散るぞ悲しき』で描き、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞したノンフィクション作家の梯久美子さん。栗林中将の生きざまは、クリント・イーストウッド監督の映画『硫黄島からの手紙』では俳優・渡辺謙さんが演じ、話題となった。その後の著書『狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ』では数々の賞に輝き、近著では原爆作家と呼ばれた原民喜の人生を追っている。日本を代表するノンフィクション作家、梯さんに尋ねる「ノンフィクションを書く」ということとは。そして平成が終わろうとする今、遠くへ去りゆく昭和は、彼女の目にどう見えているのだろうか。
亡くなっていても、知り合える
——梯さんが、ノンフィクションを書くモチベーションはなんでしょうか。
理解したい、という欲望でしょうか。知りたいことを深く知るための手段が、私にとってのノンフィクションを書くということ。私が書いているのは評伝というジャンルなので、書く対象は「ひと」。だからまずはシンプルに「好き」という気持ちから出発します。へえ、というエピソードがあったり、手紙や日記などのプライベートな文章に胸を打たれたり。あと、外見に惹かれるということもあります。島尾ミホさんの場合は、老境に入ってからの写真を見て、異様な美しさを感じたのがきっかけでした。もしかしたら恋愛と似ているかもしれませんね。好きになる相手が必ずしも人間としていい人とは限らないのも恋愛と同じです(笑)。
器用ではないし、頭もよくないので、自分の手で書いてみないと、その人のことが分からないんですね。取材にも執筆にも時間がかかって、特に執筆は、3行書いて5行消す、というようなペースで書いているので、遅々として進みませんが、そうやって苦しみながら文章にすることで、ようやく、その人のことが見えてくる。なぜその人のことを好きになり、書く必要があったのかも、少しずつですが、分かってきます。そうすると、相手がすでに亡くなっている人であっても、徐々に知り合っていく感じがある。この人とは知り合いになったな、と感じられたのは、栗林忠道と島尾ミホ、そして原民喜。いずれも、書くのに難渋した人です。
この人のことをもっと知りたいとスイッチが入るのは、それまでのイメージと異なる一面にぶつかった時ですね。栗林中将は、2万人の兵士を率いて戦史に残る闘いをした硫黄島の指揮官ですが、戦地から東京の家族に宛てた手紙では「お勝手の床板の隙間は塞(ふさ)げただろうか?」と心配し、対処法を言葉で指示するだけでなく、絵まで描いて伝えています。そういう所帯じみたところが意外でした。島尾ミホは、夫の島尾敏雄が書いた『死の棘』の影響もあり、狂うほど夫を愛した聖女というイメージを持たれていました。でも、生前にご本人とお話しした際に、「それって本当?」と思ったんです。女優さんのような、ちょっと芝居がかった感じの方なんですね。
左から『散るぞ悲しき ―硫黄島総指揮官・栗林忠道―』、『狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ』(共に新潮社刊)、『原民喜 死と愛と孤独の肖像』(岩波書店)
——最新作の『原民喜』は、どこでスイッチが入ったのですか。
故郷の広島で被爆し、その経験を「夏の花」で書いた原民喜のこれまでのイメージは、「教科書に載っている原爆作家」。でもいろいろ調べてみると、いいところのお坊ちゃんで、旧制中学校時代の5年間、クラスメートが一人も彼の声をきいたことがなかったという極度の人見知りで、かつ引きこもり。生涯で得た友人は同人誌の仲間だけという、今でいう“コミュ障”です。そして、俳号を「杞憂」としたほど怖がりだった。それなのに、轢死という恐ろしい方法で自殺を遂げる。「なぜ?」という疑問からスタートしました。
ただ、構成には悩みました。生まれてから死ぬまでを時系列で追う方法もありましたが、散々悩んだ末、私が一番こだわっているこの「なぜ?」を読者と共有しようと決め、冒頭に自殺する場面を持ってきました。最期を描いた序章だけで、1カ月以上かかっています。
どの本もそうですが、書き出す前にいかに綿密に取材し構想を練っていても、文章にして初めて気が付くことが必ず出てきます。たぶん、その気付きがなければ、私にとって書く意味はないと思うんです。結論を決めてそこに向かって書いていくのではなく、今書いている一行が次の一行を連れてくることを信じて書いています。
次ページ: 被害者を描くだけが、戦争ではない。