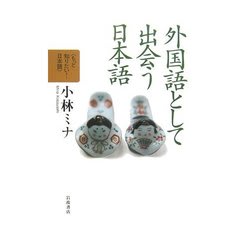FreakonomicsのPodcastはつねに楽しみにしていますが、過去、もっとも面白かったものが、The economist’s guide to parenting(経済学者による子育てガイド)です。そこで、Studies show…と断って言われていたことの一つが「その他の条件を同一にしたとき、子供を持っている人のほうが持たない人よりも(平均すると)幸福度が低い」ということ。この間、それを裏付ける学術論文を探し出しました。
Clark, A.E., Diener, E., Georgellis, Y. & Lucas, R.E. (2008). Lags and leads in life satisfaction: A test of the baseline hypothesis. Economic Journal, 118, F222-243.
この論文の存在を教えてくれた、Nattavudh Powdthavee氏の論文(Think having children make you happy? The psychologists, 22-4) によると、他にも数多の研究があるらしい。
Clark他の論文は、ドイツの男女各のべ65000人程度という膨大なデータで、子供の誕生の4年前から5年後までの時系列の(主観的な)幸福感の変化を追っています。誕生前に幸福度は上昇、平均を上回るが、誕生後すぐに落ち、平均以下に、そのまま低い値を維持し、やっと4~5歳ごろ平均に戻る、というものでした。女性・男性ともほぼ同一の変動を示します。
Powdthavee論文は、多くの人は、「子供がいる人生はより幸せ」と思うものだが、その印象と、データが示す「現実」とが食い違う理由は、Focusing Illusionが原因だと説明しています。人は、稀に訪れる、大きな喜びに強く印象付けられるので、意識的に振り返ったときには、子供が立ったとか、話したとか、その他、感動的なシーンを思い出して、幸せだ、と思う。しかし、実際の子育ての日常の大半は単調で辛い行為の繰り返しで、感じている幸福感をリアルタイムで追っていくと、ストレスを感じていたり、疲れていたり……。一人で歩いていて、お子さんを連れたお母さんが、険しい顔でプリプリ怒って歩いているのを見かけることがあって、「どうしてあんなかわいい子と一緒にいるのに、あんなに不機嫌?」と、とても不思議に思うのですが、むしろこれこそが日常の親の姿なのかもしれません。娘と幼稚園から帰るときの私も、どんな顔をしているのか。
じっさい、個人的な経験に照らしても、上記の知見には納得できる点があります。娘が生まれる前は、幸せと希望にほんわかと包まれていました。ところが生まれて2日目、病院から帰らねばならない夜(米国は短い)、突然、強烈な不安に襲われました。これから何の経験もないわれわれ二人が、この小さな、新しい命を守っていけるものだろうか、と。現実がやってきたわけです。
その後は、ある米国人のお母さんに言われたYou suddenly cease to be someone you used to be, and become someone’s parent.という言葉通り。行動が何から何まで子供の存在によって制限を受け、生活が一変しました。たまに嫁さんと、子供が生まれる前、二人の暮らしも楽しかったね~、と、もう決して戻ってこない過去を懐かしく思い返すことがあります。幸いうちの娘は元気で、望んだとおりやさしい子で、申し分ありません。とてつもない幸せを与えてもらっていると、自分たちの子として生まれてきてくれたことに感謝する日々ですが。
このような学術研究の知見の、方法論や前提の範囲内での有効性は確かだろうと思います。でも、子供がいることで幸せになるかどうかには、個人・状況による大きな変動があるでしょうし、まして研究結果からどんな知恵を引き出すかということはまた別の問題。
個人的には、こういう知見が役に立って欲しいと思うのが、「子供を持つ(持たない)」ということに対する社会、個人、両方のレベルでの「こだわり」の緩和です。個人的な印象ですが、子供を持つということについて、立場を異にする人々の間での、意見の強い対立をしばしば目にする気がします。子供は持つべき、持たないものは不幸、あるいは人として不完全、逆に子供を持つものが優遇されすぎ、身勝手になる、等等。
「子供を持つことで、人は幸せになるとは限らない」という知見が行き渡ることが、子のいる人、いない人がそれぞれ、子供を持つ人生と持たない人生に、公平な目を向け、お互いの生き方を尊重することにつながらないものでしょうか。そして、子を持つことも、持たないことも、親となる人たちそれぞれの状況の中で、自発的に、周囲からのプレッシャー等も受けることなく選ばれ、子供は、他の誰が幸せになるためでもなく、自分自身のために、生まれてくる。そんなふうに生まれることが、子供にとっていちばん望ましいと思うのです。
Clark, A.E., Diener, E., Georgellis, Y. & Lucas, R.E. (2008). Lags and leads in life satisfaction: A test of the baseline hypothesis. Economic Journal, 118, F222-243.
この論文の存在を教えてくれた、Nattavudh Powdthavee氏の論文(Think having children make you happy? The psychologists, 22-4) によると、他にも数多の研究があるらしい。
Clark他の論文は、ドイツの男女各のべ65000人程度という膨大なデータで、子供の誕生の4年前から5年後までの時系列の(主観的な)幸福感の変化を追っています。誕生前に幸福度は上昇、平均を上回るが、誕生後すぐに落ち、平均以下に、そのまま低い値を維持し、やっと4~5歳ごろ平均に戻る、というものでした。女性・男性ともほぼ同一の変動を示します。
Powdthavee論文は、多くの人は、「子供がいる人生はより幸せ」と思うものだが、その印象と、データが示す「現実」とが食い違う理由は、Focusing Illusionが原因だと説明しています。人は、稀に訪れる、大きな喜びに強く印象付けられるので、意識的に振り返ったときには、子供が立ったとか、話したとか、その他、感動的なシーンを思い出して、幸せだ、と思う。しかし、実際の子育ての日常の大半は単調で辛い行為の繰り返しで、感じている幸福感をリアルタイムで追っていくと、ストレスを感じていたり、疲れていたり……。一人で歩いていて、お子さんを連れたお母さんが、険しい顔でプリプリ怒って歩いているのを見かけることがあって、「どうしてあんなかわいい子と一緒にいるのに、あんなに不機嫌?」と、とても不思議に思うのですが、むしろこれこそが日常の親の姿なのかもしれません。娘と幼稚園から帰るときの私も、どんな顔をしているのか。
じっさい、個人的な経験に照らしても、上記の知見には納得できる点があります。娘が生まれる前は、幸せと希望にほんわかと包まれていました。ところが生まれて2日目、病院から帰らねばならない夜(米国は短い)、突然、強烈な不安に襲われました。これから何の経験もないわれわれ二人が、この小さな、新しい命を守っていけるものだろうか、と。現実がやってきたわけです。
その後は、ある米国人のお母さんに言われたYou suddenly cease to be someone you used to be, and become someone’s parent.という言葉通り。行動が何から何まで子供の存在によって制限を受け、生活が一変しました。たまに嫁さんと、子供が生まれる前、二人の暮らしも楽しかったね~、と、もう決して戻ってこない過去を懐かしく思い返すことがあります。幸いうちの娘は元気で、望んだとおりやさしい子で、申し分ありません。とてつもない幸せを与えてもらっていると、自分たちの子として生まれてきてくれたことに感謝する日々ですが。
このような学術研究の知見の、方法論や前提の範囲内での有効性は確かだろうと思います。でも、子供がいることで幸せになるかどうかには、個人・状況による大きな変動があるでしょうし、まして研究結果からどんな知恵を引き出すかということはまた別の問題。
個人的には、こういう知見が役に立って欲しいと思うのが、「子供を持つ(持たない)」ということに対する社会、個人、両方のレベルでの「こだわり」の緩和です。個人的な印象ですが、子供を持つということについて、立場を異にする人々の間での、意見の強い対立をしばしば目にする気がします。子供は持つべき、持たないものは不幸、あるいは人として不完全、逆に子供を持つものが優遇されすぎ、身勝手になる、等等。
「子供を持つことで、人は幸せになるとは限らない」という知見が行き渡ることが、子のいる人、いない人がそれぞれ、子供を持つ人生と持たない人生に、公平な目を向け、お互いの生き方を尊重することにつながらないものでしょうか。そして、子を持つことも、持たないことも、親となる人たちそれぞれの状況の中で、自発的に、周囲からのプレッシャー等も受けることなく選ばれ、子供は、他の誰が幸せになるためでもなく、自分自身のために、生まれてくる。そんなふうに生まれることが、子供にとっていちばん望ましいと思うのです。