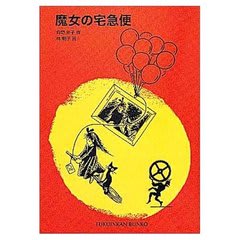吉川洋・著 2016年 中公新書
図書館で発見。現状の分析だけでなく、経済学の理念やその変遷の解説もあって、いろいろ勉強になったけれど(「ジニ係数」の概念・算出法とか)、なにより『「昔はよかった」病』につづき、「戦前の日本はずいぶんひどかった(経済、健康いずれについても不平等がおおきかった)」を再認識。問題もいっぱいあるものの、やっぱり昔にくらべれば日本はうんとマシ、ということのよう。
概略、「日本の長期的後退はまちがいないが、ゆるやかな経済成長はやっぱり必要で、それは人口減少によって妨げられるとはかぎらず、イノベーションによって達成できる」「経済成長は、なにより<健康で長生き>に結実する。長寿国になった日本は、成功なのだ」というような結論と理解したのだけれど、それで、「人口が減るのは問題ない」という結論なのか、やっぱり問題なのか、タイトルに「人口と」とあるわりには、その点についての著者の考えがしめされないままの気がして、「むー、ここで終わっちゃうのか」という読後感。「人口減少は気にするな」という結論なら(末尾にそんなようなことが述べられている)、どういう根拠からそうお考えなのか、論じてほしいな〜と。
Angus Deaton の The Great Escape が、本書にかなり影響をあたえているもよう。Freakonomics で名前をきいたおぼえはありましたが、本書を読んで「これはおもしろいのでは」と、さっそく購入(電子書籍)。すばらしい。これが本書を読んだいちばんの収穫。
図書館で発見。現状の分析だけでなく、経済学の理念やその変遷の解説もあって、いろいろ勉強になったけれど(「ジニ係数」の概念・算出法とか)、なにより『「昔はよかった」病』につづき、「戦前の日本はずいぶんひどかった(経済、健康いずれについても不平等がおおきかった)」を再認識。問題もいっぱいあるものの、やっぱり昔にくらべれば日本はうんとマシ、ということのよう。
概略、「日本の長期的後退はまちがいないが、ゆるやかな経済成長はやっぱり必要で、それは人口減少によって妨げられるとはかぎらず、イノベーションによって達成できる」「経済成長は、なにより<健康で長生き>に結実する。長寿国になった日本は、成功なのだ」というような結論と理解したのだけれど、それで、「人口が減るのは問題ない」という結論なのか、やっぱり問題なのか、タイトルに「人口と」とあるわりには、その点についての著者の考えがしめされないままの気がして、「むー、ここで終わっちゃうのか」という読後感。「人口減少は気にするな」という結論なら(末尾にそんなようなことが述べられている)、どういう根拠からそうお考えなのか、論じてほしいな〜と。
Angus Deaton の The Great Escape が、本書にかなり影響をあたえているもよう。Freakonomics で名前をきいたおぼえはありましたが、本書を読んで「これはおもしろいのでは」と、さっそく購入(電子書籍)。すばらしい。これが本書を読んだいちばんの収穫。