ニューズウィークが、地球から昆虫が消え去ろうとしているという調査報告を掲載しているが、この問題は、地球温暖化に劣らず、深刻な問題である。昆虫が減ったのは、森林の伐採や、都市化で、緑が減った目で、その結果、公害に強いゴキブリやハエなどの害虫が増えているとのこと。そして、農産物の受粉をしてくれる昆虫が少なくなって農業への問題も出てきている。
以下、ニューズウィークのレポート::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
世界中に生息する昆虫の40%が「劇的な減少率」で個体数を減らしていることが、最新の調査で明らかになった。
それによると、ハチやアリ、カブトムシなどは、ほ乳類や鳥類、は虫類と比べて8倍の速さで減少している。その一方で、イエバエやゴキブリといった一部の種は数を増やしているという。
昆虫の全般的な減少は、集中的な農業や殺虫剤、気候変動などが理由とされる。
昆虫は地球上の生命の半分以上を占めて、人類を含め重要な恩恵をもたらしている。
鳥やコウモリ、小型哺乳類には食べ物を与え、世界の穀物の75%の受粉を助け、土を作り、害虫の数を抑制する。
近年の研究では、ハチなど特定の種が、特に先進国で大きく個体数を減らしていることが明らかになっていた。
しかし、学術誌バイオロジカル・コンサベーションによると、過去13年間に発表された73件の既存の調査結果を網羅し、そこから全般的な見解を導き出した。
それによると、昆虫の減少は世界中ほぼ全ての地域で起きており、向こう数十年で全体の40%が絶滅する恐れがある。
現在、昆虫の3分の1が絶滅危惧種だという。
この研究を主導した豪シドニー大学のフランシスコ・サンチェス=バヨ博士はBBCの取材で、この原因の一つ目は「農業や都市化、森林伐採などで生息地を奪われたことが、昆虫が減少している主な要因だ」と説明した。
2つ目は「その次に、世界中の農業で使われる肥料や殺虫剤の影響や化学物質による汚染が挙げられる。3つ目は生物学的要因、つまり侵略種や病原菌によるもの。4つ目には、特に熱帯地域で大きな影響を与えている気候変動がある」
 Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
イギリスの昆虫愛護団体「バグライフ」のマット・シャードロウ氏は「これはハチだけの問題でも、あるいは受粉や我々の食糧だけの問題でもない。例えばふんを土に戻してくれるフンコロガシや、川や池で生まれるトンボといった昆虫も減少している」と指摘する。
「地球の生態系が崩壊していること、この悲惨な流れを食い止め逆転させるために世界規模で集中的な努力が必要になっていることが、ますます明らかになった。昆虫の緩慢な絶滅を引き続き座視するなど、合理的ではない」
害虫は増加傾向
研究では、昆虫の減少が食物連鎖の上流に与える影響についても懸念を示している。多くの鳥類やは虫類、魚類にとって昆虫は主な食料であり、昆虫の減少は結果的に、こうした生物の絶滅にもつながる可能性がある。
一方、人間にとって特に大事な昆虫が危険にさらされている中、一部の昆虫は環境の変化に適応し、数を増やすだろうとの指摘もある。
最新の豪研究には関わっていない英サセックス大学のデイヴ・グールソン教授は、「繁殖サイクルの速い害虫は、温暖化や、繁殖速度が遅い外敵の絶滅によって、数を増やすだろう」と話した。
「我々が将来、特定種類の害虫増大に悩まされる一方で、ハチやアブ、チョウといった人間にとって有用な素晴らしい昆虫、動物のふんを処理してくれるフンコロガシといった益虫を全て失ってしまう可能性は十分にある」
グールソン教授によると、強じんで適応力が高く雑食のイエバエやゴキブリといった昆虫が、人工の環境に馴染みやすく、殺虫剤への抵抗力を付けていると述べた。
その上で、今回の研究は危険信号を発しているものの、殺虫剤を使わないこと、有機的な食品を選ぶこと、昆虫にやさしい庭造りをするなど、我々にできる対処法はあるとしている。
また、昆虫の減少に関する研究の99%は欧州と北米のもので、アフリカや南米の資料はほとんどないことから、さらなる調査が必要だという。
究極的には大多数の昆虫が絶滅しても他の種に取って代わられるが、それには長い長い時間がかかるという。
「過去に起きた大絶滅を見てみると、その後には大規模な適応放散(一つの祖先からさまざまな種が生まれること)が発生する。少数の種が新たな環境に適応し、絶滅によって空いた席を埋め、新しい種に進化する」と、グールソン教授は説明する。
「つまり100万年たてば、20世紀と21世紀に絶滅した生物の代わりとなる多様な新生物が生まれていることは間違いない」














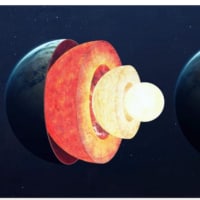

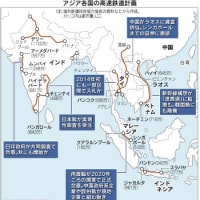
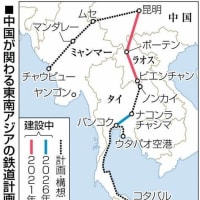

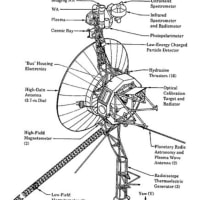
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます