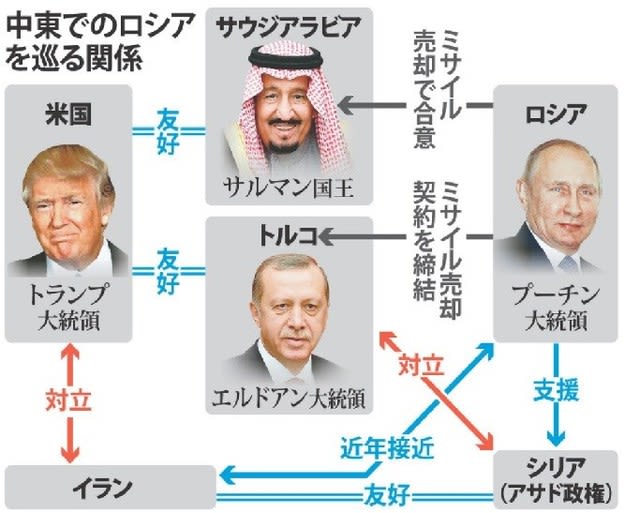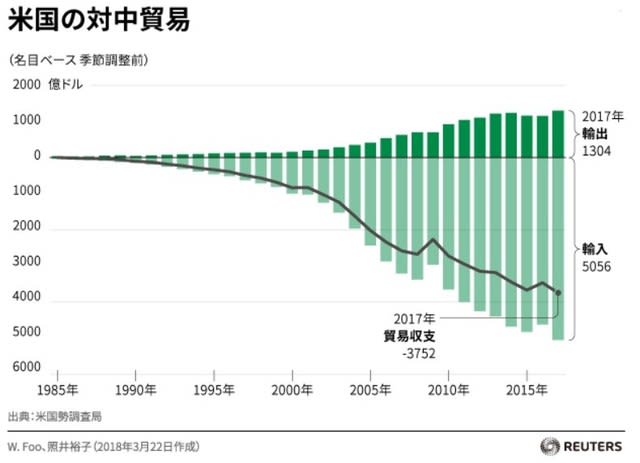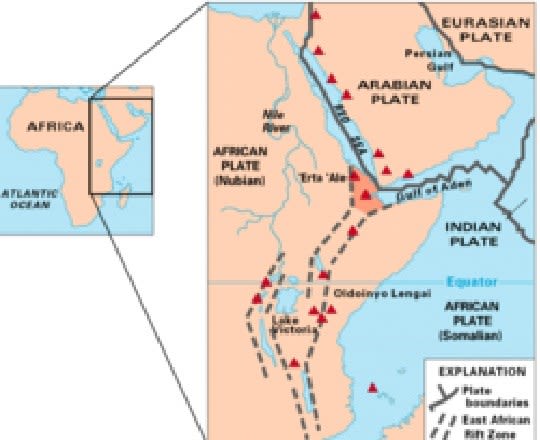日経がファミリーマートの省力化に600億円投資すると報じていた。その概要をみると、ファミリーマートの発想的外れている。
まずはファミリーマートの省力化の内容は 少ない人手で効率的に作業ができる店舗づくりで商品を並べやすいスライド式の陳列棚などの省力化設備を導入する。人手不足たいさくで、働きやすい環境を整えて競争力の向上につなげる。
既存店投資は省力化を柱に据え、おにぎりやサンドイッチ、カップ麺などの陳列棚を引き出し可能なタイプに全店で取り換える。コンビニでは商品の陳列に多くの時間を割いており、売り場に並べたり撤去したりする作業を効率化する効果が大きいとみている。冷蔵の紙パック飲料の売り場では客が商品を取り出すたびに自動で商品が最前列に並ぶ棚も導入する。
主力商品のフライドチキン「ファミチキ」などの揚げ物を店内で調理するフライヤーを従来の2倍の容量にして、商品を作る回数を減らせるようにもする。検品作業を不要とする運用も始め、一連の省力化によって1店舗当たりの作業時間を最大3.5時間減らす効果を見込む。駅前やオフィス街の約1千店には客が自ら会計するセルフレジも導入してレジでの顧客の待ち時間を短縮する。
大手各社は既存店の省力化投資を相次いで進めている。セブン―イレブン・ジャパンは2月までに70億円を投じ、自動の食洗機の設置スペースを確保できる1万3千店に導入。1日あたりの作業時間を約1時間減らした。ローソンでは4月中にも都内でスマートフォンを活用した無人レジの実験を始める。店員の操作が容易な新型レジも19年2月末までに全1万4千店に導入する。
各社が作業効率の向上に動く背景には、コンビニ市場の伸び悩みがある。大手7社の既存店客数は2月末まで24カ月連続で前年を下回る。出店拡大を続けるコンビニ同士の競合のほか、ドラッグストアやインターネット通販に客を奪われているとみられる。各社とも1人当たりの購入金額を伸ばしてきたが、客数の減少が売り上げ拡大の重荷になっている。
客数の伸び悩みに小売業を取り巻く人手不足や人件費の上昇も加わり、加盟店の経営環境は厳しさを増す。経営難に陥る既存店が増えれば、コンビニ市場が持続的に成長することが難しくなる。
コンビニに行って感ずることは、①価格が高い、②客がちょっとでも多いと清算に時間がかかる、③商品やサービスがなんでもありすぎて、店員も答えられないことが多い、④なじみになった店員が次に行くとやめていた、⑤店員のちょろまかしで、売り上げの数%が消えているという。たとえば友人が来たら、商品バーコード・リーダーを使うふりをして唯で渡したり、深夜に店のものを食ったり。
こういったことを改善しないと、先細りは明確で、ICタグを使い入個から在庫そして売り上げ管理をするとか、スマホによる決済を導入したりとかをまずはすべきで、こんなのは、アマゾンやユニクロは取り組んで実際の導入も間じかとなっている。