先週の火曜日に
「第2回関西酒質向上委員会」
が、シティプラザ大阪にて開催された
関西における蔵元・酒販店の交流は
県単位が中心であったので
県の垣根を越えて
関西の個性豊かな面々が一堂に会して
交流、技術研鑽を行う場として
昨年から開催されていたようだ
ひょんなことから
この会への参加を打診されたので
うかがうことにした
関西の参加蔵元は62蔵で
62種類の日本酒をブラインドで利き酒し、評価した
新酒鑑評会のような欠点を引き算する様式の採点方法もあるが
それでは多様な酒質
(生酒・火入れ酒・速醸・山廃・きもと・吟醸・古酒・・・・等々混在)
を評価することはできないので
私は、自分の嗜好にのっとって
「燗につけた時に美味しいか?」
「熟成に耐える強い酒質か? 熟成した時の酒質の将来性」
などを評価基準にした
1(美味しい)~5(不味い)の評価で
「1.4」と採点したのが3酒あった
「睡龍 きもと純米H19BY」(奈良・久保本家酒造)
熟成感半端ないっていうか、古酒とよべるのはこれしかないので分かりやすい・笑)
「忠臣蔵 山廃純米H28BY」(兵庫・奥藤商事)
まだ若い香りがあるが、酸と旨味のバランスも良く爽快に呑める。
以前の忠臣蔵山廃とのギャップに驚愕。
「車坂 五百万石山廃純米H26BY」(和歌山・吉村秀雄商店)
酸が複雑で、立体的な味わいでふくらみがある。燗で美味しい。
また、ほかにも気になるお酒は多数あった(嬉)
そして今回の講師の東京農大の數岡孝幸准教授の
成分から見た62酒の評価が斬新で
面白く、ワクワクしてしまった
事前に出品酒の成分調査をしておいて
当日に味利きして
成分との整合性を感応的に合致させる作業をしておられたようだが
どうしても成分と感応とのギャッ大きいものも少なからずあったようで
これこそが日本酒の複雑や奥深さに繋がるところなんだろうなと思う
そんな數岡准教授の成分評価での「キーワード」がこれだぁ!
「ピルビン酸が残る」
酵母菌は嫌気状況(酸素の少ない状況)で、アルコール発酵を行って、ブドウ糖をピルビン酸を経由してエタノール(エチルアルコール)と二酸化炭素(炭酸ガス)に分解してエネルギーを得る。
ピルビン酸が多量に残っているということは、上槽が早すぎたことを顕す。(言い換えれば、完全発酵ではない)
ただ酸や旨味・甘味の感応的バランス考慮する時には、早く上槽してピルビン酸が多くなることもある。
「酢酸エチル」
エステル香であり、清酒のなかには含まれる成分であるが、多すぎると「セメダイン臭」がきつくなり興ざめする。
酢酸イソアミル(バナナ様の香り)、カプロン酸エチル(りんご様の香り)などとの割合が重要であり
これらのエステル香の比率で、「心地よさ」「エグさ」「落ち着き」「華やかさ」などの香りの特徴が出てくる
酢酸エチルは、カプロン酸エチルや酢酸イソアミルによってマスキングされる。
「乳酸」「酢酸」
きもとや山廃もとでは、自然界(蔵付)の乳酸菌由来の乳酸が生成され、酸の複雑さの礎になるが、乳酸と一緒に生成される酢酸成分の異常に多いものがあり、個性的な酒質を主張する。私の嗜好的には、これもど真ん中!
味の多さ(複雑さととらえるのか、未熟さととらえるのかは・・・??)と、乳酸と酢酸、そして熟成期間のコラボで、著しく特徴的な旨い酒ができるのだが・・・
こんな多様な酒が日の目を見るのも間近か??
色々勉強になること数多(あまた)・・・
この会を主催していただきました
「山中酒の店」様、「銘酒館タキモト」様、「すみの酒店」様、「酒のやまもと」様、
ありがとうございます。m(__)m
本当に勉強になりました。
「第2回関西酒質向上委員会」
が、シティプラザ大阪にて開催された
関西における蔵元・酒販店の交流は
県単位が中心であったので
県の垣根を越えて
関西の個性豊かな面々が一堂に会して
交流、技術研鑽を行う場として
昨年から開催されていたようだ
ひょんなことから
この会への参加を打診されたので
うかがうことにした
関西の参加蔵元は62蔵で
62種類の日本酒をブラインドで利き酒し、評価した
新酒鑑評会のような欠点を引き算する様式の採点方法もあるが
それでは多様な酒質
(生酒・火入れ酒・速醸・山廃・きもと・吟醸・古酒・・・・等々混在)
を評価することはできないので
私は、自分の嗜好にのっとって
「燗につけた時に美味しいか?」
「熟成に耐える強い酒質か? 熟成した時の酒質の将来性」
などを評価基準にした
1(美味しい)~5(不味い)の評価で
「1.4」と採点したのが3酒あった
「睡龍 きもと純米H19BY」(奈良・久保本家酒造)
熟成感半端ないっていうか、古酒とよべるのはこれしかないので分かりやすい・笑)
「忠臣蔵 山廃純米H28BY」(兵庫・奥藤商事)
まだ若い香りがあるが、酸と旨味のバランスも良く爽快に呑める。
以前の忠臣蔵山廃とのギャップに驚愕。
「車坂 五百万石山廃純米H26BY」(和歌山・吉村秀雄商店)
酸が複雑で、立体的な味わいでふくらみがある。燗で美味しい。
また、ほかにも気になるお酒は多数あった(嬉)
そして今回の講師の東京農大の數岡孝幸准教授の
成分から見た62酒の評価が斬新で
面白く、ワクワクしてしまった
事前に出品酒の成分調査をしておいて
当日に味利きして
成分との整合性を感応的に合致させる作業をしておられたようだが
どうしても成分と感応とのギャッ大きいものも少なからずあったようで
これこそが日本酒の複雑や奥深さに繋がるところなんだろうなと思う
そんな數岡准教授の成分評価での「キーワード」がこれだぁ!
「ピルビン酸が残る」
酵母菌は嫌気状況(酸素の少ない状況)で、アルコール発酵を行って、ブドウ糖をピルビン酸を経由してエタノール(エチルアルコール)と二酸化炭素(炭酸ガス)に分解してエネルギーを得る。
ピルビン酸が多量に残っているということは、上槽が早すぎたことを顕す。(言い換えれば、完全発酵ではない)
ただ酸や旨味・甘味の感応的バランス考慮する時には、早く上槽してピルビン酸が多くなることもある。
「酢酸エチル」
エステル香であり、清酒のなかには含まれる成分であるが、多すぎると「セメダイン臭」がきつくなり興ざめする。
酢酸イソアミル(バナナ様の香り)、カプロン酸エチル(りんご様の香り)などとの割合が重要であり
これらのエステル香の比率で、「心地よさ」「エグさ」「落ち着き」「華やかさ」などの香りの特徴が出てくる
酢酸エチルは、カプロン酸エチルや酢酸イソアミルによってマスキングされる。
「乳酸」「酢酸」
きもとや山廃もとでは、自然界(蔵付)の乳酸菌由来の乳酸が生成され、酸の複雑さの礎になるが、乳酸と一緒に生成される酢酸成分の異常に多いものがあり、個性的な酒質を主張する。私の嗜好的には、これもど真ん中!
味の多さ(複雑さととらえるのか、未熟さととらえるのかは・・・??)と、乳酸と酢酸、そして熟成期間のコラボで、著しく特徴的な旨い酒ができるのだが・・・
こんな多様な酒が日の目を見るのも間近か??
色々勉強になること数多(あまた)・・・
この会を主催していただきました
「山中酒の店」様、「銘酒館タキモト」様、「すみの酒店」様、「酒のやまもと」様、
ありがとうございます。m(__)m
本当に勉強になりました。






















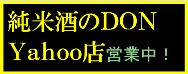












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます