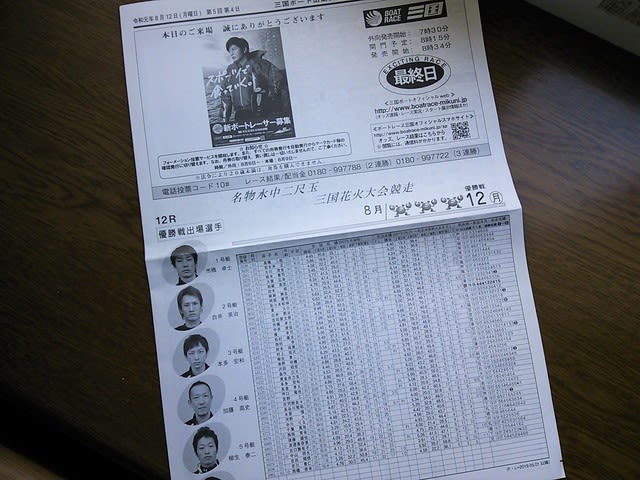きのう、家から最も近いレース場「三国競艇」へ行ってきた。
津幡町からは、高速を走り、片道1時間半程度の距離。
これだけ近いのだから、頻繁に足を運んでいてもよさそうなのだが、
訪問回数は「常滑競艇」→「びわこ競艇」→「三国競艇」の順。
ご近所のため、僕の気持ちでは「旅打ち」の情緒に欠けるのかもしれない。

展示を見て、出走表と睨めっこし、勝敗の行方を予想して、投票。
場外舟券売場(最近はボートレースチケットショップと呼ぶらしいが)と、
やる事は変わらないが、当然の事ながら臨場感がある。
改めて、本場はいいものだと実感した。
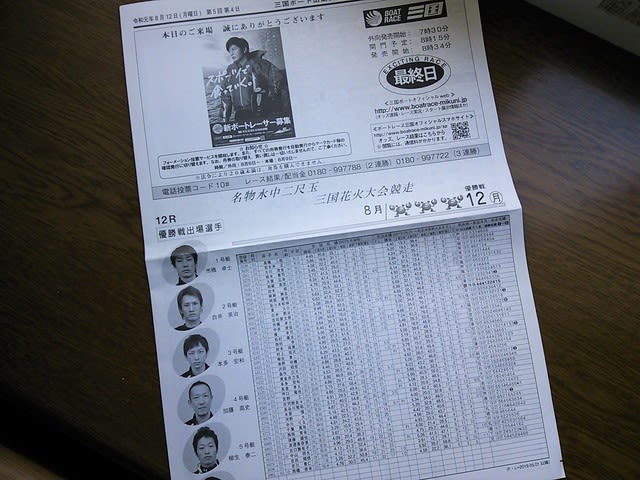
この日は、一般戦4日シリーズの最終日。
「名物水中二尺玉 三国花火大会競走」と銘打たれているのは、
前日(8月11日)に行われた、夏のイベントと連動しているからだ。

最高気温35度の中、レーサー達は熱戦を繰り広げてくれた。
12レースのうち、イン逃げは8本。
4本が捲り決着。
やはり、猛暑が影響したのか?小波乱~中穴~高配当も飛び出す。

僕の舟券は、まあまあ的中を得る。
思い返すと「惜しい展開」、「悔いの残る選択」もあったが、
プラス収支だから文句は言うまい。

三国競艇は、現在「モーニング開催」。
第一レース発走は、午前8:50と通常の時間帯より早くスタート。
最終レースは、14:48。
途中、一舟300円のたこ焼きを購入し糊口を凌ぎつつ、
優勝戦、1-2-5の順当決着を見届ける。

9月18日~23日まで開催されるプレミアムG1、
「第6回ヤングダービー」での再訪を誓い、
本場を後にし「ヨーロッパ軒」へ向かった。

“創業者、高畠増太郎がドイツ・ベルリンの日本人倶楽部での
料理研究の留学を終え、明治45年帰国。
(天皇の料理番の秋山徳蔵氏も同期)
ドイツ仕込みのウスターソースを日本人の味覚に普及さすべく
苦心を重ね、創案致しましたのが、
翌大正2年 東京で開かれた料理発表会にて
日本で初めて披露しました『ソースカツ丼』でございます。”
(※ヨーロッパ軒HPより抜粋、引用)
日本で初めて丼飯の上にトンカツを乗せた元祖・カツ丼。
「ヨーロッパ軒」とソースカツ丼は、福井名物だ。
到着は午後3時を過ぎていたが、しばし入店待ち。
人気店なのである。
・・・と、ここで「福丼県」なる幟を発見。

福井県は、お米の代表的品種「コシヒカリ」の発祥の地。
また、食材を生かした丼文化はとても豊か。
2014年9月29日、「くうふく(9・29)の日」に「福丼県プロジェクト」を始動。
福井県民80万人が総出で、丼でおもてなししようという訳だ。
・・・と、ここで幟の下部、見慣れたロゴに気付く。
 ここにも俺たち(競艇ファン)の銭が関わっていたのかっっ!
ここにも俺たち(競艇ファン)の銭が関わっていたのかっっ!
日本財団は、競艇の売上金の約2.8%を交付金として受け入れ、
国内外の公益事業を実施している団体への事業支援を行っている。
遠慮なくいただこう!

席に着き、「カツ丼」(930円)を注文。
以前、他の店でいただいた時の器は瀬戸物だった。
いざ、オープン!!

途端に、ウスターソースと香辛料の匂いが鼻孔をくすぐる。
薄くスライスしたロース肉やモモ肉を目の細かな特製パン粉にまぶし、
ラード・ヘッドでカラリと揚げたカツ。
噛み締めると、サクサクとした心地いい食感。
広がる甘みと酸味、肉の脂。
ご飯との相性もバツグン。
旨いのである。

さぁ「ミニボートピア津幡」に戻り、蒲郡競艇場で行われている
「第33回 レディースチャンピオン」優勝戦に投票だ。
最年少記録がかかる、福岡支部トップルーキーの1号艇か。
唯一人、地元・愛知支部から勝ち残った4号艇か。
どちらかの戴冠を望んで張る。
進入は123/456枠なりの3対3。
1号艇がコンマ01のトップスタート。
捲り差しを狙う3号艇の舳先が入りかけたが、
引き波で艇が浮き上がり、間隙を4号艇が突いた!
1は一人旅。
3と4の熾烈な2~3着争いの結果1-4-3でゴール!

見たかった光景も、的中舟券も恵んでもらった。
「大山千広」選手、おめでとう!!
ニューヒロイン誕生の瞬間に立ち会い満足至極。
朝から晩まで、競艇の愉悦に浸りお腹いっぱい。
ごちそう様でした!