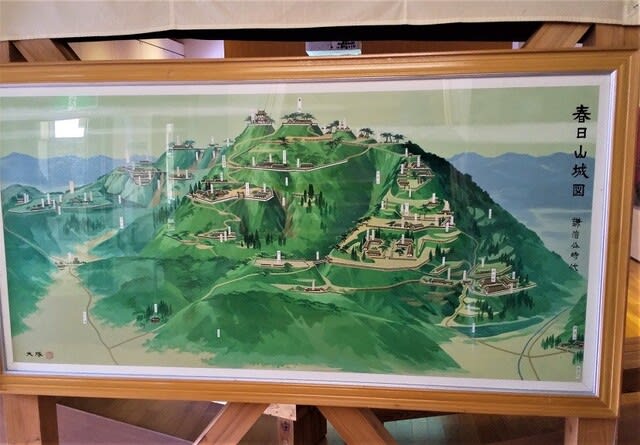季節は次のステージへと進んでいる。
ここ北陸も例外ではないが、まだ寒さも残る中、
春を感じさせてくれるのが、可憐に咲き香る「梅の花」だ。

大陸に渡った遣隋使や遣唐使、僧侶らが苗を持ち帰り普及したと考えられる梅。
8世紀半ばに編まれた「万葉集」で梅を題材にした歌は110首。
ちなみに桜モチーフが43首止まりだから、梅の人気ぶりが窺える。
--- また、次の歌も有名ではないだろうか。
東風(こち)吹かば 匂いおこせよ梅の花 あるじなしとて春を忘るな
作者は“学問の神様”とされる「藤原道真」。
都での権力争いに敗れた「道真公」が九州・大宰府に左遷される際、
日頃慈しんでいた梅に別れを告げて詠んだとか。
すると、梅の木は一晩にして500キロ余りを飛翔。
太宰府天満宮に根を下ろしたという。
わが津幡町を含む加賀を治めた大名「前田家」は、
この「飛梅」に象徴される「道真公」を祖とするとして、梅の意匠を家紋に定めた。


そんな歴史的背景もあってか、町立学校の校章には梅がデザインされている。
上掲画像、順に「津幡小学校」→「津幡中学校」。
早春に花開く力強さ。
香りで周囲を華やぐ奥ゆかしさ。
梅の花の如く成長して欲しいとの願いを込めた。
小学校も、中学校も、僕が通っていた当時とは違う学び舎になったが、
母校は、今も花のエンブレムを戴いている。

白鳥橋の上で、部活へ向かう後輩とすれ違った。
名も知らぬ彼女をはじめ年若い方々へのエールとして、
また、きのう大震災から11年の節目を迎えた東北への励ましとして、
力強い女性ボーカルを贈りたいと思う。
出だしはやゝ声量大きい。
環境によっては再生前にスピーカーレベルを落とした方が無難かもしれない。
では--- 。
2007年リリース「Metis(メティス)」、「梅は咲いたか 桜はまだかいな」。
梅は咲いたか? 桜はまだかいな?
ただただ ひらひら 華麗に舞い待ちわびる花
梅は咲いたか? 桜はまだかいな?
ただただ ひらひら 華麗に舞い待ちわびる花
なにげなく 過ごした日々が こんなに大切なものだったと知った
春の日差しが 止まる足押して 僕たちは言葉につまった
たわいもない言い争い 笑いあった日
そんな些細な出来事を 思い出しては時は過ぎ去った
誰の上にも 歩き始めるために桜は咲くのさ
全てに意味があることのように 君に桜は咲くのさ
カバンはいらない 古い荷物は捨てなさい
まだ今始まったから 道は長い
あるとき春が訪れるとき あなたたちから始める時代
梅は咲いたか? 桜はまだかいな?
ただただ ひらひら 華麗に舞い待ちわびる花
恋は咲いたか? 愛はまだかいな?
ただただ ひらひら 華麗に舞い待ちわびる花
誰でも心の奥に卒業できないものがあるでしょう?
「人は弱くもあり 強くもある」だから人は支えあえるはず
掴むために風は吹いてく
人は生きるために息をしてる
愛する誰かのために今歌う
この声がどこまでも届きます様に
誰の上にも 歩き始めるために桜は咲くのさ
全てに意味があることのように 君に桜は咲くのさ
カバンはいらない 古い荷物は捨てなさい
まだ今始まったから 道は長い
あるとき春が訪れるとき あなたたちから始める時代
誰の上にも 歩き始めるために桜は咲くのさ
全てに意味があることのように 君に桜は咲くのさ
カバンはいらない 古い荷物は捨てなさい
まだ今始まったから 道は長い
あるとき春が訪れるとき あなたたちから始める時代
梅は咲いたか? 桜はまだかいな?
ただただ ひらひら 華麗に舞い待ちわびる花
恋は咲いたか? 愛はまだかいな?
ただただ ひらひら 華麗に舞い待ちわびる花
<作詞/作曲:Metis「梅は咲いたか 桜はまだかいな」>