五十七年ぶりの日本での夏季大会となった東京五輪が閉会した。競技に挑んだ選手やコーチ、運営に尽力した関係者の努力はたたえたいが、招致の在り方から感染症が拡大する中での大会開催まで、私たちが学ぶべき教訓は多い。
一八九六年にギリシャのアテネで始まった近代五輪は国際情勢の影響を強く受けてきた。世界大戦で三度中止され、今回の東京大会は新型コロナウイルスの感染拡大で、初めて一年延期した大会として五輪史に名を刻む。
会場のほとんどは無観客となり日本国民の大多数はテレビで観戦した。選手やコーチ、大会関係者は「バブル方式」という、外部との接触を遮断された「泡」の中で過ごし、感染すれば排除され、観光で外出すれば指弾される。
こんな状況を目の当たりにすれば、コロナ禍の日本で今、開催する意味が本当にあったのか、との思いを抱くのは当然だろう。
復興五輪掛け声倒れ
一九六四年に続く二度目の東京大会は、開催そのものが目的のような大会だった。
戦災復興を掲げた前回に倣い、二〇一三年の招致当時、東日本大震災からの「復興五輪」をうたった。当時の安倍晋三首相は原発事故の影響を懸念する国際社会に対し「アンダーコントロール(管理下にある)」とアピールしたが、事故の影響はいまだ続き、特に福島復興は道半ばだ。
「復興五輪」の掛け声も、感染拡大とともに「人類がウイルスに打ち勝った証しとなる大会」「世界の団結の象徴として実現する」へと簡単に変転していく。
大会経費を節減するため、会場を都心に集約する「コンパクト五輪」を構想したが、炎暑の大会に選手への影響が懸念されると、マラソンや競歩を札幌=写真=に移転するなど、会場は拡散した。
一三年の招致立候補時は七千三百四十億円とされた大会経費はすでに、少なくとも倍以上の一兆六千億円以上に膨れ上がっている。
新型コロナの感染拡大で想定が大きく外れたにせよ、当初掲げた理念は、いずれも破綻は明白だ。
そもそも復興五輪だのコンパクト五輪だのということ自体が、招致のための方便だったのではないか。招致のロビー活動に買収疑惑が持たれたことも、理念なき五輪を強く印象づけてしまった。
無観客でスポーツ大会の巨大な集合体と化した五輪を、感染の危険を冒してまで開催する必然性があったのだろうか。
感染拡大下での開催強行には国際オリンピック委員会(IOC)の意向があったのだろう。一度決めれば、軌道修正が難しいのは、組織の弊害そのものだ。最古参のIOC委員が「予見できないアルマゲドン(世界最終戦争)でもない限り実施できる」と言い放ち、日本国内の開催中止論を一蹴したことを忘れるわけにはいかない。
収入の七割以上に当たる巨額の放映権料を米国のテレビ局などから得ることでIOCの組織は肥大化し、商業化も過度に進む。
かつての東京大会は十月のさわやかな青空の下で開かれたが、巨大マネーは夏季五輪を、米国内のプロスポーツ中継に影響がない夏の時期に固定してしまった。
巨大マネーで炎暑に
日本の七、八月は炎暑にもかかわらず「温暖」「理想的な気候」という虚偽の表現でしか、招致できない現実が迫る。地球温暖化が進めば、北半球での夏季五輪開催は困難になるに違いない。
国連機関でも何でもないIOCの硬直的で、国家主権をも顧みない独善的な体質に、私たちはもっと早く気付き、学ぶべきだった。
もちろん五輪混乱の原因はIOCだけには帰せない。歩調を合わせて五輪と感染拡大との関係を否定し続ける菅義偉首相をはじめ日本政府の責任は、特に重い。
首相は中止論を一顧だにせず、楽観的なメッセージを発信し続けた。そのことは五輪開催中、日本全国を祝祭空間に変え、感染を急速に拡大させた。国民にとどまらず、選手や大会関係者らの命と健康を危機にさらしている。
首相は一体、どう責任を取るつもりなのか。
平和への希求や人間の尊厳など五輪が掲げる理念は、今後も最大限尊重されるべきだ。ただ、IOCや、今大会では日本政府が、それらを実践するにふさわしい存在でないことも、感染拡大下での大会強行が浮き彫りにした。
そのことに気付けたことがせめてもの救いであろうか。それにしても私たち日本国民は、巨額の代償を支払うことになったが…。
















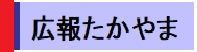












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます