米どころ、酒どころ、水どころの新潟県を旅することにした。現役の頃、担当した所で懐かしく、今回の旅を思いつた。
関越道、練馬ICから湯沢スタート。
川端康成の「雪国」のモデルになった越後湯沢、「雪国」では「長いトンネル」というのは上越線の清水トンネル、はじめに列車が止まった「信号所」は
土樽信号場(現、土樽駅)と思われる。JR上越線。
「雪国」の本文で「汽車」とあり、ドラマなどで紹介される蒸気機関車に牽引された列車の映像が出されることがあるが、上越線の該当区間は長大トンネルの
煙害対策のために初めから直流電化で開業していた。
高速道の「関越トンネル」は、 利根郡みなかみ町の谷川岳PAと、南魚沼郡湯沢町の土樽PAの間のトンネルで、全長は上り 線が11055m、下り線は10926mで、
山岳道路のトンネルでは日本最長と云われている。トンネルを抜けると山の頂上は、雪化粧に驚いた。
新潟県は、日本列島日本海中央部で、三国山脈、越後山脈、東北、関東地方と区切られて、福井、石川、富山、北陸三県と電力会社を統合し北陸に含んで
北陸四県と云う人もいる。
湯沢魚沼郡は、三国街道の宿場町として栄え、大正時代からスキー場が開設され、現代は、東京都湯沢町、都心から2時間のリゾート地として
発展している。

「湯沢温泉」は、 歴史は古く、今から800年ほど前、新発田藩士の高橋半左エ門という人が急病の折に、この地に野宿をし、食事をするために谷川へ入ったところ
湯ノ沢川の奥で、偶然、天然湧出の湯沢温泉を発見し、それが始まりと伝えられている。

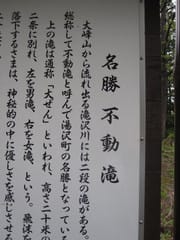

雪国と越後湯沢温泉は、 主水公園に「雪国」の石碑がある。「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった」で始まる川端康成 の小説、
雪国はここ越後湯沢を舞台に描かれた。
湯沢温泉街


「白瀧酒造」は、 湯沢は越後と江戸とを結ぶ、三国街道の宿場町だったため、初代当主の湊屋藤助が、ここに宿を開き、宿泊客や旅人に茶菓子と酒を提供したのがはじまり、
創業1855年(安政2年)以来、豪雪地帯ならではの三国山脈からの豊富な雪どけ水を水源とし、蔵の地下にある井戸からくみ上げる「水」を使い、酒づくりをしている蔵。


新潟県は、酒王国として全国に名を知られるのも、その「酒」の原料ともなる「米」「水」に恵まれていることも理由の一つ。
「水」について、ここ、白瀧酒造では、創業以来一貫して、敷地内の井戸からくみ上げられる地下水を利用。
湯沢の地下水の水脈は、大きく分けると3つの層に分けられ、浅い方から順に、①鉄分の多い地下水脈、②鉄分の少ない軟水の地下水脈、③温泉水脈となっているという。
酒造りにもっとも適しているのが、②の鉄分の少ない地下水。
「米」については、山田錦や五百万石という品種を使用し、酒に使うには、食用飯米よりも多めに精米して60%ほど削るため、小粒な米粒となる。
また、白瀧酒造は、全般に、精米歩合が高いのが特徴、白瀧酒造が純米吟醸酒中心の酒造りをしている為。
近代的な酒造り工場



主な銘柄、「上善如水」、2500年以上前の中国の思想家・老子の言葉、 「もっとも理想的な生き方(上善)は、水のようである」白瀧酒造は、
この老子の思想に重ね合わせた、「最良のお酒は限りなく水に近づく」と考え、 柔軟性のあるお酒を作り、「上善如水」。澄みきった水の如き日本酒。
増築中


「坂戸城」は、中世越後の魚沼郡南部には上田荘があり、鎌倉時代頃には清和源氏流新田氏一族の勢力下にあって、当時、荘の中心を扼する坂戸山に城郭が
築かれていたものとも推定されるが、本格的な造営は南北朝時代にはいって以降のことと考えられている。
南北朝動乱において、北朝方に立った上杉氏は、越後国南部から南朝方に属した新田氏らを放逐し、上杉憲顕のときに越後の守護に任じられたが、
その家臣長尾高景の一族の者が、文和年間(1352年-1355年)に上田荘を領し、上田長尾氏を称して、坂戸山を居城にしたと伝承される。
こののち上田長尾氏は、守護代の長尾氏とならんで越後国に枢要な位置を占めた。その居城である坂戸城は、越後府中と関東平野を結ぶ陸上交通の抑えとして、
また、魚野川を利用した河川交通の要所として、さらに魚沼の穀倉地帯を擁する経済上の要地として、重要な役割を担うこととなった。


魚野川をはさんで、三国街道を見下ろす交通上の要地に位置する。(国の史跡に指定)。
上田長尾氏ゆかりの城として知られており、長尾政景や上杉景勝、直江兼続の居城として名高い。上杉謙信の姉仙桃院の嫁ぎ先でもある。
また上杉景勝が会津へ移され、かわって堀氏が越後に入ると、堀直寄が坂戸城主を務めたことで知られる。
直江兼続像



一度も落城したことが無い越後の要塞「坂戸城」は、上杉景勝、直江兼続公の故郷である。
城跡 公園内


上杉景勝 1555-1623 初代米沢藩主、長尾政景の子、母は謙信の実姉、謙信の養子に、小田原征伐、朝鮮出兵、会津120万石就任、関ケ原で減封され米沢30万石。
直江兼続 1560-1619 上杉家の名家宰、米沢城主 晩年、米沢の地に禅林文庫を創建し、貴重な古典籍を収集保管や整理に努めた。



「お酒の話」
日本酒の歴史は古く、2000年前縄文晩期に「噛酒」(米を口の中で唾液と一緒に噛み砕き壺に寝かして醗酵させる酒)が残って居る日本独自で、
秋実った新米を寒い冬に仕込む「寒造り」は、醪の温度管理が楽で有害細菌が少ない時が良いので、冷房設備が進んでも寒造りは、何処の蔵も、変えがたいのが現状である。
次回は八海山へ
関越道、練馬ICから湯沢スタート。
川端康成の「雪国」のモデルになった越後湯沢、「雪国」では「長いトンネル」というのは上越線の清水トンネル、はじめに列車が止まった「信号所」は
土樽信号場(現、土樽駅)と思われる。JR上越線。
「雪国」の本文で「汽車」とあり、ドラマなどで紹介される蒸気機関車に牽引された列車の映像が出されることがあるが、上越線の該当区間は長大トンネルの
煙害対策のために初めから直流電化で開業していた。
高速道の「関越トンネル」は、 利根郡みなかみ町の谷川岳PAと、南魚沼郡湯沢町の土樽PAの間のトンネルで、全長は上り 線が11055m、下り線は10926mで、
山岳道路のトンネルでは日本最長と云われている。トンネルを抜けると山の頂上は、雪化粧に驚いた。
新潟県は、日本列島日本海中央部で、三国山脈、越後山脈、東北、関東地方と区切られて、福井、石川、富山、北陸三県と電力会社を統合し北陸に含んで
北陸四県と云う人もいる。
湯沢魚沼郡は、三国街道の宿場町として栄え、大正時代からスキー場が開設され、現代は、東京都湯沢町、都心から2時間のリゾート地として
発展している。

「湯沢温泉」は、 歴史は古く、今から800年ほど前、新発田藩士の高橋半左エ門という人が急病の折に、この地に野宿をし、食事をするために谷川へ入ったところ
湯ノ沢川の奥で、偶然、天然湧出の湯沢温泉を発見し、それが始まりと伝えられている。

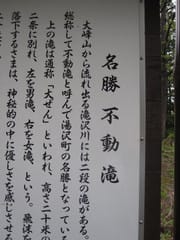

雪国と越後湯沢温泉は、 主水公園に「雪国」の石碑がある。「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった」で始まる川端康成 の小説、
雪国はここ越後湯沢を舞台に描かれた。
湯沢温泉街


「白瀧酒造」は、 湯沢は越後と江戸とを結ぶ、三国街道の宿場町だったため、初代当主の湊屋藤助が、ここに宿を開き、宿泊客や旅人に茶菓子と酒を提供したのがはじまり、
創業1855年(安政2年)以来、豪雪地帯ならではの三国山脈からの豊富な雪どけ水を水源とし、蔵の地下にある井戸からくみ上げる「水」を使い、酒づくりをしている蔵。


新潟県は、酒王国として全国に名を知られるのも、その「酒」の原料ともなる「米」「水」に恵まれていることも理由の一つ。
「水」について、ここ、白瀧酒造では、創業以来一貫して、敷地内の井戸からくみ上げられる地下水を利用。
湯沢の地下水の水脈は、大きく分けると3つの層に分けられ、浅い方から順に、①鉄分の多い地下水脈、②鉄分の少ない軟水の地下水脈、③温泉水脈となっているという。
酒造りにもっとも適しているのが、②の鉄分の少ない地下水。
「米」については、山田錦や五百万石という品種を使用し、酒に使うには、食用飯米よりも多めに精米して60%ほど削るため、小粒な米粒となる。
また、白瀧酒造は、全般に、精米歩合が高いのが特徴、白瀧酒造が純米吟醸酒中心の酒造りをしている為。
近代的な酒造り工場



主な銘柄、「上善如水」、2500年以上前の中国の思想家・老子の言葉、 「もっとも理想的な生き方(上善)は、水のようである」白瀧酒造は、
この老子の思想に重ね合わせた、「最良のお酒は限りなく水に近づく」と考え、 柔軟性のあるお酒を作り、「上善如水」。澄みきった水の如き日本酒。
増築中


「坂戸城」は、中世越後の魚沼郡南部には上田荘があり、鎌倉時代頃には清和源氏流新田氏一族の勢力下にあって、当時、荘の中心を扼する坂戸山に城郭が
築かれていたものとも推定されるが、本格的な造営は南北朝時代にはいって以降のことと考えられている。
南北朝動乱において、北朝方に立った上杉氏は、越後国南部から南朝方に属した新田氏らを放逐し、上杉憲顕のときに越後の守護に任じられたが、
その家臣長尾高景の一族の者が、文和年間(1352年-1355年)に上田荘を領し、上田長尾氏を称して、坂戸山を居城にしたと伝承される。
こののち上田長尾氏は、守護代の長尾氏とならんで越後国に枢要な位置を占めた。その居城である坂戸城は、越後府中と関東平野を結ぶ陸上交通の抑えとして、
また、魚野川を利用した河川交通の要所として、さらに魚沼の穀倉地帯を擁する経済上の要地として、重要な役割を担うこととなった。


魚野川をはさんで、三国街道を見下ろす交通上の要地に位置する。(国の史跡に指定)。
上田長尾氏ゆかりの城として知られており、長尾政景や上杉景勝、直江兼続の居城として名高い。上杉謙信の姉仙桃院の嫁ぎ先でもある。
また上杉景勝が会津へ移され、かわって堀氏が越後に入ると、堀直寄が坂戸城主を務めたことで知られる。
直江兼続像



一度も落城したことが無い越後の要塞「坂戸城」は、上杉景勝、直江兼続公の故郷である。
城跡 公園内


上杉景勝 1555-1623 初代米沢藩主、長尾政景の子、母は謙信の実姉、謙信の養子に、小田原征伐、朝鮮出兵、会津120万石就任、関ケ原で減封され米沢30万石。
直江兼続 1560-1619 上杉家の名家宰、米沢城主 晩年、米沢の地に禅林文庫を創建し、貴重な古典籍を収集保管や整理に努めた。



「お酒の話」
日本酒の歴史は古く、2000年前縄文晩期に「噛酒」(米を口の中で唾液と一緒に噛み砕き壺に寝かして醗酵させる酒)が残って居る日本独自で、
秋実った新米を寒い冬に仕込む「寒造り」は、醪の温度管理が楽で有害細菌が少ない時が良いので、冷房設備が進んでも寒造りは、何処の蔵も、変えがたいのが現状である。
次回は八海山へ









