江戸時代、寺社の占める面積は約366万坪以上。大都市江戸の15%もの広さになる。寺の広さは墓地の広さだった。当時は土葬だったから、100万都市江戸の死者の埋葬にはこれだけの土地が必要だったのである。疫病や大火、地震などによる大量死の場合にのみ火葬が行われた。
人々は焼き場で焼かれるのは、非業の死と受け止めていた、しかし、埋葬のために貴重な土地を拡げ続けることはできなくなり、必然的に火葬の需要が増えてく。
新井薬師の近くに、上高田寺町がある。こちらの寺町も高円寺南寺町、烏山寺町、十一カ寺などと同様と明治末から大正・昭和初めにかけて東京市中から移転してきた寺によって形成された寺町。ここは、早稲田通り沿いの一画。
まずは、「曹洞宗万昌院功運寺」。寺は、もともと別寺院で、「万昌院(牛込)」と「功運寺(芝三田)」の両寺が合併した寺。
万昌院の門楼



「万昌院」は、今川家の開基で、今川家と吉良家は関係あることから、吉良家の墓がある。
「今川 氏真」は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、江戸時代の文化人、駿河国の戦国大名。駿河今川氏10代当主、父義元が桶狭間の戦いで織田信長によって討たれ、その後、武田信玄と徳川家康の侵攻を受けて敗れ、戦国大名としての今川家は滅亡した。
その後は北条氏を頼り、最終的には徳川家康の庇護を受け、今川家は江戸幕府のもとで高家として家名を残している。
鐘楼 本殿 吉良義央の墓



「吉良家歴代の墓のある・ 曹洞宗万昌院功運寺」区の上高田にある。、大きなお寺で入ってびっくり、他に、作家の林芙美子など有名人の墓もあった。
吉良家の歴代のお墓も立派。
吉良家四代の基・吉良家討死家臣慰l塔 十四代義定・十五代義弥・十六代義冬・十七代義央
「萬昌院」は、山号 久寶山1574年の創建と伝えられる。開基は今川長得、開山は仏照円鑑禅師(喚英長応)、長得は戦国大名今川義元の三男であり、長得の兄今川氏真もはじめは萬昌院に葬られた。
今川家と先祖を同じくする一族であり、江戸時代初期には極めて近い姻戚関係にあった吉良家の菩提寺に。
江戸城半蔵門近くにあったが、その後市谷田町、筑土八幡町と幾度かの移転を繰り返し、1914年に現在地に。
1917年に火災により本堂・書院などが焼失。
「功運寺」は、山号 竜谷山 1598年、創建。開基は永井尚政、開山は黙室芳禅師。永井尚政は将軍徳川秀忠のもとで老中を務めた人物で、功運寺は永井家の菩提寺となっている。
創建当初は江戸城桜田門外にあったが、三田(芝三田功運町)に移り、1922年に当地に移転。
戦後の1948年に萬昌院と功運寺が合併し現在に至っている。本尊は、釈迦如来坐像。
吉良家の墓


「林芙美子」 1903-51 山口県生まれ、幼い時から各地を放浪、働きながら尾道高等女学校卒業、後も逆境と貧因の中童話、詩を書く、
明治26年画家修業中の手塚緑敏と結婚、代表作牡蠣、泣き虫小僧、晩菊、浮雲、放浪記、従軍作家で活躍、めしが絶筆。
「歌川豊国」 1769-1825 江戸 浮世絵師 歌川豊春門下 18歳で美人画発表、20歳で役者絵、絵草子屋「和泉屋」で売れた
豊国は、和泉屋の恩義を忘れなかったという。同門の豊広と派閥抗争を。
「水野重左ヱ門」(水野十郎左衛門)は、生年不詳ながら実在の人物。 「旗本奴」の首領として悪名を馳せた人物。
「旗本奴」と並ぶもう一方のヤクザ集団である「町奴」の親分「幡随院長兵衛」を裏三番町の自宅の風呂場で謀殺したことで有名。
生涯その不法な行動は止むことはなく、1664年、遂に切腹させられたという。
1664年行状不行跡により幕府評定所に召喚された水野十郎左衛門は、わざと袴も着けず、ふり乱した髪には泥を塗りつけ、乞食同然の身なりだったという。
これに激怒した時の幕府老中・土屋但馬守の命により、水野は即日切腹、水野家は家名断絶となったとのこと。
林芙美子の墓などがある



「宝仙寺」は 平安後期の1087~94年、「源義家」によって創建。
義家は、奥州後三年の役を平定して凱旋帰京の途中にあり陣中に護持していた「不動明王像を安置」するための一寺を建立したという。
その地は 父頼義がかつて祭祀した八幡社のある阿佐ヶ谷の地でこの造寺竣成の時、地主稲荷の神が出現して義家に一顆の珠を与え、
「この珠は希世之珍 宝中之仙である是を以って鎭となさば 則ち武運長久 法燈永く明かならん」と言い、おわるや白狐となって去り、これにより山号を 明王山、寺号を 宝仙寺と号したと伝えられる。
鎌倉時代には相模国大山寺の高僧願行上人が訪ねられ、本尊の不動明王像をご覧になり、その霊貌の凡常でないことに驚かれ、あやまって尊像を穢してはいけないと厨子の奥深くに秘蔵せられたともいう。
その後、室町時代には当寺中興第一世聖永が現在の地に寺基を遷し、江戸初期の1636年には三重塔が建立され、江戸庶民にも親しまれ歴代将軍の尊崇もあつく御鷹狩りの休憩所と成る。大伽藍は昭和20年の戦禍により焼失。
万昌院の隣に宝仙寺が
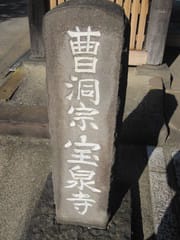


「真宗大谷派寺院・高徳寺」は、山号 新居山法喜院。
寺は、近江佐々木氏一族出身の了智法印(1228年歿)が信州栗原に建立した正行寺を源としている。
その後、正行寺を上野国新田郡新井村(群馬県太田市)へ移転、荒居山法喜院高徳寺したという。
1570-1573年に戦乱を避けて十二世了応法師が、千葉県下総の国相馬郡小目村へ高徳寺を移転、十四世宗信法師が高徳寺を中興したものの、
戦乱に遭い寺院を焼失、江戸下谷御小人町へ移転、その後十七世了也権律師の代に八丁堀への移転を経て、浅草報恩寺境内へ移転した。
上野国新田郡新井村(群馬県太田市)の土豪出身と伝えられる新井白石は、十代・三十代の2度に亘り高徳寺に寄食していたという。
「新井白石」の墓所となっている。
「新井白石」1657-1725 儒学者 30歳で木下順庵の門下、後、徳川綱豊(後の徳川家宣将軍)儒臣、正徳の治・文治政治を推進する。
読史余論、折たく柴の記などの著作を残している。師の恩、木下門下を離れなかったと云う。
早稲田通りに面し寺が続く



「臨済宗妙心寺派・ 松源寺」は、麹町四番町に創建されたが、年代は不詳。1613年に牛込神楽坂に移り、1909年に移転している。
通称"さる寺"と呼ばれ、さる寺縁起として「江戸名所図会」に記されている。入口に猿の石像が目に付いた。


「曹洞宗 天壽山 宗清禅寺」は、 通称 なが寺又たつ寺とも言われている。
曹洞宗は、中国の禅宗五家(曹洞、臨済、潙仰、雲門、法眼)の1つで、 日本においては禅宗(曹洞宗・日本達磨宗・臨済宗・黄檗宗・普化宗)の1つである。本山 は永平寺(福井県)・總持寺(横浜市鶴見区)。専ら坐禅に徹する黙照禅であること。



「曹洞宗 保善寺(通称 獅子寺)」山号 盛山。本尊は釋迦牟尼沸をまつる。
開山は勅得賜円明宝鑑禅師蟠翁門龍大和尚で武田信玄の従弟にあたる。1593年の創建、
3代将軍徳川家光公牛込酒井邸にあそびし折り、立寄られ獅子に似た犬を賜う、以後獅子寺と称すとある。
1906年牛込通寺町より中野に移る。 本堂正面に月舟禅師筆「獅子窟」の額がある。



忠臣蔵を歩くをここで終わります。
人々は焼き場で焼かれるのは、非業の死と受け止めていた、しかし、埋葬のために貴重な土地を拡げ続けることはできなくなり、必然的に火葬の需要が増えてく。
新井薬師の近くに、上高田寺町がある。こちらの寺町も高円寺南寺町、烏山寺町、十一カ寺などと同様と明治末から大正・昭和初めにかけて東京市中から移転してきた寺によって形成された寺町。ここは、早稲田通り沿いの一画。
まずは、「曹洞宗万昌院功運寺」。寺は、もともと別寺院で、「万昌院(牛込)」と「功運寺(芝三田)」の両寺が合併した寺。
万昌院の門楼



「万昌院」は、今川家の開基で、今川家と吉良家は関係あることから、吉良家の墓がある。
「今川 氏真」は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、江戸時代の文化人、駿河国の戦国大名。駿河今川氏10代当主、父義元が桶狭間の戦いで織田信長によって討たれ、その後、武田信玄と徳川家康の侵攻を受けて敗れ、戦国大名としての今川家は滅亡した。
その後は北条氏を頼り、最終的には徳川家康の庇護を受け、今川家は江戸幕府のもとで高家として家名を残している。
鐘楼 本殿 吉良義央の墓



「吉良家歴代の墓のある・ 曹洞宗万昌院功運寺」区の上高田にある。、大きなお寺で入ってびっくり、他に、作家の林芙美子など有名人の墓もあった。
吉良家の歴代のお墓も立派。
吉良家四代の基・吉良家討死家臣慰l塔 十四代義定・十五代義弥・十六代義冬・十七代義央
「萬昌院」は、山号 久寶山1574年の創建と伝えられる。開基は今川長得、開山は仏照円鑑禅師(喚英長応)、長得は戦国大名今川義元の三男であり、長得の兄今川氏真もはじめは萬昌院に葬られた。
今川家と先祖を同じくする一族であり、江戸時代初期には極めて近い姻戚関係にあった吉良家の菩提寺に。
江戸城半蔵門近くにあったが、その後市谷田町、筑土八幡町と幾度かの移転を繰り返し、1914年に現在地に。
1917年に火災により本堂・書院などが焼失。
「功運寺」は、山号 竜谷山 1598年、創建。開基は永井尚政、開山は黙室芳禅師。永井尚政は将軍徳川秀忠のもとで老中を務めた人物で、功運寺は永井家の菩提寺となっている。
創建当初は江戸城桜田門外にあったが、三田(芝三田功運町)に移り、1922年に当地に移転。
戦後の1948年に萬昌院と功運寺が合併し現在に至っている。本尊は、釈迦如来坐像。
吉良家の墓


「林芙美子」 1903-51 山口県生まれ、幼い時から各地を放浪、働きながら尾道高等女学校卒業、後も逆境と貧因の中童話、詩を書く、
明治26年画家修業中の手塚緑敏と結婚、代表作牡蠣、泣き虫小僧、晩菊、浮雲、放浪記、従軍作家で活躍、めしが絶筆。
「歌川豊国」 1769-1825 江戸 浮世絵師 歌川豊春門下 18歳で美人画発表、20歳で役者絵、絵草子屋「和泉屋」で売れた
豊国は、和泉屋の恩義を忘れなかったという。同門の豊広と派閥抗争を。
「水野重左ヱ門」(水野十郎左衛門)は、生年不詳ながら実在の人物。 「旗本奴」の首領として悪名を馳せた人物。
「旗本奴」と並ぶもう一方のヤクザ集団である「町奴」の親分「幡随院長兵衛」を裏三番町の自宅の風呂場で謀殺したことで有名。
生涯その不法な行動は止むことはなく、1664年、遂に切腹させられたという。
1664年行状不行跡により幕府評定所に召喚された水野十郎左衛門は、わざと袴も着けず、ふり乱した髪には泥を塗りつけ、乞食同然の身なりだったという。
これに激怒した時の幕府老中・土屋但馬守の命により、水野は即日切腹、水野家は家名断絶となったとのこと。
林芙美子の墓などがある



「宝仙寺」は 平安後期の1087~94年、「源義家」によって創建。
義家は、奥州後三年の役を平定して凱旋帰京の途中にあり陣中に護持していた「不動明王像を安置」するための一寺を建立したという。
その地は 父頼義がかつて祭祀した八幡社のある阿佐ヶ谷の地でこの造寺竣成の時、地主稲荷の神が出現して義家に一顆の珠を与え、
「この珠は希世之珍 宝中之仙である是を以って鎭となさば 則ち武運長久 法燈永く明かならん」と言い、おわるや白狐となって去り、これにより山号を 明王山、寺号を 宝仙寺と号したと伝えられる。
鎌倉時代には相模国大山寺の高僧願行上人が訪ねられ、本尊の不動明王像をご覧になり、その霊貌の凡常でないことに驚かれ、あやまって尊像を穢してはいけないと厨子の奥深くに秘蔵せられたともいう。
その後、室町時代には当寺中興第一世聖永が現在の地に寺基を遷し、江戸初期の1636年には三重塔が建立され、江戸庶民にも親しまれ歴代将軍の尊崇もあつく御鷹狩りの休憩所と成る。大伽藍は昭和20年の戦禍により焼失。
万昌院の隣に宝仙寺が
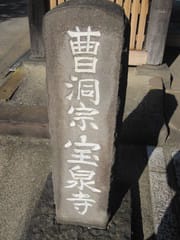


「真宗大谷派寺院・高徳寺」は、山号 新居山法喜院。
寺は、近江佐々木氏一族出身の了智法印(1228年歿)が信州栗原に建立した正行寺を源としている。
その後、正行寺を上野国新田郡新井村(群馬県太田市)へ移転、荒居山法喜院高徳寺したという。
1570-1573年に戦乱を避けて十二世了応法師が、千葉県下総の国相馬郡小目村へ高徳寺を移転、十四世宗信法師が高徳寺を中興したものの、
戦乱に遭い寺院を焼失、江戸下谷御小人町へ移転、その後十七世了也権律師の代に八丁堀への移転を経て、浅草報恩寺境内へ移転した。
上野国新田郡新井村(群馬県太田市)の土豪出身と伝えられる新井白石は、十代・三十代の2度に亘り高徳寺に寄食していたという。
「新井白石」の墓所となっている。
「新井白石」1657-1725 儒学者 30歳で木下順庵の門下、後、徳川綱豊(後の徳川家宣将軍)儒臣、正徳の治・文治政治を推進する。
読史余論、折たく柴の記などの著作を残している。師の恩、木下門下を離れなかったと云う。
早稲田通りに面し寺が続く



「臨済宗妙心寺派・ 松源寺」は、麹町四番町に創建されたが、年代は不詳。1613年に牛込神楽坂に移り、1909年に移転している。
通称"さる寺"と呼ばれ、さる寺縁起として「江戸名所図会」に記されている。入口に猿の石像が目に付いた。


「曹洞宗 天壽山 宗清禅寺」は、 通称 なが寺又たつ寺とも言われている。
曹洞宗は、中国の禅宗五家(曹洞、臨済、潙仰、雲門、法眼)の1つで、 日本においては禅宗(曹洞宗・日本達磨宗・臨済宗・黄檗宗・普化宗)の1つである。本山 は永平寺(福井県)・總持寺(横浜市鶴見区)。専ら坐禅に徹する黙照禅であること。



「曹洞宗 保善寺(通称 獅子寺)」山号 盛山。本尊は釋迦牟尼沸をまつる。
開山は勅得賜円明宝鑑禅師蟠翁門龍大和尚で武田信玄の従弟にあたる。1593年の創建、
3代将軍徳川家光公牛込酒井邸にあそびし折り、立寄られ獅子に似た犬を賜う、以後獅子寺と称すとある。
1906年牛込通寺町より中野に移る。 本堂正面に月舟禅師筆「獅子窟」の額がある。



忠臣蔵を歩くをここで終わります。









