渋谷禅寺散策に戻ります。
広尾界隈は、江戸時代は近郊農村であったが、甲州街道、大山街道、目黒道などで、大名の下屋敷や、幕臣の邸宅が設置されていった。
渋谷区の南東、渋谷川北岸寺院が多く移っている。台地上には、屋敷跡に学校が出来、今では文教地域。
JR山手線の敷設に地元民は猛反対し、1885年頃、都市化が遅れたという。
今に残る仙台坂、南部坂、北条坂、青木坂は、各藩の屋敷に由来する。江戸中期には、将軍家の別荘である白銀御殿(麻布御殿・富士見御殿とも呼ばれる)が存在した。明治から大正時代にかけ開発が行われ、後に各国の大使館が設置されるに伴い徐々に今日の国際色豊かな都心の住宅街へと変貌を遂げている。
南部坂と言うと、忠臣蔵で有名な南部坂が思い浮かびますが、その南部坂は赤坂。こちらの南部坂は忠臣蔵とのゆかりは無い。盛岡藩南部家の下屋敷の横を走る坂だったことが、坂名の由来。その屋敷こそ、現在の「有栖川宮記念公園」次回に。
「商店町」は、広尾橋交差点から南西側に広がる。洒落たイメージの広尾だが、ここには昔からの店舗が残っていたり、お惣菜の店があったりと、生活色も感じられる商店街となっている。
JRなどの駅前の商店街と違い、雑然とした賑やかさではない、歩道や街灯・街路樹は綺麗に整備され、奥には、寺町の祥雲寺などいくつかの寺院、北には聖心学園、外苑西通りを東へ渡れば、大使館が多く立ち並ぶ地域である。立地環境も独特であった。
門前町の広尾散歩通り 突き当りが寺町 南部坂



日本の禅は、13世紀(鎌倉時代)に伝えられたとされている。だが、9世紀(平安時代前期)に皇太后橘嘉智子に招かれて唐の禅僧・義空が来日して檀林寺で禅の講義が行われたものの、当時の日本における禅への関心の低さに失望して数年で唐へ帰国したとする記録が残っている。
また、日本天台宗の宗祖最澄の師で近江国分寺の行表は中国北宗の流れを汲んでいる。臨済禅の流れは中国の南宋に渡った栄西が日本に請来したことから始まる。曹洞禅も道元が中国に渡り中国で印可を得て日本に帰国することから始まるが、それ以前に大日房能忍が多武峰で日本達磨宗を開いていた事が知られ、曹洞宗の懐鑑、義介らは元日本達磨宗の僧侶であったことが知られている。
鎌倉時代以後、武士や庶民などを中心に広まり、各地に禅寺(禅宗寺院・禅林)が建てられるようになった。
また、五山文学や水墨画のように禅僧による文化芸術活動が盛んに行われた。
禅寺の中央に、可なり大きな仏教5代、「天空、風、火、水、地」の石塔が建っていた。

江戸名所図会によると「大徳寺派瑞泉山祥雲寺」には子院が8宇あったという。今は、子院でも塔頭でもなく、別の寺という。でも、墓はすべて祥雲寺の境内にある。
「妙高山・東江寺」は、瓦に、信濃飯田藩主堀氏の梅鉢紋が使用されている。開基 堀美作守親昌、父・親良の菩提を弔うために建立。
1661年 以前に、下野州那須郡烏山に建立され、1672年 信州飯田に転封により、寺を廃して、後に景徳院境内に再建し、景徳院と合寺。
東江寺の名前に改め現在に。
東江寺境内に入るとすぐ左に、「東江菴」と刻まれた古い石標が立っている。堀親良の号「梅也宗月東江菴」とある。堀家墓あり。



「霊泉院」は、 開基 出雲広瀬城主松平佐渡守近栄(結城秀康の孫) 開山 1669年に建立。



霊泉院所蔵の文化財は、 板碑、歴代頂相画 15幅 附 子順和尚像(区指定有形文化財)、木造十一面観音立像(区指定有形文化財)等がある。


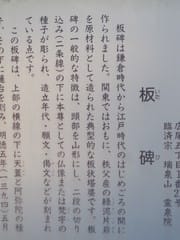
「香林院」は、1665年三河奥藩主松平真次の菩提を弔うため、松平(大給)乗次を開基 絶山宗信和尚を開山として建立。
初め麻布小山にあり、江戸の大火により 1668年現在地に移る。
建築物では、本堂、院門が、1825年のもの、江戸時代の貴重な文化遺産。





「徳寺派寺院・祥雲寺」は、瑞泉山と号し、福岡藩主黒田長政を追善して、嫡子忠之が開基となり、長政が帰依していた京都紫野大徳寺の龍岳和尚を開山として赤坂溜池の自邸内に龍谷山興雲寺と称して創建。
1666年に麻布台へ移転の上瑞泉山祥雲寺と改称、1668年の江戸大火により当地へ移転した。



「黒田孝高」1548-1604 黒田長政は嫡男、秀吉天下の座に付けた軍師、九州征伐軍奉行を務める。小田原、朝鮮出兵参加、関ケ原で東軍に
与した。北九州を席捲し天下を狙っていた。
「黒田長政」1568-1623 初代福岡藩主 「腹を立てぬ、他言せぬ、恨みに思わぬ」重臣に誓詞を交わし、合点のゆくまで語り合ったという、
また、「太平に成りては、武を隠して、顕さぬが本意」自分の武功を語らなかった。
本殿 境内 釈迦像



江戸期には塔頭6ヵ寺を擁していた他、臨済宗大徳寺派の触頭として御府内にある臨済宗大徳寺派寺院をまとめていたという。
開山の龍岳和尚は、本山大徳寺164世で、笠仙大法禅師と後水尾帝より勅賜された名僧。


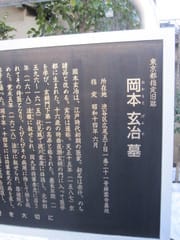
長政の墓所は横岳山崇福寺にもある。長政は、1623年に京都で亡くなっている。 遺骸・遺髪などが祥雲寺,崇福寺のどちらに埋葬されているのかはわからない。祥雲寺山門をくぐるとすぐ右手に妙高山東江寺、さらに進むと左手に瑞泉山霊泉院、右手に瑞泉山香林禅院がある。 いずれも「臨済宗大徳寺派」の寺院である。



次回は、麻布方面へ。
広尾界隈は、江戸時代は近郊農村であったが、甲州街道、大山街道、目黒道などで、大名の下屋敷や、幕臣の邸宅が設置されていった。
渋谷区の南東、渋谷川北岸寺院が多く移っている。台地上には、屋敷跡に学校が出来、今では文教地域。
JR山手線の敷設に地元民は猛反対し、1885年頃、都市化が遅れたという。
今に残る仙台坂、南部坂、北条坂、青木坂は、各藩の屋敷に由来する。江戸中期には、将軍家の別荘である白銀御殿(麻布御殿・富士見御殿とも呼ばれる)が存在した。明治から大正時代にかけ開発が行われ、後に各国の大使館が設置されるに伴い徐々に今日の国際色豊かな都心の住宅街へと変貌を遂げている。
南部坂と言うと、忠臣蔵で有名な南部坂が思い浮かびますが、その南部坂は赤坂。こちらの南部坂は忠臣蔵とのゆかりは無い。盛岡藩南部家の下屋敷の横を走る坂だったことが、坂名の由来。その屋敷こそ、現在の「有栖川宮記念公園」次回に。
「商店町」は、広尾橋交差点から南西側に広がる。洒落たイメージの広尾だが、ここには昔からの店舗が残っていたり、お惣菜の店があったりと、生活色も感じられる商店街となっている。
JRなどの駅前の商店街と違い、雑然とした賑やかさではない、歩道や街灯・街路樹は綺麗に整備され、奥には、寺町の祥雲寺などいくつかの寺院、北には聖心学園、外苑西通りを東へ渡れば、大使館が多く立ち並ぶ地域である。立地環境も独特であった。
門前町の広尾散歩通り 突き当りが寺町 南部坂



日本の禅は、13世紀(鎌倉時代)に伝えられたとされている。だが、9世紀(平安時代前期)に皇太后橘嘉智子に招かれて唐の禅僧・義空が来日して檀林寺で禅の講義が行われたものの、当時の日本における禅への関心の低さに失望して数年で唐へ帰国したとする記録が残っている。
また、日本天台宗の宗祖最澄の師で近江国分寺の行表は中国北宗の流れを汲んでいる。臨済禅の流れは中国の南宋に渡った栄西が日本に請来したことから始まる。曹洞禅も道元が中国に渡り中国で印可を得て日本に帰国することから始まるが、それ以前に大日房能忍が多武峰で日本達磨宗を開いていた事が知られ、曹洞宗の懐鑑、義介らは元日本達磨宗の僧侶であったことが知られている。
鎌倉時代以後、武士や庶民などを中心に広まり、各地に禅寺(禅宗寺院・禅林)が建てられるようになった。
また、五山文学や水墨画のように禅僧による文化芸術活動が盛んに行われた。
禅寺の中央に、可なり大きな仏教5代、「天空、風、火、水、地」の石塔が建っていた。

江戸名所図会によると「大徳寺派瑞泉山祥雲寺」には子院が8宇あったという。今は、子院でも塔頭でもなく、別の寺という。でも、墓はすべて祥雲寺の境内にある。
「妙高山・東江寺」は、瓦に、信濃飯田藩主堀氏の梅鉢紋が使用されている。開基 堀美作守親昌、父・親良の菩提を弔うために建立。
1661年 以前に、下野州那須郡烏山に建立され、1672年 信州飯田に転封により、寺を廃して、後に景徳院境内に再建し、景徳院と合寺。
東江寺の名前に改め現在に。
東江寺境内に入るとすぐ左に、「東江菴」と刻まれた古い石標が立っている。堀親良の号「梅也宗月東江菴」とある。堀家墓あり。



「霊泉院」は、 開基 出雲広瀬城主松平佐渡守近栄(結城秀康の孫) 開山 1669年に建立。



霊泉院所蔵の文化財は、 板碑、歴代頂相画 15幅 附 子順和尚像(区指定有形文化財)、木造十一面観音立像(区指定有形文化財)等がある。


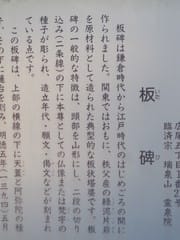
「香林院」は、1665年三河奥藩主松平真次の菩提を弔うため、松平(大給)乗次を開基 絶山宗信和尚を開山として建立。
初め麻布小山にあり、江戸の大火により 1668年現在地に移る。
建築物では、本堂、院門が、1825年のもの、江戸時代の貴重な文化遺産。





「徳寺派寺院・祥雲寺」は、瑞泉山と号し、福岡藩主黒田長政を追善して、嫡子忠之が開基となり、長政が帰依していた京都紫野大徳寺の龍岳和尚を開山として赤坂溜池の自邸内に龍谷山興雲寺と称して創建。
1666年に麻布台へ移転の上瑞泉山祥雲寺と改称、1668年の江戸大火により当地へ移転した。



「黒田孝高」1548-1604 黒田長政は嫡男、秀吉天下の座に付けた軍師、九州征伐軍奉行を務める。小田原、朝鮮出兵参加、関ケ原で東軍に
与した。北九州を席捲し天下を狙っていた。
「黒田長政」1568-1623 初代福岡藩主 「腹を立てぬ、他言せぬ、恨みに思わぬ」重臣に誓詞を交わし、合点のゆくまで語り合ったという、
また、「太平に成りては、武を隠して、顕さぬが本意」自分の武功を語らなかった。
本殿 境内 釈迦像



江戸期には塔頭6ヵ寺を擁していた他、臨済宗大徳寺派の触頭として御府内にある臨済宗大徳寺派寺院をまとめていたという。
開山の龍岳和尚は、本山大徳寺164世で、笠仙大法禅師と後水尾帝より勅賜された名僧。


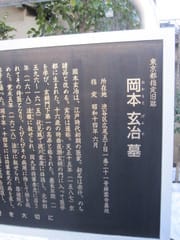
長政の墓所は横岳山崇福寺にもある。長政は、1623年に京都で亡くなっている。 遺骸・遺髪などが祥雲寺,崇福寺のどちらに埋葬されているのかはわからない。祥雲寺山門をくぐるとすぐ右手に妙高山東江寺、さらに進むと左手に瑞泉山霊泉院、右手に瑞泉山香林禅院がある。 いずれも「臨済宗大徳寺派」の寺院である。



次回は、麻布方面へ。









