古墳時代後期(AC500-600)には、葛城(馬見古墳群)・飛鳥など奈良盆地に帰り、大王の大宮が、河内より磐余、飛鳥へと移動する間に、大和朝廷の全国制覇・中央集権化が進み、諸国に国造・縣主制、部民制が成立し、伴造氏族の台頭と中央政権への進出が徐々に進行する。
7~8世紀には、政治の中心は飛鳥・藤原宮に移り、律令国家が形成されていく。
「山辺の道」に沿って、大和古墳群に属する西殿塚古墳(手白香皇女衾田陵)、柳本古墳群に属する行燈山古墳(崇神陵)や、渋谷向山古墳(景行陵)などの巨大古墳と多数の古墳が群在している。
天皇陵に比定された宮内庁管轄御陵は、試掘はおろか測量・立入も出来ません。
古墳の形状・寸法は、江戸末期の修復の際に描かれた“山陵図”や“宮内庁書陵部の図面”、航空写真などをもとに決められ、築造年代は立入り可能な濠や付近の民有地からの出土品から推定されている。
古墳の名称は、「記紀」や「延喜式」などから比定されていますが、解釈の違いもありニ転三転する。
天皇が実在したかどうかを含めて、考古学上の名前(西殿塚古墳、行燈山古墳、渋谷向山古墳など)の方が正確だという。
古事記では、「崇神陵」は“山辺道匂之崗上”で、「景行陵」は“山辺之道上”と記され、日本書紀と延喜式では、「崇神」と「景行陵」ともに“山辺道上陵”と呼んでいると云う。
山辺の道・第11代垂仁天皇宮跡・纏向珠城宮は、 桜井市穴師 。天皇の宮は纏向にあるのですが御陵は奈良市の尼ヶ辻にもある。



「景行天皇纏向日代宮跡」
「山の辺の道」から少し外れて、東の山間部へ辿ると、穴師で、道の脇に石碑「景行天皇纏向日代宮跡」が建っています。
第12代景行天皇は、第11代垂仁天皇の第二皇子で、母は比羽州比売命、丹波道王の娘、妃の伊那毘能大郎女との間に五人の皇子が有り、
その内二皇子が双生児の大碓命と小碓命で、兄の大碓命を殺した小碓命が日本武尊です。
宮跡・古墳 景行天皇纏向遺跡 ミカン発祥の地でもある



古墳らしき小山が 太古の山道 この辺は古墳の銀座


山辺の道は歴史街道 のどかな遊歩道が続く(7世紀の道)


「纏向遺跡」は、御諸山とも三室山とも呼ばれる三輪山の北西麓一帯に広がる弥生時代末期から古墳時代前期にかけての大集落遺跡である。
建設された主時期は3世紀で、前方後円墳発祥の地とされている。
邪馬台国に比定する意見もあり、卑弥呼の墓との説もある箸墓古墳などの6つの古墳を持つ。
第12代景行天皇は、日本書紀によると、六年間にわたって、日向に滞在 と記され、 ~ある年、九州南部に住むクマソの一族が朝廷 に反抗し、みつぎ物を差し出しません、 景行天皇はクマソを討つことを、、、、。(次回で)



「纒向」の村名は垂仁天皇の「纒向珠城宮」、景行天皇の「纒向日代宮」より名づけられたもの。
2011年現在で把握されている「纒向遺跡」の範囲は、北は烏田川、南は五味原川、東は山辺の道に接する巻野内地区、西は東田地区およびその範囲は約3km²になる。遺跡地図上では遺跡範囲はJR巻向駅を中心に東西約2km・南北約1.5kmにおよび、およそ楕円形の平面形状となって、その面積は3,000m²に達する。
地勢は、東が高く西が低い。三輪山・巻向山・穴師山などの流れが巻向川に合流し、その扇状地上に遺跡が形成されている。
遺跡内出土遺物で最も古いものは、縄文時代後・晩期のものである。粗製土器片やサヌカイト片に混じって砂岩製の石棒破片、あるいは土偶や深鉢などが遺跡内より出土しており、この地に縄文時代の集落が営まれていたと考えられている。
遺跡からは弥生時代の集落は発見されておらず、環濠も検出されていない。銅鐸の破片や土坑が2基発見されているのみである。
この遺跡より南に少し離れた所からは弥生時代中期・後期の多量の土器片が出土しており、方形周濠墓や竪穴住居なども検出している。
南西側からも多くの弥生時代の遺物が出土している。
ただし、纒向遺跡の北溝北部下層および灰粘土層からは畿内第V様式末の弥生土器が見つかっており、「纒向編年」では「纒向1類」とされ、
発掘調査、纒向1類の暦年代としては西暦180年から210年をあてていると云う。
この辺り、三輪山の里山、大和高原が見渡せる。現在でも果実・米の畑が続いいている
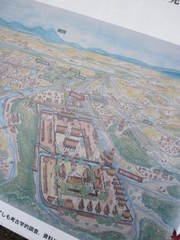

「相撲神社」は、野見宿禰と當麻蹶速が初めて天覧相撲を行ったところと云う。桜井市穴師鎮座で、大兵主神社の隣
天覧相撲発祥地 と土俵がある



相撲の元祖、野見宿禰が當麻蹴速と力比べをしたという伝承から、相撲発祥の地といわれ、二人が勝負したと伝わる土俵跡がある。
当麻蹶速と野見宿弥が御前試合をしたところ。



巻向駅の東方約1.7kmの巻向山山麓に鎮座する古社で、延喜式神名帳に記す
「大和国城上郡 穴師坐兵主神社 名神大 月次相嘗新嘗」・「大和国城上郡 穴師坐大兵主神社」・「大和国城上郡 巻向坐若御魂神社 大 月次相嘗新嘗」の3社を合祀した神社で、今、「大兵主神社」と称していると云う。
JR桜井線・巻向駅の東約1.3kmの巻向山西南山麓に鎮座。
相撲神社と隣接し、横に鳥居が立ち、参道に。
神社の道沿いに、垂仁天皇纏向珠城宮跡・景行天皇纏向日代宮跡・珠城古墳群(前方後円墳3基)などが点在する。



「兵主神」初見は、三代実録(901)・貞観元年(859)正月条の「穴師兵主神」「壱岐嶋兵主神」といわれ、9世紀までには伝来していたらしく、延喜式神名帳(927)によれば、兵主神社は三河国(愛知県東部)から壱岐国(長崎県)といった広い範囲に19社がある。
兵主とは、漢の高祖が兵を挙げたとき(BC200頃)、蚩尤(シユウ)を祀って勝利を祈ったことに由来するというが、中国の史記・封禅書に、泰山における封禅の儀を終えた秦始皇帝が「そのまま東へ進んで海岸地帯を旅行し、道すがら名山・大川および八神を礼をもって祀・・・八神の第一は天主といって天斉で祀る。第二は地主といって泰山・梁父山で祀る。第三は兵主といって蚩尤(の冢・墓-山東省・斉国の西境にあったという)でお祀りする。(以下、陰主・陽主・月主・日主・四時主と続く)」(大意)とある伝説上の神で、特に山東地方の斉国(BC386--221・戦国時代)では篤く崇敬されたという。 始皇帝が、兵主を蚩尤の墓に祀ったというように、蚩尤は兵主の別名とされる。
古代の面影を残している



「ひもろぎ遺跡」
山の辺の道から20メートルほど入ったところにある。
この一帯の小字名を「ひもろぎ」と言い、「神籬=ひもろぎ」、神の憑代といった意味合いがあると云う。
近くには、檜原神社(檜原神社~三輪鳥居 )があり、弥生時代の大規模遺跡・纏向遺跡に含まれており、纏向の祭祀と関連があるとみなされている。
雨は止みそうもないようだ



次回も山辺の道を。
7~8世紀には、政治の中心は飛鳥・藤原宮に移り、律令国家が形成されていく。
「山辺の道」に沿って、大和古墳群に属する西殿塚古墳(手白香皇女衾田陵)、柳本古墳群に属する行燈山古墳(崇神陵)や、渋谷向山古墳(景行陵)などの巨大古墳と多数の古墳が群在している。
天皇陵に比定された宮内庁管轄御陵は、試掘はおろか測量・立入も出来ません。
古墳の形状・寸法は、江戸末期の修復の際に描かれた“山陵図”や“宮内庁書陵部の図面”、航空写真などをもとに決められ、築造年代は立入り可能な濠や付近の民有地からの出土品から推定されている。
古墳の名称は、「記紀」や「延喜式」などから比定されていますが、解釈の違いもありニ転三転する。
天皇が実在したかどうかを含めて、考古学上の名前(西殿塚古墳、行燈山古墳、渋谷向山古墳など)の方が正確だという。
古事記では、「崇神陵」は“山辺道匂之崗上”で、「景行陵」は“山辺之道上”と記され、日本書紀と延喜式では、「崇神」と「景行陵」ともに“山辺道上陵”と呼んでいると云う。
山辺の道・第11代垂仁天皇宮跡・纏向珠城宮は、 桜井市穴師 。天皇の宮は纏向にあるのですが御陵は奈良市の尼ヶ辻にもある。



「景行天皇纏向日代宮跡」
「山の辺の道」から少し外れて、東の山間部へ辿ると、穴師で、道の脇に石碑「景行天皇纏向日代宮跡」が建っています。
第12代景行天皇は、第11代垂仁天皇の第二皇子で、母は比羽州比売命、丹波道王の娘、妃の伊那毘能大郎女との間に五人の皇子が有り、
その内二皇子が双生児の大碓命と小碓命で、兄の大碓命を殺した小碓命が日本武尊です。
宮跡・古墳 景行天皇纏向遺跡 ミカン発祥の地でもある



古墳らしき小山が 太古の山道 この辺は古墳の銀座


山辺の道は歴史街道 のどかな遊歩道が続く(7世紀の道)


「纏向遺跡」は、御諸山とも三室山とも呼ばれる三輪山の北西麓一帯に広がる弥生時代末期から古墳時代前期にかけての大集落遺跡である。
建設された主時期は3世紀で、前方後円墳発祥の地とされている。
邪馬台国に比定する意見もあり、卑弥呼の墓との説もある箸墓古墳などの6つの古墳を持つ。
第12代景行天皇は、日本書紀によると、六年間にわたって、日向に滞在 と記され、 ~ある年、九州南部に住むクマソの一族が朝廷 に反抗し、みつぎ物を差し出しません、 景行天皇はクマソを討つことを、、、、。(次回で)



「纒向」の村名は垂仁天皇の「纒向珠城宮」、景行天皇の「纒向日代宮」より名づけられたもの。
2011年現在で把握されている「纒向遺跡」の範囲は、北は烏田川、南は五味原川、東は山辺の道に接する巻野内地区、西は東田地区およびその範囲は約3km²になる。遺跡地図上では遺跡範囲はJR巻向駅を中心に東西約2km・南北約1.5kmにおよび、およそ楕円形の平面形状となって、その面積は3,000m²に達する。
地勢は、東が高く西が低い。三輪山・巻向山・穴師山などの流れが巻向川に合流し、その扇状地上に遺跡が形成されている。
遺跡内出土遺物で最も古いものは、縄文時代後・晩期のものである。粗製土器片やサヌカイト片に混じって砂岩製の石棒破片、あるいは土偶や深鉢などが遺跡内より出土しており、この地に縄文時代の集落が営まれていたと考えられている。
遺跡からは弥生時代の集落は発見されておらず、環濠も検出されていない。銅鐸の破片や土坑が2基発見されているのみである。
この遺跡より南に少し離れた所からは弥生時代中期・後期の多量の土器片が出土しており、方形周濠墓や竪穴住居なども検出している。
南西側からも多くの弥生時代の遺物が出土している。
ただし、纒向遺跡の北溝北部下層および灰粘土層からは畿内第V様式末の弥生土器が見つかっており、「纒向編年」では「纒向1類」とされ、
発掘調査、纒向1類の暦年代としては西暦180年から210年をあてていると云う。
この辺り、三輪山の里山、大和高原が見渡せる。現在でも果実・米の畑が続いいている
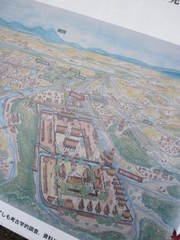

「相撲神社」は、野見宿禰と當麻蹶速が初めて天覧相撲を行ったところと云う。桜井市穴師鎮座で、大兵主神社の隣
天覧相撲発祥地 と土俵がある



相撲の元祖、野見宿禰が當麻蹴速と力比べをしたという伝承から、相撲発祥の地といわれ、二人が勝負したと伝わる土俵跡がある。
当麻蹶速と野見宿弥が御前試合をしたところ。



巻向駅の東方約1.7kmの巻向山山麓に鎮座する古社で、延喜式神名帳に記す
「大和国城上郡 穴師坐兵主神社 名神大 月次相嘗新嘗」・「大和国城上郡 穴師坐大兵主神社」・「大和国城上郡 巻向坐若御魂神社 大 月次相嘗新嘗」の3社を合祀した神社で、今、「大兵主神社」と称していると云う。
JR桜井線・巻向駅の東約1.3kmの巻向山西南山麓に鎮座。
相撲神社と隣接し、横に鳥居が立ち、参道に。
神社の道沿いに、垂仁天皇纏向珠城宮跡・景行天皇纏向日代宮跡・珠城古墳群(前方後円墳3基)などが点在する。



「兵主神」初見は、三代実録(901)・貞観元年(859)正月条の「穴師兵主神」「壱岐嶋兵主神」といわれ、9世紀までには伝来していたらしく、延喜式神名帳(927)によれば、兵主神社は三河国(愛知県東部)から壱岐国(長崎県)といった広い範囲に19社がある。
兵主とは、漢の高祖が兵を挙げたとき(BC200頃)、蚩尤(シユウ)を祀って勝利を祈ったことに由来するというが、中国の史記・封禅書に、泰山における封禅の儀を終えた秦始皇帝が「そのまま東へ進んで海岸地帯を旅行し、道すがら名山・大川および八神を礼をもって祀・・・八神の第一は天主といって天斉で祀る。第二は地主といって泰山・梁父山で祀る。第三は兵主といって蚩尤(の冢・墓-山東省・斉国の西境にあったという)でお祀りする。(以下、陰主・陽主・月主・日主・四時主と続く)」(大意)とある伝説上の神で、特に山東地方の斉国(BC386--221・戦国時代)では篤く崇敬されたという。 始皇帝が、兵主を蚩尤の墓に祀ったというように、蚩尤は兵主の別名とされる。
古代の面影を残している



「ひもろぎ遺跡」
山の辺の道から20メートルほど入ったところにある。
この一帯の小字名を「ひもろぎ」と言い、「神籬=ひもろぎ」、神の憑代といった意味合いがあると云う。
近くには、檜原神社(檜原神社~三輪鳥居 )があり、弥生時代の大規模遺跡・纏向遺跡に含まれており、纏向の祭祀と関連があるとみなされている。
雨は止みそうもないようだ



次回も山辺の道を。









