イチイが生い茂った原が転訛して「市原」、千葉県のほぼ中央部で東京湾岸の「工業・農業・住宅・・」・1963年市原・五井・姉ヶ崎・・合併し
「市原市」に、大部分が「上総丘陵」と北流する「養老川」、南部は丘陵地帯、中部に台地・縄文、弥生時代遺跡が多い所。
海岸低地は埋め立て地で「京葉工業地帯」。また、この地は、大化の改新後「上総国の中心地」、国衙が置かれ、奈良時代に上総国国分寺が建立されている。鎌倉時代は、神奈川県・三浦半島と結び交通の要地として栄えている。
江戸時代は、幕府直轄地で旗本知行地。明治に入り、海苔・貝など半農半漁となる。
丘陵部には、全国一位のゴルフ場が20ヶ所を超えてていたが、現在はわからない。
「聖武天皇」 701-756 仏教政治。45代天皇で文武天皇の皇子、嫡流・仏教南都6宗の学問を助成「天平文化」
国々に「国分寺」を創る。中央に東大寺を置いた。聖武系皇統は、その後途絶える。
「孝謙・称徳天皇」 718-770 仏教保護で国乱れる。
46・48代天皇、聖武務天皇の皇女「国分寺尼寺」を置いた。妖僧「弓削道鏡」を引き立て、藤原仲麻呂を除き、道鏡一派の思いのままの仏教保護が
なされたと云う。
「植木・イチイ」
耐陰性、耐寒性があり刈り込みにもよく耐えるため、日本では中部地方以北の地域で庭木や生垣に利用される。
東北北部と北海道ではサカキ、ヒサカキを産しなかったため、サカキ、ヒサカキの代わりに玉串など神事に用いられる。
また、神社の境内にも植えられる。

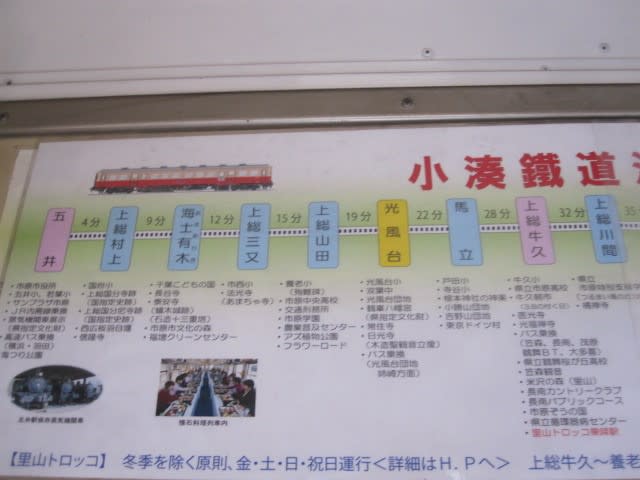
国分寺は,今から1250年ほど前の奈良時代中頃,国の平和と繁栄を祈るため,全国60か所余りに建てられた僧寺と尼寺からなる国立寺院。
上総国分尼寺跡は上総国分寺跡から北東1.5kmの台地上に立地する。寺域は南北約372m,東西約285mの長方形。昭和43~45年の発掘調査で講堂,中門が確認された。史跡の整備が進められ,復元された中門,回廊が。
上総国分寺

境内には「将門塔」と称される1372年、建立の宝篋印塔がある。指定文化財。

「新皇塚古墳」は、墳丘全長80m・一辺長40mで4世頃の古墳ー形は残っていない。「王賜」銘鉄剣の出土した「稲荷台1号墳」がある。

境内へ

「国分寺」
養老川北岸の台地上に所在し、北東方には国分尼寺跡が残るほか、周辺には古墳・遺跡や瓦の窯跡が多く確認・旧国分寺の跡地に重複して位置し、その法燈を受け継ぐといわれる。
旧国分寺は、1394年-1427年頃までの存続は確認され、その後は、荒廃。
寺伝では、元禄年間の1688年-1704年、に僧の「快応」によって再興・1716年、に現在の薬師堂が落成したと伝える。
後に、仁王門も設けられたとある。
薬師堂は、江戸時代の1716年に建立。
堂内の厨子に本尊が安置されている。門・薬師堂は、(市原市指定文化財)
金剛力士像は、それぞれ阿形は南北朝時代、吽形は江戸時代の作と云う。市指定文化財。

西門跡

寺内基石配置

仁王門


鐘楼

境内には巨老木が

銀杏の大木

国分寺薬師堂 江戸時代中旬に再建ー 市指定文化財

天平13年の741年頃。
寺域・南北約490m,東西325mで,長方形が重なった形をしている。
塔は七重で,高さは63m以上、大きな礎石が往時をしのばせる。
上総国分寺尼寺展示館

「金光明四天王護国の寺」
金光明最勝王経」を敬い、国土に続み広める王があれば、四天王が常に来て守護し、災いを除いて至福をもたらすと説いている。
上総国分寺の寺領は、北東と南西・谷・古墳を避けているために四角形では無く、南北478m・東西北辺で25m・中央345m・南辺299m
面積13.9万m2で武蔵国・下野国に次ぐ広さ。「七堂伽藍の広さー南北219m・東西194mが国定史跡」
全国国分寺跡68ケ所ある。総国分寺・東大寺 総国分尼寺法華寺(奈良県にある)

千葉県には、安房、館山国分・下総、市川国分・(武蔵、国分寺・上野高崎・下野栃木・・)

寺内配置は、
北門ー政所院ー講堂ー経楼ー金堂(回廊)-中門ー南門ー東西南北の門ー築地塀

七重塔は、国分寺を象徴する最大の建築物とされた。








「市原氏と古墳群」
養老川の右岸で,国分寺台古墳群や諏訪台古墳群,神門古墳群など数多くの古墳群があったが,宅地造成に伴って発掘調査され,保存古墳は公園として宅地のなかにわずかに点在するだけとなった。稲荷台1号墳は,「王賜」銘という銀象嵌の施された鉄剣が出土したことで一躍全国的に知られた。この古墳の主は,鉄剣の他に鉄鏃,短甲などが出土していることから,畿内と関係のある武人と考えられている。また,出現期の古墳として知られる神門古墳からは畿内,北陸,東海の様相をもった土器群が出土していて,この地域の豪族がそれらの地域と行き来していたことが分かる。
奈良時代になると,この地域には場所は特定されていないが,国府が所在しており,上総国の中心であった。上総国分寺は礎石から当時の面影を知ることができる。
国分僧寺、国分尼寺、総社などが集中している。(惣社地区)










