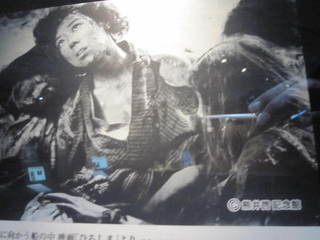「弥山」(標高・530m)
瀬戸内海と島全体として、瀬戸内海国立公園内に位置、弥山の山麓は、ユネスコの世界遺産「厳島神社」の登録区域の一部となっている。
北側斜面には、国の天然記念物となっている「瀰山原始林」が存在し、暖温帯性針葉樹のモミと南方系高山植物ミミズバイの同居やヤグルマの群落など、特異な植物・植生の分布が見られる。
平安時代の 806年、に空海(弘法大師)が弥山を開山し、真言密教の修験道場となったと伝えられ、山頂付近には御山神社、山頂付近から山麓にかけては大聖院の数々の堂宇、裾野には厳島神社を配し、信仰の山として古くから参拝者が絶えない。
山名については、山の形が須弥山に似ていることからという説や、元は「御山」と呼んでいたのが「弥山」となったという説などがある。
山頂にある三角点の名称は「御山」。
山頂から北に向かって延びる尾根上の、標高270-280m地点にある岩塊群周辺から、古墳時代末-奈良時代に掛けての須恵器や土師器、瑪瑙製勾玉、鉄鏃などの祭祀遺物が採集されており、山頂から麓の斎場に神を招き降ろす祭祀が行なわれた磐座だったのではないか、と考えられている。
本堂付近からは、奈良-平安時代頃の緑釉陶器や仏鉢などの遺物が発見され、鎌倉期に対岸から移建されたと考えられて来た「弥山水精寺」の創建年代を遡らせるもの、として注目されている[5]。
「宮島ロープウエー」
1959年に開業。宮島の紅葉谷駅(紅葉谷公園)と弥山の獅子岩駅を結んでいる。途中に榧谷駅があるが、この駅での乗下車はできない。



標高535m、今も原始林が残り、一部世界遺産に登録、紅葉谷駅ー獅子岩駅約15分・獅子岩駅ー霊火堂徒歩20分ー頂上10分
弥山(みせん)は、宮島(厳島)の中央部にある標高535 mの山で、古くからの信仰の山。

山頂には、展望台が、伊藤博文は「日本三景の一の真価は頂上の眺めにあり」と絶賛した。
海域(瀬戸内海)および島全体として、「瀬戸内海国立公園内」に位置しており、「弥山」の山麓は、北側斜面には、国の天然記念物となっている
瀰山原始林が存在し、暖温帯性針葉樹のモミと南方系高山植物ミミズバイの同居やヤグルマの群落など、特異な植物・植生の分布が見られると云う。
「干満岩」大きな岩の側面に開いた小さな穴で、その中の水は海の潮が満ちると溢れ、潮が引くと乾くと言われている。

「空海」 774-835 真言宗開祖 讃岐国に生まれ、仏教の道に、四国で修行(四国遍路)後、入唐し、嵯峨帝と親交、高野山を賜る。
京都東寺を真言宗の密教道場に。
庶民学校・綜芸種智院の開設・讃岐満濃池ノ修築・書は、三筆の一人多種あり活動範囲が広い。各地で伝説も多い。
全集が刊行し延喜21年「弘法大師」。



「錫杖の梅」弥山本堂のすぐ脇の梅の木で、弘法大師が立てかけた錫杖が、根を張り八重紅梅が美しく咲き始めたといわれている。
また弥山に不吉な兆しがあるときは咲かないともいわれている。



日本天台宗の開祖最澄と共に、日本仏教・奈良仏教から平安仏教へと、転換していく流れの劈頭に位置し、中国より真言密教をもたらし、能書家としても知られ、嵯峨天皇・橘逸勢と共に三筆のひとりに数えられている「空海」。
「消えずの霊火」



「曼荼羅岩」弥山本堂の南側に数十畳の大岩があり、弘法大師が筆したものを、石面に梵字と真字で「三世諸物天照大神宮正八幡三所三千七百余神云々」と彫り込まれている。



「空海の誕生日」は、
中国密教の大成者である不空三蔵の入滅の日であり、空海が不空の生まれ変わりとする伝承によるもの、正確な誕生日は不明である。
「拍子木の音」人気のない深夜に拍子木の音が聞こえると言われ、天狗の仕業だろうと伝えられている。



空海が阿波の大瀧岳(太竜寺山付近)や、土佐の室戸岬などで求聞持法を修ましたことが記されている。
室戸岬の御厨人窟で修行をしているとき、口に明星が飛び込んできたと記されている。
このとき空海は悟りを開いたといわれ、当時の御厨人窟は海岸線が今よりも上にあり、洞窟の中で空海が目にしていたのは空と海だけであったため、
空海と名乗ったと伝わっている。
平安時代の 806年、に空海が弥山を開山し、真言密教の修験道場となったと伝えられる。(空海が厳島を訪れたことを示す記録は存在しない)



山頂から北に向かって延びる尾根上の、標高270-280m地点にある岩塊群周辺から、古墳時代末-奈良時代に掛けての須恵器や土師器、瑪瑙製勾玉、鉄鏃などの祭祀遺物が採集されており、山頂から麓の斎場に神を招き降ろす祭祀が行なわれた磐座だったのではないか、と考えられている。
本堂付近からは、奈良-平安時代頃の緑釉陶器や仏鉢などの遺物が発見され、鎌倉期に対岸から移建されたと考えられて来た「弥山水精寺」の創建年代を遡らせるもの、として注目されている。



日本各地の霊山を修行の場とし、深山幽谷に分け入り厳しい修行を行うことによって超自然的な能力「験力」を得て、衆生の救済を目指す実践的な
真言宗の密教。
山岳修行者のことを「修行して迷妄を払い験徳を得る」、山に伏して修行する姿から山伏と呼ぶ。
山岳修業は、奈良時代に役小角(役行者)が創始したとされるが、役小角は伝説的な人物なので開祖に関する史実は不詳である。
役小角は終生を在家のまま通したとの伝承から、開祖の遺風に拠って在家主義を貫いている。
平安時代ごろから盛んに信仰されるようになった。
平安初期に伝来した密教との結びつきが強く、鎌倉時代後期から南北朝時代には独自の立場を確立した。
江戸幕府は、1613年に修験道法度を定め、真言宗系の当山派と、天台宗系の本山派のどちらかに属さねばならない。
明治になると、1868年の神仏分離令に続き、明治5年、修験禁止令が出され、修験道は禁止された。里山伏(末派修験)は強制的に還俗させられた。
廃仏毀釈により、修験道の信仰に関するものが破壊された。修験系の講団体のなかには、明治以降、仏教色を薄めて教派神道となったものもある。
御嶽教、扶桑教、実行教、丸山教などが主で、教派神道にもかかわらず不動尊の真言や般若心経の読誦など神仏習合時代の名残も見られる。
「消えずの霊火」 806年、空海が宮島で修行をした時に焚かれた護摩の火がおよそ1,200年間、昼夜燃え続け、元火の絶えない霊火。
不消霊火堂にある。大茶釜の湯は、万病に効く霊水と言われている。広島平和記念公園の平和の灯の元火の一つとなった。

桓武天皇の孫、「高岳親王」は、十大弟子のひとり、
「十大弟子」は、878年に、空海の弟子真雅が朝廷に言上した「本朝真言宗伝法阿闍梨師資付法次第の事」によれば、
空海の付法弟子は、真済、ー真雅、ー実恵、ー道雄、ー円明、ー真如、ー杲隣、ー泰範、ー智泉、ー忠延ーの10人とされる。
(10人を釈迦の十大弟子になぞらえている。)


山名については、山の形が須弥山に似ていることからという説、元は「御山」と呼んでいたのが「弥山」となったという説などがある。
なお、山頂にある三角点の名称は「御山」である。

次回は、宮島・要害山へ。