「王子と紙」
「王子製紙」の社名の由来は、東京の王子で創業し、国内(内地)各地のみならず朝鮮や樺太へと 進出。
富士製紙・樺太工業などとの合併を繰り返して国内市場8割以上を握る巨大製紙 会社へと発展していった。
その規模から「大王子製紙」と称された企業。
紙の原料は、洋紙では木材と古紙がほとんどを占め,木材が紙の原料となったのは19世紀後半からで、それより前は非木材植物原料が主流だったと云う。
近年では製紙による森林伐採を抑制する観点から、ケナフ、サトウキビ、タケなどの非木材植物が注目。
紙の原料である植物繊維は、セルロースが主成分である。植物繊維細胞壁の成分を細分するとセルロース・ヘミセルロース・リグニンの分けられる。
セルロースが骨格を、ヘミセルロースが接続を、リグニンが空隙充填を担う。
セルロースは、水素結合によって結びつく性質がある。紙を構成する繊維がくっつき合うのは、主にこうした水素結合のため、水素結合は水が入るとすぐ切れるため、防水加工していない紙は水濡れに弱いと云う。
直径100マイクロメートル以下の細長い繊維状であれば、鉱物、金属、動物由来の物質、または合成樹脂など、ほぼあらゆる種類の原料を用いて作ることができ不織布は紙の一種として分類されることもあるが、一般には、紙は植物繊維を原料にしているものを指す。
紙の用途は様々で、原初の紙は単純に包むための包装用に使われ、やがて筆記可能な紙が開発され、パピルスや羊皮紙またはシュロ・木簡・貝葉などに取って代わり情報の記録・伝達を担う媒体など。
製法に工夫がこらされ、日本では和紙の技術確立とともに発展し、江戸時代には襖や和傘、提灯・扇子など建築・工芸材料にも用途を広げ、西洋では工業的な量産化が進行し、木材から直接原料を得てパルプを製造する技術が確立されたていった。
19世紀に入るとイギリスでフルート(段)をつけた紙が販売され、瓶やガラス製品の包装用途を通じて段ボールが開発、クラフト紙袋など高機能化が施され、包装用としての分野を広げ現在に至っている。(紙の博物館)
飛鳥山公園を後に「名主の滝」方面へ歩く。
音無親水公園は,江戸時代から音無川と呼ばれ行楽の名所。
石神井川を整備し、緑とせせらぎを楽しめる空間として昭和63年、公園。(日本の都市公園100選に一つ」
音無の名前の由来は、八代将軍吉宗が紀州の音無川にちなんで命名したとも云われている。
徳川吉宗が川沿いに100本の紅葉を植え、飛鳥山に桜を植えた。
弁天の滝、不動の滝、大滝と、名勝であった。「音無川の水でいれたお茶は、美味しかったと伝った」と云う。
本郷通りをそのまま直進すると「音無橋」を渡る。今は「親水公園」、右手は、東京10社北方守護「王子神社」。

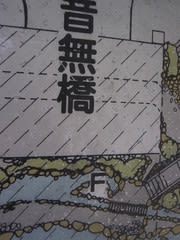

飛鳥山に沿ってJR王子駅があり、その間に音無川流れていた。JRガードを潜ると都電荒川線・地下鉄南北線・北本通りに出る。
音無川は,石神井川から王子の滝(音無橋下流にあった滝)付近で分岐し、飛鳥山の東を流れ、日暮里、根岸、三ノ輪、思川、山谷堀(日本堤)、今戸
隅田川に流れていた。



「王子神社」北区王子本町に鎮座。(旧称王子権現。この一帯の「王子」という地名の由来)
創建年月日不詳・1322年 当地の領主豊島氏が社殿を再興し、熊野新宮の浜王子より「若一王子宮」を改めて勧請・奉斎、王子神社となる。
明治初期 准勅祭社に指定。昭和20年 戦災で社殿を焼失。昭和39年)、昭和57年、二回の造営を経て社殿を再建。
御神徳ー開運厄除・子育大願。



「春日局」 1579-1643 三代将軍徳川家光の乳母・明智光秀の重臣斉藤利光の娘・稲田正成に嫁ぎ4男、離婚・26歳で乳母・大奥の実力者。
江戸時代、春日局は、王子神社に祈願し、家光の将軍就任が叶えられたことで、「子育大願」の神社で知られている。
特に七五三の御神徳で賑わう。
戦国時代の小田原北条氏の崇敬し朱印状を寄せている。徳川家康公は、1591年200石寄進し「王子権現」の呼称で江戸名所の一つ。特に吉宗は、
紀州ゆかりの神社、飛鳥山に桜を植え庶民遊楽の地としている。
拝殿

田楽舞ー8月の例大祭には北区無形民俗文化財に指定されている「王子神社の田楽舞」が奉納。
攝末社・関神社ー主祭神 蝉丸公(神霊) 逆髪姫(神霊) 古屋美女(神霊)
蝉丸公は、延喜帝の第四皇子、髪の毛が逆髪である故に嘆き悲しむ姉君「逆髪姫」のために侍女の「古屋美女」に命じて「かもじ・かつら」を考案し髪を整える工夫をしたことから「音曲諸芸道の神」、「髪の祖神」と崇敬を集めていて、「関蝉丸神社」として、滋賀県大津の逢坂山に祀られている、
その御神徳を敬仰する人達が「かもじ業者」を中心として江戸時代に奉斎された。
1945年 戦災により社殿焼失・1959年 全国各地の「かもじ・かつら・床山・舞踊・演劇・芸能・美容師」の浄財により再建した。
8月上旬例大祭「槍祭」槍の形をした「御槍」のお守り・2年一度の本祭神輿数10基・12月6日の熊手市



「王子稲荷の坂」
坂は、王子稲荷神社の南側に沿って東から西に登る坂で、神社名から名前が。
江戸時代には、この坂を登ると日光御成道があり、それを北へ少し進むとさらに北西に続く道があり、姥ヶ橋を経て、蓮沼村(現板橋区清水町)まで続き、そこで中山道につながって、この道が「稲荷道」。
中山道から来る王子稲荷神社への参詣者に利用されていた。
急な坂道、中間に稲荷神社の石鳥居

大晦日の夜、王子は幻想的な光景に包まれ,面をかぶったり、メイクをほどこし、「きつね」に扮した人たちが王子装束稲荷神社に集まり、行列を成して大勢の見物に囲まれながら練り歩き王子稲荷へ参詣する一大イベント「きつねの行列」が。
「毎年大晦日になると、関東一円から狐が集まり装束を整えて、王子稲荷にお参りした」そんな昔の言い伝えを、今に残そうと。
拝殿
![]()

「名主の滝公園」-子供の頃、ヨツデを持って遊んだ公園
江戸時代、王子村の名主「畑野孫八」が屋敷内に滝を開き、茶を栽培して避暑のために一般に開放したのが始まりで、「名主」はそこに由来。
明治中期には貿易商「垣内徳三郎」の所有となり、栃木の塩原の風景を模して庭石を入れ、ヤマモミジなどを植栽、渓流をつくり一般に供した。
昭和13年には、「株式会社精養軒」が買収し食堂やプールなどを営業していたが、戦災で焼失。その後は荒れ果てていたが、都が土地の買収と橋や東屋などの修理を進め、昭和35年に都の有料公園として開園した。昭和50年、区に移管。
園内は回遊式の庭園となっており、男滝、女滝、独鈷の滝、湧玉の滝の4つの滝が復元。
滝は、地下水をポンプで汲み上げて水を流しており、滝から流れた水は小川となって園内を巡り大小の池に注いでいる。
一時、園内に人工飼育し放流されたヘイケボタルが自生していることが確認。
石神井川とその支流には、「王子七滝」-名主の滝・稲荷の滝・権現の滝・大工の滝・見晴の滝・不動の 滝・弁天の滝が



整備は明治の中頃。傾斜地を利用した庭園なのですが、規模も相当あり、傾斜に延びる散策道を歩いていると、うっそうとした森。
王子は武蔵野台地の突端で、元々滝が多く、「王子七滝」と呼ばれる滝があった。
落差8メートルの滝ほか、そのいくつかがここに残っている。
現存する滝が「名主の滝」ですが、ここも現在は湧水が枯渇して、深さ180mの 井戸からポンプで揚水していると云う。



広重の浮世絵に描かれた王子界隈の音無川流域は、飛鳥山と王子の台地にはさまれた渓谷で、両岸の断崖からは幾筋もの滝が形成されていたと思う。
「王子五滝」「王子七滝」と言われたように滝が多く、音無川に滔々と流れ落ち水量も豊富だったようで。
昔は、ここ王子の「独立行政法人 酒類総合研究所」( 赤レンガ酒造工場が重要文化財に指定)があった所。
現在の旧醸造試験所第一工場には、全国の新酒が集められ検定されていたとこれである。。
飛鳥山の桜と云い、音無橋親水公園・王子神社など緑が多いが、音無川は、今無く、水豊であった「名主の滝」も私には、寂しく感じた。



王子の「不動の滝」は有名で、広重が残した浮世絵中最大の滝である。
滝近くの褌姿の男、これがまさしく滝浴みをしている光景であると云う。滝を眺めている二人連れの女性、茶屋も出て老婆が客に給仕をしている様子。
心地よい滝の音や飛沫を感じながら、一時の清涼感につつまれ、滝浴みをしている。
元首相田中角栄が夜学で学んだ工学校の校舎が分散していた。



明治44年、王子電気鉄道(株)として、昭和17年に陸上交通事業調整法に基づき、東京市電気局が王子電気鉄道(株)を統合し、「市電」となり、
昭和18年には、都制施行により「都電」の名称が、都内の大衆輸送の花形だった都電も、昭和30年代から始まった自動車の増大などで、輸送効率が著しく低下し経営は極度に悪化。このため、都は、都電撤去にふみきり、昭和42年~47年にかけて、35路線を廃止。
荒川電車営業所の27系統(三ノ輪橋~赤羽)と32系統(荒川車庫前~早稲田)も廃止予定でした。しかし、この2線路は、
1.大部分が専用軌道で、
2.他に代替交通機関がなく、
3.沿線住民の強い存続希望があったため、27系統のうち、王子駅前~赤羽以外は存続することになりました。
昭和49年に27系統と32系統を1本化し、三ノ輪橋~早稲田を走る荒川線と名称を変えました。
バラの咲き誇る三ノ輪橋停留所が「関東の駅100選」に選ばれた。(パンフレットより)
専用路を走る荒川線 終点三ノ輪駅



「石川屋敷跡・ 伊勢亀山藩主石川日向守屋敷」
三の輪一帯(現在のジョイフル三の輪)あたりにあって、総坪数11040坪(約36400m2)にも及ぶ広さであったと云う。
1658年、主殿頭憲之の時に、三河島・三ノ輪・小塚原3か村のうち10530坪(約34700m2)の地を拝領し下屋敷を増築。
寛文5年の1665年、三河島村重右衛門の所有地518坪(約1700平方m2)を買上げ、屋敷・庭園を増築。
現在、荒川区立瑞光公園に屋敷

「対馬府中藩」
江戸時代に対馬国(長崎県対馬市)全土と肥前国田代(佐賀県鳥栖市東部及び基山町)及び浜崎(佐賀県唐津市浜玉町浜崎)を治めていた藩で、
別名厳原藩。
「府中」は当時厳原の城下町をこう称していたことに由来する。
藩庁は当初金石城(対馬市厳原町西里)、のち桟原城(対馬市厳原町桟原)。藩主は宗氏で初代藩主義智以来、官位は従四位下を与えられ、
官職は主に対馬守・侍従を称した。
「音無川」は、王子ー日暮里ー根岸ー三ノ輪ー日本堤ー浅草山谷ー隅田川へ。
三ノ輪は、下屋敷ー26700m2



次回は、三ノ輪から旧国際通り(旧竜泉寺)樋口一葉館方面を。
「王子製紙」の社名の由来は、東京の王子で創業し、国内(内地)各地のみならず朝鮮や樺太へと 進出。
富士製紙・樺太工業などとの合併を繰り返して国内市場8割以上を握る巨大製紙 会社へと発展していった。
その規模から「大王子製紙」と称された企業。
紙の原料は、洋紙では木材と古紙がほとんどを占め,木材が紙の原料となったのは19世紀後半からで、それより前は非木材植物原料が主流だったと云う。
近年では製紙による森林伐採を抑制する観点から、ケナフ、サトウキビ、タケなどの非木材植物が注目。
紙の原料である植物繊維は、セルロースが主成分である。植物繊維細胞壁の成分を細分するとセルロース・ヘミセルロース・リグニンの分けられる。
セルロースが骨格を、ヘミセルロースが接続を、リグニンが空隙充填を担う。
セルロースは、水素結合によって結びつく性質がある。紙を構成する繊維がくっつき合うのは、主にこうした水素結合のため、水素結合は水が入るとすぐ切れるため、防水加工していない紙は水濡れに弱いと云う。
直径100マイクロメートル以下の細長い繊維状であれば、鉱物、金属、動物由来の物質、または合成樹脂など、ほぼあらゆる種類の原料を用いて作ることができ不織布は紙の一種として分類されることもあるが、一般には、紙は植物繊維を原料にしているものを指す。
紙の用途は様々で、原初の紙は単純に包むための包装用に使われ、やがて筆記可能な紙が開発され、パピルスや羊皮紙またはシュロ・木簡・貝葉などに取って代わり情報の記録・伝達を担う媒体など。
製法に工夫がこらされ、日本では和紙の技術確立とともに発展し、江戸時代には襖や和傘、提灯・扇子など建築・工芸材料にも用途を広げ、西洋では工業的な量産化が進行し、木材から直接原料を得てパルプを製造する技術が確立されたていった。
19世紀に入るとイギリスでフルート(段)をつけた紙が販売され、瓶やガラス製品の包装用途を通じて段ボールが開発、クラフト紙袋など高機能化が施され、包装用としての分野を広げ現在に至っている。(紙の博物館)
飛鳥山公園を後に「名主の滝」方面へ歩く。
音無親水公園は,江戸時代から音無川と呼ばれ行楽の名所。
石神井川を整備し、緑とせせらぎを楽しめる空間として昭和63年、公園。(日本の都市公園100選に一つ」
音無の名前の由来は、八代将軍吉宗が紀州の音無川にちなんで命名したとも云われている。
徳川吉宗が川沿いに100本の紅葉を植え、飛鳥山に桜を植えた。
弁天の滝、不動の滝、大滝と、名勝であった。「音無川の水でいれたお茶は、美味しかったと伝った」と云う。
本郷通りをそのまま直進すると「音無橋」を渡る。今は「親水公園」、右手は、東京10社北方守護「王子神社」。

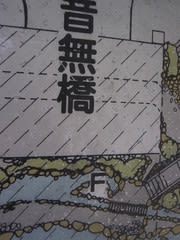

飛鳥山に沿ってJR王子駅があり、その間に音無川流れていた。JRガードを潜ると都電荒川線・地下鉄南北線・北本通りに出る。
音無川は,石神井川から王子の滝(音無橋下流にあった滝)付近で分岐し、飛鳥山の東を流れ、日暮里、根岸、三ノ輪、思川、山谷堀(日本堤)、今戸
隅田川に流れていた。



「王子神社」北区王子本町に鎮座。(旧称王子権現。この一帯の「王子」という地名の由来)
創建年月日不詳・1322年 当地の領主豊島氏が社殿を再興し、熊野新宮の浜王子より「若一王子宮」を改めて勧請・奉斎、王子神社となる。
明治初期 准勅祭社に指定。昭和20年 戦災で社殿を焼失。昭和39年)、昭和57年、二回の造営を経て社殿を再建。
御神徳ー開運厄除・子育大願。



「春日局」 1579-1643 三代将軍徳川家光の乳母・明智光秀の重臣斉藤利光の娘・稲田正成に嫁ぎ4男、離婚・26歳で乳母・大奥の実力者。
江戸時代、春日局は、王子神社に祈願し、家光の将軍就任が叶えられたことで、「子育大願」の神社で知られている。
特に七五三の御神徳で賑わう。
戦国時代の小田原北条氏の崇敬し朱印状を寄せている。徳川家康公は、1591年200石寄進し「王子権現」の呼称で江戸名所の一つ。特に吉宗は、
紀州ゆかりの神社、飛鳥山に桜を植え庶民遊楽の地としている。
拝殿

田楽舞ー8月の例大祭には北区無形民俗文化財に指定されている「王子神社の田楽舞」が奉納。
攝末社・関神社ー主祭神 蝉丸公(神霊) 逆髪姫(神霊) 古屋美女(神霊)
蝉丸公は、延喜帝の第四皇子、髪の毛が逆髪である故に嘆き悲しむ姉君「逆髪姫」のために侍女の「古屋美女」に命じて「かもじ・かつら」を考案し髪を整える工夫をしたことから「音曲諸芸道の神」、「髪の祖神」と崇敬を集めていて、「関蝉丸神社」として、滋賀県大津の逢坂山に祀られている、
その御神徳を敬仰する人達が「かもじ業者」を中心として江戸時代に奉斎された。
1945年 戦災により社殿焼失・1959年 全国各地の「かもじ・かつら・床山・舞踊・演劇・芸能・美容師」の浄財により再建した。
8月上旬例大祭「槍祭」槍の形をした「御槍」のお守り・2年一度の本祭神輿数10基・12月6日の熊手市



「王子稲荷の坂」
坂は、王子稲荷神社の南側に沿って東から西に登る坂で、神社名から名前が。
江戸時代には、この坂を登ると日光御成道があり、それを北へ少し進むとさらに北西に続く道があり、姥ヶ橋を経て、蓮沼村(現板橋区清水町)まで続き、そこで中山道につながって、この道が「稲荷道」。
中山道から来る王子稲荷神社への参詣者に利用されていた。
急な坂道、中間に稲荷神社の石鳥居

大晦日の夜、王子は幻想的な光景に包まれ,面をかぶったり、メイクをほどこし、「きつね」に扮した人たちが王子装束稲荷神社に集まり、行列を成して大勢の見物に囲まれながら練り歩き王子稲荷へ参詣する一大イベント「きつねの行列」が。
「毎年大晦日になると、関東一円から狐が集まり装束を整えて、王子稲荷にお参りした」そんな昔の言い伝えを、今に残そうと。
拝殿

「名主の滝公園」-子供の頃、ヨツデを持って遊んだ公園
江戸時代、王子村の名主「畑野孫八」が屋敷内に滝を開き、茶を栽培して避暑のために一般に開放したのが始まりで、「名主」はそこに由来。
明治中期には貿易商「垣内徳三郎」の所有となり、栃木の塩原の風景を模して庭石を入れ、ヤマモミジなどを植栽、渓流をつくり一般に供した。
昭和13年には、「株式会社精養軒」が買収し食堂やプールなどを営業していたが、戦災で焼失。その後は荒れ果てていたが、都が土地の買収と橋や東屋などの修理を進め、昭和35年に都の有料公園として開園した。昭和50年、区に移管。
園内は回遊式の庭園となっており、男滝、女滝、独鈷の滝、湧玉の滝の4つの滝が復元。
滝は、地下水をポンプで汲み上げて水を流しており、滝から流れた水は小川となって園内を巡り大小の池に注いでいる。
一時、園内に人工飼育し放流されたヘイケボタルが自生していることが確認。
石神井川とその支流には、「王子七滝」-名主の滝・稲荷の滝・権現の滝・大工の滝・見晴の滝・不動の 滝・弁天の滝が



整備は明治の中頃。傾斜地を利用した庭園なのですが、規模も相当あり、傾斜に延びる散策道を歩いていると、うっそうとした森。
王子は武蔵野台地の突端で、元々滝が多く、「王子七滝」と呼ばれる滝があった。
落差8メートルの滝ほか、そのいくつかがここに残っている。
現存する滝が「名主の滝」ですが、ここも現在は湧水が枯渇して、深さ180mの 井戸からポンプで揚水していると云う。



広重の浮世絵に描かれた王子界隈の音無川流域は、飛鳥山と王子の台地にはさまれた渓谷で、両岸の断崖からは幾筋もの滝が形成されていたと思う。
「王子五滝」「王子七滝」と言われたように滝が多く、音無川に滔々と流れ落ち水量も豊富だったようで。
昔は、ここ王子の「独立行政法人 酒類総合研究所」( 赤レンガ酒造工場が重要文化財に指定)があった所。
現在の旧醸造試験所第一工場には、全国の新酒が集められ検定されていたとこれである。。
飛鳥山の桜と云い、音無橋親水公園・王子神社など緑が多いが、音無川は、今無く、水豊であった「名主の滝」も私には、寂しく感じた。



王子の「不動の滝」は有名で、広重が残した浮世絵中最大の滝である。
滝近くの褌姿の男、これがまさしく滝浴みをしている光景であると云う。滝を眺めている二人連れの女性、茶屋も出て老婆が客に給仕をしている様子。
心地よい滝の音や飛沫を感じながら、一時の清涼感につつまれ、滝浴みをしている。
元首相田中角栄が夜学で学んだ工学校の校舎が分散していた。



明治44年、王子電気鉄道(株)として、昭和17年に陸上交通事業調整法に基づき、東京市電気局が王子電気鉄道(株)を統合し、「市電」となり、
昭和18年には、都制施行により「都電」の名称が、都内の大衆輸送の花形だった都電も、昭和30年代から始まった自動車の増大などで、輸送効率が著しく低下し経営は極度に悪化。このため、都は、都電撤去にふみきり、昭和42年~47年にかけて、35路線を廃止。
荒川電車営業所の27系統(三ノ輪橋~赤羽)と32系統(荒川車庫前~早稲田)も廃止予定でした。しかし、この2線路は、
1.大部分が専用軌道で、
2.他に代替交通機関がなく、
3.沿線住民の強い存続希望があったため、27系統のうち、王子駅前~赤羽以外は存続することになりました。
昭和49年に27系統と32系統を1本化し、三ノ輪橋~早稲田を走る荒川線と名称を変えました。
バラの咲き誇る三ノ輪橋停留所が「関東の駅100選」に選ばれた。(パンフレットより)
専用路を走る荒川線 終点三ノ輪駅



「石川屋敷跡・ 伊勢亀山藩主石川日向守屋敷」
三の輪一帯(現在のジョイフル三の輪)あたりにあって、総坪数11040坪(約36400m2)にも及ぶ広さであったと云う。
1658年、主殿頭憲之の時に、三河島・三ノ輪・小塚原3か村のうち10530坪(約34700m2)の地を拝領し下屋敷を増築。
寛文5年の1665年、三河島村重右衛門の所有地518坪(約1700平方m2)を買上げ、屋敷・庭園を増築。
現在、荒川区立瑞光公園に屋敷

「対馬府中藩」
江戸時代に対馬国(長崎県対馬市)全土と肥前国田代(佐賀県鳥栖市東部及び基山町)及び浜崎(佐賀県唐津市浜玉町浜崎)を治めていた藩で、
別名厳原藩。
「府中」は当時厳原の城下町をこう称していたことに由来する。
藩庁は当初金石城(対馬市厳原町西里)、のち桟原城(対馬市厳原町桟原)。藩主は宗氏で初代藩主義智以来、官位は従四位下を与えられ、
官職は主に対馬守・侍従を称した。
「音無川」は、王子ー日暮里ー根岸ー三ノ輪ー日本堤ー浅草山谷ー隅田川へ。
三ノ輪は、下屋敷ー26700m2



次回は、三ノ輪から旧国際通り(旧竜泉寺)樋口一葉館方面を。


























































































