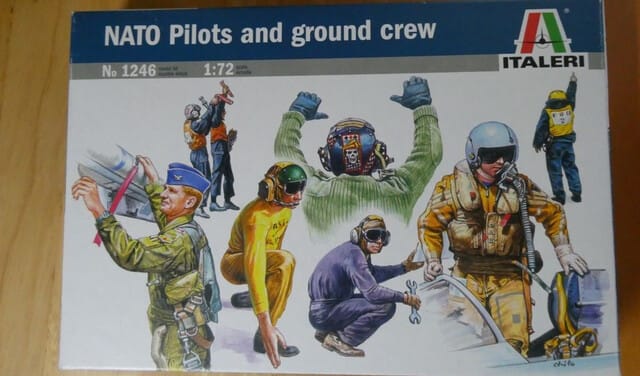週末のIH予選、帰宅してから発熱でダウン
まだ咳ゲボゲボと鼻水タラタラでティッシュ大量消費中ですが
何とか机に向かえるようになりました(^^;
お約束のコックピットです
ここをクリアしなければヒコーキ模型は先に進めません
まぁ所謂、工程管理で云うクリチカルパスというヤツですか(笑)
 、
、
無事キャノピー切断が出来ましたので
と云ってもキットは第1風防が別になっており、後ろの部分は2タイプ入ってます
このスライドキャノピーと後ろの固定部分をそれぞれ切断して、ニコイチにすればいいのですから
早い話『楽です』(笑)
ガンサイトのリフレクターはフィルムの切れ端で自作しました

第1風防を付けてみましたが、ちゃんと見えますね~(;'∀')
BoB時のMkⅠのガンサイトはGM2Mk1というヤツでした
これの外見的特徴はリフレクターが円形で有る事です
キットのものは、リフレクターが方形なんですよね
これはMkⅤに装備されていたType1 Mk1を形にしているようです
そんな訳での自作だったのですが、下半分を黒く塗るのを忘れていました💦
コックピット周りが出来たので、機体塗装に入ります
まず上面の迷彩から
当時のRAFはAスキームとBスキームという
(面倒くさい)2つの迷彩パターンが有ったのはご存じだと思います
このスピットはどっちの方になるかと云えばAスキーム
1回目の写真、コックピット前側の迷彩塗り分けラインで判ります

因みにBスキームは、メーカーの箱絵ですがこうなります

パターンも判明、面相筆でペタペタ塗り始めます
使用色はC361ダークグリーンとC360ダークアース、いつものヤツです(^^;

5~6回塗り重ね、迷彩の境界を混色したものを極細面相筆でなぞったところ


スプレー塗装の感じを出したつもり...スケールとの兼ね合いも有ってここ難しいです💦
裏面はNo24:スカイでまた筆塗りです

明度の高い色は、ポッテリ盛りにならないよう気を使いますよね
この後上面と同様、色を重ねていきます。
【続く】
まだ咳ゲボゲボと鼻水タラタラでティッシュ大量消費中ですが
何とか机に向かえるようになりました(^^;
お約束のコックピットです
ここをクリアしなければヒコーキ模型は先に進めません
まぁ所謂、工程管理で云うクリチカルパスというヤツですか(笑)
 、
、無事キャノピー切断が出来ましたので
と云ってもキットは第1風防が別になっており、後ろの部分は2タイプ入ってます
このスライドキャノピーと後ろの固定部分をそれぞれ切断して、ニコイチにすればいいのですから
早い話『楽です』(笑)
ガンサイトのリフレクターはフィルムの切れ端で自作しました

第1風防を付けてみましたが、ちゃんと見えますね~(;'∀')
BoB時のMkⅠのガンサイトはGM2Mk1というヤツでした
これの外見的特徴はリフレクターが円形で有る事です
キットのものは、リフレクターが方形なんですよね
これはMkⅤに装備されていたType1 Mk1を形にしているようです
そんな訳での自作だったのですが、下半分を黒く塗るのを忘れていました💦
コックピット周りが出来たので、機体塗装に入ります
まず上面の迷彩から
当時のRAFはAスキームとBスキームという
(面倒くさい)2つの迷彩パターンが有ったのはご存じだと思います
このスピットはどっちの方になるかと云えばAスキーム
1回目の写真、コックピット前側の迷彩塗り分けラインで判ります

因みにBスキームは、メーカーの箱絵ですがこうなります

パターンも判明、面相筆でペタペタ塗り始めます
使用色はC361ダークグリーンとC360ダークアース、いつものヤツです(^^;

5~6回塗り重ね、迷彩の境界を混色したものを極細面相筆でなぞったところ


スプレー塗装の感じを出したつもり...スケールとの兼ね合いも有ってここ難しいです💦
裏面はNo24:スカイでまた筆塗りです

明度の高い色は、ポッテリ盛りにならないよう気を使いますよね
この後上面と同様、色を重ねていきます。
【続く】