今、関心があり、考えています。
知的障害のある児童生徒に対して、この視点でどのような授業づくりができるのかと・・・。
そんな思いで、学級で自由に裁量できる時間を使って試みていますが、あまりうまくいっていなくて、子どもたちにとって苦痛な時間を強いているように感じています・・・。研究デザイン、仮説に問題があるのだと思います・・・。
知的障害教育には教科書がなく、子どもたちの実態に応じて弾力的に授業づくりができます。
その「弾力的」をはき違えると(子どもたちの今現在の学び、及び予後に対しても)、あまり良くない結果しか出ないようにも感じています(教員の責任の重さを感じます)。
年度末の事務処理に追われつつ、人間の思考、子どもたちへの言語指導に関する勉強をもっともっとしていかなければと空回りしている感じです・・・。
畠山










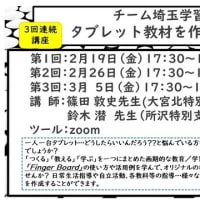
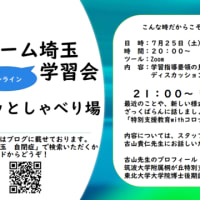
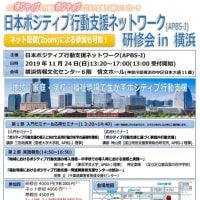







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます