どのような題にしたらよいものか。
途方に暮れました。
そして、このような場で、語ることが許されるかという事も。
ただ、遠くとは言え、多少なりとも縁があれば、それをお伝えすることも「くだまき」なのであろうかとも。
2011年9月11日放送 22:00 - 23:15 フジテレビ
Mr.サンデー 3.11市民映像ドキュメント
東日本大震災発生時に、石巻市立病院で手術をしていた内山哲之医師は、避難せずに手術を続行した。しかし病院内が停電したことで、懐中電灯を使い手術を終わらせた。
東日本大震災から半年が経過した、石巻市立病院を取材。病院内はいまだにガレキが撤去されずに残っている。津波に襲われた石巻市立病院では、上の階に患者を避難させていた。病院の屋上には、ヘリコプターに向けた救援メッセージが書かれた。
東日本大震災発生から3日たっても救助がこなかったことから、石巻市立病院
の内山医師は自ら救助を求めに行った。地震発生から68時間後、石巻市立病院にようやく救助のヘリコプターが到着した。
石巻市立病院では、重症患者から順番にヘリコプターで搬送した。すべての患者を搬送した後、医師や看護師たちが医療器具を病院から運び出した。
患者150人 空から救え
東日本大震災の翌朝、浜松市にある聖隷三方原病院の救急医、矢野賢一(やの・けんいち)(40)はドクターヘリで福島県に飛んだ。大災害時、緊急医療にあたる「災害派遣医療チーム(DMAT)」の任務だった。
福島県立医大で待機していた3月13日午前10時、出動要請が来た。福島ではなく、宮城県の石巻市立病院から手術患者を運んでほしいという。
「地震でけがをした人の緊急手術でもしたのかな」。矢野はヘリに乗り込んだ。
約30分後、汚泥とがれきに覆い尽くされた街に、5階建ての病院がぽつんと見えてきた。「えっ、こんなところで手術をしているのか?」
その病院には患者約150人とスタッフ約250人が取り残されていた。地震時、胃の手術中だった患者は、仮縫い状態で手術を中断したまま40時間がたっていた。水道、ガス、電気は止まり、発電機は水没。食料は尽きた。電話も無線も通じない。周囲の道路は寸断され、外との連絡のすべすらなかった。
その日の早朝、循環器科部長の赤井健次郎(あかい・けんじろう)(52)は助けを求める最後の手段として、外科部長の内山哲之(うちやま・てつゆき)(44)を約5キロ離れた石巻赤十字病院へ送り出していた。内山は、がれきだらけの冷たい水に腰までつかり歩いていった。
そして、ドクターヘリが来た。内山が無事にたどり着き、ヘリ出動につながったのだと赤井は察した。
◇
ヘリから降りた矢野は石巻市立病院の姿に息をのんだ。1階の窓に車や流木が突き刺さっている。「患者1人と手術スタッフを運ぶ」という要請だったが、衛星携帯電話に叫んでいた。「1人運んですむ話じゃありません!」
矢野が「いしまき、いしまき」と連呼するのを、赤井は横で聞いていた。名も知らぬ街の病院を救おうと、必死になってくれていると感じた。
日没直前に、追加のドクターヘリ2機と自衛隊ヘリが到着した。危険な状態にあった患者6人を急いで運んだ。
3月26日叔母から電話があった。
「あなたの書いた『くだまき3.11記憶そして記録 花は咲く・・・のか』に出て来る石巻の病院って市立病院のことなの?」
「違うっちゃ。おらいの先輩がいる民間の病院(外科医院)だべ」
「ああそうなの・・・てっきり内山君のことかって思って・・」
「その先生なら知ってっちゃ。震災当日、手術だった先生だすぺ。マスコミでも取り上げられたっちゃ・・」
「やっぱりあんた知ってたんだ・・」
「何して、そげなこと聞くのすか?」
「先だって、ね。内山君、亡くなって・・・」
「亡くなったのすか?」
「自宅のアパートの部屋で亡くなってたって・・・」
言葉が出ない。
震災から一年。
彼もまた、震災の犠牲者となってしまった。
震災当日の石巻市民病院の出来事は、多くの人が知る事となった。
内山医師はその最前線におり、強烈な揺れ、そして津波の被害に遭いながらも最後まで患者を救う事だけを念頭に置き、その任を全うしていた。
上記、報道によると、自身の患者の手術中に地震と遭遇。当日、石巻日赤病院まで徒歩で救出要請に出かけている。
彼の判断、勇気、実行力が患者を救った事実。
従弟の友人、そして、くだまきへコメントを下さる「うの君」の高校、大学での後輩になる。
「優秀な外科医」そう聞いていた。
その内山哲之医師が亡くなられた。
「震災本コーナー」大手本屋には、今だこのコーナーが大きなスペースを取っている。
「いつなくなるのだろうか・・・」大概、表紙が震災の様子を写した街の様子となっている。
それらの本が正面を見せて何十冊と並べられているのだ。
題名を見なければ、あたかも「震災写真展」でも開催されていると錯覚するほどだ。
ご丁寧にも、エスカレーターを上がり切ると、まずこのコーナーが目に入る。
「震災本は売れているのだ」。
マーケットの「いろは」である。否定しない。
だが、どうしても、目を逸らす。
現実から目を逸らすのでない。
どれも、内容が似か寄った本ばかりなのである。
正直、あきれる。
内山医師の話を掲載させている物を数冊見つける。
元気な彼の姿を見つけて、涙がでそうになった。
そして、彼の死を知らせる事が少ないことにも気づいた。
多くは、復興が進んでいるような記事ばかりが目につく。
しかし、実情は本当なのだろうか。
仮設住宅での孤独死。過労死。
精神的に追い詰められている人も多いとも聞く。
それらの記事は単にデータとしてだけの紹介しかない。
「被災地には、本当の春は今年も来なかったのではないか」
そう考えてしまった。
僕たちは、若く、そして勇気をも持ち合わせた優秀な外科医を失ってしまった。
劣悪な環境で、多くの命を救ってきた内山哲之医師。
彼の事を、多くの人に知って頂きたく「くだまき」を語った。
内山哲之君のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
追記
■消化器外科学会で優秀賞
2009.08.08 三陸河北 記事
■消化器外科学会で優秀賞 2009.08.08 石巻市立病院の内山外科部長 手術糸変更で感染症抑制 データ集積効果を全国発信/
石巻市立病院の内山哲之外科部長(42)が、大阪市で開かれた第64回日本消化器外科学会での発表を高く評価され、優秀賞を受賞した。外科手術に用いる「縫合結紮(けっさつ)糸」を絹糸から合成吸収系に切り替え、手術部位の感染症を減少させるとともに、早期治癒に結び付けた。医療チーム内の問題意識を共有して業務改善して総合的な効果を導いた点も評価された。日本では遅れている手術糸の変更が進む研究発表になる可能性もあり、地方の病院が全国に医療効果のメッセージを情報発信した意義は大きい。 内山部長は「地味な仕事を積み重ねて4年間のデータを集積した。コスト的には高くなるが、絹糸より合成吸収系にした方が感染症や炎症が少なく、結果として早く治るので合理的。患者のためになることを証明できた。地道な努力が評価されてうれしい」と、受賞の喜びを話した。
2013年3月3日 追記

震災後奔走の医師を絵本に 宮城・石巻、昨春に急逝
[文]熊井洋美 [掲載]2013年02月24日
市立石巻病院の仮設診療所で患者と談笑する内山哲之さん=2011年12月、石巻市
著者:WILLこども知育研究所 出版社:学研 価格:¥ 20,160
Amazon.co.jp 楽天ブックス 紀伊國屋書店BookWeb TSUTAYA online
東日本大震災の際に、石巻市で活躍した医師の物語が今月、絵本になった。孤立した病院の患者と仲間の救出に力を尽くし、その後も被災者の診療にあたるさなかの昨春に急逝した。懸命の救援活動は、学校や公共図書館向けに置かれる絵本で読み継がれることになる。
この医師は、石巻市立病院の外科部長だった内山哲之さん。享年45歳。
津波で浸水し、丸2日間にわたり孤立した病院で、懐中電灯の光を頼りに仲間の手術を手伝い、約150人の入院患者とスタッフ、近くの老人保健施設の入所者ら総勢約480人の安全確保に奔走した。
そして、ヘドロまみれのがれきの中を、水につかりながら歩いて約2キロ先の市役所へ助けを求めに行き、震災から3日後の夜、すべての患者が助け出された。
その後も石巻赤十字病院と協力、毎日20キロ以上歩き回って被災者を診療した。昨年1月からは同病院で勤務。診察と手術の合間に、みずからの極限体験を全国の医療関係者に役立ててほしいと、各地で講演した。
名取市に家族を置いての単身赴任は8年近くに及んだ。妻の裕子さん(46)が健康を気遣うと、「自分の家族には、名取に帰れば会える。でも石巻は、もう家族に会えない人がたくさんいるんだ。その人たちを残して、いま去ることはできない」と話したという。
昨年3月21日夜、「手術の連携がすごくうまくいったんだ」と弾んだ声で電話してきた内山さんを、裕子さんがねぎらうと、「明日は当番だからそろそろ休むね」と答えた。それが夫婦の最後の会話になった。
不整脈が何らかの死因を招いたとみられる。昨秋、震災関連死と認められた。
こうした内山さんの活躍を、東京の編集プロダクションが取材し、震災の記録を子どもに伝える絵本「語りつぎお話絵本 3月11日」(発行・学研教育出版)に収めた。全8冊(16話)のシリーズの1話として描かれている。
題は「二つの勇気」。孤立した病院の患者と仲間を守るため、救援を求めた内山さんの行動を「勇気」ととらえ、それが救助に入った医師の「勇気」と呼応して、救助が成功したと紹介されている。
「夫が被災地で体を張って頑張った姿を、多くの人に知って記憶にとどめてもらうことが、私たち家族が生きる支えにもなる」。裕子さんは、そう話している。
Book Asahi Com 「本のニュース」より抜粋
途方に暮れました。
そして、このような場で、語ることが許されるかという事も。
ただ、遠くとは言え、多少なりとも縁があれば、それをお伝えすることも「くだまき」なのであろうかとも。
2011年9月11日放送 22:00 - 23:15 フジテレビ
Mr.サンデー 3.11市民映像ドキュメント
東日本大震災発生時に、石巻市立病院で手術をしていた内山哲之医師は、避難せずに手術を続行した。しかし病院内が停電したことで、懐中電灯を使い手術を終わらせた。
東日本大震災から半年が経過した、石巻市立病院を取材。病院内はいまだにガレキが撤去されずに残っている。津波に襲われた石巻市立病院では、上の階に患者を避難させていた。病院の屋上には、ヘリコプターに向けた救援メッセージが書かれた。
東日本大震災発生から3日たっても救助がこなかったことから、石巻市立病院
の内山医師は自ら救助を求めに行った。地震発生から68時間後、石巻市立病院にようやく救助のヘリコプターが到着した。
石巻市立病院では、重症患者から順番にヘリコプターで搬送した。すべての患者を搬送した後、医師や看護師たちが医療器具を病院から運び出した。
患者150人 空から救え
東日本大震災の翌朝、浜松市にある聖隷三方原病院の救急医、矢野賢一(やの・けんいち)(40)はドクターヘリで福島県に飛んだ。大災害時、緊急医療にあたる「災害派遣医療チーム(DMAT)」の任務だった。
福島県立医大で待機していた3月13日午前10時、出動要請が来た。福島ではなく、宮城県の石巻市立病院から手術患者を運んでほしいという。
「地震でけがをした人の緊急手術でもしたのかな」。矢野はヘリに乗り込んだ。
約30分後、汚泥とがれきに覆い尽くされた街に、5階建ての病院がぽつんと見えてきた。「えっ、こんなところで手術をしているのか?」
その病院には患者約150人とスタッフ約250人が取り残されていた。地震時、胃の手術中だった患者は、仮縫い状態で手術を中断したまま40時間がたっていた。水道、ガス、電気は止まり、発電機は水没。食料は尽きた。電話も無線も通じない。周囲の道路は寸断され、外との連絡のすべすらなかった。
その日の早朝、循環器科部長の赤井健次郎(あかい・けんじろう)(52)は助けを求める最後の手段として、外科部長の内山哲之(うちやま・てつゆき)(44)を約5キロ離れた石巻赤十字病院へ送り出していた。内山は、がれきだらけの冷たい水に腰までつかり歩いていった。
そして、ドクターヘリが来た。内山が無事にたどり着き、ヘリ出動につながったのだと赤井は察した。
◇
ヘリから降りた矢野は石巻市立病院の姿に息をのんだ。1階の窓に車や流木が突き刺さっている。「患者1人と手術スタッフを運ぶ」という要請だったが、衛星携帯電話に叫んでいた。「1人運んですむ話じゃありません!」
矢野が「いしまき、いしまき」と連呼するのを、赤井は横で聞いていた。名も知らぬ街の病院を救おうと、必死になってくれていると感じた。
日没直前に、追加のドクターヘリ2機と自衛隊ヘリが到着した。危険な状態にあった患者6人を急いで運んだ。
3月26日叔母から電話があった。
「あなたの書いた『くだまき3.11記憶そして記録 花は咲く・・・のか』に出て来る石巻の病院って市立病院のことなの?」
「違うっちゃ。おらいの先輩がいる民間の病院(外科医院)だべ」
「ああそうなの・・・てっきり内山君のことかって思って・・」
「その先生なら知ってっちゃ。震災当日、手術だった先生だすぺ。マスコミでも取り上げられたっちゃ・・」
「やっぱりあんた知ってたんだ・・」
「何して、そげなこと聞くのすか?」
「先だって、ね。内山君、亡くなって・・・」
「亡くなったのすか?」
「自宅のアパートの部屋で亡くなってたって・・・」
言葉が出ない。
震災から一年。
彼もまた、震災の犠牲者となってしまった。
震災当日の石巻市民病院の出来事は、多くの人が知る事となった。
内山医師はその最前線におり、強烈な揺れ、そして津波の被害に遭いながらも最後まで患者を救う事だけを念頭に置き、その任を全うしていた。
上記、報道によると、自身の患者の手術中に地震と遭遇。当日、石巻日赤病院まで徒歩で救出要請に出かけている。
彼の判断、勇気、実行力が患者を救った事実。
従弟の友人、そして、くだまきへコメントを下さる「うの君」の高校、大学での後輩になる。
「優秀な外科医」そう聞いていた。
その内山哲之医師が亡くなられた。
「震災本コーナー」大手本屋には、今だこのコーナーが大きなスペースを取っている。
「いつなくなるのだろうか・・・」大概、表紙が震災の様子を写した街の様子となっている。
それらの本が正面を見せて何十冊と並べられているのだ。
題名を見なければ、あたかも「震災写真展」でも開催されていると錯覚するほどだ。
ご丁寧にも、エスカレーターを上がり切ると、まずこのコーナーが目に入る。
「震災本は売れているのだ」。
マーケットの「いろは」である。否定しない。
だが、どうしても、目を逸らす。
現実から目を逸らすのでない。
どれも、内容が似か寄った本ばかりなのである。
正直、あきれる。
内山医師の話を掲載させている物を数冊見つける。
元気な彼の姿を見つけて、涙がでそうになった。
そして、彼の死を知らせる事が少ないことにも気づいた。
多くは、復興が進んでいるような記事ばかりが目につく。
しかし、実情は本当なのだろうか。
仮設住宅での孤独死。過労死。
精神的に追い詰められている人も多いとも聞く。
それらの記事は単にデータとしてだけの紹介しかない。
「被災地には、本当の春は今年も来なかったのではないか」
そう考えてしまった。
僕たちは、若く、そして勇気をも持ち合わせた優秀な外科医を失ってしまった。
劣悪な環境で、多くの命を救ってきた内山哲之医師。
彼の事を、多くの人に知って頂きたく「くだまき」を語った。
内山哲之君のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
追記
■消化器外科学会で優秀賞
2009.08.08 三陸河北 記事
■消化器外科学会で優秀賞 2009.08.08 石巻市立病院の内山外科部長 手術糸変更で感染症抑制 データ集積効果を全国発信/
石巻市立病院の内山哲之外科部長(42)が、大阪市で開かれた第64回日本消化器外科学会での発表を高く評価され、優秀賞を受賞した。外科手術に用いる「縫合結紮(けっさつ)糸」を絹糸から合成吸収系に切り替え、手術部位の感染症を減少させるとともに、早期治癒に結び付けた。医療チーム内の問題意識を共有して業務改善して総合的な効果を導いた点も評価された。日本では遅れている手術糸の変更が進む研究発表になる可能性もあり、地方の病院が全国に医療効果のメッセージを情報発信した意義は大きい。 内山部長は「地味な仕事を積み重ねて4年間のデータを集積した。コスト的には高くなるが、絹糸より合成吸収系にした方が感染症や炎症が少なく、結果として早く治るので合理的。患者のためになることを証明できた。地道な努力が評価されてうれしい」と、受賞の喜びを話した。
2013年3月3日 追記

震災後奔走の医師を絵本に 宮城・石巻、昨春に急逝
[文]熊井洋美 [掲載]2013年02月24日
市立石巻病院の仮設診療所で患者と談笑する内山哲之さん=2011年12月、石巻市
著者:WILLこども知育研究所 出版社:学研 価格:¥ 20,160
Amazon.co.jp 楽天ブックス 紀伊國屋書店BookWeb TSUTAYA online
東日本大震災の際に、石巻市で活躍した医師の物語が今月、絵本になった。孤立した病院の患者と仲間の救出に力を尽くし、その後も被災者の診療にあたるさなかの昨春に急逝した。懸命の救援活動は、学校や公共図書館向けに置かれる絵本で読み継がれることになる。
この医師は、石巻市立病院の外科部長だった内山哲之さん。享年45歳。
津波で浸水し、丸2日間にわたり孤立した病院で、懐中電灯の光を頼りに仲間の手術を手伝い、約150人の入院患者とスタッフ、近くの老人保健施設の入所者ら総勢約480人の安全確保に奔走した。
そして、ヘドロまみれのがれきの中を、水につかりながら歩いて約2キロ先の市役所へ助けを求めに行き、震災から3日後の夜、すべての患者が助け出された。
その後も石巻赤十字病院と協力、毎日20キロ以上歩き回って被災者を診療した。昨年1月からは同病院で勤務。診察と手術の合間に、みずからの極限体験を全国の医療関係者に役立ててほしいと、各地で講演した。
名取市に家族を置いての単身赴任は8年近くに及んだ。妻の裕子さん(46)が健康を気遣うと、「自分の家族には、名取に帰れば会える。でも石巻は、もう家族に会えない人がたくさんいるんだ。その人たちを残して、いま去ることはできない」と話したという。
昨年3月21日夜、「手術の連携がすごくうまくいったんだ」と弾んだ声で電話してきた内山さんを、裕子さんがねぎらうと、「明日は当番だからそろそろ休むね」と答えた。それが夫婦の最後の会話になった。
不整脈が何らかの死因を招いたとみられる。昨秋、震災関連死と認められた。
こうした内山さんの活躍を、東京の編集プロダクションが取材し、震災の記録を子どもに伝える絵本「語りつぎお話絵本 3月11日」(発行・学研教育出版)に収めた。全8冊(16話)のシリーズの1話として描かれている。
題は「二つの勇気」。孤立した病院の患者と仲間を守るため、救援を求めた内山さんの行動を「勇気」ととらえ、それが救助に入った医師の「勇気」と呼応して、救助が成功したと紹介されている。
「夫が被災地で体を張って頑張った姿を、多くの人に知って記憶にとどめてもらうことが、私たち家族が生きる支えにもなる」。裕子さんは、そう話している。
Book Asahi Com 「本のニュース」より抜粋















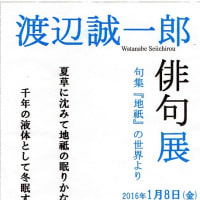

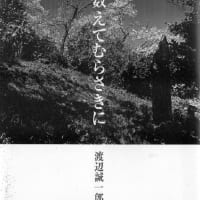








そうでないと分かって、少しほっとしました。
内山さんは直接のお知り合いではないのですが、ご親族の知合いです。
この度はコメントありがとうございます。
決して「野次馬」とは思っておりません。
被災地の方々の様々な思い、私の言葉が足りず、結果、シロ様の想いを汲みとれなかったこと、反省いたします。
シロ様のコメントは、次回の「くだまき」で本編として、語ろうかと考えております。
壊滅した門脇町に7年住んでおり、今は東松島に住んでいます。
内山先生のことは直接知りませんが、お名前はお聞きしました。とても悲しいことでした。
でも我が家では、河北新報から一番最初の本が出たとき、すぐに買いました。
その後次々に本が出たとき、買いました。たくさん買いました。
当時のことを知りたかったからです。
通信手段も何もない現場で夢中で、自分の視界から外のことは何もわからなかったからです。
似たりよったりでも、同じではないです。自分のゆかりの
場所がないかと、必死で探します。
同じ思いの人がたくさんいたと思います。だから、本屋のああいったコーナーにはたくさん人がいました。
見たくない人もいますが、知りたい見たいもまた切実な思いなのです。断じて野次馬根性ではありません。
うまく言えないけど。安易な金儲けだとか、決め付けて欲しくもありません。
切実に求めている当事者だっていたんです。
理解されるかわかりませんが、断じて野次馬根性ではありません。
忘れ去られるのも辛いことです。私はああいう本が無くなってしまえとは思いません。今も大切に持っています。
今更ですが。こういう現地民も、います。
仕事だから?
そういう視点ではなくて、システムをはっきりさせませんと、命を徒す方が増えてしまう事実があります。
そういう意味も込めました。
サイレンの音が耳についているそうです。
内山さんの事を少しでも多くの方に知って頂きたくて、語りました。
いつもより緊張しました。
私は「ようやく一年たった」と思ってます。また地震が来るんじゃないか、また津波が来るんじゃないか、そう思って過ごした一年でした。
当時を振り返ると「震災ハイ」というのでしょうか、精神状態が尋常では無かったな、と思います。そうでなければ、電気やガスが復旧するまでの何ヶ月は過ごせなかったからです。
被災地の病院の先生、看護婦さん、スタッフの皆さんには、心から申し訳ないと思いつつ、当時は他にすがるものがありませんでした。そのすがりつく何百という手を握り返して下さった方たちに、私たちが背負わせてしまった心労や疲労、お詫びのしようがありません。役所や消防、警察などの公務員の皆さんもそうです。
一年たったいま、どれだけお疲れが心と身体に溜まっていることか。そういった方たちをなにか手助けするシステムをと、願うばかりです。
私もあの本の山を見ると買いたくなくなります。
記録として購入しようかと一時思いましたが、未だにあの山には向かいません、ページすらめくりません。不幸を商売にしているようでいやなのです。
友人の本には二冊ほど写真を提供しましたが、鉄道関係の記録です。どうしてもと言うので無償で提供しました。
ヘリでの救出・・・大学病院は重症患者をヘリで受け入れてました。坂病院は救急車での受け入れをしていました。次々と到着する救急車の数は半端じゃありませんでした。全部長野ナンバーの救急車でした。
しかし、被災した病院は地獄のような有り様だったことでしょう。
トイレや食料、水や電気のない空間は地獄ですよ。
家族だけならともかく何百人もですからね。
あの日一日中塩竃の街にはサイレンがなってました。
あの音を聴くと、あの日の恐怖を思いだします。
妻もあの音は聞きたく無いといいます。
昨年チョッとした地震で津波警報が発令され、あのサイレンがなったのです。
ものすごく嫌な音でしたよ。