私鉄や地下鉄の一部通学定期券で料金の取り過ぎが判明した問題で、返金を受けられず泣き寝入りする購入者が続出する可能性が強まっている。
鉄道事業者のほとんどは1年以内しか発売記録を残しておらず、実態を把握できないためだ。国土交通省は可能な限り返金に応じるよう指導しているが、事業者の多くは購入者側に「証拠」の提出を求めており、自らのミスを棚上げした対応が批判を呼びそうだ。
この問題は、横浜市営地下鉄で今年4月、JR東日本との連絡通学定期券を継続購入しようとした中学生に、JR区間で適用される割引をしていなかっ たことに市職員が気付き表面化。市交通局が残っていた過去9年の販売データを調べたところ、約54万円の料金取り過ぎが判明した。
国交省が全国の事業者に調査を指示すると、他に26事業者で同様のミスが見つかった。JRとの乗り入れが多い首都圏の大手9社と都営地下鉄は“全滅”だった。
JRの通学定期券は旧国鉄時代の1968年から、小学生から大学生まで4種類あるのに対し、私鉄では小学生とそれ以外の2種類。各事業者による と、誤発売の原因は、窓口の駅員がJR区間で中・高生割引を適用し忘れるという単純ミスだった。国交省は「相当以前からミスが放置されていた」とみて、各 事業者に対し、適切な返金処理を求める異例の警告を行った。
しかし、各事業者は、定期申込書などの販売記録を1年~半年で廃棄しており、記録が残っていない期間の返金について態度を決めかねている。
過去1年間で計166万円のミスが判明した東京メトロは、返金の条件として「使い終わった定期券など購入を客観的に証明できるものが必要」と話す。首都圏の他事業者もクレジットカードの利用明細や家計簿など「証拠」の提示を基本的に求める考えだ。
記録が残っていた人に過去の購入歴を聞き取り、記録の保存期間以外での取り過ぎを認定したケースは、相鉄が14人、東京メトロと京急が各6人、東 急が5人。全く記録がなく、在学の証明などだけで過去の取り過ぎの返還に応じたケースとなると、京急で1人、東急で9人だけだ。
東武、西武、京成、京王、小田急、都営地下鉄は、「証拠」なしでの返金例は今のところないという。
JR連絡通学定期を1年間購入した場合、1人当たりの取り過ぎは数千~1万円強とみられる。国交省鉄道局の幹部は「購入者の申告に頼る以上、例え ば駅名など料金を取り過ぎた可能性があるケースを具体的に提示し、記録がなくても一人でも多くに返金できるよう知恵を絞るべきだ」と注文する。












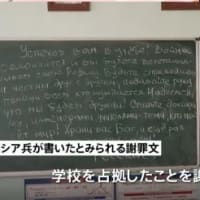





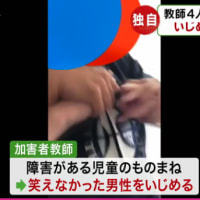

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます