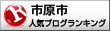いちはら自然育児サークル「ゆるゆる」の皆さんの企画で、「子どもの薬」をテーマにお話をしてきました。
会場のフクマスベース。

「ゆるゆる」では、子どもの健康に関することや子育てについて、同じ思いを持ったママ仲間が緩やかに繋がり、肩ひじ張らずに楽しみながら活動しています。
「ゆるゆる」とは言いながらも、今年1月には小児科医による講演会を夢ホールで開催し、なんと100名以上もの来場者を集めたんですよ。自分たちの想いを着実に行動に移している、頼もしいママたちなんです。
今回は、薬の基本的なお話として、薬の特徴や作用機序、風邪によく使う抗菌剤や解熱剤、咳止めなどについてお話しました。
乳幼児は、感染症にかかることが何かと多い時期なので、ママたちの心配も絶えないものです。でも、お医者さんから当たり前のように出される薬については、大事なわが子の体に入るものなのに、意外に知らないことが多いようです。
つたない話になってしまいましたが、少しでもママたちのお役に立てばうれしいですね。
自分にとっても良い経験になりました。

ゆるゆるの皆さん、楽しい時間をありがとう!
また呼んでくださいね(^^)/
会場のフクマスベース。

「ゆるゆる」では、子どもの健康に関することや子育てについて、同じ思いを持ったママ仲間が緩やかに繋がり、肩ひじ張らずに楽しみながら活動しています。
「ゆるゆる」とは言いながらも、今年1月には小児科医による講演会を夢ホールで開催し、なんと100名以上もの来場者を集めたんですよ。自分たちの想いを着実に行動に移している、頼もしいママたちなんです。
今回は、薬の基本的なお話として、薬の特徴や作用機序、風邪によく使う抗菌剤や解熱剤、咳止めなどについてお話しました。
乳幼児は、感染症にかかることが何かと多い時期なので、ママたちの心配も絶えないものです。でも、お医者さんから当たり前のように出される薬については、大事なわが子の体に入るものなのに、意外に知らないことが多いようです。
つたない話になってしまいましたが、少しでもママたちのお役に立てばうれしいですね。
自分にとっても良い経験になりました。

ゆるゆるの皆さん、楽しい時間をありがとう!
また呼んでくださいね(^^)/