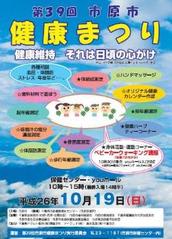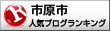高齢化が進むなか、在宅医療の必要性が叫ばれていますが、服薬に関しても例外ではありません。例えば、「薬局までお薬を取りにいけない」とか「自分ではお薬が管理できない」など、薬剤師の在宅訪問指導のニーズは今後ますます高まることが予想されています。
しかし、医療保険にかかる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した薬局の割合は、まだ1割にも達していません(H21年度 中医協調べ)。薬剤師の在宅医療への取り組みは、まだまだこれからといった状況なのです。
そこで市原市薬剤師会では、在宅医療に関する薬剤師へのサポート、医療機関や市民への啓発を目的とした「在宅研究会」を立ち上げました。
現在は12月に開催する薬剤師向けの在宅医療研修会の準備に取り掛かっているところです。
何しろ、患者宅に訪問して指導した経験が全くないという薬局がほとんどですから、手続きのイロハから学んでもらう必要があります。
そこで、最初の訪問の流れを研修会でわかりやすく説明するために、動画を作成することにしました。
本番前の打ち合わせ中。場所は薬剤師会の事務所がある急病センターの会議室です。

【モデルケース】
患者は80歳の男性、歩行不能、末期がん、全身の掻痒感あり。がん治療は副作用のため断念、疼痛コントロールのみ。
キーパーソンは妻だが、足が不自由になり、車もなく、付き添いの通院困難。
子どもは一人、別居でたまに様子を見ににくる程度。
こんな想定で、患者宅に薬剤師が薬を持って訪問し、在宅で服薬指導をするための契約を交わし、残薬を確認するという流れで演技し、ビデオに収めました。
その時の演技の様子が下の写真です。
ちなみに、私は若妻(??)役で出演しております(^_^;)。

皆で画面を確認中。「結構上手くできたね~」

役者揃いだったので(笑)、台本なし・簡単な打ち合わせと1回のリハーサルで、すんなりOKが出ました。
この日はビデオ撮りの他、今月19日に開催される「健康まつり」で薬剤師会が出すブースの確認もしました。
今回は「在宅コーナー」を設けて、薬剤師の在宅訪問に関する啓発リーフレットやパネルを用意し、栄養補助食品・とろみ剤・介護食などの試飲・試食も行います。
タンパク質が補給できるスープ、低タンパクのパンやご飯、舌の力だけでとろける鮭(この加工技術はスゴイ!!)。

お時間がある方はぜひ立ち寄ってみてください♪
場所は保健センター・YOUホールです(^_^)/
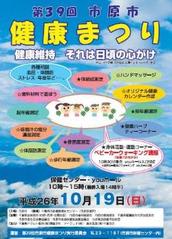
しかし、医療保険にかかる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した薬局の割合は、まだ1割にも達していません(H21年度 中医協調べ)。薬剤師の在宅医療への取り組みは、まだまだこれからといった状況なのです。
そこで市原市薬剤師会では、在宅医療に関する薬剤師へのサポート、医療機関や市民への啓発を目的とした「在宅研究会」を立ち上げました。
現在は12月に開催する薬剤師向けの在宅医療研修会の準備に取り掛かっているところです。
何しろ、患者宅に訪問して指導した経験が全くないという薬局がほとんどですから、手続きのイロハから学んでもらう必要があります。
そこで、最初の訪問の流れを研修会でわかりやすく説明するために、動画を作成することにしました。
本番前の打ち合わせ中。場所は薬剤師会の事務所がある急病センターの会議室です。

【モデルケース】
患者は80歳の男性、歩行不能、末期がん、全身の掻痒感あり。がん治療は副作用のため断念、疼痛コントロールのみ。
キーパーソンは妻だが、足が不自由になり、車もなく、付き添いの通院困難。
子どもは一人、別居でたまに様子を見ににくる程度。
こんな想定で、患者宅に薬剤師が薬を持って訪問し、在宅で服薬指導をするための契約を交わし、残薬を確認するという流れで演技し、ビデオに収めました。
その時の演技の様子が下の写真です。
ちなみに、私は若妻(??)役で出演しております(^_^;)。

皆で画面を確認中。「結構上手くできたね~」

役者揃いだったので(笑)、台本なし・簡単な打ち合わせと1回のリハーサルで、すんなりOKが出ました。
この日はビデオ撮りの他、今月19日に開催される「健康まつり」で薬剤師会が出すブースの確認もしました。
今回は「在宅コーナー」を設けて、薬剤師の在宅訪問に関する啓発リーフレットやパネルを用意し、栄養補助食品・とろみ剤・介護食などの試飲・試食も行います。
タンパク質が補給できるスープ、低タンパクのパンやご飯、舌の力だけでとろける鮭(この加工技術はスゴイ!!)。

お時間がある方はぜひ立ち寄ってみてください♪
場所は保健センター・YOUホールです(^_^)/