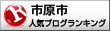1月末、山本さんが所属する県議会会派の視察に同行して、千葉市内4か所の病院を回りました。
今日はそのうちの一か所、千葉県精神科医療センターをレポートします。
千葉市美浜区にある精神科医療センターは病床50、医師は16名。
昭和60年、日本で最初の精神科救急に対応した病院として診療開始、
以来27年間、千葉県の精神科救急医療の基幹病院としての役割を果たしてきました。

同センターは、大きく4つの部門に分かれています。
1)外来部門
2)病棟(入院)部門
3)デイホスピタル
4)救急医療
まずは外来部門から。
一日平均患者数は約134人。
本人や家族からのアプローチが半数を占め、残りは警察・救急隊・他の精神科医療機関・保健所・その他で各々10%ずつという構成です。
市原市からの来院は5%ほど。
診療の半数は夜間や休日に行っているというからびっくりです。
次は、病棟部門です。
急性期の病室に入れてもらえました。

部屋の反対側にはドアのないトイレがありました。驚くほどシンプルでした。
この病院の大きな特徴として挙げられているのは、在院日数の短さです。
なんと平均45日!
全国平均の340日に比べたら、極端に短いですよね。
これは、あくまでも急性期への対応がこの病院の使命だからなのでしょう。
その分、退院後のフォローに力を入れているということでした。
そのための機能の一つが、次に紹介するデイホスピタルです。
復職・復学・生活への援助として、作業療法士や精神保健福祉相談員などが作業やスポーツ、レクリェーションなどのプログラムを指導しています。
一日平均34名が利用しているのだそうです。
そして、夜間や休日の救急医療体制に関して。
千葉県では平成10年度から精神科救急医療システムの運用が開始されていて、同センターはその中核を担っており、24時間365日、電話相談に応じています。
一日平均100件もの相談があるそうです。
このシステムでは、県内を大きく4ブロックに分け、それぞれのブロックでは、外来事例を主に担う輪番病院と、入院事例を主に担う基幹病院が指定されています。
市原市の場合、君津や安房と一緒の南ブロックに属していて、市内の輪番病院は鶴岡病院と磯ヶ谷病院。基幹病院は袖ケ浦さつき台病院になります。
が、そうはいうものの、きっちり棲み分けるのはあまり現実的ではないでしょうね。
実際には、ブロックや基幹・輪番の枠にとらわれずに柔軟に対応されているのではないでしょうか?
例えば救急車がどのように病院を選んで精神科の患者さんを運んでいるのか、また近いうちに実態を聞いてみようと思います。
核家族化や単身生活者の増加によって、退院後の患者さんを在宅でケアする力はどんどん低下しています。
同センターでは、担当の精神保健福祉相談員が、入院から退院後の地域生活まで丸ごと支援する取り組みを積極的に行っています。
「転院先探し」の依頼が「アパート探し」に変わることも珍しくないそうです(もちろん報酬は入りません)。
同センターのように、入院期間をなるべく短くし、代わりに退院後の生活支援に力を入れている精神科病院はまだまだ少数派のようですが、これからの主流になることは間違いないでしょう。
市原市の精神科領域の医療や福祉の体制は現在どうなのか、そして今後どうすればよいのか、大きな課題ができた視察でした。
写真は同センターの屋上。とっても気持ちのいい眺めでした!

今日はそのうちの一か所、千葉県精神科医療センターをレポートします。
千葉市美浜区にある精神科医療センターは病床50、医師は16名。
昭和60年、日本で最初の精神科救急に対応した病院として診療開始、
以来27年間、千葉県の精神科救急医療の基幹病院としての役割を果たしてきました。

同センターは、大きく4つの部門に分かれています。
1)外来部門
2)病棟(入院)部門
3)デイホスピタル
4)救急医療
まずは外来部門から。
一日平均患者数は約134人。
本人や家族からのアプローチが半数を占め、残りは警察・救急隊・他の精神科医療機関・保健所・その他で各々10%ずつという構成です。
市原市からの来院は5%ほど。
診療の半数は夜間や休日に行っているというからびっくりです。
次は、病棟部門です。
急性期の病室に入れてもらえました。

部屋の反対側にはドアのないトイレがありました。驚くほどシンプルでした。
この病院の大きな特徴として挙げられているのは、在院日数の短さです。
なんと平均45日!
全国平均の340日に比べたら、極端に短いですよね。
これは、あくまでも急性期への対応がこの病院の使命だからなのでしょう。
その分、退院後のフォローに力を入れているということでした。
そのための機能の一つが、次に紹介するデイホスピタルです。
復職・復学・生活への援助として、作業療法士や精神保健福祉相談員などが作業やスポーツ、レクリェーションなどのプログラムを指導しています。
一日平均34名が利用しているのだそうです。
そして、夜間や休日の救急医療体制に関して。
千葉県では平成10年度から精神科救急医療システムの運用が開始されていて、同センターはその中核を担っており、24時間365日、電話相談に応じています。
一日平均100件もの相談があるそうです。
このシステムでは、県内を大きく4ブロックに分け、それぞれのブロックでは、外来事例を主に担う輪番病院と、入院事例を主に担う基幹病院が指定されています。
市原市の場合、君津や安房と一緒の南ブロックに属していて、市内の輪番病院は鶴岡病院と磯ヶ谷病院。基幹病院は袖ケ浦さつき台病院になります。
が、そうはいうものの、きっちり棲み分けるのはあまり現実的ではないでしょうね。
実際には、ブロックや基幹・輪番の枠にとらわれずに柔軟に対応されているのではないでしょうか?
例えば救急車がどのように病院を選んで精神科の患者さんを運んでいるのか、また近いうちに実態を聞いてみようと思います。
核家族化や単身生活者の増加によって、退院後の患者さんを在宅でケアする力はどんどん低下しています。
同センターでは、担当の精神保健福祉相談員が、入院から退院後の地域生活まで丸ごと支援する取り組みを積極的に行っています。
「転院先探し」の依頼が「アパート探し」に変わることも珍しくないそうです(もちろん報酬は入りません)。
同センターのように、入院期間をなるべく短くし、代わりに退院後の生活支援に力を入れている精神科病院はまだまだ少数派のようですが、これからの主流になることは間違いないでしょう。
市原市の精神科領域の医療や福祉の体制は現在どうなのか、そして今後どうすればよいのか、大きな課題ができた視察でした。
写真は同センターの屋上。とっても気持ちのいい眺めでした!