永平寺開山記 ③
さて、何も知らない神道丸が、父の元を尋ねますと、特段の用事も無く、せっかく来たのだからと、諸々話し込んでいましたが、金若が自室で待っているのでと、早々に退出すると、金若丸と今宵は語り明かそうと、急いで寝所に戻りました。
ところが、目に飛び込んだ有様は、朱(あけ)に染まった金若丸のいたわしい姿でした。驚いた神道丸は、
「これは、いったい、何者の仕業。出合え出合え、者ども、敵を討ち取れ。」
と、郎党どもに辺りを探索させますが、既に人影もありません。神道丸は、あまりの悲しさに、首の無い死骸に抱きついて、
「金若丸。いかなる者の仕業ぞ。いったいどんな恨みがあって、まだいとけなき弟を殺したのだ。このような邪険な仕業は、人間のすることとも思えない。」
と、流涕焦がれて泣き崩れるのでした。
直ちに、使者が立って、父道忠卿に知らせが入りました。突然の事に驚いた道忠と御台は、急いで神道丸の寝所に駆けつけました。夫婦諸共に死骸に抱きつき、呼べど、叫べど、首の無い金若は答えません。自分の誤りに気が付いた将監は、ぶるぶると震えるしかありませんでした。
やがて、金若の野辺送りが営まれました。御台は木下将監を呼びつけると、
「いかに、将監。なんの遺恨で、金若を討ったのだ。我が子返せ木下。金若返せ将監。」と、泣き崩れました。答えるすべも無い将監です。やがて、御台はきっと顔を上げると、
「憎っくきは、神道丸。神道丸こそ敵。今宵の内に神道丸が首討って見せよ。早く、早く。」
と、噛みつかんばかりの血相です。ははっとばかりに、飛び上がった将監は、そのまま家に立ち帰ると、覚悟を決めました。
「さて、是非もない次第。道にもあらぬ宮仕え。いかに、御主(ごしゅう)の御意(ぎょい)とは言え、なかなか、思いも寄らざること。さりながら、命惜しみては、末代の恥辱。よしよし、浮き世もこれまで。」
と、思い切り、一子、梅王を呼ぶと、
「梅王、よっく聞け。我は、誤って金若殿の首を落としてしまった。これは、天命であるから是非もない。只今これにて、自害いたす。介錯いたせ。その後、この首を神道丸殿へ持参し、ことの次第を、全て報告いたすのじゃ。父に代わり、主君に忠孝いたすのじゃぞ。悪事をなしたる将監行正の子の行く末見よと、人に後ろ指を指されるなよ。それから、父の死骸を他人の手にかけて、後を見苦しくしてはならぬぞ。よいな、早、早、用意いたされよ。」
と、潔く言い渡しましたが、これが、我が子の見納めかと、さすが勇猛血気の将監正行も、涙を流して無念の歯がみをしました。梅王は事の重大さに驚きながらも、
「仰せはごもっとは存じますが、昔より今に至るまで、親の首を、子が切る例(ためし)はありません、それだけは、ご勘弁下さい。」
と、涙をながして懇願しました。将監はこれを聞いて、
「いやいや、よっく聞け、梅王。金若殿を手に掛け、討ってしまった以上、冥途の責め苦もさぞやあること、今、お前の手に掛かるなら、少しは罪の贖い(あがない)じゃ。介錯いたせ。」
と、許しません。梅王が、重ねて辞退すると、将監は怒って、
「何を情けない、物の道理も分からぬか。班足太子(はんぞくたいし)は千人の首を取る。(九尾狐伝説:インドのマカダ国の王子は、九尾狐が化けた華陽夫人に操られて、千人の首を刎ねた。)その時、一人足りなかったので、父、大王の首を切り、近くでは、源義朝は、父為義の首を切る。(保元の乱)かかる例は数多くあるのだ。これでも、嫌だと言うのなら、今生、後生の勘当言い渡す。」
と、無理矢理に介錯を迫りました。道理に詰められた梅王は、返す言葉もなく、仕方なく父に従うことにしました。
怒りを収めた将監は、直ぐさま切腹の用意をすると、大肌脱いで、脇差しを取り直すと、心を静め、しばし瞑想していました。やがて、観念すると、左の脇にさっと脇差しを突き立て、やっとばかりに突き刺し、右手にきりきりと引き回してから、顔を上げ、
「早、首取れ、梅王丸」
と、叫びました。梅王は、
「心得ました。」
と、太刀を振り上げたものの、どうして親の首が討てましょう。目は眩み、心は消え果て、わなわなと、座り込んでしまいました。将監は、きっと、振りあおのくと、苦しい息をつぎながら、
「ええ、こりゃ、梅王。しっかりせよ。最早、名残もこれまでぞ。ええ、早、早、首を取らぬか。梅王丸。」
と、必死の形相です。梅王は、泣く泣く立ち上がると、南無阿弥陀仏と父の首を落とし、わっとばかりに、父の首を拾い上げました。繋げても繋がらない首を抱きしめて、梅王は、
「父上、父上。」
と、叫びつづけるのでした。
つづく










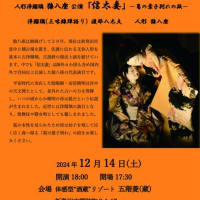


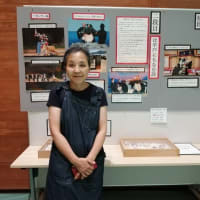
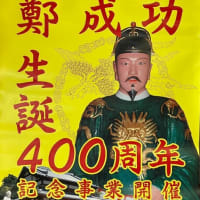




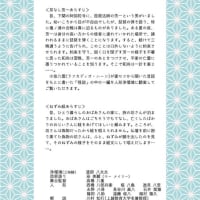
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます