この映画では、メキシコ、モロッコ、東京、別々のストーリーが平行して進んでいきます。
それをつなぐものは一丁のライフル銃。
ただ、互いの地の人々は最後まで、顔を合わせることがない。
銃がつなぐ縁を、ドキュメンタリーのように、つなぎ合わせていく。
旧約聖書の物語。
人々が神に近づこうと天まで届く塔を建てようとした。
神は怒り、人々の言葉をばらばらにして、通じ合わなくしてしまった。
・・・それ以降私たちは未だに、それぞれの言葉を持ち、気持ちを通じ合わせることが出来ずにいる。
これは、それぞれの国の言葉の問題だけでなく、今や、同じ国の隣人、親子でさえも、言葉が通じない。
そんな状況を重ね合わせている。
気持ち、言葉。
そのまま伝えることは何と難しいのだろう。
神のなしたことだから・・・それはどうにもならないことなのだろうか。
************
心が離れ、ほとんど壊れかけているアメリカの夫婦。
モロッコを旅行中、妻がいきなり狙撃される。
病院もなく、ろくな手当も出来ないまま,瀕死の妻を励まし、本国の救援を待つ夫。
しかし、この事件が逆に2人の絆を確かなものにして行く。
************
モロッコの山の中でつつましく暮らす家族。
兄弟の少年たち。
兄はまじめで、兄らしく勤めようとしている。
弟は自由奔放。何でも要領がいい。
ある日コヨーテを撃つために手に入れたライフルを、練習のつもりでバスに向けて撃ってしまった。
アメリカの観光客にあたってしまったらしい。
テロではないかということで、国際紛争にもなりかねず、徹底した捜査が行われる。貧しくも平和だった家族に、いきなり襲ってきた難題。
*************
モロッコを旅行中の両親に替わり、二人の子供たちの世話をしているメキシコ人の乳母。
メキシコで、息子の結婚式があり、2人の子供を誰にも預けることができず、やむなく、子供たちも引き連れてメキシコへ帰ることにする。
その帰路、甥が酔ったまま国境を越えようとして、トラブルとなり、国境を強行突破、警察に追われる身となってしまう。
**************
東京。
聾者である高校生のチエコ。
母を自殺でなくしている。
耳が不自由であることで、人からは敬遠され、疎外感を感じている。
言葉では気持ちを伝える事が出来ない故に、直接に人と体のつながりを求めようとするチエコ。
さて、これら、それぞれの国のそれぞれの立場の人たち全てに、私たちは、共感を覚え、共に哀しむことができる。
人種、言葉や風習が違っても、同じ人間として、心のありようはやはり同じ。
だから、大丈夫。
きっといつか気持ちは通じ合えるのだ・・・と、この作品は語っているのではないかと思います。
菊地凛子さん、オールヌードでした。
体を張った演技という評判でしたが、なるほど・・・です。
あまりにも特殊な役でしたので、これからまた、他の作品ででもお会いしたいものです。
2006年/アメリカ=メキシコ/142分
監督:アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ
出演:ブラッド・ピット、ケイト・ブランシェット、ガエル・ガルシア・ベルナル、菊地凛子
 | バベル スタンダードエディション [DVD] |
| ブラッド・ピッド.ケイト・ブランシェット.ガエル・ガルシア・ベルナル.役所広司.菊地凛子.二階堂智.アドリアナ・バラッサ | |
| ギャガ・コミュニケーションズ |


















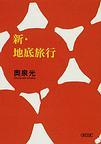








 え~また、おじゃまします。
え~また、おじゃまします。 出ましたねー、隔月刊の、新作が。この、表紙のグインが一段とマッチョですねー。
出ましたねー、隔月刊の、新作が。この、表紙のグインが一段とマッチョですねー。



 あれ、何で突然対談形式なんですか?
あれ、何で突然対談形式なんですか?






