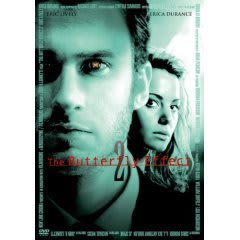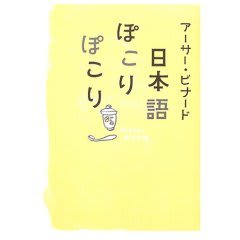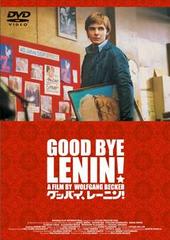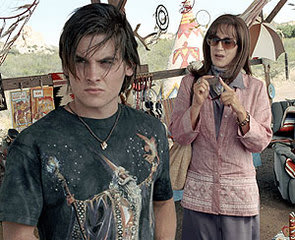(DVD)
大好きなシリーズなので、見ました。
今回、全く登場人物も背景も違うので、こちらを初めてみるということでもぜんぜん問題ありません。
つまり、主人公が時間をさかのぼり、前とは違う行動をとることにより、
その後の人生や周りの状況までもが大きく変わってしまう、
というそのシチュエーションが引き継がれているわけです。
前回はアシュトン・カッチャー演じる学生が主人公でしたが、今回は、エリック・ライヴリー。
社会人です。
だから、ちょっぴりその内容も大人向き。
主人公ニックは、写真を見つめることにより、意識がその写真を写した当時の自分の中に入り込んでゆく。
きっかけは、交通事故により、彼の恋人ジュリーと友人、そしてその彼女という3人を一度に失ってしまったこと。
その直前に写した写真を見つめるうちにいつしかその時点に舞い戻っており、
そして辛くも彼はその事故を避けることができたのです。
気がついてみると、彼の恋人も、友人もその彼女も、みな健在の”現在”にいる。
彼はその、幸福を噛みしめる。
それだけで、実はもう何もいらないはずなのです。
けれども、欲が出る。
友人たちが元気なのは良かったけれど、仕事がうまくいかない。
彼はまた、過去の写真を見つめ、人生の修正を試みる・・・。
しかし、これは繰り返せば繰り返すほど悲惨な結果になっていくのです。
結局は恋人や友人たちを傷つけてしまうことに絶望し、
彼はある悲壮な覚悟を決めて、また、過去に戻っていくのですが・・・・。
前作の「切ないラブストーリー」路線がここでも受け継がれています。
全体的に、このシチュエーションは、前作で感動しつくしているので、やはり以前ほどの驚きはありません。
まあ、無難にまとまっていると思います。
それから、この、タイムトリップの素質は遺伝的なものであることが、浮かび上がってきます。
とすれば、この物語には「3」もあるのか・・・。
う~ん、でも、もうたくさんですよね・・・。
2006年/アメリカ/92分
監督:ジョン・R・レオネッティ
出演:エリク・ライヴリー、エリカ・デュランス、デヴィッド・ルイス、ダスティン・ミリガン