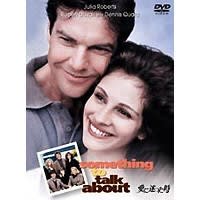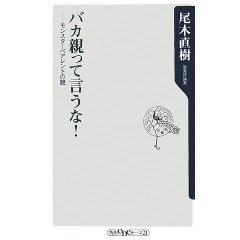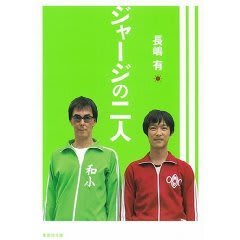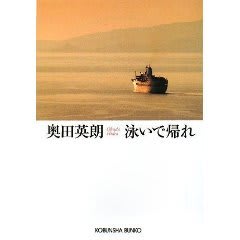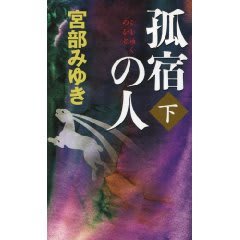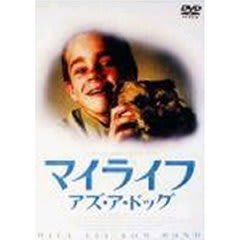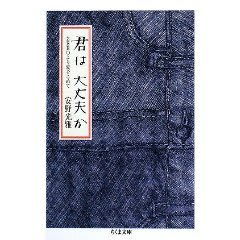(DVD)
夫の浮気を知って、実家の姉のところに身を寄せながら、自分らしい生き方を模索し、新しい愛の形を追及していくヒロインの物語。
1995年作品でありながら、もっと古い時代の話かと、思えてしまいました。
それはこの話の舞台がアメリカ南部ということと関係するかも知れません。
かなり登場人物の様子が古風というか保守的なのです。
特に、女性の立場について。
こんなシーンもありました。
料理の本に、執筆者の名前を入れる。
これまでの習慣では、ミセス○○、と、夫の姓を入れていた。
主人公グレイスは、これからはしっかりと、自分のフルネームを入れましょうと提案する。
大方の女性は、うなずいていたのですが、中には、結婚は私の人生最大の偉業だと、反対する人も・・・。
ジェーン・オースティン時代の話?と思わず疑ったのですが、現代が舞台です。
夫の浮気に反抗し、実家へ戻ったグレイスに、実家の父の視線が冷たい。
ましてや離婚などといったら不名誉な恥ずかしいこと・・・。
昨今のハリウッド映画では、考えられないですね。
10数年前といって、それほど事情が変わっているとも思えないのですが、
やはり、これは土地柄と考えた方がよさそうです。
日本も、同じかな、田舎はとかく保守的。
本筋から、それちゃいましたが、とにかく、いろいろなやりとりのうちに、
夫の浮気は必ずしも、夫の責任ばかりではないと、グレイスも気付き始めるのです。
彼女は昔、獣医になりたいと思っていたのですが、
妊娠してしまったため、やむなくその道をあきらめ、エディと結婚した。
そんな思いがあるためか、次第に、彼女は夫には無関心になってしまっていたのです。
エディは娘を大変愛している申し分ない父親。
少しづつ、お互いの本心が見えてきて、これはお定まりの元のサヤに戻ってハッピーエンド?と思いきや、
意外にも、彼女は、自分のもともとの夢を優先したんですね。
このラストがなければ、ごく平凡な恋愛もので終わるところでした。
総じて、これはあまりラッセ・ハルストレム色が感じられません。
ジュリア・ロバーツファン向きのちょっぴりユーモアを交えたほろ苦いラブストーリー、そんなところでしょうか。
ところで、グレイスの姉、エマ・レイは独身なんですね。
こんな土地なら、それこそ、いつまでもいい年で独身で・・・と、
周りからうるさく言われそうな気がするのですが。
この作中では彼女がこれまで独身の理由に触れていない。
私はむしろこのストーリーは、
妹の家出をからめた、結婚しない女エマ・レイを中心にしたストーリーにした方が面白いと思う。
エマ・レイとエディは過去に絶対何かあったと思う・・・。
1995年/アメリカ/106分
監督:ラッセ・ハルストレム
出演:ジュリア・ロバーツ、デニス・クエイド、ロバート・デュバル、キーラ・セジウィック
明日から、大阪出張のため、3日ほど更新をお休みします。
何で、こんな時期に大阪で会議をするんだか・・・、
この夏、札幌は涼しいので、厳しそう・・・。